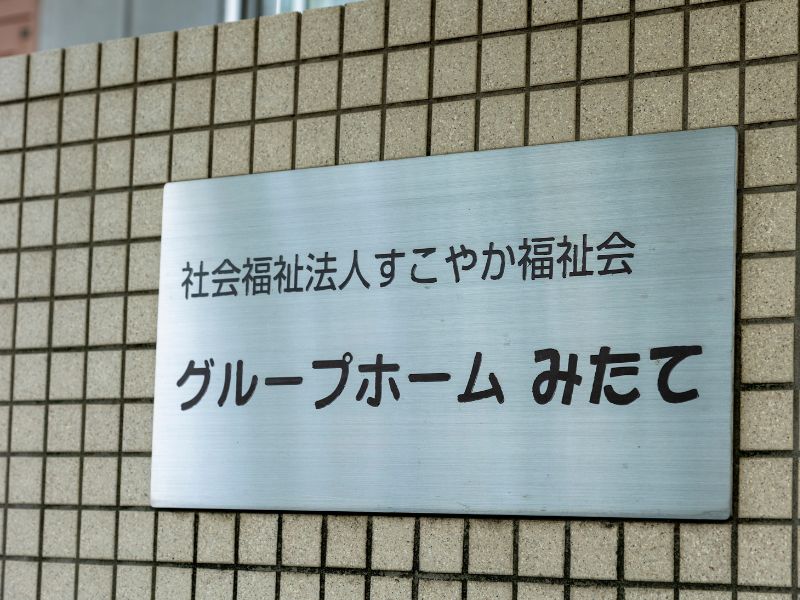このページのまとめ
- 運送業界は、ドライバーの人員不足や2024年問題への対応といった課題を抱えている
- 運送業界・運送会社のM&A需要は増加している
- 運送業界は、M&Aによるシナジー効果を発揮しやすいのが特徴である
- 運送会社のM&Aでは、運送業許可に注意する必要がある
- 運送会社のM&Aをスムーズに進めるためには、適切な仲介会社を選ぶことが大切
「運送会社のM&Aを行うべきか」「どのようにM&Aを進めればよいかわからない」と悩んでいる企業も多いでしょう。運送会社のM&Aは、需要が高まっています。事業承継のためのM&Aに加え、2024年問題への対応策として、 M&Aが注目されているのが現状です。
今回は、運送会社のM&Aについて、価格相場や事例、メリット・デメリットやポイントなどを解説します。M&Aを検討している方は、ぜひ参考にしてください。
目次
運送業界・運送会社とは
運送会社とは、法人や個人から依頼を受け、目的地まで人や物を運ぶ仕事のことです。トラックなどで輸送を行うことに特化している特徴があります。鉄道や船、飛行機などを使う場合は、運輸業と呼ばれるようになります。
運送業界と物流業界との違い
そもそも運送とは、人や物を目的の所に運ぶことです。
一方、物流は生産者から消費者に至るまでの商品の一連の流れのことを指します。物流では、商品の運送以外にも、商品の保管や荷役、包装といった業務を行うのが特徴です。
つまり、運送業界は物流業界の一部と考えられます。
運送業界の特徴
運送業界の特徴は、中小企業の多さです。「日本のトラック輸送産業 現状と課題 2023」によると、2022年3月末時点でのトラック運送事業者数は63,251件でした。そのうち、99%以上が中小企業に該当するとされています。
運送業界に中小企業が多い理由は、運転手が1人とトラック1台があれば事業が始められ、新規参入のハードルが低いためです。
ただし、他社との差別化を図ることが難しい業種でもあります。そのため、収益性の確保や、価格競争に陥りやすい点に注意が必要です。
参照元:全日本トラック協会「日本のトラック輸送産業 現状と課題 2023」
運送会社・業界でM&A需要が増加している背景
運送会社・業界でM&A需要が増加している背景としては、以下が挙げられます。
- ドライバーの人員不足が苦しい
- 長時間労働が常態化している
- 2024年問題への懸念がある
- 経営に苦しむ企業が増加している
- 業界の競争が激しい
- 燃料費の高騰に苦しんでいる
- 後継者不足に悩んでいる
- DXへの対応が求められている
それぞれ見ていきましょう。
ドライバーの人員不足が苦しい
運送業界は、ドライバー不足にも悩まされています。
国土交通省の「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃の告示について」によると、トラック運送業がほかの産業に比べて、長時間労働や低賃金などの問題を抱えていると指摘されています。その結果、ドライバー不足が発生し、公共工事の資材調達不足などにも影響が発生している状況です。
参照元:国土交通省「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃の告示事案に関する答申について」
長時間労働が常態化している
運送業界は、トラックドライバーの長時間労働が常態化しているという課題も抱えています。
全日本トラック協会によると、2021年のトラックドライバーの平均労働時間は以下のとおりでした。
| 大型トラックドライバー | 2,544時間 |
| 中小型トラックドライバー | 2,484時間 |
| 全産業平均 | 2,112時間 |
長時間労働の原因としては、ドライバー不足や渋滞、荷待ち時間の発生などが挙げられます。
長時間労働問題を解消するためには、ドライバーの確保や経営効率の向上などが必要であり、M&Aが有効な方法として注目されています。
参照元:全日本トラック協会「トラック運送業界の2024年問題について」
2024年問題への懸念がある
2024年問題とは、働き方改革関連法の試行によって、運送業界に影響を及ぼすと考えられている問題のことです。2024年問題の例には、時間外労働の上限規制があります。
2024年の4月1日からは、自動車運転業務での時間外労働が、「年に960時間まで」と上限の設定が実施されます。この上限が決められることで、運転手1人あたりに走行できる距離が短くなり、遠方まで荷物を運べなくなる事態が懸念されるでしょう。
そのほかにも、「勤務間インターバル制度」「時間外労働への割増賃金の値上げ」などが、運送業界に影響すると考えられています。
経営に苦しむ企業が増加している
運送業界では、経営に苦しむ企業が増加しています。東京商工リサーチが2022年に発表したデータによると、最新期(2021年)で損益が判明した1万5,525社中、赤字は3,370社でした。赤字企業の構成比率が、はじめて2割を超えたのがポイントです。
また、50億円以上の赤字を計上した企業も発生しています。
このように、経営に苦しむ企業が増加しているのが現状です。
参照元:東京商工リサーチ「大手と中小の業績格差が拡大 ~ 2021年『道路貨物運送業の業績動向』調査 ~」
業界の競争が激しい
運送業界では、ネットショッピングの急成長により、業界内の競争が激しくなっています。
競争が激しくなることで、運送単価の低下が発生します。その結果、運送費や人件費の確保が難しくなっているという問題も抱えています。
燃料費の高騰に苦しんでいる
燃料費の高騰も、運送業の経営に影響を及ぼしています。海外の貿易摩擦の影響もあり、燃料費は高止まりになっている状況です。燃料費の改善が進まなれば、経営悪化に苦しむ企業は増加していくでしょう。
後継者不足に悩んでいる
高齢の経営者が引退し始めており、後継者不足に悩んでいる企業が多いのも特徴です。運送業は荷物を運ぶため身体的な負担が多く、高齢になると業務の遂行が難しくなります。
後継者不足で事業承継できない場合、経営者の引退を機に廃業を余儀なくされてしまいます。廃業を防ぐために、外部に事業を承継するM&Aが活発化しているのもポイントです。
DXへの対応が求められている
DXへの対応が各企業に求められている昨今、大手企業を中心にベンチャー企業やIT企業への投資が増加しているのも、運送業のM&Aが増加している背景の1つです。
システム投資に対応できれば、消費者のニーズに合ったサービスを提供でき、新規顧客の獲得や売り上げ増加につながります。
しかし、大手企業ほど資金に余裕がない中小企業は投資をためらう傾向にあり、企業間の格差が広がっているのが現状です。
運送業の中小企業が生き残るためには他社との差別化をどのようにして進めるかがポイントです。ベンチャー企業やIT企業に投資し、IT化を促進することがますます求められます。
運送会社のM&A価格相場
運送会社のM&Aを行うためには、価格相場を知っておくことが大切です。価格相場が分かれば、買い手企業でも、売り手企業でも、損をする事態を避けることができます。
ここでは、運送会社の価格相場について、事業譲渡の場合と株式譲渡の場合で分けて解説します。
事業譲渡の場合
事業譲渡の場合は、事業資産に事業利益の2年〜5年分を足して、相場を算出します。
事業譲渡で価格相場を算出する場合には、次のような計算で求めましょう。
事業資産+事業利益の2年〜5年分=価格相場
株式譲渡の場合
株式譲渡の場合は、次のような計算式で価格相場を算出します。
時価純資産+(営業利益+役員報酬)×2年から5年分=相場
大体の相場を知りたいときは、「時価純資産+営業利益の2年〜5年分」の計算式で算出すると良いでしょう。
ただし、最終的な取引価格を決める際は、企業価値をもとに決定します。企業価値を算出するための方法には、下記の3種類があります。
- コストアプローチ
- マーケットアプローチ
- インカムアプローチ
それぞれ解説します。
コストアプローチ
コストアプローチとは、賃借対照表に記載された純資産をもとに、企業価値を算出する応報です。コストアプローチには、「簿価純資産法」と「時価純資産法」などがあります。
- 簿価純資産法:賃借対照表に記載された純資産をそのまま使用する
- 時価純資産法:資産を時価で算出した時価純資産を使用する
コストアプローチのメリットは、客観的な企業価値を算出できる点です。
ただし、将来に発生する収益を考慮していない点には注意しましょう。
マーケットアプローチ
マーケットアプローチとは、自社と類似している企業の株式相場や、過去に行われたM&A事例を参考に算出を行う方法です。マーケットアプローチには、「類似会社比較法」「類似取引比較法」などがあります。
- 類似会社比較法:対象企業と事業が似ている上場企業の株価倍率を使用する
- 類似取引比較法:過去に行われた、似ているM&A事例の価格を参考にする
マーケットアプローチのメリットは、対象企業と似ている企業や取引を参考にできることから、客観的な企業価値を算出しやすい点です。
ただし、似ている事例が見つからなかった場合には使用できなかったり、一時的な市場価値の変動によって適切な評価ができなかったりする場合があるため、注意しましょう。
インカムアプローチ
インカムアプローチとは、対象企業の収益性を基準に、企業価値を算出する方法です。インカムアプローチには、「DCF法」「配当還元法」などがあります。
- DCF法:将来にわたって生みだす収益を現在価値に割引いて算出する手法
- 配当還元法:予想配当金を資本還元し、算出する方法
インカムアプローチのメリットは、企業が生み出す将来の利益を反映できる将来点です。そのため、企業規模を問わず、使用されています。
注意点は、売り手側が作成した事業計画書を使用する点です。インカムアプローチでは、事業計画書に記載された利益や配当金をもとに算出します。売り手側の主観が含まれていると、客観的な価値が算出しにくい点には注意しましょう。
運送会社のM&A事例10選
ここでは、運送会社のM&A事例を10個紹介します。
- ウインローダー×トナミホールディングス
- ケーワイケー×トナミホールディングス
- 名鉄運輸×日本通運
- パナソニックロジスティクス×日本通運
- MD LOGISTICSら×日本通運
- 北区小型運送×HINODE&SONS
- 古河物流×SBSホールディングス
- AirRoad Pty Ltd×センコーグループ
- オーナミ×センコーグループ
- セイノーホールディングスの合併
それぞれ、M&Aに至った背景やM&Aの目的なども解説しているため、ぜひ参考にしてください。
1.ウインローダー×トナミホールディングス
トナミホールディングス株式会社(以下、トナミ)は、2023年7月、株式会社ウインローダー(以下、ウインローダー)の株式を取得し、連結子会社としました。
トナミは、事業の継続的な成長に向けて、資本提携やM&Aを積極的に行っている企業です。そしてウインローダーは、東京都の三多摩地域を中心に、地域密着型の物流サービスを提供しています。
連結子会社化により、ウインローダーが持つ運送能力の発揮と経営基盤の強化、事業規模の拡大が期待できるとして、M&Aが行われました。
参照元:トナミホールディングス「『株式会社ウインローダー』の株式取得に伴う連結子会社化のお知らせ」
2.ケーワイケー×トナミホールディングス
株式会社ケーワイケー(以下、ケーワイケー)は、2018年6月、トナミのグループ企業となりました。
ケーワイケーは、運送業のほか、倉庫保管管理業や流通加工業、企画販売業など、事業を拡大してきた企業です。
ケーワイケーは、トナミとの M&Aを通じて、トナミが持つ豊富な経営資源や技術、ノウハウなどを活かし、業務改善や事業の拡大、安全運行の確保、コンプライアンス強化などを目指すとしています。
さらに、従業員にとって働きやすい環境を整え、働き方改革への対応も進める方針です。
参照元:株式会社ケーワイケー「ごあいさつ」
3.名鉄運輸×日本通運
名鉄運輸株式会社(以下、名鉄運輸)は、2023年8月、日本通運株式会社(以下、日本通運)の特別積合せ運送事業について、事業統合を行うことを決定しました。
両社は、2015年に資本業務提携契約を締結し、特別積合せ運送事業について協業を進めていました。しかし、昨今のエネルギー価格高騰やドライバー不足、特別積合せ運送事業の需要低迷などに伴い、事業の統合を決めたといいます。
今後は、名鉄運輸を吸収分割承継会社、日本通運を吸収分割会社とする会社分割を行い、名鉄運輸が分割会社の発行済普通株式と対象事業を承継する予定です。
参照元:名古屋鉄道株式会社「名鉄運輸株式会社と日本通運株式会社の特別積合せ運送事業における事業統合(子会社が当事会社となる会社分割)に関する基本合意書締結のお知らせ」
4.パナソニック ロジスティクス×日本通運
日本通運株式会社は、2014年1月、パナソニック株式会社が保有するパナソニック ロジスティクス株式会社(以下、パナソニック ロジスティクス)の株式を66.6%取得しました。この株式取得により、商号を日通・パナソニック ロジスティクス株式会社に変更しています。(2022年には、NX・NPロジスティクス株式会社に社名変更。)
パナソニック ロジスティクスは、家電を中心とした物流事業を展開しており、電機物流で培ったノウハウに強みがあります。日本通運の一員となったことで、さらに幅広いインフラを利用できるようになりました。エレクトロニクス物流の分野で頂点を目指す方針を掲げ、物流の可能性に挑戦しています。
参照元:NIPPON EXPRESSホールディングス「日通・パナソニック ロジスティクス株式会社の発足について」
5.MD LOGISTICSら×日本通運
米国日本通運株式会社(以下、米国日本通運)は、2020年9月、アメリカのMD Logistics, LLC社とMD Express, LLC社(以下、MD社)の全出資持分を取得し、子会社化しました。
MD社は、医薬品産業の流通加工業務や、配送サービスを手がける企業です。
日本通運は、医薬品産業に適した物流サービスの体制強化を進めていました。アメリカは、医薬品需要で世界全体の約4割を占める消費大国です。この子会社化によって、アメリカにおけるロジスティクス機能を獲得し、事業をさらに拡大させる方針です。
参照元:NIPPON EXPRESSホールディングス「米国物流会社の出資持分取得(子会社化)完了に関するお知らせ」
6.北区小型運送×HINODE&SONS
HINODE&SONS株式会社(以下、HINODE&SONS)は、2019年9月、北区小型運送株式会社(以下、北区小型運送)をグループ化しました。グループ会社間で協力体制を強化し、シナジー効果を創出するとして行われました。
そして、2023年5月には、北区小型運送を含むグループ会社5社が合併し、株式会社日之出運輸(東日本)が発足しています。市場競争力強化のため、合併を決めたそうです。
参照元:HINODE&SONS株式会社「子会社の合併について(株式会社日之出運輸(東日本))」「会社沿革」
7.古河物流×SBSホールディングス
SBSホールディングス株式会社(以下、SBSホールディングス)は、2021年12月、古河物流株式会社(以下、古河物流)の普通株式の66.6%を取得し、子会社化しました。そして、商号をSBS古河物流株式会社に変更しています。
古河物流は、電子部品や自動車部品などの輸配送や流通加工、保管などを手がける企業です。SBSホールディングスの子会社になることで、SBSホールディングスが持つノウハウやITに関する技術などを活用し、物流業界の変化に対応するとしています。
参照元:SBSホールディングス「古河物流株・・式会社株式の一部取得(子会社化)完了及び商号変更に関するお知らせ」
8.AirRoad Pty Ltd×センコーグループ
センコーグループホールディングス株式会社(以下、センコーグループ)は、2021年4月、オーストラリアのAirRoad Pty Ltd(以下、エアロード社)をグループ化しました。
エアロード社は、精密機器や自動車部品の輸送を行う企業です。オーストラリア国内で30年以上貨物自動車運送業を営んでいます。
また、オーストラリアは人口が増加し、物流市場の拡大が期待できる国です。センコーグループは、エアロード社をグループ化することで、3PL事業の拡大とコールドチェーン事業への本格参入に取り組むとしています。
参照元:センコーグループホールディングス株式会社「ASEAN・オセアニア地域で3PL 事業を拡充エアロード社をグループ化」
9.オーナミ×センコーグループ
センコーグループは、2022年12月、日立造船株式会社の子会社である株式会社オーナミ(以下、オーナミ)を子会社化する株式譲渡契約を締結しました。
オーナミは、大型貨物や重量物の荷役・保管・輸送などを得意とする企業です。大阪を中心に、茨城・滋賀・京都・広島・熊本に拠点を持ち、海上・陸上一貫輸送体制を持っています。
センコーグループは、センコーグループのネットワークとオーナミの持つ重量物輸送や輸出梱包のノウハウを活用し、効率的な輸送と重量物輸送事業のグローバル展開を目指す方針です。
参照元:センコーグループホールディングス株式会社「国内外の重量物輸送拡大を図る~海陸一貫輸送会社オーナミをグループ化~ 」
10.セイノーホールディングスの合併
セイノーホールディングス株式会社は、2023年3月、西濃運輸を存続会社として子会社4社を統合しました。西濃運輸株式会社、関東西濃運輸株式会社、濃飛西濃運輸株式会社、東海西濃運輸株式会社が統合し、新しい西濃運輸がスタートしています。
この合併により、運行の効率化や運行コストの低減、ドライバーの負担軽減などを目指しています。また、2024年問題やSDGsに対応すると同時に、幹線ネットワークを強化し、国内物流基盤としての役割を果たす予定です。
参照元:セイノーホールディングス「西濃運輸を存続会社として4社を統合 2022年04月01日」
M&Aで運送会社を買収する4つのメリット
M&Aで運送会社を買収するメリットは、次の4つです。
- 業界への新規参入が行いやすい
- 事業をスピーディに拡大できる
- ドライバーを確保できる
- シナジー効果が発揮される
それぞれのメリットに関して、詳しく解説します。
1.業界への新規参入が行いやすい
M&Aで運送会社を買収するメリットは、業界への新規参入が行いやすい点です。ゼロから事業を立ち上げるより、低いリスクで新規参入が行えます。
運送業界に参入するためには、トラックやドライバー、運送業許可の要件を満たす事業所や駐車場などを確保する必要があります。人員については、運行管理者と運行管理補助者、整備管理者と整備管理補助者についても確保しなければなりません。
また、事業を軌道に乗せるためには、多くの顧客を確保したり、従業員を育成したりすることも必要です。
M&Aを利用することにより、これらの経営資源をそのまま引き継げるため、スムーズに運送業に新規参入できます。
2.事業をスピーディに拡大できる
事業をスピーディに拡大しやすいのも、M&Aで運送会社を買収するメリットです。
たとえば、自社が対応できていないエリアに営業所を構える運送会社を買収すれば、地域シェアをスピーディーに拡大できる可能性が高いです。
また、製造や販売を行う会社が運送会社を買収することで、物流機能も自社で保持できます。その結果、より安価かつスピーディにサービスを提供できるようになり、売上の拡大につながる可能性も期待できます。
3.ドライバーを確保できる
売り手の従業員を獲得できることも、M&Aを行うメリットです。特に、トラック運転手不足の解消はポイントになるでしょう。
前述のとおり、運送会社には2024年問題への対応が求められています。時間外労働の上限規制に対応するためには、ドライバーの確保が欠かせません。
M&Aを行うことで、売り手の従業員を獲得できるため、人材確保にかかる時間を短縮できます。
4.シナジー効果が発揮される
シナジー効果が発揮される点も、M&Aで買収を行うメリットです。シナジー効果とは、複数企業がまとまることで、1社ではなしえない大きな成果を生みだすことを指します。
運送業界は、特にM&Aによるシナジー効果を発揮しやすいとされている業界です。
たとえば、大型商品の運送に強みがある企業と、冷凍の商品を運送できる設備が揃っている企業がM&Aを行うことで、取り扱える商品の幅が広がります。
関東に拠点を構えていた企業が関西の運送会社を買収することで、関東から関西に荷物を運んだ帰りに関西からの荷物を運べるようになり、片荷の解消につながるでしょう。
このように、M&Aによってシナジー効果が発揮され、売上増加やコストカット、経営の効率化などが期待できます。
M&Aで運送会社を売却する6つのメリット
M&Aで運送会社を売却するメリットは、以下の6つです。
- 売却で利益が得られる
- 後継者問題を解決できる
- 従業員の雇用を維持できる
- 従業員の待遇改善が期待できる
- 経営基盤が安定する
- 債務を解消できる
それぞれ解説します。
1.売却で利益が得られる
M&Aで運送会社を売却することで、利益を得られます。経営引退後の資金を獲得でき、生活費用にあてることができるでしょう。
企業を売却した場合、営業利益数年分の利益を得られるケースが一般的です。もし、廃業を選んでしまうと、資金を得られず、手続きに費用が掛かってしまいます。廃業を選ぶのであれば、会社売却の方が良いケースも多くなります。
2.後継者問題を解決できる
後継者問題を解決できる点も、M&Aで運送会社を売却するメリットです。経営が安定していても、後継者がいない企業は、廃業を選ばざるを得なくなります。
M&Aで第三者に事業承継を行えば、後継者問題を解決できます。事業はもちろん、育ててきたノウハウや技術を残せる点も、メリットになるでしょう。
3.従業員の雇用を維持できる
従業員の雇用を維持できる点も、M&Aで売却するメリットです。M&Aであれば、従業員の雇用が買い手企業に引き継がれ、仕事を失わずに済みます。
もし、廃業を選択してしまえば、雇用していた従業員は職を失ってしまいます。従業員のことを考えると、雇用が引き継がれるM&Aを選択することも大切です。
4.従業員の待遇改善が期待できる
資金力がある大手企業に譲渡できれば、従業員の待遇が改善する可能性が高いです。従業員にとって働きやすい環境が整うことで、働き方改革にもスムーズに対応できるでしょう。
魅力的な職場であることが評価されれば、人材も確保しやすくなります。
また、大手企業の傘下に入って知名度が向上し、人材の採用難易度が下がる効果も期待できます。
5.経営基盤が安定する
経営基盤が安定するのも、売り手側のメリットです。大手企業のグループに入ることで、安心して事業を継続できるでしょう。
また、大手企業のグループに入った場合、グループが持つブランドイメージやネットワークを活用できるようになります。自社だけで事業を行うよりも、成長速度や売上にプラスの影響が出るでしょう。
6.債務を解消できる
M&Aを行うことで、債務を解消できるメリットがあります。株式譲渡で会社ごと譲渡する場合、自社が抱えている債務も合わせて承継されるためです。また、経営者保証ガイドラインの条件を満たせば、個人保証の解消も可能になります。
抱えていた債務がなくなれば、経営者は安心して今後の生活を送れるようになります。ストレスや不安から解消される点もメリットでしょう。
M&Aで運送会社を買収する3つのデメリット
M&Aで運送会社を買収するデメリットは、次の3つです。
- 簿外債務が見つかる
- 従業員が流出してしまう
- のれんの減損で業績が悪化する
それぞれのデメリットに関して解説します。
1.簿外債務が見つかる可能性がある
M&Aで買収を行う場合、簿外債務に注意しましょう。簿外債務とは、賃借対照表に記載されていない債務のことです。たとえば、従業員に対する未払いの賃金や、債務保証が該当します。
企業買収で株式譲渡を採用する場合、負債もまとめて引き継がれます。簿外債務を見落としてしまうと、将来的に損をしてしまうでしょう。
簿外債務を見落とさないためにも、デューデリジェンスの実施が重要です。もし、簿外債務のリスクを発見した場合には、事業譲渡に切り替えてM&Aを進めることもできます。
2.従業員が流出してしまうリスクがある
M&Aで買収する場合、従業員が流出してしまわないように注意しましょう。特に、優秀な人材を獲得するのは、M&Aを行ううえで重要です。
従業員が流出してしまうケースには、「労働条件が合わなかった」「買い手企業の従業員と対立してしまう」などのケースがあります。
M&Aで運送会社を買収する際には、従業員が流出してしまうリスクを想定して計画を立てましょう。売り手企業から引き継ぐ従業員が勤務しやすいように、自社の環境を整えることも必要です。
3.のれんの減損リスクがある
のれんの減損を行うことで、業績が悪化するデメリットもあります。のれんとは、ブランド力や顧客リストのような、目には見えない資産のことです。M&Aで買収価格を決める際には、のれんの価値も合わせて算出を行います。
M&A後の事業が予定通り進めば、買収時に掛かったのれん代の回収が可能です。しかし、経営がうまくいかず、想定していた利益がでない場合もあるでしょう。
のれん代が回収できない場合、株式評価損、または減損損失で計上を行います。多額の損失計上に該当し、業績悪化につながる点は注意しましょう。
M&Aで運送会社を売却する3つのデメリット
M&Aで運送会社を売却するデメリットは、次の3つです。
- 買い手が見つからない可能性がある
- 従業員や取引先から反発を受ける
- 競業避止義務が課される
それぞれ解説します。
1.買い手が見つからない可能性がある
M&Aで売却したいと考えても、自社に合う買い手が見つからない可能性があります。
特に、異業種とM&Aを行いたい場合は、注意が必要です。運送を自社で行うとなると、事故のリスクや荷物の破損・汚損など、さまざまなリスクがあります。損害賠償に発展する可能性もあるため、あえて運送を外注している企業も存在します。
運送会社のM&Aでは、買い手探しに苦労する可能性が高い点に注意しましょう。自社に合う相手を見つけるためには、M&A仲介会社やマッチングサービスなどを利用することが大切です。
また、買い手が見つかっても、希望どおりの条件でM&Aを進められるとは限りません。
買い手は、売り手企業の経営状況や、M&A後のシナジー効果などを判断しながら条件を決めます。提示された条件が希望とは合わず、納得できないこともあるでしょう。
希望条件で売却を進めるためには、企業価値の向上に力を入れたり、余裕をもって交渉相手を探すことが求められます。
2.取引先から反発を受けるリスクがある
M&Aを行うことで、取引先から反発を受ける可能性があります。支配権が買い手企業に移行した結果、契約や料金設定などが変更されてしまう場合があるからです。十分な説明がないまま変更が行われると、反発を受けてしまうでしょう。
運送会社の売却を行う際には、取引先から反発を受けるような変更を実施しないよう、交渉しておくと良いでしょう。また、顧客に対して、M&Aを行うことを伝え、説明しておくことも大切です。
3.競業避止義務が課される
M&Aで売却した結果、競業避止義務が課せられる場合があります。会社法第21条にて、「譲渡企業は、譲受企業と競業避止義務に関しての取り決めがなくても、同一の市町村と隣接する市町村の区域内では、20年間同一事業を行ってはならない」と定められているからです。
会社を売却したのち、新規事業を始めようと考える経営者もいます。契約内容や法律を確認し、競業避止義務が課されているか確認しましょう。
参照元:e-Gov法令検索「会社法第21条」
運送会社のM&Aは運送業許可に注意する
事業譲渡で運送会社のM&Aを行う場合、運送業許可に注意しましょう。貨物自動車運送事業法第30条で、「般貨物自動車運送事業の譲渡しおよび譲受けは、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない」と定められているためです。
運送業許可は自動的に引き継がれないため、許可取得の手続きを実施しなければなりません。
事業譲渡の認可申請を行う場合は、譲渡譲受認可申請が必要です。譲渡譲受認可申請では、次のような内容を記載します。
- 譲渡渡および譲受人の氏名・名称・住所(法人の場合は代表者の氏名)
- 事業の種別
- 譲渡および譲受しようとする事業の種別・営業区域
- 譲渡価格
- 譲渡・譲受を予定する時期
- 譲渡・譲受を必要とする理由
また、申請時には、次の書類を添付しましょう。
- 譲渡譲受契約書の写し
- 事業譲渡価格の明細書
- 定款・資産目録・貸借対照表などの資料(譲受側が一般貨物自動車運送事業を経営していない場合)
一方、株式譲渡でM&Aを行う場合は、包括的承継が発生するため、基本的には許認可を再取得する必要はありません。ただし、株式譲渡後に商号や本店所在地、役員、運行管理者や整備管理者などが変更になる場合は、別途変更手続きを行う必要があります。
参照元:e-Gov法令検索「貨物自動車運送事業法第30条」「貨物自動車運送事業法施行規則第17条」
関東運輸局「一般貸切旅客自動車運送事業の譲渡譲受認可申請について」
運送業許可を引き継ぐ要件
運送業許可を引き継ぐためには、定められた要件を満たしている必要があります。
貨物自動車運送事業法の第30条3項で、「第5条および第6条の規定は、前2項の認可について準用する」と定められているからです。
許可を引き継ぐ要件に関しては、次のようなものがあります。
- 運送事業の運営に必要な資源が確保されている
- 運行管理者・整備管理者・運転者の確保ができている
- 運転事業に必要な資金を確保している
運送業許可を引き継ぐ要件は、複雑です。専門家に相談をしながら進めるようにしましょう。
参照元:e-Gov法令検索「貨物自動車運送事業法第30条」
関東運輸局「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可申請の処理方針について」
M&A仲介会社を選ぶ4つのコツ
M&A仲介会社を選ぶコツには、次の4つが挙げられます。
- 業界特化型で選ぶ
- 自社と同じ規模や業種でのM&A実績があるか確認する
- 専門家との連携があるM&A仲介会社にする
- 料金体系の種類で選ぶ
それぞれの選び方に関して、解説します。
1.業界特化型で選ぶ
M&A仲介会社は、業界特化型か、特化していないかで選ぶことができます。業界特化型の場合、特定の業界に詳しいメリットがあります。運送業界に特化したM&A仲介会社であれば、運送業界ならではのポイントまで気づいてもらえるでしょう。
非特化型の場合は、異業種も含めて幅広い範囲でM&Aが行えるメリットがあります。同業では考え付かない効果が発生するケースもあるでしょう。
2.自社と同じ規模や業種でのM&A実績があるか確認する
M&A仲介会社を選ぶ際には、自社と同じ規模や業種での実績があるか確認しましょう。自社と同規模などで実績を持つM&A仲介会社であれば、安心して相談ができます。
また、実績が多いM&A仲介会社ほど、「交渉のスムーズな進め方」「企業価値を高めるポイント」なども把握しています。
実績から、自社が安心して依頼できるM&A仲介会社を探しましょう。
3.専門家との連携があるM&A仲介会社にする
専門家との連携がある、M&A仲介会社を選ぶこともポイントです。M&Aでは、法務や会計など、専門的な知識が求められます。特に買い手が実施するデューデリジェンスでは、専門家のサポートを受けることが欠かせません。
弁護士や公認会計士のような専門家との連携ができているM&A仲介会社なら、スムーズにM&Aを進められるでしょう。
もし専門家との連携がない場合は、自社で手続きを進めたり、外部に依頼をしたりしなければなりません。M&Aを進めやすくするためにも、専門家との連携や人脈があるか確認しましょう。
4.料金体系で選ぶ
料金体系で選ぶことも、M&A仲介会社を選ぶコツです。料金体系が分かりやすく、無理なく費用を支払える先を選びましょう。
資金に不安がある場合は、完全成功報酬型のM&A仲介会社を選ぶと良いでしょう。M&Aが成立してから、料金の支払いを行えます。また、着手金や中間報酬が不要のM&A仲介会社もあります。M&A前の資金で不安があっても、相談できるでしょう。
運送会社のM&Aを成功させる3つのポイント
運送会社のM&Aを成功させるポイントは、次の3つです。
- シナジーが発揮できる企業を探す
- 適正な相場を調べる
- 税金対策を行う
それぞれのポイントについて解説します。
1.シナジーが発揮できる企業を探す
運送会社のM&Aでは、シナジーが発揮できる案件を探しましょう。シナジー効果を発揮させるためには、次のようなポイントが重要です。
- 事業内容
- トラック運転手
- 車両などの設備
- 営業エリア
事前にこれらの調査を行ってから、M&A相手を選ぶことが大切です。
2.適正な相場を調べる
M&A実施に向け、適正な相場を調べるようにしましょう。相場を調べないことで、損をしてしまう場合もあります。条件面だけに注目しないよう、気を付けましょう。
適正な相場を知るためには、専門家の力が欠かせません。M&A仲介会社に相談し、価格で損をしないようにしましょう。
3.税金対策を行う
運送会社のM&Aを行う場合、税金対策を実施しましょう。M&Aでは、譲渡側に高額の税金が発生するためです。また、事業承継を目的にするM&Aでは、相続税や贈与税が猶予・免除される制度もあります。
M&Aで活用できる税金対策としては、以下が挙げられます。
| 税金対策 | |
| 事業承継税制を活用する | 一定の要件を満たすと、事業承継で発生する相続税や贈与税の支払いが猶予・免除される制度 |
| 買い手が必要とする資産のみを売却する | M&Aの対価が低くなるため、税額も抑えられる |
| M&Aの売却益を経費で相殺する | M&Aの売却益が生じた同年度に経費で相殺する |
| 第三者割当増資を活用する | 株式譲渡ではなく、買い手に50%超の議決権を取得させるよう第三者割当増資を行う。増資によって売り手の資金が増加するのみであるため、税金の発生が0になる。 |
活用できる制度は有効活用し、M&Aを進めましょう。
まとめ
運送会社のM&Aは、後継者不足や2024年問題への対応などで注目が集まっています。M&Aを活用することで、売り手にとっては事業承継問題の解決や従業員の待遇改善、経営基盤の安定化といったメリットがあります。買い手にとっては、経営資源の確保やシナジー効果の発揮により、事業をスピーディに拡大できる可能性が高いです。
運送会社のM&Aを行う際は、適切な相手を見つけ、プロのサポートを受けながらM&Aを進めることが大切です。特に、運送業許可については注意が必要であり、自社だけで行うと失敗してしまう可能性があります。
M&AならレバレジーズM&Aアドバイザリーにご相談を
運送会社のM&Aを検討している方は、レバレジーズM&Aアドバイザリー株式会社にご相談ください。レバレジーズM&Aアドバイザリー株式会社には、各領域に特化したコンサルタントが在籍しており、相談から成約まで一貫してサポートします。料金は、M&Aの成約時に料金が発生する、完全成功報酬型です。M&A成約まで、無料でご利用いただけます。(譲受側のみ中間金あり)運送会社のM&Aを成功させたい方は、お気軽にお問い合わせください。