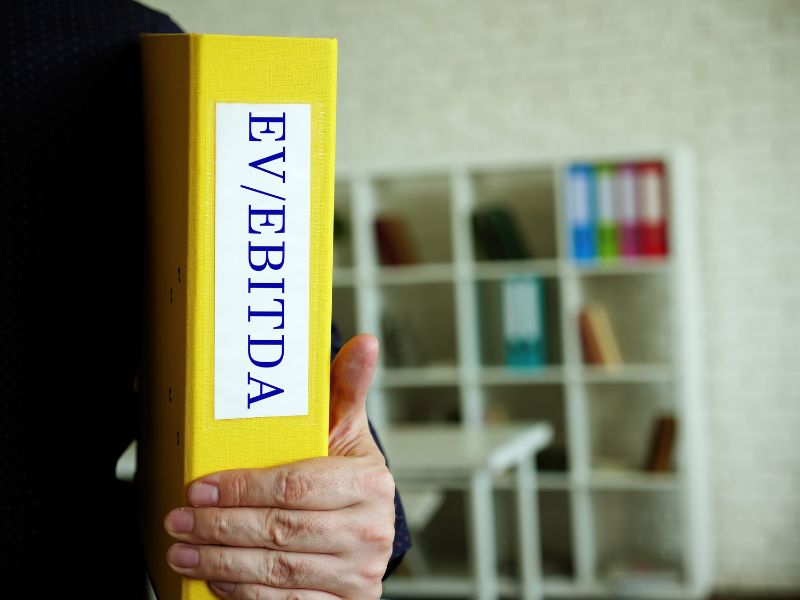このページのまとめ
- 工場を売却する方法には業者に直接売るほか、仲介やM&Aを利用するスキームがある
- 利用しやすい構造・立地であったり、現行の基準に沿ったりしている工場は売れやすい
- 工場を売却する際、解体費用や土壌汚染の調査および浄化費用がかかることがある
- 不動産M&Aで工場を売却する場合、株式譲渡や会社分割を活用することが多い
- 不動産M&Aで工場売却するときは、M&A仲介会社等の専門家を利用するのがおすすめ
「工場はどうやって売却すればよい?」とお悩みの方もいるのではないでしょうか?
工場は直接業者に売却するほか、仲介会社やM&Aを活用して売る方法があります。
本記事では、工場を売却する方法や手順、必要書類、注意点などについて解説します。また、売れやすい工場・敷地の特徴や、売却にかかる費用や税金も紹介。さらに、不動産M&Aのやり方やおすすめの相談先も紹介します。
目次
工場を売却する4つの方法
工場を売却する方法は、主に下記の4つです。
- 不動産会社の仲介で売却する
- 業者に直接売却する
- 買い取り保証付きで売却に出す
- 不動産M&Aをして売却する
それぞれの内容を紹介しますので、自社に合う方法を選ぶ際の参考にしてください。
不動産会社の仲介で売却する
不動産会社に仲介してもらって買い手を探し、工場を売却する方法です。
不動産会社に依頼すると仲介手数料がかかりますが、自分で売却先を探したり価格交渉をしたりする手間が省けます。
業者に直接売却する
業者に直接工場を売却する方法です。工場の買い取りを受け付けている業者を探して、買い取りを依頼しましょう。
買い取り保証付きで売却に出す
不動産会社に仲介を依頼することに加え、買い取り保証をつけて売却する方法です。購入希望者が見つけられなかった場合は、契約時に決めた価格で業者が買い取ってくれます。
不動産M&Aをして売却する
工場を不動産M&Aによって売却する方法です。不動産M&Aにおいては「株式譲渡」か「会社分割 + 株式譲渡」の手法をとることが多いです。
不動産M&Aを行うと高い節税効果が期待できます。
このあとは、不動産会社に依頼して工場を売却する方法をみていきましょう。
不動産として工場売却を行う際の流れ
不動産会社に依頼し、工場を売却する流れは以下のとおりです。
- 工場売却の価格相場を調べる
- 査定を依頼する
- 媒介契約を締結する
それぞれの内容を詳しくみていきましょう。
1.工場売却の価格相場を調べる
まずは、工場を売却したときの価格相場を調べてみましょう。相場を知らないまま不動産会社に売却を任せると、相場よりも安く見積もりを出されても気づけません。不当な価格で購入されることを防ぐためにも、最初は自分で調べることが大切です。
工場売却の価格相場は、チラシやインターネット上に掲載されている売り出し中の物件情報を参考にします。また、国土交通省が運営しているサイト「土地総合情報システム」の情報も参考にしてください。
2.査定を依頼する
工場のおおよその相場価格を把握したら、不動産会社に査定を依頼します。査定金額は業者によって異なるため、複数の不動産会社に依頼することがおすすめです。
また、査定の際、提供しているサービス内容や価格、担当者の誠実さなどをチェックしておきましょう。
3.媒介契約を締結する
査定を依頼した不動産会社の中から、最も良いと思った業者と媒介契約を交わします。
媒介契約とは、工場をはじめとする不動産の売買の契約成立を不動産会社に依頼する際に結ぶ、仲介契約です。工場の売買の契約が成立した場合、業者には仲介手数料を支払います。
不動産会社との契約の種類については、次の段落で解説します。
不動産会社の媒介契約の3つの種類
不動産会社と結ぶ媒介契約には、3つの種類があります。
- 一般媒介契約
- 専任媒介契約
- 専属専任媒介契約
媒介契約の違いは、主に「自己発見取引の可否」「複数業者への依頼の可否」「経過報告の有無」「流通システムへの登録義務の有無」の4つの観点で分けられます。
下記の表は、違いを一覧でまとめたものです。
| (契約名) | 自己発見取引 | 複数業者への依頼 | 経過報告の義務 | 流通システムへの登録義務 |
| 一般媒介契約 | 可 | 可 | なし | なし |
| 専任媒介契約 | 可 | 不可 | あり(2週間に1回以上) | あり(7日以内) |
| 専属専任媒介契約 | 不可 | 不可 | あり(1週間に1回以上) | あり(5日以内) |
特徴を押さえ、自社工場の売却に合った契約方法を選びましょう。
以下で各契約形態の特徴を詳しく解説します。
一般媒介契約
一般媒介契約は、3つの中で最も自由度が高い契約方法です。同時に複数の不動産会社と媒介契約を結ぶことができます。
また、自己発見取引も制限されていないので、自分で購入希望者を探して直接売買をしても構いません。
一般媒介契約は、依頼中のほかの不動産会社を知らせるか否かで2種類に分けられます。ほかに依頼している不動産会社を知らせるのが「明示型」で、知らせないのが「非明示型」です。明示型の契約を選んだ場合、ライバル会社を意識し、積極的に販売活動をしてくれる可能性が高まります。
一般媒介契約のメリット
制限が少ないので、より良い条件で買ってくれる相手を自ら選ぶことが可能です。売却したい工場が魅力的であれば、満足のいく金額での売却が叶います。
また、売却予定の工場が売れやすい物件であれば、依頼先の不動産会社が「我こそは」と販売活動に注力してくれます。不動産会社がより好条件で購入してくれる相手を見つけてきてくれるでしょう。
一般媒介契約のデメリット
一般媒介契約のデメリットは、不動産会社が販売活動をないがしろにする可能性があることです。不動産会社が報酬を得られるのは売買成約時であるため、他社に先を越されてしまうと売却先を探すために費やした労力がすべて無駄になります。一般媒介契約では複数の不動産会社に依頼するため、売れる見込みが薄い工場に関しては販売活動に力を入れない不動産会社も存在するでしょう。
また、一般媒介契約の場合、流通システムへの登録義務はありません。そのため、自社工場の情報を日本全国に広めることは難しくなります。
そのほか、販売活動状況の報告が義務付けられていないこともデメリットの1つです。不動産会社から販売活動の状況報告をすることは基本的にないので、もし現在の進捗を知りたい場合は自分から連絡して確認する必要があります。
専任媒介契約
専任媒介契約においては、選び抜いた1社のみと仲介契約を結びます。複数の不動産会社と契約を結ぶことはできません。
ただし、自己発見取引は禁止されていないため、自分で工場の売却先を探すことも可能です。
専任媒介契約のメリット
1社のみと契約する専任媒介契約の場合、他社に成約の機会を奪われることがないので、依頼した不動産会社が販売活動に精力的に取り組んでくれます。工場の売却先を見つけるために奮闘してくれるでしょう。
また、専任媒介契約では、媒介契約の締結から7日以内に不動産を全国に広める流通システムに登録することが義務付けられています。売却したい工場の情報が全国各地の不動産会社の目に触れるようになるので、売却先が見つかる可能性が高まります。
さらに、2週間に1回の現状報告をしてくれることも、専任媒介契約のメリットの1つです。やりとりをする不動産会社も1社のみなので、最低限の手間で済みます。
専任媒介契約のデメリット
専任媒介契約のデメリットは、悪質な不動産会社にあたってしまったときに生じます。
不動産会社の中には、売買を成立させるために嘘の情報を伝えたり、あえて情報を隠したりする悪徳業者もいます。いわゆる「囲い込み」という違法行為です。契約する不動産会社が1つだけだからといって、違法行為を行う業者もいる可能性があるので注意しましょう。最初の業者選びが非常に大切です。
専属専任媒介契約
専属専任媒介契約では、1つの不動産会社としか契約を交わせないうえ、自己発見取引も禁止されています。専属専任媒介契約は、3つのタイプの中で最も制約が多い媒介契約です。制約が厳しい代わりに、手厚いサポートを受けることができます。
専属専任媒介契約のメリット
専属専任媒介契約の場合、工場が売却できるかどうかは不動産会社の力量にかかっています。責任を一身に負う分、力を入れて販売活動に従事してくれるでしょう。
また、不動産の流通システムへの登録期間は、5日以内と定められています。工場の物件情報を、日本全国の不動産会社にすぐに知らせることが可能です。
販売活動の進捗報告についても、専属専任媒介契約は専任媒介契約より多い頻度で行っています。専属専任媒介契約では報告を1週間に1回の頻度でしてくれるので、現状に合わせた売買戦略の変更をスピーディに行うことができるでしょう。
専属専任媒介契約のデメリット
専属専任媒介契約のデメリットは、専任媒介契約と同様、囲い込みをする業者に気を付けなければならない点です。専属専任媒介契約を結ぶときは、複数の不動産会社にコンタクトをとり、しっかり比較してください。工場売却の成功を左右する選択になるので、熟考したうえで最も信用できる不動産会社に依頼しましょう。
売却相手が見つかりやすい工場の3つの特徴
ここでは、売却先が見つかりやすい工場の特徴を3つ紹介します。
- 工場の構造が単純である
- 建築確認済証と検査済証が交付されている
- 現行の建築基準法に沿っている
それぞれ理由とともに紹介するので、工場売却の際の参考にしてください。
工場の構造が単純である
工場の構造が単純なものだと、同業の売却相手が見つかりやすくなります。
工場の構造が複雑でなければ改築もしやすいので、同業の買い手に好評を得られます。仕切りがあまり多くなければ、スペースも有効活用しやすいでしょう。
建築確認済証と検査済証が交付されている
「建築確認済証」と「検査済証」が交付されている工場であれば、滞りなく売却に進むことができます。
建築確認済証とは、建築基準法や自治体の条例を守っている計画であることを証明する書類です。建築確認を終え、建築確認済証が交付されることによって、工事への着工が可能になります。
検査済証とは、建物の建築にあたって建築基準法を遵守していることを証明する書類です。検査済証は工事完了後の検査をクリアしたときに交付されます。
建築確認済証と検査済証がそろっていれば、工場が違法建築ではないことが証明できます。工場に対する信頼性が高まり、売却相手が見つかりやすくなるでしょう。
現行の建築基準法に沿っている
現行の建築基準法に沿っている工場は、売却先が見つかりやすい傾向にあります。
建築確認済証と検査済証により工場が違法建築ではない証明になると先述しましたが、時が経つにつれ、建築基準法自体が改正される可能性があります。現行の建築基準法に合っていない工場である場合、売却に不利にはたらくことがあるかもしれません。建築から時間が経っている古い工場を売却する際は注意しましょう。
売却相手が見つかりやすい工場敷地の3つの特徴
次に、敷地の特徴にフォーカスして紹介します。売却相手が見つかりやすい工場敷地の特徴は、主に以下の3つです。
- アクセスが良好である
- 車両が利用しやすい環境である
- 土壌が汚染されていない
以下で詳しく解説します。
アクセスが良好である
住居用ではなく工場であっても、アクセスが良好であることは買い手に評価されるポイントです。
工場がアクセスしやすい場所にあれば、製品を運びやすくなります。また、工場での雇用を希望する人も集めやすくなるでしょう。
車両が利用しやすい環境である
工場を稼働する場合、車両を利用することがほとんどです。敷地の周りの道路の幅が十分に広かったり駐車スペースが広かったりと、車両が利用しやすい環境だと、売却相手が見つかりやすくなります。
土壌が汚染されていない
土壌が汚染されていないことが証明できれば、売却先が見つかりやすくなるでしょう。
自社工場が汚染物質を利用していないかを確認してください。少しでも土壌汚染の可能性があるのなら、土壌の調査をすることがおすすめです。万が一あとから土壌汚染が発覚した場合、売買契約が無効になったり、訴訟に至ったりする恐れがあります。
もし土壌汚染があった場合は、専門業者に依頼して土壌浄化をしましょう。
工場を売却するときに必要な8つの書類
ここでは、工場を売却するときに必要な書類を紹介します。
必要となる書類は、主に以下の8つです。
- 登記識別情報通知書(登記済権利証)
- 登記事項証明書(登記簿謄本)
- 固定資産税の納税通知書
- 工場(指定作業場)廃止届出書の控え
- 建築確認済証
- 検査済証
- 公図
- 工場の図面
工場売却の方法や工場の状況によってはほかの書類が求められる可能性もあるので、都度対応しましょう。
登記識別情報通知書(登記済権利証)
「登記識別情報通知書」とは、不動産の所有権取得の登記が完了したときに発行される情報の通知書です。2006年以前は、同じ役割を果たす書類として「登記済権利証」が発行されていました。
登記識別情報通知書(登記済権利証)は、不動産の所有権移転登記の申請を行う際に使用します。
登記事項証明書(登記簿謄本)
「登記事項証明書」とは、不動産の所有者や不動産自体の詳細情報が記録されている書類です。「登記簿謄本」は以前書面で発行されていたときの名称ですが、「登記事項証明書」を指して使用されることもあります。
工場売却の際、登記事項証明書(登記簿謄本)は、自分が工場の所有者であることを証明してくれます。
固定資産税の納税通知書
「固定資産税の納税通知書」は、所有者の納付状況を確認するために必要な書類です。移転登記での登録免許税を算出するときにも必要になります。
通知書は基本的に再発行されないので、自宅に届いたら大切に保管しておきましょう。
工場(指定作業場)廃止届出書の控え
「工場(指定作業場)廃止届出書」は、工場や指定作業場の事業を廃止した際に提出する書類です。
工場・指定作業場を廃止したことを証明するために、控えをとっておいてください。
建築確認済証
「建築確認済証」とは、工場の建築の計画が建築基準法などを遵守している適切なものだったことを証明する書類です。買い手が工場の安全性を確かめる安心材料になります。
検査済証
「検査済証」とは、工事が完了したあとの検査に合格したときに発行される書類です。
検査済証は、工場が建築基準法に則って建築されたことを証明します。
違法建築ではないことが分かるので、売却先探しにプラスにはたらきます。
公図
「公図」とは、法務局が管理している法的な図面です。
公図には土地の形状や地番、道路、水路などが示されています。公図を確認し、自分が所有している土地の範囲を確認しましょう。
もし認識していた所有権の範囲と公図の内容にズレがあった場合は、工場売却の前にズレを修正する必要があります。法務局に相談して、実測図を作成してください。
工場の図面
「工場の図面」は、工場の物件情報を作成するために必要です。
工場の設計が分かる設計図やリフォーム図などを用意しましょう。
工場売却にかかる3つの費用
ここでは、工場売却をする際にかかる費用を3つ紹介します。
- 工場の解体費用
- 土壌汚染の調査費用
- 土壌の浄化費用
上記3つの費用は必ずしもかかるわけではありません。稼働していた工場の内容によるので、必要かどうか確認してください。
工場の解体費用
工場をそのまま売却せず土地として売却する場合は、工場の解体費用が必要です。工場を解体し、更地にしてから売却します。
更地にすれば土地活用の自由度が上がるため、買い手が見つかりやすくなる可能性があります。
土壌汚染の調査費用
工場が建っている土壌が汚染されていないかどうかを確認する調査にかかる費用です。有害物質を扱っていた工場を閉鎖するケースなど、土壌汚染調査が法律で義務付けられている場合は、必ず土壌汚染調査を実施してください。
義務付けられていない場合も、土壌汚染の可能性が少しでもあれば調査しておくことがおすすめです。
土壌汚染調査を実施して安全だということが証明できた状態で売却に出すと、買い手が見つかりやすくなります。
土壌の浄化費用
土壌汚染調査の結果、汚染されていることが判明したら、土壌の浄化費用がかかります。業者に依頼して土壌の浄化を行いましょう。
もし土壌汚染を隠蔽して工場を売却した場合、罰則を科されたり訴訟問題に発展したりする危険性があります。
工場売却にかかる5つの税金
法人が工場を売却した場合、売却益に対してかかる税金は、主に以下の6つです。
- 法人税
- 法人住民税
- 法人事業税
- 地方法人税
- 消費税
かかる税金を知らずに工場売却すると、あとから想定外の納税額に頭を悩ませることになります。
納めるべき税金について、あらかじめ把握しておきましょう。
法人税
「法人税」とは、法人の事業活動によって得た所得に対して課せられる国税です。
法人税は、課税所得に規定の税率をかけて算出します。なお、税率は法人の種類や資本金などによって変動します。
法人住民税
「法人住民税」とは、事業所が所在する地方自治体に対して法人が納める地方税です。
法人住民税は、法人税割に均等割を足して算出します。法人税割は法人税の金額をもとに計算されます。均等割は法人の規模に応じて課税される仕組みです。
法人事業税
「法人事業税」とは、法人の事業活動に対して、法人が所在する都道府県から科される地方税です。
法人事業税は、課税所得に法人事業税率をかけて算出されます。法人事業税率は資本金額や出資金額によって変動します。
地方法人税
「地方法人税」とは、法人の事業活動で得た所得に対して課されます。地方法人税は、地域間の格差を縮小することを目的とする国税です。
地方法人税の税率は、2019年10月1日以後に開始する課税事業年度からは10.3%の一律です。
消費税
「消費税」は、土地のみの売却であればかかりませんが、工場を売却する場合は課税されます。
ただし、2期前の課税売上が1,000万円に満たない場合は免除対象です。
工場を売却する際の注意点
工場を売却する際は、以下の5点に注意が必要です。売却する前に、確認しておきましょう。
- 土壌汚染がないか確認する
- 工場の区域区分を確認する
- 敷地境界を確定しておく
- 用途不適格でないか確認する
- 各種証明書があるか確認する
それぞれの内容を、詳しく紹介します。
土壌汚染がないか確認するる
化学プラントや排水処理施設など、工場によっては過程で有害物質を使用している場合があり、土壌汚染の有無を調査することが義務付けられています。
浄化を行わずに売却後に汚染が見つかった場合、損害賠償責任が問われる可能性もあるため、注意が必要です。
調査期間が長くなることもあるので、早めに調査の手配をしましょう。
調査により土壌汚染が認められた場合、土の入れ替えや不溶化処理、吸着処理などによって浄化対策をしてください。
工場の区域区分を確認する
売却時は、工場の区域区分の確認が必要です。
区域区分とは都市計画法で指定されたエリアのことを指し、「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引き区域」に分けられます。
このうち市街化調整区域に該当する場合は、居住用不動産は原則建てることができません。たとえば、工場を解体して家を建てる目的では購入できないことになります。
この区域にある工場は、工場として利用する買い手を探すことが必要です。
敷地境界を確定しておく
工場の売却では、敷地境界の確定が重要です。
境界を明示せずに土地を売買してしまうと、買主と隣地の所有者の間でトラブルが発生する可能性があります。安心して購入してもらうためにも、境界を確定しなければなりません。
境界を確定するためには、境界標などの検証が必要です。検証に時間がかかる場合は土地家屋調査士へ依頼して測量を実施し、境界線を確定しましょう。
用途不適格でないか確認する
古くからある工場の場合、用途不適格になる物件があります。
用途不適格とは、建築時点では工場として利用できる地域であったものの、その後の法改正で用途地域が変更され、不適格になることです。用途不適格の物件の場合であっても、新たな用途地域に適合した用途で使用することに問題はありません。
一方、工場として買い取ってもらうためには都道府県庁もしくは市役所の担当部署で既存不適格台帳に登載することが必要です。既存不適格台帳に登載すれば、買い手は工場として使用し続けることができます。
各種証明書があるか確認する
建築確認済証や検査済証など、工場が適法であることを示す各種証明書がそろっているかどうかを確認してください。
これらの証明書を紛失してしまっている場合、増改築や改修、用途変更をしたい際に不都合が生じます。各種証明書がない場合は、台帳記載事項証明書の取得やガイドライン調査を求められることがあります。
また、工場に違法な状態があれば、解消しておくことが必要です。
たとえば、建築確認済証を取得しないまま増築している箇所がある場合、売却できても、何か事故が発生した際には買い手が責任を問われます。
違反建築物を購入する買い手は、銀行からの融資が認められない場合もあるでしょう。
そのような事態を避けるため、違法な増築部分を事前に解体をしておくなどの対応が求められます。
不動産M&Aによる工場の売却方法
工場の売却は、不動産M&Aという方法もあります。
一般的なM&Aにおいても買収対象に不動産が含まれることもありますが、メインの目的はあくまで事業を取得することです。しかし、不動産M&Aの場合は、不動産の取得をメインの目的として対象企業も含めたM&Aを実施します。
不動産M&Aによる工場売却は、主に以下のどちらかの手法で行います。
- 株式譲渡
- 会社分割 + 株式譲渡
それぞれの方法を詳しくみていきましょう。
株式譲渡による方法
株式譲渡とは、株式を第三者に売却するM&Aの手法です。
不動産M&Aでは、目的の工場を所有する企業の全株式を買い手企業が取得し、完全子会社とします。
買い手企業は、子会社を通して不動産を所有するという流れです。
子会社に利益を生み出す見込みがない場合は、不動産を親会社に移転させたあとに、子会社は解散させます。
会社分割 + 株式譲渡による方法
会社分割と株式譲渡を組み合わせた手法です。
会社分割とは、会社が行っている事業の一部またはすべてを切り離し、ほかの会社に移転する手法です。会社分割には、既存の会社に事業の権利を移す「吸収分割」と、新設の会社に移す「新設分割」の2種類があります。
不動産M&Aでよく利用されるのは、新設分割です。
会社を新設して工場を所有する事業を移転させて、その新設会社の経営権を株式譲渡によって買い手へ移します。
不動産M&Aでの売却にかかる税金
不動産M&Aをした際、売却益に対してかかる税金は以下のとおりです。
法人の場合は「法人税」
株主が法人の場合は、「法人税」がかかります。
法人税は、譲渡益に法人税率をかけて算出します。法人税率は29〜42%ほどです。
個人の場合は「所得税」と「住民税」
株主が個人の場合、納める税金は「所得税」と「住民税」です。
所得税と住民税の計算には、譲渡益の金額を使用します。譲渡益は、譲渡額から取得額とかかった経費を引いて算出します。
所得税の計算式は、「譲渡益×15%」です。
住民税の計算式は、「譲渡益×5%」です。
【売り手側】不動産M&Aのメリット・デメリット
ここでは、売却側の不動産M&Aを行うメリットとデメリットを紹介します。
売り手側が得られる4つのメリット
不動産M&Aによって工場を売却するときのメリットは、主に以下の4つです。
- 節税効果が見込める
- 解体費用がかからない
- 後継者問題が解決できる
- 従業員の雇用を継続させられる
順に解説します。
節税効果が見込める
不動産M&Aを行う大きなメリットは、節税効果が得られることです。
不動産M&Aではなく一般的な方法で工場売却をした場合、法人税・法人住民税・法人事業税・地方法人税・消費税を納める必要があります。
一方、株主が法人の不動産M&Aでは、法人税のみです。株主が個人の場合でも所得税と住民税です。不動産M&Aであれば納税の負担が軽減されるので、手元に残る利益が多くなります。
解体費用がかからない
不動産M&Aを行うメリットは、工場の解体費用がかからないことです。
工場を売却する場合、閉鎖にともなって解体が必要になることがあります。しかし不動産M&Aでは会社や事業の権利とともに不動産である工場も移行されるため、解体費用はかかりません。
後継者問題が解決できる
不動産M&Aを選ぶメリットの1つは、後継者問題が解決できることです。
もし後継者がいないために工場を閉鎖せざるを得ない状況だった場合、不動産M&Aをすれば会社や事業を存続させることができます。
不動産M&Aによって後継者に承継できれば、これまで積み上げてきた歴史や技術などを守り続けることができるでしょう。
従業員の雇用を継続させられる
不動産M&Aを行うメリットは、従業員の雇用を継続できることです。
工場をただ閉鎖して売却した場合は、従業員は職を失うことになります。しかし、不動産M&Aを実施して会社や事業を第三者に引き継ぐと、従業員も譲受側の企業に移行されます。
今まで工場で働いてくれていた従業員の雇用を守れることは、不動産M&Aを行う大きな意義となるでしょう。
売り手側に生じる2つのデメリット
不動産M&Aによって工場を売却するときの懸念点は、以下の2つです。
- 手続きが増える
- 時間がかかる
不動産M&Aにはたくさんのメリットがあるので、実施にあたって大変なところをあらかじめ押さえて、準備に取り掛かりましょう。
手続きが増える
不動産M&Aは会社や事業を譲り渡すことになるため、単に工場を売却するよりも手続きが多くなります。取締役会・株主総会を実施したり、株主名簿の書き換え請求など、多数の手続きが発生します。
不動産M&Aを行う場合も、サポートしてくれる支援機関を利用することがおすすめです。M&A仲介会社を利用すれば、相談から成約まで一貫してサポートしてくれます。
時間がかかる
不動産M&Aのデメリットの1つは、時間がかかってしまうことです。
踏むべき手続きが多い分、売却完了までに多くの時間を要します。
【買い手側】不動産M&Aのメリット・デメリット
ここでは、不動産M&Aによって工場を取得する買い手側のメリットとデメリットについて解説します。
買い手側が得られる3つのメリット
不動産M&Aによって工場を取得するときのメリットは、主に下記の3つです。
- 節税効果が期待できる
- 従業員やノウハウを獲得できる
- 相場よりも安く購入できる可能性がある
以下で一つずつ解説します。
節税効果が期待できる
工場を不動産M&Aで取得する大きなメリットは、節税効果があることです。
一般的な方法で工場売却をする場合には、登録免許税や不動産取得税、印紙税などを納める必要があります。しかし、株式譲渡を行う不動産M&Aにおいては、買い手側に税金はかかりません。
従業員やノウハウを獲得できる
不動産M&Aでは工場だけでなく、従業員も買い手企業に移行します。技術を備えた従業員を獲得できることは、不動産M&Aを行うメリットだといえるでしょう。
専門性の高い工場で働いていた従業員のノウハウ獲得により、会社のさらなる成長を目指している場合は、不動産M&Aを検討してください。
相場よりも安く購入できる可能性がある
不動産M&Aは、工場の売却側にとっても節税効果がある方法です。工場売却で発生する手取り額が節税効果により大幅な増加が見込まれる場合、売却額を下げて相場と比べて安価な価格で購入できる可能性があります。価格交渉も比較的応じてくれる傾向があるでしょう。
買い手側に生じる2つのデメリット
不動産M&Aによって工場を取得するときに発生する懸念点は、以下の2つです。
- 負債を引き継ぐリスクがある
- 混乱を招く可能性がある
不動産M&Aを検討する際は、あらかじめリスクを把握し、対策をしておく必要があります。
負債を引き継ぐリスクがある
不動産M&Aでは工場を譲受するだけではなく、マイナスの資産も引き継ぐ可能性があります。「どのような負債があるのか」「負債を上回るメリットがあるのか」などを事前にしっかり確認しましょう。
また、簿外債務という隠された負債があとで発覚することも。想定外の債務を抱えることになった場合、経営が傾いてしまう恐れもあります。不動産M&Aを実施する際は、相手の会社に対して入念な調査をしましょう。
混乱を招く可能性がある
不動産M&Aの実施は、会社に大きな変化をもたらします。売り手側の従業員が入ってきたり、社内ルールが変更されたりすることにより、現場が一時的に混乱する可能性があります。
不動産M&Aを行う場合は、経営統合プロセスの計画を組みましょう。綿密な計画を立てて経営統合を円滑に進めることができれば、不動産M&Aによるシナジー効果が得られるはずです。
不動産M&Aに関する6つの相談先
不動産M&Aの実施には、専門家のサポートが必要です。
相談先は主に以下の6つです。
- 中小企業診断士
- ファイナンシャルプランナー
- 地域の商工会議所や商工会
- 担当の士業専門家
- 事業承継・引継ぎ支援センター
- M&A仲介会社
ここでは、不動産M&Aに関する相談先を紹介します。
中小企業診断士
中小企業診断士とは、中小企業の経営課題に対してアドバイスをする専門家です。
買い手を探す前に相談すれば、経営診断で事業の問題点を洗い出してくれます。経営戦略を見直して改善を行うことで、企業や事業の価値を高めることが可能です。
「できるだけ良い条件で自社を売却したい」と考えている場合には、中小企業診断士に相談してみましょう。
また、中小企業診断士はM&Aが合意に至り、最終契約が結ばれたあとの統合手続き(PMI)もサポートします。M&Aの実施後に従業員へのヒアリングなどコミュニケーションを行い、メンタル面をケアするなどの役割も担います。
ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナーとは、税金や保険、年金などお金に関する幅広い知識を持ち、ライフプランの設計や資産運用・形成についてアドバイスをする専門家です。
不動産や事業承継に通じているファイナンシャルプランナーも存在しており、幅広い知識でM&Aの相談に対応します。
工場の経営者が引退後の収入を得るために不動産M&Aを検討する場合、その後の資産運用も含めた相談ができるでしょう。
銀行や証券会社などに所属しているファイナンシャルプランナーであれば、社内の専門部署を紹介してもらえる場合もあります。
地域の商工会議所や商工会
地域の商工会議所・商工会に相談するという方法もあります。
全国の都道府県(商工会は町村部)に設置されており、会員であれば無料で相談ができます。
中小企業に関する相談実績が豊富であり、買い手・売り手の双方が中小企業のM&Aの場合、相談するメリットも大きいでしょう。
担当の士業専門家
顧問弁護士や顧問税理士、公認会計士など、日ごろから業務を依頼している専門家がいればM&Aについても相談ができる場合があります。M&Aの支援がサービスの対象範囲かどうか確認してみましょう。
弁護士は法務の専門家として企業および経営者の代理人となり、M&Aの交渉にあたります。トラブルの際も、法的観点からアドバイスをしてくれます。
税理士や公認会計士は、税務や会計の相談ができます。企業価値の算定や節税のアドバイス、売買価格の相談など、さまざまなサポートを受けられるでしょう。
事業承継・引継ぎ支援センター
事業承継・引継ぎ支援センターは、全国に設置されている公的機関です。
中小企業診断士や金融機関OBなど経験豊富なプロフェッショナルが在籍し、中小企業の事業承継に関するあらゆる相談に無料で対応しています。
「第三者承継支援」では、買い手企業の紹介から成約に至るまでサポートしています。後継者が不在で、工場売却を含む不動産M&Aを考えている方におすすめです。
M&A仲介会社
M&A仲介会社はM&Aのサポート業務を専門に扱う会社です。相談から相手先候補の紹介、交渉、成約まで、一貫したサポートを受けられます。
会社ごとに実績や得意分野はさまざまなので、自社に合ったM&Aの仲介会社を選ぶことが大切です。
不動産M&Aの実績があり、自社に合うM&A仲介会社を選べば、適切なM&Aの相手候補先を紹介してもらえます。
思い当たる相談先がなく迷ったときは、まずM&A仲介会社を探してみるのもよいでしょう。
まとめ
売却相手が見つかりやすい工場の特徴は、単純な構造であることや、現行の基準に沿っていて証明書が揃っていることです。
工場がある敷地は、アクセスが良好であったり、土壌汚染などの問題がなかったりすると売れやすくなります。
工場を売却する方法には、不動産会社の仲介を利用して売却したり業者に直接売ったりする方法のほか、不動産M&Aを行って売却する方法があります。
不動産M&Aを行う場合、通常の工場売却とは手順が大きく異なります。そのため、M&Aに関する専門的な知識を持った仲介会社の利用がおすすめです。
M&AならレバレジーズM&Aアドバイザリーにご相談を
レバレジーズM&Aアドバイザリー株式会社は、各領域に特化したM&Aサービスを提供する仲介会社です。各領域で実績を積み重ねたコンサルタントが、相談から成約まで一貫してサポートを行います。工場を含む不動産M&Aの相談も無料で行いますので、お気軽にお問い合わせください。