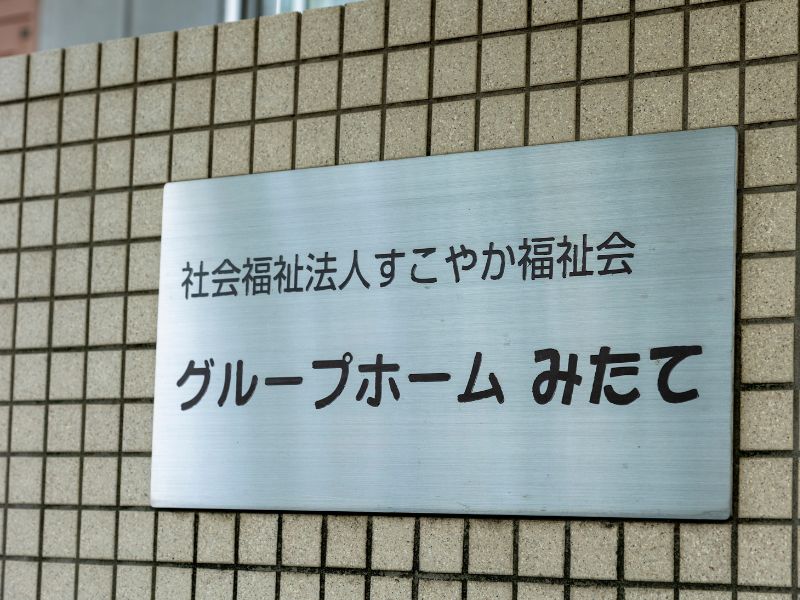このページのまとめ
- 建設業界では後継者問題により統廃合が活発に行われている
- 海外進出を目的としたM&Aや建設業界以外とのM&Aが増加している
- 経営管理責任者の引退により売却するケースでは、後任探しが必要
- 安定した取引先・高い技術力・優秀な人材を備える企業はM&Aにおいて高く評価される
「建設業界のM&A事情について知っておきたい」と考えている経営者も多いことでしょう。建設業界ではM&Aが活発に行われており、建設業同士だけでなく異業種とのM&Aも増えています。
本コラムでは、建設業界のM&A状況やM&Aを行うメリット・デメリット、M&Aの事例、注意点について解説します。M&Aを成功させるためにも、ぜひ参考にしてください。
目次
建設業界のM&Aの状況
従来、建設業界ではあまり活発にM&Aは実施されていませんでした。その理由としては、規模を拡大してもコスト削減効果が見込みにくいことが挙げられます。
たとえば工場でものを生産するときであれば、規模を拡大することで設備や仕入れにかかる費用を削減し、製品あたりのコストを抑えて、利益を拡大できます。建設業界でも材料などの仕入れをまとめて行うことである程度はコストを抑えられますが、実際に建設作業を行う作業員は減らせないため、規模を拡大すればするほどコスト削減につながるというものではありません。
また、入札機会が減ってしまうことも挙げられます。後述しますが、建設関連の資金のうちの多くの部分を政府関連や公共事業が占めており、透明性・公正性を保つために入札制度で依頼業者が決まります。複数の企業がM&Aにより統合して一企業となると、入札の機会が減少し、利益の機会も減ってしまうことになりかねません。
しかし、現在では建設業界でもM&Aが活発に行われるようになってきました。M&Aが盛んになった背景としては、次の事情が挙げられます。
- 後継者問題による統廃合が多い
- 建設業界以外の企業とのM&Aが増えている
- 海外進出を目的としたM&Aも増加傾向にある
それぞれの事情について解説します。
後継者問題による統廃合が多い
多くの中小企業では、後継者問題に直面しています。家業としての意識が希薄化していることや、少子化により跡継ぎとなる子どもや親族がいないことなどの理由により後継者が見つからず、事業売却を考える経営者も少なくありません。
建設業界も同様です。中小企業では後継者問題が深刻化しており、廃業を視野に入れている会社も増えてきました。また、経験ある作業員が高齢化し、現場に出ることが難しくなっている会社もあります。人材の若返り、そして後継者問題の解消のためにも、M&Aによる事業の統廃合が増えています。
建設業界以外の企業とのM&Aが増えている
建設業界以外とのM&Aが増加しています。かつては、事業規模の拡大や対応分野・エリアを増やすために、業務内容をほぼ同じくする企業同士がM&Aを実施することが一般的でした。たとえばローカルゼネコンが近隣エリアのローカルゼネコンと合併し、対応エリアを拡大することがあります。設備などの仕入れにかかるコストを削減できるだけでなく、事業規模が拡大することで地域における影響力が高まり、受注しやすくなるメリットが得られるでしょう。
現在でも建設業界内のM&Aは多く実施されていますが、事業の多角化やシナジー効果の獲得を目指して、異業種とのM&Aも増えてきました。建設会社とM&Aを実施することが多い異業種としては、次の業種が挙げられます。
- 設備関連企業
- 不動産業
- IT業界
それぞれの業種と建設会社がM&Aを実施することで、どのようなメリットや効果を期待できるのか解説します。
設備関連企業
建設会社が建築設備企業とM&Aを実施するケースは少なくありません。設備を内製することで、仕入れコストの削減や、より自社に合った設備を製造して独自性を発揮する、設備設計から建築までをワンストップで行い工期を短縮できるなどのメリットが得られます。
また、近年は設備関連企業とのM&Aも増えてきました。たとえば設備工事会社と提携するなら、設備の提供から工事まで一貫して対応できるため、取引先へのサービスが拡充できます。他にも、電気工事会社や通信工事会社、管工事会社、空調設備工事会社などの建設に関わる工事会社と連携することで、周辺領域へ進出するケースもあります。
不動産業
建設業界と不動産業界のM&Aも増えています。たとえば、建設会社と不動産販売会社が提携すれば、マンションや建売住宅、オフィスビルなどの建設から販売までがシームレスに実現できます。設計段階から宣伝活動を行えるため、時間的な無駄がなくなるだけでなく、早期に資金を確保でき、建築がスムーズに進むようになるでしょう。
また、ビルメンテナンス会社と提携すれば、建設から管理まで一貫して請け負うことも可能です。販売して終わりといった従来の建設会社の在り方から、管理を通して長期的にクライアントと関わり、利益も長期的に得る仕組みへと発展できるのもメリットです。
ビルメンテナンス会社にとっても、建設会社と関わることには大きなメリットがあります。設計段階から関わることで、メンテナンスしやすいビルを完成させられます。事業領域を拡大する不動産業とのM&Aは、今後も増加するといえるでしょう。
IT業界
建設業界とIT業界が提携するケースも増加しています。たとえば、設計システム会社が設計事務所を買収し、事業範囲を広げるだけでなく、重複業務を削減して時短やコストダウンを実現するケースもあります。
また、セキュリティ機器の販売会社が電気工事会社を買収し、機器販売から施工までをワンストップ対応できるようにするケースも見られるようになってきました。サービスの依頼やサポートの問い合わせが一元化されるため、クライアント側にとっても、「メンテナンスを受けたいけれど問い合わせ先がわからない」といった状況がなくなり、利用しやすくなります。
海外進出を目的としたM&Aも増加傾向にある
海外進出を目的とし、海外基盤のある企業とM&Aを実施する企業が増加しています。実際のところ、少子化などにより、建設業界の国内需要は今後減少する可能性があります。また、高齢化や人口減少により労働人口が減少することで、国内供給の増加が難しい点も課題です。
そのため、建設業界で生き残るためには、海外に目を向けることが必要とされています。譲渡企業・譲受企業のいずれかが外国企業である「クロスボーダーM&A」なども、建設業界のトレンドの一つといえます。
そもそも建設業とは
日本のGDP(国内総生産)の約1割は建設業界関連といわれています。巨額の資金が動く建設業とは、そもそもどのような業種なのでしょうか。定義や含まれる工事内容、市場規模について解説します。
参照元:一般社団法人 日本建設業協会「建設業ハンドブック2021」
建設業の定義
建設業法では、建設業を「元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業」と定めています。つまり、建設工事が完成するまでに関わるすべての行為は、いずれも建設業に関わる業務です。
国土交通省では、建設業許可が必要な29種類の業種区分を定めています。
建設工事の種類に注目すると、上記の建設業許可が必要な業種区分を次の3つに大別できます。
- 建築工事
- 土木工事
- 機械装置などの工事
それぞれの工事に含まれる業務について見ていきましょう。
参照元:国土交通省「建設業許可の業種区分」
建築工事
建築工事とは、地面より上の工事全般を指します。たとえば戸建住宅やマンション、オフィスビルなどを建てる工事は、いずれも建築工事です。建築工事に含まれる工事内容については、以下をご覧ください。
| 建設工事の種類 | 工事内容 |
| 建築一式工事 | 総合的な企画や調整のもと、建築物を建設する工事 |
| 大工工事 | 木材の加工や取付により建造物を作る工事 |
| 左官工事 | 工作物にモルタルや漆喰などを塗る、あるいは吹付や貼付を行う工事 |
| 石工事 | 石材やコンクリートブロックなどの加工・積方により工作物を建築、あるいは工作物に石材を取り付ける工事 |
| 屋根工事 | 瓦やスレートなどを使って屋根を葺く工事 |
| タイル・れんが・ブロック工事 | れんがやコンクリートブロックを用いて工作物を作る工事。工作物にタイルやれんがなどを取り付ける工事。コンクリートブロック積み工事・サイディング工事などを含む |
| 鋼構造物工事 | 鋼板などの加工や組立てにより工作物を作る工事。鉄骨工事や屋外広告工事などを含む |
| 鉄筋工事 | 棒鋼などの鋼材を加工し、接合や組立てる工事 |
| しゅんせつ工事 | 河川や港湾などの水底をしゅんせつする工事 |
| 板金工事 | 金属薄板などを加工し、工作物に取り付ける工事。建築板金工事など |
| ガラス工事 | 工作物にガラスを加工し、取り付ける工事 |
| 塗装工事 | 塗料や塗材を工作物に取付、塗付、張付などを行う工事。布張り仕上工事やライニング工事、路面標示工事などを含む |
| 防水工事 | アスファルトやモルタル、シーリング材により防水加工を行う工事 |
| 内装仕上工事 | 木材や石膏ボード、吸音板、たたみ、カーペットなどを使って建築物の内装を仕上げる工事。インテリア工事・たたみ工事・ふすま工事・家具工事・防音工事などを含む |
| 機械器具設置工事 | 機械器具の組立てなどにより、工作物を建設する工事。もしくは工作物に機械器具を取り付ける工事。プラント設備工事・サイロ設置工事・立体駐車設備工事・舞台装置設置工事などを含む |
| 建具工事 | 工作物に木製あるいは金属製の建具を取り付ける工事。サッシ取り付け工事やシャッター取り付け工事、自動ドア取り付け工事などを含む |
| 解体工事 | 工作物を解体する工事 |
土木工事
土木工事とは、地面より下や地面の工事を指すことが一般的です。たとえば、道路や河川、橋梁などを作る工事は土木工事に該当します。
| 建設工事の種類 | 工事内容 |
| 土木一式工事 | 総合的な企画や調整のもと、土木工作物を建設する工事 |
| とび・土木・コンクリート工事 | 足場の組立て、機械器具・建築資材などを使って重量物を運搬して鉄骨などを組み立てる工事、くい打ち・くい抜き、コンクリートにより工作物を建造する工事 |
| 舗装工事 | アスファルトや砂利、コンクリート、砕石などで道路などを塗装する工事 |
| 造園工事 | 整地や樹木の植栽、景石の据付などにより、庭園や公園、緑地帯などを作る工事。植栽工事・地ごしらえ工事・緑地育成工事などを含む |
| さく井工事 | さく井機械などを用いて、さく孔・さく井を行う工事。あるいはさく井工事に伴う揚水設備の設置を行う工事。さく井工事・温泉掘削工事・天然ガス掘削工事などを含む |
機械装置などの工事
建物そのものの工事や土木工事に分類されない工事もあります。機械装置や設備などに関わる工事としては、以下の種類が挙げられます。
| 建設工事の種類 | 工事内容 |
| 電気工事 | 発電設備や香典設備、構内電気設備などを設置する工事。照明設備や電車線工事、信号設備工事なども含む |
| 管工事 | 冷暖房設備や空気調和設備、給排水設備などの設置工事、水やガス、水蒸気などを送配する設備の設置工事。ダクト工事や浄化槽工事なども含む |
| 熱絶縁工事 | 工作物や工作物の設備を熱絶縁する工事。冷暖房設備やウレタン吹付断熱工事などを含む |
| 電気通信工事 | 有線電気通信設備や無線電機通信設備、情報設備、ネットワーク設備などの設置工事。包装機械設備工事やデータ通信設備工事などを含む |
| 水道施設工事 | 上水道や工業用水道などのための取水・浄水・配水施設を作る工事。取水設備工事、下水処理設備工事などを含む |
| 消防施設工事 | 火災警報設備や消火設備などを設置・取り付ける工事。スプリンクラー設置工事、屋外消火栓設置工事などを含む |
| 清掃施設工事 | ごみ処理施設やし尿処理施設を設置する工事 |
なお、建設業許可が必要な工事を3つの区分に分類しましたが、工事内容によっては建築工事と土木工事、その他の工事のいずれかに明確に分けられないものや複数の工事にまたがるものがあります。そのため、紹介した区分に明確に当てはまらないケースも生じます。
また、工事に関わらない形の建設会社も少なくありません。主な業態・業者としては、以下のものが挙げられます。
建設業の市場規模
建設業界の市場規模は約60兆円です。そのうち、政府関連の投資が約4割、民間投資が約6割を占めます。なお、政府関連の投資には、公的施設の建築や、震災の復旧・復興に関わる資金なども含まれます。
| 年度 | 建設投資額(兆円) | 政府による投資額(兆円) | 民間による投資額(兆円) |
| 2012 | 42.4 | 16.0 | 26.4 |
| 2013 | 48.3 | 18.4 | 29.9 |
| 2014 | 47.5 | 18.8 | 28.9 |
| 2015 | 56.6 | 20.2 | 36.4 |
| 2016 | 58.7 | 21.0 | 37.7 |
| 2017 | 61.3 | 21.8 | 39.5 |
| 2018 | 61.8 | 21.6 | 40.2 |
| 2019 | 62.5 | 22.7 | 39.8 |
| 2020 | 60.9 | 24.0 | 37.0 |
| 2021 | 62.7 | 24.5 | 38.1 |
1992年の84兆円をピークに、建設投資額は減少傾向にありました。2010年には約半分程度にまで下がりましたが、東日本大震災の復旧・復興を目的としたニーズや東京オリンピック関連の工事増、民間投資の回復などにより、近年では増加傾向が見られています。
参照元:日本建設業連合会「建設業ハンドブック2021」
開業に必要な許可
建設工事を行うときには、建設業許可を取得することが必要です。上記でも紹介したとおり、建設業許可には土木と建築の一式工事許可2種類と、専門工事許可が27種類があります。
一式工事許可とは、受注から完成までのすべての業務を請け負うときに必要な工事許可です。たとえば建築一式工事許可を取得していると、鉄筋工事や内装仕上工事などもまとめて対応できます。そのため、自社で一貫して建設を請け負うときは一式工事許可、工程ごとの専門的な工事のみ請け負うときは専門工事許可と使い分けることが一般的です。
ただし、工事費用が税込み500万円に満たない場合は、建設業許可を取得していなくても工事を行えます。また、一式工事の場合は、工事費用が税込み1,500万円に満たないとき、もしくは150平米未満木造住宅の工事のときは一式工事許可は不要です。たとえば、建具の製造・設置のみを請け負う会社や、個人住宅の小規模リフォームを請け負う会社などは、建設業許可なしに業務を行えます。
また、建設業許可には、一般建設業許可と特定建設業許可の2つの種類があります。それぞれの違いについて見ていきましょう。
一般建設業許可
一般建設業許可とは、次に紹介する特定建設業許可以外の建設業許可のことです。許可不要で行える税込み500万円未満の建設工事や、税込み1,500万円未満もしくは150平米未満の木造住宅の建築一式工事を行うときに、一般建設業許可を取得します。営業所が1つの都道府県のみにあるときは都道府県知事、2つ以上の都道府県に営業所を設置するときは国土交通大臣に許可申請を提出します。
なお、建設業許可制度は、建設業者の資質向上を目的として設けられました。許可を受ける際には、次の4つの要件を満たしているか確認されます。
- 経営能力
- 業種ごとの技術力
- 誠実性
- 財産的基礎
すべてを満たしていることが確認されると、申請した業種の一般建設業許可を取得できます。なお、業務ごとに建設業許可を取得する必要があり、申請ごとに要件を満たしているかが確認される点に注意が必要です。また、建設業許可は5年ごとに取得が必要で、自動更新されません。
特定建設業許可
特定建設業許可とは、発注者から直接請け負う工事1件の金額が税込み4,500万円以上となる下請契約を締結するとき、建築工事業の場合は税込み7,000万円以上のときに取得する許可です。なお、建設工事の金額には材料費用は含まれません。
営業所を1つの都道府県のみに設置するときは都道府県知事、2つ以上の都道府県に設置するときは国土交通大臣に許可申請を提出します。また、一般建設業許可と同じく許可を受ける際には経営能力と業種ごとの技術力、誠実性、財産的基礎の4つの要件が確認されます。
特定建設業許可も5年ごとに取得が必要です。法令違反などを犯すと許可が取り消されることがありますが、取り消しから5年以内は再申請ができません。継続して建設業に関わるためにも、法令を遵守し、建設業許可を正しく申請・更新することが必要です。
建設業の取引フロー
建設業にはさまざまな業種が含まれるだけでなく、不動産業やインフラ関連業などの他業界とのつながりもあり、取引フローが複雑化する傾向にあります。建設規模に分けて、一般的な取引フローを紹介します。
大規模建設の場合
売上高が1兆円を超えるスーパーゼネコンが関わるような大規模建設工事は、次のようなフローで取引が進みます。
- 地方公共団体や民間企業がゼネコンに発注する
- ゼネコンがサブコンに発注する
ゼネコンが設計業を担うこともありますが、専門の設計業者が設計を担当することもあります。その場合は、地方公共団体や民間企業は、ゼネコンと設計業者の双方に発注しなくてはいけません。
なお、ゼネコンとはゼネラル・コントラクター(general contractor)の略語で、総合工事請負業者を指します。基本的には元請業者となり、工事依頼を受け、自社あるいはサブコンに発注して建築物などを完成させます。
一方、サブコンとはサブコントラクター(subcontractor)の略語です。足場工事や管工事、電気工事などの特定分野にのみ対応する専門工事業者を指します。
中小規模建設の場合
中小規模の建設工事は、不動産ディベロッパーが主軸となって進めていくことが一般的です。取引フローは以下のとおりです。
- 不動産ディベロッパーがゼネコンに企画・発注する
- ゼネコンが不動産ディベロッパーに納品する
- 不動産ディベロッパーが顧客に販売する
ゼネコンから納品される前に販売活動を始めることもあります。たとえば不動産ディベロッパーが大規模な宅地造成やマンション建築などを企画し、ゼネコンに発注すると同時に販売活動を開始し、完成と同時に居住できるようにスケジュールを調整するケースもあります。
建設業界でM&Aを実施するメリット
建設業同士、あるいは建設業と異なる業界の企業がM&Aを実施することで、さまざまなメリットを得られます。売り手企業と買い手企業に分けてメリットを紹介します。
売り手企業のメリット
売り手企業のメリットとしては、次のものが挙げられます。
- 創業者利益を獲得できる
- 経営者の高齢化や後継者問題による廃業を回避できる
- 雇用を維持できる
- 人材を確保しやすくなる
- 連帯保証を外せる
それぞれのメリットについて解説します。
創業者利益を獲得できる
倒産や廃業を選択すると、ほぼ利益は得られません。廃業手続きにはさまざまな文書の作成もあり、会計士や税理士などに支払う専門家報酬なども多く、赤字になってしまうことが一般的です。また、建設業は特殊かつ大がかりな設備や機器が多く、処分費用が高額になる傾向にあります。
しかし、企業や事業を売却すれば、利益を得られる可能性があります。処分費用が高額になる建設設備や機器も、資産として評価を受けられるようになり、獲得金額の増加につながるのもメリットです。
経営者の高齢化や後継者問題による廃業を回避できる
経営者の高齢化により、廃業を検討する建設会社もあります。経営者が経営管理責任者や専任技術者である会社も多いため、経営者が引退すると会社の存続が難しくなり、廃業以外の選択肢がなくなってしまうこともあります。
少子化により親族に後継者候補がいない場合や、候補はいるものの家業意識が薄く、引き継ぎを拒否する場合もあるでしょう。後継者がいないと、いずれ廃業を余儀なくされます。高額な設備や今まで築いてきたノウハウが無駄になってしまうかもしれません。
しかし、M&Aを実施すれば後継者問題は解決します。他社の優秀な人材が経営者となれば、企業の発展も期待できるでしょう。親族や社内などに適切な後継者が見つからないときでも、M&Aにより廃業を回避し、経営者は希望する時期に引退できるようになります。
雇用を維持できる
M&Aにより会社や事業を他企業が引き継げば、従業員もそのまま引き継がれ、雇用の維持が可能です。従業員の生活を守るためにも、M&Aを検討する必要があるでしょう。
M&Aを実施せず、会社を廃業するときは、従業員は仕事を失うことになります。建設業では従業員の高齢化が問題になっており、人材不足とはいえ、すぐに再就職先が見つかるとは限りません。
2022年時点、55歳以上の建築業就業者は全体の35.9%を占めるのに対し、29歳以下は11.7%のみです。実数ベースでは、2021年から2022年の1年で55歳以上は1万人の増加、29歳以下は2万人の減少と、今後より一層高齢化が進むと推測されます。
経営者の高齢化により廃業を検討する企業なら、従業員も高齢化が深刻と考えられます。技術力や経験があっても、体力的に対応が難しい業務も多いため、人材不足の建設業界内でも再就職は難しくなるかもしれません。
参照元:国土交通省「建設業を巡る現状と課題」
人材を確保しやすくなる
M&Aにより大手建設会社と提携すれば、大規模な採用活動が可能になり、人材を確保しやすくなるというメリットがあります。また、知名度の高さから人材が集まりやすいため、優秀な人材を確保しやすいのもメリットです。
実際のところ、建設業界の人材不足は深刻で、1997年のピーク時(685万人)と比べると、2022年は479万人と約30%も減少しています。そのため、人材確保は建設会社にとっては事業存続を左右する重要な課題です。将来性のある企業へと躍進するためにも、M&Aによる企業規模の拡大を検討できます。
参照元:国土交通省「建設業を巡る現状と課題」
連帯保証を外せる
会社譲渡を実施すると、会社が保有する資産だけでなく負債もすべて譲渡先企業に引き継がれることになります。経営者が個人で連帯保証人になっていた負債も、譲渡先企業に引き継がれるため、連帯保証を外すことが可能です。
建設会社で用いる機械や設備は高額なものが多く、生コンクリートやセメント、棒鋼などの建設資材の価格も高騰しているため、建設会社の借入金は高額になる傾向があります。連帯保証を外し、負債による負担を軽減するためにも、M&Aを検討できるでしょう。
買い手企業のメリット
M&Aは、売り手企業だけでなく買い手企業にも大きなメリットがあります。建設業界の企業が買い手企業になるメリットとしては、次のものが挙げられます。
- 人材を確保できる
- 対応できる業務の幅が広がる
- 取引先が広がる
- 対応エリアが広がる
- 業界内シェアを拡大できる
それぞれのメリットについて見ていきましょう。
人材を確保できる
建設業界の企業が人材不足であることは、売り手企業だけでなく買い手企業も同様です。事業を拡大しようにも従業員不足により対応できない企業や、人材不足で工期が長引き、業界内競争力が低いことに悩んでいる企業もあります。M&Aにより企業提携すれば、売り手企業の従業員を雇用でき、人材不足の解消が可能です。
また、建設業界の中でも同業種の企業と提携するなら、熟練したスキルや専門知識を有する人材を確保できます。
建設関連の業務は資格を必要とするものも多いため、業界未経験の人材を雇用すると働けるようになるまでに多大なコストと時間がかかりますが、有資格者などの経験者なら新たに教育する必要がありません。費用をかけずに即戦力として人材を活用できるのも、建設業界内のM&Aのメリットといえます。
対応できる業務の幅が広がる
建設業界内のM&Aであっても、対応できるノウハウが増えることで、業務の幅が広がり、顧客を獲得しやすくなります。また、今まで外注していた業務を内製化できるようになり、費用対効果が飛躍的に向上する可能性もあるでしょう。
建設業は不動産業やインフラ業、IT関連などのように提携可能な業界・業種が多いため、異業種を買収することで、さらに飛躍的に業務の幅が広がります。異業種と提携することで顧客に一貫したサービスを提供できるようになると、企業競争力が高まり、案件を獲得しやすくなるのもメリットです。
取引先が広がる
建設業が手掛ける事業は、政府や地方公共団体などの公的事業が多いという特徴があります。公的事業に強い会社や民間事業に強い会社など、ある程度、棲み分けが進んでいるのも建設業の特徴です。
公的事業に強い会社が民間事業に強い会社を買収する、あるいは民間事業に強い会社が公的事業に強い会社を買収すれば、不得意とする分野を補完でき、取引先が一気に拡大します。取引先が広がることで受注が安定するようになれば、閑散期が減り、仕事を平準化しやすくなるでしょう。
そのほかにも、買収先が安定的に受注を獲得できる大企業を顧客としている場合、取引先の拡大と受注の安定を同時に得られます。顧客と信頼関係を構築して安定的に依頼を受けるためには、本来ならば長い時間がかかります。M&Aなら時間をかけなくても、信頼関係ごとまとめて買収が可能です。
対応エリアが広がる
一つの都道府県内にのみ営業所を有していた企業でも、買収した企業が他の都道府県を営業エリアとしているなら、営業所を新設しなくても対応エリアの拡大が可能です。また、すでに複数の都道府県で事業展開している場合でも、隣接県で営業する会社を買収すれば、さらに対応エリアが広がります。
建設業は、事業を行ううえで多くの企業と関わる業種です。建築会社なら、建築設計会社や建築資材卸売業者、不動産会社、電気工事会社などのさまざまな業界・業種の企業と関わって建造物を作ります。そのため、新たな場所で事業を開始しようとしても、他企業との関係構築に時間がかかり、経営が安定するまでに長い時間を要します。
しかし、M&Aによって会社ごと買収すれば、時間をかけなくても営業エリアの拡大が可能です。スピード感のある事業展開を実現するためにも、M&Aが有効です。
また、建設業では国内需要の低下が予想されるため、海外進出を目指す企業も増えています。海外に拠点を作り、地元企業とのコネクションを構築して……となると莫大なコストと時間がかかりますが、すでに海外に拠点のある企業や海外企業を買収すれば、コスト・時間ともに抑えて海外進出が可能です。
業界内シェアを拡大できる
企業規模が大きくなると、受注を取りやすくなります。業界内シェアを拡大するためにも、業界内外の企業を買収し、規模を拡大しておくことが必要です。
また、公共事業は入札により担当業者が決まります。入札するには入札資格を満たすことが必要ですが、経営規模や経営状況などによって等級が決まり、その等級に応じた案件にのみ入札に参加できる仕組みです。
M&Aにより企業を買収して経営規模が拡大すれば、より大きな案件に入札できるようになります。また、グループ企業として子会社化すれば、入札機会が増えるだけでなく自社と異なる等級の案件にも入札できる可能性もあります。建設業ならではの入札制度に対応し、業界内での競争力を高めるためにも、M&Aによる企業買収を検討できるでしょう。
建設業界でM&Aを実施するデメリット
建設業界にとってもメリットの多いM&Aですが、いくつかデメリットも想定されます。よくあるデメリットについて、売り手企業と買い手企業に分けて紹介します。
売り手企業のデメリット
売り手企業にとって、以下のポイントがデメリットになることがあります。
- 進行中の案件引き継ぎがうまくいかないこともある
- 期待するほどの価格がつかないこともある
それぞれのデメリットについて説明します。
進行中の案件引き継ぎがうまくいかないこともある
建設業の案件は長期的になる傾向があるため、事業や企業を売却するときにもいくつかの案件は進行中となる可能性があります。請け負ったからには完了させてから他社に引き継ぐのがベストですが、案件によっては数年かかるものもあるため、M&Aを実施するタイミングで区切りがついているとは限りません。
自社や事業を売却するときには、進行中の案件も引き継いでもらう必要がありますが、買い手企業が建設業でないときは引き継ぎができず、同業他社に引き継ぎを依頼しなくてはいけない可能性があります。
買い手企業が建設業であっても、進行中の案件を完成させるために必要な建設業許可を取得していない場合も想定されます。また、買い手企業が進行中案件を引き継げる場合でも、進行時に追加費用が発生するなどのトラブルが生じるかもしれません。
建設会社によっては、進行中の案件が複数ある状態でM&Aを実施することになります。トラブルを回避するためにも、案件依頼者に状況を率直に説明し、案件依頼者と買い手企業も含めて3社で話し合い、丁寧な引き継ぎを行うことが必要です。
期待するほどの価格がつかないこともある
買い手企業が見つかったとしても、期待するような価格で売却できない可能性があります。
その理由としては、建設業界特有の入札制度が挙げられます。建設業では入札方式によって受注が決まる公的事業の案件が多いため、落札するには業務を適正価格で行い、価格面で他企業よりも競争力を有していなくてはいけません。そのため、利益が限定的になり、想定よりも低く企業価値を見積もられてしまう原因になることがあります。
また、完成までに数年かかる案件を請け負っているときなど、一時的に経営状態が赤字に傾くこともあります。建設業ならではの状況を理解した上で企業価値が評価されれば良いですが、事情を加味せずに数字どおりの利益で企業価値が評価されると、想定したよりも低く見積もられるかもしれません。
買い手企業のデメリット
買い手企業もいくつか注意すべき点があります。デメリットになり得る点としては、次のものが挙げられます。
- シナジー効果が得られないこともある
- 民事責任や罰金刑などに問われることがある
- 瑕疵担保責任を引き継ぐことになる
それぞれのデメリットが生じる状況や回避するポイントについて見ていきましょう。
シナジー効果が得られないこともある
シナジー効果を期待して相手企業を買収しても、思うようなシナジー効果を得られないことがあります。
たとえば事業拡大を目的として同じ建設業界の企業を買収するケースでも、営業エリアが離れすぎている場合や、お互いの得意とする分野に接点がない場合は、シナジー効果を得にくいかもしれません。事業方針が違いすぎて統合プロセスがうまくいかない場合も、シナジー効果どころか、事業継続に障壁が生じる可能性があります。
また、建設業は他の業界・業種との接点も多いため、異業種とM&Aを実施することでシナジー効果を得られる可能性があります。しかし、どの業種でも良いわけではなく、中には何の接点もない業種や、協働できる範囲が限定的でシナジー効果がほとんどない業種もあるため注意が必要です。
シナジー効果を得られる買収を実現するためにも、相手企業を丁寧に調査することが欠かせません。事業分野やエリアを調べるのは当然のこと、どのようなシナジー効果を得られるのか具体的にシミュレーションしておくことが必要です。
粉飾決算などが行われていると、民事責任や罰金刑などに問われることがある
買収先企業が粉飾決算をしていると、後日、民事責任や罰金刑などに問われることがあります。建設業許可が取り消されることにでもなれば、事業継続が難しくなるため注意が必要です。
建設業は粉飾決算が比較的多い業界とされています。粉飾決算とは実際よりも利益が多くあったように帳簿に記載し、赤字の状態を黒字にみせることです。粉飾決算をすると納める必要のない税金を納めることになりますが、金融機関からは信用力のある企業だと評価されるようになり、融資を受けやすくなります。
また、建設には時間がかかるため、年度や決算期をまたぐ工事も少なくありません。そのため、売上や利益を前倒し・後ろ倒しして帳簿に記載することにもなり、粉飾決算が発生しやすくなります。
粉飾決算をしている企業を買収しないためにも、丁寧にデューデリジェンスを実施することが必要です。デューデリジェンスを実施することで、円滑な事業継続が可能になるだけでなく、企業としての信頼を守ることにもつながります。
瑕疵担保責任を引き継ぐことになる
M&Aにより企業・事業を買収すると、相手企業の瑕疵担保責任も引き継ぐことになります。施工に問題がある企業とM&Aを実施した場合は、工事のやり直しや損害賠償を求められるケースが多くなるため、事業進行に影響が出るばかりか、損失が増えてしまうかもしれません。
トラブルを回避するためにも、相手企業の過去の事業実績や瑕疵担保責任を問われたケース、瑕疵担保責任の対応なども買収前に確認しておきましょう。
建設業界のM&A事例20選
建設業界の企業同士、あるいは建設業と異業種との間で多くのM&Aが実施されています。実際の事例を通して、M&Aが実施された背景や目的、各企業の特徴、期待できるシナジー効果などについての理解を深めていきましょう。
ナカノフドー建設×トライネットホールディングス
2023年3月、株式会社ナカノフドー建設は株式会社トライネットホールディングスの株式を取得し、子会社化を実現しました。
トライネットホールディングスは、株式会社トライネット・株式会社パテック・株式会社トライネット不動産・株式会社住まいる工房・株式会社創力の全株式を保有している企業です。そのため、M&A実施後は、ナカノフドー建設がこれらの企業もすべて子会社化することになりました。
トライネットホールディングスは長野県を中心に事業展開している地域密着型の企業ですが、技術力の確かさや信頼性で知られています。全国的に事業展開しているナカノフドー建設はトライネットホールディングスを子会社化することで、両社のノウハウを共有し、土木事業の強化を進め、企業価値向上を目指します。
| M&Aの目的 | 土木事業の強化 |
| M&Aのスキーム | 株式譲渡 |
| 業界 | 建設業×建設業 |
参照元:ナカノフドー建設「株式会社トライネットホールディングス及びそのグループ子会社の株式の取得(子会社化)に関するお知らせ」
矢作建設工業×北和建設
2023年3月、矢作建設工業株式会社は北和建設株式会社の全株式を取得し、子会社化を実現しました。矢作建設工業では持続的成長の実現のために、クライアントや地域が抱える課題解決にとどまらず、よりよい社会のための建設エンジニアリングによる価値創造・提供を目指しています。
目的を実現するためには、加速度的な成長が求められます。生産体制の強化や生産性向上のために、安全レベル・品質レベルの向上、職場環境の整備などを急速に進めていかなくてはいけません。
その目的実現の一環として、東海圏に根付いた矢作建設工業の事業範囲をリニア経済圏に合わせて拡大するため、京都府有数の建設会社として知られる北和建設を子会社化し、京都を中心とする関西圏の営業基盤の確立を目指しました。
また、北和建設はマンション建築だけでなく、福祉施設やホテルなどのさまざまな建物の建築を請け負っています。商圏拡大に加え、対応事業の拡大も見込めることからも、北和建設とのM&Aにつながったと考えられます。
| M&Aの目的 | 商圏拡大、対応事業の拡大 |
| M&Aのスキーム | 株式譲渡 |
| 業界 | 建設業×建設業 |
参照元:矢作建設工業株式会社「株式取得(子会社化)に関する株式譲渡契約締結のお知らせ」
東京エネシス×日本プラントコンストラクション
2021年7月、株式会社東京エネシスは、株式会社日立プラントコンストラクションの火力発電に関する事業の一部を会社分割により承継しました。東京エネシスでは持続的な成長と拡大のために、コア事業である電力設備の建設・保守を強化することを決定しました。また、従来の設備建設に加え、バイオマス発電設備や石油化学プラント発電設備、太陽光発電設備などにも事業拡大することを予定しています。
スムーズな事業拡大を実現するためにも、日立プラントコンストラクションのボイラーや発電機の据付工事事業が必要と判断し、吸収分割により事業承継を実現しました。また、日立プラントコンストラクションが有する優れた技術や人材は、東京エネシスの技術力強化に役立つだけでなく工期短縮や生産性向上、競争力強化にもつながると見込まれています。
| M&Aの目的 | 事業拡大、競争力強化 |
| M&Aのスキーム | 吸収分割 |
| 業界 | 建設業×建設業 |
参照元:株式会社東京エネシス「会社分割(簡易分割)による株式会社日立プラントコンストラクションの事業承継に関するお知らせ」
飛島建設×アクシスウェア
2021年2月、飛島建設株式会社は株式取得により、株式会社アクシスウェアを子会社化しました。アクシスウェアは、システム開発から運用・保守まで戦略的なITサービスを提供するIT企業です。高い技術力と企画力、開発力を有し、加速するデジタルトランスフォーメーションへの対応をスムーズに実現してきました。
建設業を主力事業とする飛島建設がアクシスウェアを買収することで、建設分野にとどまらないボーダーレスなビジネスソリューションの提供が可能になります。次世代に対応できる事業運営体制を構築するためにも、ITスペシャリスト集団として豊富な実績を持つアクシスウェアの買収を実現しました。
| M&Aの目的 | 事業拡大、運営体制の変革 |
| M&Aのスキーム | 株式譲渡 |
| 業界 | 建設業×IT業 |
参照元:飛島建設株式会社「株式会社アクシスウェアの株式の取得(子会社化)に関するお知らせ」
東宝ファシリティーズ×シコー
2021年11月、東宝株式会社の連結子会社である東宝ファシリティーズ株式会社は、発行済み株式の全部取得により株式会社シコーを子会社化しました。
シコーは内装工事を営む企業ですが、とりわけ商業施設の内装工事・監理業務に強みがあります。建設事業を営む東宝ファシリティーズは、事業拡大と技術力強化、営業力の増強によるシナジーを目指し、シコーの買収を実現しました。また、東宝ファシリティーズの成長による、東宝グループ全体の価値向上も目指しています。
| M&Aの目的 | 事業拡大、技術力・営業力の強化 |
| M&Aのスキーム | 株式譲渡 |
| 業界 | 建設業×建設業 |
参照元:東宝株式会社「当社連結子会社による株式取得(孫会社化)に関するお知らせ」
ワキタ×グランドアース、九州機械センター
2021年9月、土木・建設機械、荷役運搬機械などの販売や賃貸を手掛ける株式会社ワキタは、株式会社グランドアースと株式会社九州機械センターの株式を90%ずつ取得し子会社化しました。
ワキタは大阪市に本社を置く企業ですが、東京や名古屋、仙台などにも支店を置き、全国規模で事業展開をしている企業です。建築機器販売以外にも、不動産の賃貸業や戸建分譲住宅の販売、ホテル経営なども手掛け、幅広く建設や不動産の分野で事業を展開してきました。
福岡県に本社を置くグランドアースは、土木機器や建設機器の賃貸業を手掛ける企業です。一方の九州機械センターは、同じく福岡県に本社を置き、土木機器や建設機器の販売を行っています。両社を買収することで、ワキタは九州北部への事業展開を加速度的に進めることが可能です。既存拠点とのシナジー効果も期待でき、さらなる飛躍を目指せます。
| M&Aの目的 | 事業拡大、九州北部の拠点確保 |
| M&Aのスキーム | 株式譲渡 |
| 業界 | 小売業×建設業 |
参照元:株式会社ワキタ「株式の取得(子会社化)に関するお知らせ」
前田道路×前田建設工業
2020年3月、土木建築工事をトータルで請け負うゼネコン・前田建設工業株式会社は、道路整備工事などを主軸事業とする前田道路株式会社をTOB(公開買付け)により子会社化しました。
TOBを実施する前の状態でも、前田建設工業は前田道路の24.68%を有する筆頭株主でした。安定した収益基盤を確立するために前田道路の株式の過半数取得を目的として、TOBの実施に踏み切っています。
ただし、前田道路はTOBに対して反対を表明していたため、実際は敵対的買収(売り手企業の同意を得ない形の買収)として成立しました。
| M&Aの目的 | 収益基盤の確立 |
| M&Aのスキーム | TOB |
| 業界 | 建設業×建設業 |
参照元:前田建設工業株式会社「前田道路株式会社株式(証券コード:1883)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」
大林組×大林道路
2017年9月、スーパーゼネコンの一つ、株式会社大林組は、道路舗装工事などの請負事業を手掛ける大林道路株式会社をTOBにより完全子会社化しました。
TOB前も大林組は大林道路の株式のうち41.67%を有していましたが、生産性向上やグループ企業としての自由度を高める目的で完全子会社化を目指し、TOBを進めることになりました。また、営業面で協力体制を強化することで、技術開発の効率化や収益力向上も目指しています。
| M&Aの目的 | グループ再編、収益力向上 |
| M&Aのスキーム | TOB |
| 業界 | 建設業×建設業 |
参照元:株式会社大林組「大林道路株式会社株券等(証券コード:1896)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」
トヨタホーム×ミサワホーム
2017年1月、トヨタホーム株式会社は、ミサワホーム株式会社の株式を過半数取得し、連結子会社化しました。
トヨタホーム・ミサワホームは、いずれも戸建住宅の建設や販売などを手掛けるハウスメーカーです。元々資本提携関係にありましたが、さらに事業を成長させるために協力関係の強化が必要と判断し、トヨタホームがミサワホームを買収する形でM&Aを実現しました。なお、買収はTOBと第三者割当増資の2つの手法で実施されました。
| M&Aの目的 | 協力関係の強化 |
| M&Aのスキーム | TOB、第三者割当増資 |
| 業界 | 建設業×建設業 |
参照元:トヨタホーム株式会社「トヨタホーム&ミサワホーム資本業務提携を強化」
コニシ×山昇建設
2020年7月、ボンドの製造・販売や土木建設事業を手掛けるコニシ株式会社は、株式譲渡のスキームにより山昇建設株式会社を買収しています。
山昇建設は東海地方を中心に土木工事事業を展開し、技術力の高さに定評がある企業です。本M&Aによって、コニシが有する全国規模の営業ネットワークと山昇建設の技術力をかけ合わせ、収益拡大を目指します。
| M&Aの目的 | 収益拡大 |
| M&Aのスキーム | 株式譲渡 |
| 業界 | 化学工業×建設業 |
参照元:コニシ株式会社「山昇建設株式会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ」
OCHIホールディングス×長豊建設
2020年7月、OCHIホールディングス株式会社は、長豊建設株式会社の発行済み全株式取得による連結子会社化を決議しています。
建材や住宅設備機器の卸売事業を経営の主軸とするOCHIホールディングスは、建材事業や加工事業、環境アメニティ事業なども展開する企業です。長野県に本社を置き公共土木事業をコア事業とする長豊建設の買収により、中部地方での事業拡大と、建材事業などの連携、グループシナジーの実現を図りました。
| M&Aの目的 | 中部地方での事業拡大 |
| M&Aのスキーム | 株式譲渡 |
| 業界 | 総合企業×建設業 |
参照元:OCHIホールディングス株式会社「長豊建設株式会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ」
不二サッシ×日本防水工業
2019年5月、窓関連の製造・販売などを手掛ける不二サッシ株式会社は、企業買収を実施しました。対象となったのは日本防水工業株式会社と日本スプレー工業株式会社で、技術力の向上を目的としています。
不二サッシは、ビルやマンションの窓改修を注力事業と位置づけて事業を展開する企業です。首都圏においてビル・マンションの修繕工事を手掛けてきた日本防水工業と、さいたま市に拠点を置き防水工事などを手掛ける日本スプレー工業の買収により、窓関連事業の工事力アップも目指します。
| M&Aの目的 | 技術力向上、工事力強化 |
| M&Aのスキーム | 株式譲渡 |
| 業界 | 化学工業×建設業 |
参照元:不二サッシ株式会社「日本防水工業株式会社グループの株式取得(子会社化)に関するお知らせ」
ヤマダ電機×レオハウス
2020年5月、ヤマダ電機株式会社は株式会社ナックの傘下企業・レオハウスの買収を行いました。
レオハウスは注文住宅の建設請負事業を行い、ローコスト住宅を強みとする企業です。家電量販店の運営を主軸とするヤマダ電機は、スマートハウスの建設や不動産事業にも注力してきました。レオハウスの買収により、住宅事業とのシナジー効果を図ります。
| M&Aの目的 | 事業拡大 |
| M&Aのスキーム | 株式譲渡 |
| 業界 | 小売業×建設業 |
参照元:株式会社ナック「子会社株式の譲渡契約締結に関するお知らせ(開示事項の経過)」
京成電鉄×式田建設工業
2019年4月、京成電鉄株式会社は、千葉県に拠点を持ち官公庁や民間の建設工事を広く手掛ける式田建設工業株式会社の株式をすべて取得しました。
また、同年7月には京成グループの京成建設と合併し、さらなる事業発展を目指します。グループの既存強化と収益拡大を図り、京成沿線地域の発展への寄与を目的とします。
| M&Aの目的 | 事業拡大 |
| M&Aのスキーム | 株式譲渡 |
| 業界 | 交通インフラ×建設業 |
参照元:京成電鉄株式会社「式田建設工業が京成グループに加わりました」
アサノ大成基礎エンジニアリング×三協建設
2018年9月、建設ソリューションを提供する株式会社アサノ大成基礎エンジニアリングは、同じく建築ソリューションに定評のある三協建設株式会社の買収を実現しました。
地下と建物に関する課題をワンストップで解決するアサノ大成基礎エンジニアリングでは、静岡県を中心に豊富な実績を有する三協建設と提携することで、建築分野におけるソリューションの幅を広げることを目指します。
| M&Aの目的 | 事業拡大 |
| M&Aのスキーム | 株式譲渡 |
| 業界 | 建設業×建設業 |
参照元:株式会社ACKグループ「株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング 株式譲渡契約締結のお知らせ」
オープンハウス×ホーク・ワン
2021年10月、株式会社オープンハウスは株式会社ホーク・ワンの株式を一部取得し、その後、株式交換を実施して完全子会社化しました。
不動産の仲介事業や戸建住宅の分譲事業を手掛けているオープンハウスは、首都圏や東海圏で建設工事や不動産売買を手掛けるホーク・ワンを子会社とすることで、事業エリアの拡大や建設力の強化を実現します。
| M&Aの目的 | 営業エリア拡大 |
| M&Aのスキーム | 株式譲渡、株式交換 |
| 業界 | 不動産業×建設業 |
参照元:株式会社オープンハウス「株式会社ホーク・ワンの株式取得及び簡易株式交換(完全子会社化)に関するお知らせ」
サーラ住宅×太陽ハウジング
2017年10月、木造住宅の施工・販売を手掛けるサーラ住宅株式会社は、太陽光発電システムの設置事業などを展開してきた太陽ハウジング株式会社を買収しています。
愛知県や静岡県などを中心に活動するサーラ住宅が、愛知県西三河で強力な経営基盤を築く注文住宅を請け負う太陽ハウジングと協働することで、西三河での基盤強化の実現を目指します。また、太陽ハウジング側にとっては、サーラ住宅の有する信用力を活用し、収益性強化の実現を目指すためのM&Aです。
| M&Aの目的 | 西三河での基盤強化 |
| M&Aのスキーム | 株式譲渡 |
| 業界 | 建設業×建設業 |
参照元:株式会社サーラコーポレーション「当社連結子会社による株式取得に関するお知らせ」
長谷工コーポレーション×総合地所
2015年5月、株式会社長谷工コーポレーションの子会社・不二建設株式会社は、総合地所株式会社の株式すべてを取得しました。
長谷工コーポレーションは3大都市圏をメイン商圏とし、マンション関連の幅広い事業を展開しています。首都圏や近畿圏でマンション分譲事業を展開する総合地所との提携により、顧客ニーズを設計に反映し、サービスの拡充を目指します。
| M&Aの目的 | 事業拡大 |
| M&Aのスキーム | 株式譲渡 |
| 業界 | 建設業×不動産業 |
参照元:株式会社長谷工コーポレーション「当社及び当社子会社による株式の取得(子会社化)に関するお知らせ」
日成ビルド工業×アーバン・スタッフ
2018年7月、日成ビルド工業株式会社は、建築ソリューションに定評のあるアーバン・スタッフ株式会社の買収を実現しました。
日成ビルド工業では建設需要変動の影響を最小限にする経営基盤の確立を重要課題として捉え、土地開発から建設・メンテナンスまでワンストップソリューション体制を強化しています。高い技術力と遊休不動産のソリューション提案力を有するアーバン・スタッフとの協働により、提案力の深みを増し、収益安定型ビジネスの実現を目指します。
| M&Aの目的 | 提案力強化、収益安定 |
| M&Aのスキーム | 株式譲渡 |
| 業界 | 建設業×建設業 |
参照元:日成ビルド工業株式会社「アーバン・スタッフ株式会社の株式の取得(子会社化)に関するお知らせ」
日本創発グループ×ササオジーエス
2019年2月、クリエイティブサービスを展開する株式会社日本創発グループは、内装工事をメイン事業とする株式会社ササオジーエスの株式をすべて取得しました。
ササオジーエスは、設計から製作・施工をワンストップで提供する企業です。ササオジーエスとの提携により、大判加工や施工体制の拡充、納期短縮などの実現を目指します。
| M&Aの目的 | 事業拡大 |
| M&Aのスキーム | 株式譲渡 |
| 業界 | IT×建設業 |
参照元:株式会社日本創発グループ「株式会社ササオジーエスの株式取得(完全子会社化)に関するお知らせ」
建設業がM&Aを実施する際の注意点
活発にM&Aが行われている建設業界ですが、実施の際には業界ならではの注意すべき点もいくつかあります。主な注意点は以下の4つです。
- 経営管理責任者を確保する
- 経営事項審査の点数に注意する
- 粉飾決算に注意する
- M&Aスキームにより建設業許可の引き継ぎ方法が異なる
それぞれの注意点について説明します。
経営管理責任者を確保する
建設業許可の取得には、適切に経営管理責任者を配置することが求められます。しかし、譲渡企業の経営管理責任者が社長で、M&A完了後に退任する場合も少なくありません。
買収後スムーズに事業を継続するためにも、建設業許可の種類に応じた経営管理責任者を確保しておきましょう。
経営事項審査の点数に注意する
経営事項審査の点数によってランクが決まり、入札参加できる公共工事が変わります。M&Aの相手企業が自社と異なるランクであれば、入札参加できる工事の幅が広がります。
M&Aを進める前に、相手企業の経営事項審査の点数やランクもチェックしておきましょう。
粉飾決算に注意する
案件の長期化や多額の融資を必要とすることから、建設業界は粉飾決算が多いとされています。粉飾決算をしている企業を買収すると、後日民事責任に問われ、場合によっては事業停止や許可取り消しなどに発展するかもしれません。
丁寧にデューデリジェンスを実施することで、粉飾決算の有無を調べておきましょう。
M&Aスキームにより建設業許可の引き継ぎ方法が異なる
M&Aスキームによって、建設業許可の引き継ぎ方法が異なります。たとえば株式譲渡では売り手企業の許認可をそのまま引き継げますが、事業譲渡では許認可の引き継ぎに時間がかかり、空白期間が生じる可能性があります。
業務のスムーズな進行のためにも、スキームに応じた引き継ぎ方法を確認・実施することが必要です。
建設業界のM&A相場
建設業界のM&A相場は、企業規模や財務状況、保有資産によって異なります。中小規模の建設会社の場合、次の価格が相場の目安とされています。
時価純資産+2~5年分の営業利益
M&Aの価格は、企業価値をベースに交渉することが一般的です。企業価値の計算方法や価格に影響をおよぼす要素を説明します。
計算方法
企業価値を評価する主な方法としては、次の3つが挙げられます。
- コストアプローチ
- マーケットアプローチ
- インカムアプローチ
それぞれの方法について見ていきましょう。
コストアプローチ
コストアプローチとは、貸借対照表に記載された純資産をベースに企業価値を評価する方法です。計算がシンプルで納得感が高い反面、将来性や企業特性が反映されない点に注意が必要です。ある程度の将来性・特性を反映させるために、資産にのれんを加えるケースもあります。
マーケットアプローチ
マーケットアプローチとは、類似する規模や事業内容の企業を選び、その企業の株価やM&Aの取引価格をベースに企業価値を評価する方法です。具体的な数字で計算できるため客観性が高い方法ですが、中小企業にとっては上場企業に類似企業が見つかりにくい可能性があります。
インカムアプローチ
インカムアプローチとは、将来予測されるフリーキャッシュフローをベースに企業価値を評価する方法です。将来性や企業特性を企業価値に反映できますが、主観が入りやすいために客観性が低くなる可能性があります。
M&Aの価格に影響をおよぼす要素
M&Aの価格に影響をおよぼす要素を把握しておくと、自社の価格目安を理解しやすくなります。主な要素としては、次のものが挙げられます。
- コンプライアンス遵守
- 安定した取引先
- 高い技術力
- 優秀な人材
- 健全な財務・税務状況
- 事業展開の方向性・将来性
それぞれの要素について見ていきましょう。
コンプライアンス遵守
コンプライアンスを遵守している企業なら、訴訟や補償問題にも発展しにくいため、企業価値も高く評価されやすくなります。社会保険に加入しているか、未払残業代がないか、談合した事実がないかなどをチェックしておきましょう。また、コンプライアンスを遵守する企業なら、誠実に施工しているため、瑕疵担保責任に問われる可能性も少ないと考えられます。
安定した取引先
安定した取引先があると、将来的にも利益を見込めるため、企業価値も高く評価されるようになります。また、取引先の多さや下請先の多さなども、企業価値に反映されます。
高い技術力
技術力がある企業なら、工事にミスが起こりにくいため、後日瑕疵担保責任に問われる可能性が低いと考えられます。また、最新技術に対応している企業や特許を取得している企業も、将来性が高く、企業価値に反映されやすくなります。
優秀な人材
建設は人による部分が多いため、優秀な人材を確保している企業は価値が高いと評価されます。また、慢性的に建設業界は人材が不足していますが、とりわけ若手人材の不足は深刻です。若手人材の割合が多い企業も、高く評価されやすくなります。
健全な財務・税務状況
健全な財務・税務状況の企業も、高く評価されます。建設業界は、工事が年度をまたぐことから粉飾決算が起こりやすいため、とくに厳しくチェックされる傾向にあります。
事業展開の方向性・将来性
建設業界の国内ニーズは減少するという見方もあります。生き残れる企業かどうかチェックするためにも、事業展開の方向性や拠点・事業の多様性などから将来性が確認されます。
M&Aについての相談先
M&Aについて悩んだときは、信頼できる相手に相談することが必要です。おすすめの相談先を紹介します。
金融機関
銀行などの金融機関の中には、M&Aの相談に対応しているところもあります。取引のない金融機関であっても相談に乗ってもらえることがあるため、一度、問い合わせてみましょう。ただし、中小規模のM&Aについては、対応していない可能性があります。
税理士や公認会計士などの士業専門家
自社の税務や財務を知り尽くしている顧問税理士・顧問会計士なら、経営状況の改善などについての適切なアドバイスを得られます。ただし、税理士・会計士によってはM&Aについて詳しくない可能性があります。。M&Aの相談や実務に対応している税理士・会計士事務所もあるため、まずは問い合わせてみましょう。
M&A仲介会社
M&Aの相談から実務までを専門的に請け負うM&A仲介会社に、相談する方法もあります。相手企業探しからM&Aの成立まで一貫して依頼できるため、スムーズなM&Aを実現できます。ただし、M&A仲介会社によって得意とする業界や企業規模が異なるため、事前に確認しておきましょう。
まとめ
後継者問題による統廃合や建設業界以外の企業とのM&A、海外進出を目的としたM&Aが増加傾向にあることから、従来よりも建設業ではM&Aが活発に実施されるようになっています。売り手にとっては創業者利益を獲得できることや雇用の維持、連帯保証を外せるなどのメリットが、買い手にとっては取引先や対応エリアの拡大などのメリットも期待できます。
M&AならレバレジーズM&Aアドバイザリーにご相談を
M&Aを成功させるには、信頼できる相手に相談することが不可欠です。レバレジーズM&Aアドバイザリー株式会社は、各領域に特化したM&Aサービスを提供する仲介会社です。実績を積み重ねたコンサルタントが、相談から成約まで一貫してサポートを行います。
料金に関しては、M&Aの成約時に料金が発生する、完全成功報酬型です。
M&A成約まで、無料でご利用いただけます(譲受側のみ中間金あり)。ご相談は無料です。
M&Aを検討している際には、お気軽にお問い合わせください。