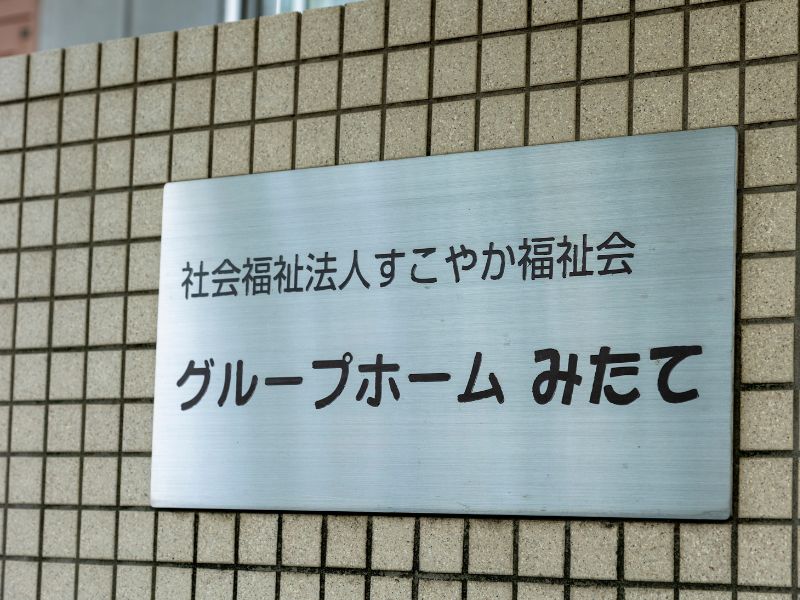このページのまとめ
- ホテル・旅館業界のM&Aは、新規事業進出や経営基盤強化などを目的にした事例がある
- 宿泊者数や訪日外国人数はコロナ禍で急落したが、2022年に入り回復傾向にある
- ホテル・旅館業界では、市場変化に対応したM&Aが増えつつある
- ホテル・旅館業界M&Aの買い手のメリットは新規参入や事業拡大が可能なことなど
- ホテル・旅館業界のM&Aの売り手のメリットは廃業の回避や経営基盤の強化ができることなど
「ホテル・旅館業界のM&Aを検討しているけど、イメージがつかない」とお悩みの方もいるのではないでしょうか?
ホテル・旅館業界のM&Aは活発化しており、事例が豊富です。海外企業相手や異業種相手のケースも増えています。
このコラムでは、ホテル・旅館業界におけるM&Aの45事例を紹介します。そのほか、ホテル・旅館業界のM&A動向や、M&Aのメリットなども紹介するので、ぜひ参考にしてください。
目次
ホテル・旅館業界のM&A事例45選
最初に、ホテル・旅館業界におけるM&A事例を45件紹介します。自社が置かれた状況に近い事例を参考にしてください。
ベストワンドットコムとJourneyのM&A事例
2021年11月、株式会社ベストワンドットコム(以下、ベストワンドットコム)が、株式会社Journeyの運営するWebサイト「minute(ミニッツ)」と「minuteマガジン」の事業譲受を決定し、契約を締結したことを発表しました。
ベストワンドットコムは、主にクルーズ旅行や船旅を専門としたオンライン・トラベル・エージェント(OTA)事業を営んでいる会社です。
ベストワンドットコムが事業譲受を決めた「minute」は、若者カップルをターゲットにしたホテル予約サイトです。後払い決済が可能で、キャリア決済・クレジットカード決済に対応しています。
ベストワンドットコムの発表(2021年11月時点)によると、「minute」に掲載されているホテル数は27,000軒以上で、年間取扱高は4千万円前後、累計取扱人数は1万人以上です。
また、「minute」と「minuteマガジン」のUU数(サイトを訪問した人数を表す指標)は20万人以上で、集客力の強さを示していました。
ベストワンドットコムでは、サイトの事業譲受をきっかけに、「minuteマガジン」から自社の既存ホテル・旅館予約サイト「ベストワン宿泊予約」へ送客することで、シナジー効果を高めることを検討しているとのことです。
参照元:
株式会社ベストワンドットコム「後払い決済ができるホテル予約サイト『minute』、旅行・ホテル情報サイト『minuteマガジン』の事業譲受について」
株式会社ベストワンドットコム「会社概要」
ベストワンドットコムとえびす旅館のM&A事例
2018年12月、株式会社ベストワンドットコム(以下、ベストワンドットコム)は、株式会社GLOBAL NETWORKから株式会社えびす旅館(以下、えびす旅館)の株式を取得し、子会社化することを発表しました。
えびす旅館は、京都でホテル・旅館・簡易宿泊所を経営しています。えびす旅館子会社化前の直近決算では、売上高約3千9百万円、営業利益約2百4十万円でした。子会社化後は、親会社に支払っている業務委託手数料を見直すことで、収益改善を見込むとのことです。
一方、ベストワンドットコムは、クルーズ旅行専門サイトや国内旅行における専門サイトなどを運営するオンライン旅行会社です。
えびす旅館が持つホテルの所有・運営、集客ノウハウなどを取得してホテル事業に参入し、マーケットの大きいインバウンド旅行者向けのホテル・旅館・ホステル事業への足掛かりとすることを目的に、株式の取得を決定したとのことです。
ベストワンドットコムは、今後もクルーズの港に近い大都市へのホテル・旅館・ホステルを積極的に取得し、運営拡大していく方針を示しています。
なお、ベストワンドットコムが取得する株式数は100株で、取得価額は非公表です。
参照元:株式会社ベストワンドットコム「株式会社えびす旅館の株式の取得(子会社化)に関するお知らせ 」
HMIホテルグループと三日月ホテルのM&A事例
2021年11月、ホテルマネージメントインターナショナル株式会社(以下、HMIホテルグループ)が、「勝浦スパホテル三日月」と「鴨川スパホテル三日月」の2館(いずれも千葉県勝浦市)を事業承継することを発表しました。
当時、「勝浦スパホテル三日月」は株式会社勝浦ホテル三日月、「鴨川スパホテル三日月」は「株式会社小湊ホテル三日月」が所有・経営するホテルでした。
HMIホテルグループは、ホテル・旅館経営や旅行業務・交通事業などを手がける会社です。「勝浦スパホテル三日月」「鴨川スパホテル三日月」と同じく千葉県に所在する、「ホテル南海荘」を長年経営してきました。
HMIホテルグループは、長年の経営を通じて得たノウハウを駆使して、今回事業承継する2館をさらに高品質な海浜リゾートホテルにすることを目指すと発表しています。また、2館のホテル社員はHMIホテルグループが継続雇用するとのことです。
なお、「勝浦スパホテル三日月」は「三日月シーパークホテル勝浦」、「鴨川スパホテル三日月」は「三日月シーパークホテル安房鴨川」として、2022年3月より新規営業を開始しています。
参照元:HMIホテルグループ「勝浦スパホテル三日月と鴨川スパホテル三日月事業承継のお知らせ」(PR TIMES)
ハウステンボスとウォーターマークホテル長崎のM&A事例
2021年4月、ハウステンボス株式会社(以下、ハウステンボス)が取締役会で株式会社ウォーターマークホテル長崎を完全子会社化することを決議し、翌月の5月に同社の全株式を取得しました。
ハウステンボスは、長崎県でヨーロッパの街並みを体験できる施設を運営する会社です。
ウォーターマークホテル長崎は、もともと「ホテル デン・ハーグ」という名のホテルで、ハウステンボス直営のホテルでした。2011年以降はHISグループ傘下で運営されていました。
ハウステンボス園内に立地するホテルである点、ハウステンボスグループに加わることでハウステンボスブランドの構築になる点、顧客への新たな連動商品を展開できる可能性などを考慮し、ハウステンボスはウォーターマークホテル長崎の株式取得を決定したとのことです(取得額は非公表)。
なお、「ウォーターマークホテル長崎」の名称は、オランダのハーグ市を由来とする「ホテルデンハーグ」に変更されました(2023年10月26日付け)。
参照元:
ハウステンボス株式会社「株式の取得(子会社化)に関するお知らせ」(PR TIMES)
ハウステンボス株式会社「2023年10月26日(木)お洒落でスマートなカジュアルホテル『ホテルロッテルダム』誕生ハウステンボスオフィシャルホテルのリニューアル、および名称変更について」
ベルーナとカラカミのM&A事例
2023年3月、Karakami HOTELS&RESORTS株式会社(以下、カラカミ)は、株式会社ベルーナ(以下、ベルーナ)と売買契約を締結し、北海道内に所有する「洞爺サンパレスリゾート&スパ」と「ザ・レイクスイート湖の栖」を資産譲渡することを発表しました。いずれも、カラカミが運営受委託を予定しているため、当面は従前通り対応するとのことです。
カラカミは、資産配分の見直しによる経営基盤の強化などの観点で、資産譲渡を決断しました。
今後は、従来の大規模リゾートホテルを保有する運営形態から、運営受託を主軸とした新たな収益基盤の構築を目指すとのことです。
一方、資産譲受を決定したベルーナは、主にアパレル・雑貨や化粧品などの通信販売を手がけています。2021年には「洞爺サンパレスリゾート&スパ」や「ザ・レイクスイート湖の栖」と同様に北海道に所在するリゾートホテル「定山渓ビューホテル」も取得しました。
ベルーナとカラカミの事例は、他都道府県に所在する異業種企業とのM&Aケースといえるでしょう。
参照元:
Karakami HOTELS&RESORTS株式会社「【Karakami H&R】北海道内に所有する3施設の譲渡に関するお知らせ」
株式会社ベルーナ「札幌の奥座敷 定山渓温泉に位置するリゾートホテル「定山渓ビューホテル」の取得に関するお知らせ」
三菱地所とロイヤルパークホテルのM&A事例
2021年5月、三菱地所株式会社(以下、三菱地所)が株式交換契約により、株式会社ロイヤルパークホテル(以下、RPH)を完全子会社化することを発表しました。
RPHは、「ロイヤルパークホテル」チェーンの旗艦ホテルとして、ホテルを所有・経営しています。完全子会社化以前から、RPHはすでに三菱地所の出資比率が54.4%の連結子会社でした。
コロナ禍で激変したホテル業界を展望し、「チェーン展開を活かしたポートフォリオ分散とリスク分散」、「IT デジタルを活用した業務効率化・労働生産性向上」などさまざまな構造改革をいち早く進めることが不可欠と判断したことが、連結子会社から完全子会社にすることに至った主な理由とのことです。
株式交換では、三菱地所(株式交換完全親会社)が1、RPH(完全交換完全子会社)が0.025の比率で株式を割り当てています。株式交換で交付する株式数は1,368,010株とのことでした。
その後2022年2月に、三菱地所は完全子会社になったRPHを吸収合併してグループ組織再編することを発表しています。RPHが持つホテル運営機能と不動産保有機能を分離し、ホテル運営機能を自社の完全子会社「RPH&R」に承継、不動産保有機能を三菱地所が承継することを決めたのに伴い、組織再編するに至ったとのことです。
なお、2022年4月の同日に、RPHの会社分割(RPH&Rに不動産運営機能を分割)と三菱地所への吸収合併が実施されています。
参照元:
三菱地所株式会社「三菱地所株式会社による株式会社ロイヤルパークホテルの完全子会社化に係る株式交換契約の締結(簡易株式交換)に関するお知らせ」
三菱地所株式会社「グループ組織再編(当社子会社の吸収合併)に関するお知らせ」
ベインキャピタルと大江戸温泉のM&A事例
2015年2月、米国投資ファンドのベインキャピタルが、「お台場大江戸温泉物語」を始めとする温泉旅館や温浴施設を運営する大江戸温泉ホールディングスを買収することを発表しました。
温泉業界は訪日客増加で成長が見込める点が、M&Aの理由のひとつです。
買収後、大江戸温泉物語は、収益を着実に伸ばしていきます。しかし、新型コロナウイルス感染拡大をきっかけに集客が落ち込み、他ファンドへ転売せざるを得なくなりました。
2022年1月、ベインキャピタルは投資先の大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツを米国投資ファンドのローンスターに売却することを発表しています。
参照元:
日本経済新聞(電子版)「ベインキャピタル、大江戸温泉HD買収 訪日客に狙い」
日本経済新聞(電子版)「大江戸温泉、米ローンスターが買収 コロナで苦戦」
ベインキャピタル日本法人「ポートフォリオ大江戸温泉物語」
大江戸温泉物語とホテル水葉亭のM&A事例
2016年9月、大江戸温泉物語株式会社(以下、大江戸温泉物語)が静岡県熱海市の「ホテル水葉亭」を取得しました。
ホテル水葉亭は、1951年に設立された老舗ホテルで、目の前に相模湾が広がるロケーションや広い大浴場が特徴の施設です。
大江戸温泉物語は、宿泊客数の面などから熱海市に注目していました。2012年4月には、熱海エリアですでに「大江戸温泉物語 あたみ」の営業を開始しています。
今回、熱海で2館目となるホテル水葉亭を取得することで、より多くの顧客をもてなし、熱海の観光の一助になることを期待しているとのことです。本件取得に伴い、大江戸温泉が伊豆エリアで運営する温泉宿の数は4館に増えました。
その後2017年4月に、大江戸温泉物語は由緒あるホテル水葉亭の施設を大切にしつつ、大浴場の改修や大江戸温泉物語流のレストランの新設、オーシャンビューの客室の新規増室などをしたうえで、リニューアルオープンしています。
参照元:
大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会社「大江戸温泉物語グループ 静岡県熱海の『ホテル水葉亭』を取得」
大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会社「大江戸温泉物語「『ホテル水葉亭』」 2017年4月28日リニューアルオープン予定」
アールビバンと大江戸温泉物語のM&A事例
2018年5月に、大江戸温泉物語株式会社(以下、大江戸温泉物語)と、アールビバン株式会社(以下、アールビバン)の連結子会社、TSCホリスティック株式会社(以下、TSCホリスティック)の間で不動産等売買契約書が交わされました。
契約は、TSCホリスティックの所有するリゾート事業「タラサ志摩ホテル&リゾート(以下、タラサ志摩ホテル)」を大江戸温泉物語に譲渡する内容です。
TSCホリスティックは、リピーター率の高い施設を目指すも、宿泊者数・客単価を伸ばすことができず、営業損失が続いていました。2018年3月期のタラサ志摩ホテルの営業損失は5千6百万円です。
そこで、経営資源の有効活用や財務体質の強化を目的に、タラサ志摩ホテルの売却を決断したとのことです。
タラサ志摩ホテルの土地・建物(帳簿価額2億4百万円)が、譲渡資産の対象となります。譲渡価額は15億3千万円(現金決済)で、アールビバンによると12億4千万円を事業譲渡益として見込んでいるとのことです。
参照元:
大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会社「当社子会社における事業譲受に係る契約締結のお知らせ」
アールビバン株式会社「当社子会社における事業譲渡のお知らせ」
霞ヶ関キャピタルとメゾンドツーリズム京都のM&A事例
2021年4月、霞ヶ関キャピタル株式会社(以下、霞ヶ関キャピタル)は、メゾンドツーリズム京都株式会社(以下、メゾンドツーリズム)の全株式を取得して子会社化することを発表しました。
霞ヶ関キャピタルは、物流施設開発やアパートメントホテル開発などの不動産コンサルティング事業を主に営む会社です。
霞ヶ関キャピタルは、メゾンドツーリズムの保有する「ホテル京都木屋町」の取得を目的に、同社の全株式取得、子会社化を決定しました。
ホテル京都木屋町の運営は、ソラーレホテルズアンドリゾーツ株式会社が引き継ぎ、運営を継続するとのことです。同年8月には「SH by the square hotel京都木屋町」としてリブランド開業されることが発表されました。
なお、霞ヶ関キャピタルはメゾンドツーリズムの全株式取得、同社の既存借入金の借り換えを目的として、金融機関から資金調達しています。
参照元:
霞ヶ関キャピタル株式会社「メゾンドツーリズム京都株式会社の株式取得(子会社化)及び資金の借入に関するお知らせ」(PR TIMES)
ソラーレホテルズアンドリゾーツ株式会社「プレスリリース2021.07.28『SH by the square hotel京都木屋町』を8月1日にリブランド開業」
穴吹興産と祖谷渓温泉観光のM&A事例
2020年7月、穴吹興産株式会社(以下、穴吹興産)は、祖谷渓温泉観光株式会社(以下、祖谷渓温泉観光)と有限会社祖谷温泉(以下、祖谷温泉)の株式を譲り受け、子会社化する契約を締結しました。
祖谷渓温泉観光は「和の宿 ホテル祖谷温泉」などの運営を、祖谷温泉は「和の宿 ホテル祖谷温泉」のケーブルカー運営などを手がける会社です。
穴吹興産が属するあなぶきグループには、香川県・岡山県でホテル5施設・旅館1施設を運営する穴吹エンタープライズ株式会社、地域ならではの魅力的なコンテンツを見つけ出し、世界へ発信している旅行業者の株式会社穴吹トラベルなどがあります。
「和の宿 ホテル祖谷温泉」を始めとする「大歩危祖谷温泉郷」のブランド構築やプロモーション戦略などが、あなぶきグループの観光関連の事業戦略や四国・瀬戸内地域全体の観光促進にとって魅力のあるもので、相乗効果も期待できると判断したことが、祖谷渓温泉観光を穴吹興産が子会社化するきっかけになったとのことです。
なお、祖谷渓温泉観光も祖谷温泉も、子会社化前の代表取締役が留任しています。
参照元:あなぶきグループ「『祖谷渓温泉観光株式会社』『有限会社祖谷温泉』の株式譲受(子会社化)に関するお知らせ」
FRACTALEとアレグロクスホテルマネジメントのM&A事例
2020年9月、FRACTALE株式会社(以下、FRACTALE)は、連結子会社であるFRACTALEホテルマネジメント株式会社を存続会社として、株式会社アレグロクスホテルマネジメント(以下、アレグロクスホテルマネジメント)を消滅会社とする吸収合併を実施しました。
アレグロクスホテルマネジメントは、ホテルなどの運営受託事業や、レベニューマネジメントコンサルティング事業を営んでいます。
FRACTALEは、自社の連結子会社であるホテル金沢の運営受託事業の外注先として、これまでアレグロクスホテルマネジメントと取引がありました。
アレグロクスを統合することで、業務効率化やシナジー効果を期待できることが、吸収合併を決断した理由とのことです。
取得の対価は約2,111万円で、株式は1(吸収合併存続会社):8(吸収合併消滅会社)の比率で割り当てられています。
なお、吸収合併後、存続会社はFRACTALEホテルマネジメント株式会社から、フラクタルホスピタリティ株式会社に名称変更するとのことです。
参照元:FRACTALE株式会社(株式会社サイトリ細胞研究所)「有価証券報告書ー第17期」
プリンスホテルと英国のホテルのM&A事例
2018年11月、株式会社プリンスホテル(以下、プリンスホテル)が英国・ロンドンにあるラグジュアリーホテル「The Arch London」の事業を取得したことを発表しました。
具体的には、プリンスホテルの子会社、 StayWell Holdings Pty Ltd(本社:オーストラリア・シドニー)がさらに英国の子会社を通じて「The Arch London」を運営するAB Hotels Ltdの事業を取得するものです。
その後、プリンスホテルの子会社であるStayWell Holdings Pty Ltdが、2019年9月に「The Arch London」をリブランドした「The Prince Akatoki London」をロンドンで開業しました。
「The Prince Akatoki」ブランドは、世界中の富裕層をターゲットに、海外で日本の文化的要素を取り入れたラグジュアリーなサービスを提供することを目指しているとのことです。
本事例のように、日本でホテルを営む会社が、海外ホテルを買収するケースもあります。
参照元:
株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド「【プリンスホテル】イギリス・ロンドンのラグジュアリーホテル『The Arch London』の事業取得に関するお知らせ」
株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド「NEWS RELEASE 2019 年 8 月 30 日 プリンスホテル 知名度向上と国内外のラグジュアリー層獲得を目指しグローバルラグジュアリーブランド第 1 号店『The Prince Akatoki London』が開業【開業日】2019 年 9 月 16 日」
バルニバービと菊水のM&A事例
2020年7月、株式会社バルニバービ(以下、バルニバービ)は、株式会社菊水(以下、菊水)の全株式を譲渡することを決議しました。決議に伴い、菊水がバルニバービの連結対象子会社から除外されることになります。
バルニバービは、飲食店の経営・運営やコンサルタント業などを営む会社です。2017年9月より、京都で飲食業・旅館業を営む菊水を連結子会社化していました。
経営資源の有効活用や財務体質の強化が、全株式譲渡に至った主な理由とのことです。
バルニバービでは、本件譲渡によりグループ全体における事業の選択と集中の観点で、総合的な企業価値の向上につながると見込んでいます。
譲渡する株式数は10,000株(全株式)で、譲渡先や譲渡価額は非公表です。株式譲渡に伴い、バルニバービは特別損失に関係会社株式売却損約8,200万円を計上しました。
参照元:株式会社バルニバービ「第30期定時株主総会招集ご通知(p.36)」
ビーロットとヴィエント・クリエーションのM&A事例
2017年1月、株式会社ビーロット(以下、ビーロット)は、株式会社ヴィエント・クリエーション(以下、ヴィエント・クリエーション)を完全子会社化しました。
ヴィエント・クリエーションは、JR山手線の主要駅に立地するカプセルホテルを所有・運営する会社です。
一方、ビーロットは不動産投資開発事業・不動産コンサルティング事業など、不動産経営にかかわるサービスを提供する会社です。
本件は異業種によるM&A事例のひとつといえるでしょう。
ビーロットはインバウンド戦略でオフィスビルから宿泊施設へのコンバージョンや、ホテル開発に取り組む中で、オペレーショナルアセットとしての不動産再生を図ることや、新規事業へ進出することを目指し、ヴィエント・クリエーションの完全子会社化を決断したとのことです。
完全子会社化後、ビーロットはヴィエント・クリエーションが渋谷区恵比寿に保有するカプセルホテル「ドシー恵比寿」の不動産再生プロジェクトを進めてきました。2017年12月には大規模リニューアルを終えています。
なお、2019年12月にビーロットは子会社であるヴィエント・クリエーションが保有するカプセルホテル「ドシー恵比寿」を売却しました。売却先や売却価格は非公表です。
参照元:ブリッジコンサルティンググループ株式会社「株式会社ビーロットによる株式会社ヴィエント・クリエーションの株式取得(子会社化)に関しての当社関与について」
レッド・プラネット・ジャパン子会社とトラストホールディングスのM&A事例
2017年2月、株式会社レッド・プラネット・ジャパンは、連結子会社のダイキサウンド株式会社(以下、ダイキサウンド)の全株式を株式会社トラストホールディングス(以下、トラストホールディングス)に売却する株式譲渡契約を締結しました。
ダイキサウンドは、音楽ディストリビューション事業を運営する会社です。
レッド・プラネット・ジャパンは、業績好調なホテル事業に経営資源を集中させ、ホテル事業を強化することが営業利益および営業キャッシュ・フローの黒字化、企業価値の向上につながると判断して売却を決断したとのことです。
売却先のトラストホールディングスは、Web 製作・システム開発・システムコンサルティングなど、主にIT をベースにしたビジネスプロデュース業を営んでいます。同社は映像制作やミュージックレストラン運営もしているため、本M&Aでシナジー効果が期待できると判断しました。
譲渡対象の株式は9株(全株式)で、譲渡価額は1億8千万円です。発表段階で、レッド・プラネット・ジャパンは約1億1千万円を関係会社株式売却益として特別利益に計上することを見込んでいます。
なお、その後レッド・プラネット・ジャパンの会社名は、株式会社メタプラネットに変更されました。
参照元:
株式会社レッド・プラネット・ジャパン(株式会社メタプラネット)「(開示事項の経過)子会社の異動(株式譲渡)及び音楽ディストリビューション事業の売却に関するお知らせ」
株式会社レッド・プラネット・ジャパン(株式会社メタプラネット)「臨時株主総会招集ご通知」
アエリアとTWISTのM&A事例
2017年7月、株式会社アエリア(以下、アエリア)は、TWIST合同会社(以下、TWIST)の持分を取得して子会社化することを決議しました。
TWISTは、民泊運営代行サービス「Airbnb(エアビーアンドビー)」を展開している会社です。投資に適した利回りが出せる民泊物件選定のサポートや内装、アメニティなどを揃えた民泊物件化、各民泊サイトへの掲載、集客など、物件管理をワンストップで運営しています。
設立初年度の売上高は約8千2百万円、営業利益は約1千万円、当期純利益は約7百万円でした。
一方、アエリアはITサービス事業やコンテンツ事業などを担う会社です。アエリアとTWISTがそれぞれの得意分野を活かして事業を拡大させるための手段として、M&Aを選択しました。
今後は、アエリアのITノウハウやリソースを活用して、業界のリーダーになれることを目指すとのことです。
なお、相手先が個人のため、取得金額は公開されておりません。
参照元:株式会社アエリア「子会社の異動(取得)に関するお知らせ 」
インベスターズクラウドとBIJのM&A事例
2017年2月、株式会社インベスターズクラウド(以下、インベスターズクラウド)が、株式会社インターアクションから株式会社BIJ(以下、BIJ)の株式を譲受することを決定しました。株式譲受に伴い、BIJはインベスターズクラウドの持分法適用関連会社になっています。
BIJは、IoTを活用したスマートホステル事業の展開や、ソフトウェア開発などを手がける会社です。
一方、インベスターズクラウドは、アプリで始めるアパート経営「TATERU(タテル)」の開発・運営をしています。
インベスターズクラウドは、M&Aをきっかけに自社・自社の子会社とBIJのシナジー効果で新たな事業領域への取り組みや企業価値向上につなげるとのことです。
なお、インベスターズクラウドは2018年4月に株式会社TATERU、2021年4月に株式会社Robot Homeへ商号変更しています。
参照元:
株式会社Robot Home「IoTを活用したスマートホステル事業を展開する、株式会社BIJの株式を取得 関連会社化し、事業シナジーの拡大」
株式会社Robot Home「「インベスターズクラウド」が「TATERU」へ社名変更 当社グループのブランド統一と事業強化のため、CI(コーポレートアイデンティティ)を一新」
株式会社Robot Home「当社『TATERU』が『Robot Home』へ商号変更 業界における知名度・ブランド力の更なる向上とより効果的な事業展開を目指す2021.02.12」
ウェルス・マネジメントのM&A事例
2017年3月、ウェルス・マネジメント株式会社(以下、ウェルス・マネジメント)が京都市下京区にある「ホテルサンルート京都」の物件を取得しました。物件は、外部投資家と、私募形式で組成する特別目的会社を通じて取得しています。
当初の発表によると、当該特別目的会社に対してウェルス・マネジメントが最大5億円の優先匿名組合出資、外部投資家と設立した持分法適用会社が10億円の劣後匿名組合出資する見込みとのことです。
ウェルス・マネジメントは、主に投資事業を営んでいます。
同社は、物件取得後も運営を現在の運営会社に委託するとのことです。
また、ウェルス・マネジメントの子会社(株式会社ホテルWマネジメント大阪ミナミ)との間でマスターリース契約を締結し、ホテル運営会社にサブリースすることを予定しています。
なお、物件の取得先や価格については公表されていません。
参照元:ウェルス・マネジメント株式会社「当社による特別目的会社を通じたホテルサンルート京都の取得に関するお知らせ」
レンブラントホテルと日越カインホアのM&A事例
2016年9月、株式会社レンブラントホテルホールディングス(以下、レンブラントホテルホールディングス)が、日越カインホア有限会社(以下、日越カインホア)が発行する株式の80%を取得しました。日越カインホアは、ベトナム・カインホア省にある「Mer Perle Sea Sun Hotel(メーパールシーサンホテル)」を運営する会社です。
レンブラントホールディングスは、ホテル事業の拡大を展開するなかで、海外進出1号店としてベトナムのリゾートエリア・ニャチャンへの進出を決めていました。
ニャチャンでは近年宿泊施設が続々と建設され、観光客も年々増加しており、ベトナム国内でも注目されるエリアとのことです。
その後、2018年2月にレンブラントホールディングス(*)は、残り20%分の株式を取得し、日越カインホアを完全子会社化しました。
今後も、さらなる成長が見込まれるマーケットとしてベトナム国内での事業展開を進めていくとのことです。
*レンブラントホテルホールディングスは、2017年4月に「株式会社レンブラントホールディングス」へ社名変更しています
参照元:
株式会社レンブラントホールディングス「ベトナム新規出店のお知らせ」
株式会社レンブラントホールディングス「日越カインホア有限会社の完全子会社化について 」
日本管財と沖縄星光のM&A事例
2016年7月、日本管財株式会社が星光ビル管理株式会社より、沖縄星光株式会社(以下、沖縄星光)の株式を取得し、子会社化することを発表しました。沖縄星光は、沖縄でオフィスビル・ホテルを中心とした清掃や、総合ビル管理などを営む会社です。
日本管財は、建物管理運営事業を主に営んでいます。2015年6月には、株式会社沖縄日本管財を設立し、ホテル施設を中心とした建物管理事業やプロパティマネジメント事業における業容拡大を図っていました。
日本管財は、沖縄星光の株式取得をきっかけに、沖縄県における地元経済に対する貢献、市場浸透を図るとのことです。また、安定的な経営基盤の確立や業務効率化、新規営業での営業力の強化なども同時に進めて業容拡大を目指すと発表しています。
本件、M&Aにおける株式取得数は60,000株です(発行済株式総数の100%)。
参照元:日本管財株式会社「沖縄星光株式会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ」
オリックス不動産とホテル万惣のM&A事例
2015年10月、オリックス不動産株式会社(以下、オリックス不動産)が北海道・函館市の「ホテル万惣」を取得し、運営を開始したことを発表しました。ホテル万惣は(1954年創業)は、北海道の三代温泉郷のひとつとされる湯の川温泉にあるホテルです。
オリックス不動産は、主にホテル・旅館、水族館、研修所などの開発・運営を手がけています。ホテル・旅館の分野では、温泉旅館7施設・シティホテル3施設・ビジネスホテル1施設・リゾートホテル3施設を保有しています(取得発表時点)。
取得するホテル万惣は、オリックス不動産の旅館事業において北海道進出第一号の旅館です。函館市が豊富な観光資源を有する観光地である点、北海道新幹線の開業や訪日外国人の増加を背景に、今後もさらなるマーケット拡大が見込めるポテンシャルを備えていると、オリックス不動産は発表しています。
オリックス不動産は施設運営事業や老舗旅館再生事業で培ったノウハウを活かし、今後も旅館事業を積極的に展開していくとのことです。
なお、2016年9月、オリックス不動産はホテル万惣の雅館を全面リニューアルオープンしました。
マーケットの大きな変化を見据え、客室や大浴場の充実を図り、外観やロビーを含めて全面改装を実施したとのことです。
参照元:
オリックス不動産株式会社「函館湯の川温泉『ホテル万惣』の取得のお知らせ」
オリックス不動産株式会社「2016年9月15日(木)『ホテル万惣』雅館を全面リニューアルオープン~函館の歴史と今を感じる快適な空間に刷新~」
第三セクターと三河湾リゾートリンクスのM&A事例
国・地方自治体と民間企業とが共同出資して運営する法人である第三セクターがM&Aに乗り出した事例です。
2016年4月、駒ヶ根観光開発株式会社(以下、駒ヶ根観光開発)が運営する「駒ヶ根ビューホテル四季」が、株式会社三河湾リゾートリンクスに譲渡されることが決定しました。
駒ヶ根観光開発は、株式の半数を駒ヶ根市が出資する第三セクターです。駒ヶ根ビューホテル四季開業当初は、年商6億3千万円を売り上げるなど、順調に推移していましたが、平成の長期不況を背景とする観光産業の低迷、リーマンショックを発端とした景気悪化を受け、2007年以降経営赤字が常態化していました。
駒ヶ根ビューホテル四季を含め、駒ヶ根市を象徴する観光施設を3施設所有しているため、駒ヶ根観光開発の経営悪化は観光地自体のイメージ悪化につながりかねません。また、経営が改善されない場合、同社の借入金を損失補填している駒ヶ根市の財政リスクも増大します。
そこで、観光施設2施設から経営撤退することと、駒ヶ根ビューホテル四季の資産と経営を譲渡することを駒ヶ根観光開発と駒ヶ根市が決断しました。
駒ヶ根ビューホテル四季の営業が途切れず引き継がれ、長期的に健全なホテル経営が続くように、譲渡先は、駒ヶ根観光開発と駒ヶ根市合同のプロポーザル方式で決まりました。
譲渡先の三河湾リゾートリンクスは、住宅関連事業・健康スポーツ事業・介護福祉事業などを営むフジケングループの中で、ホテル事業を営む会社です。
参照元:駒ヶ根市 「第三セクター等抜本的改革の概要 (p.17)」
ロイヤルホテルとFlorentiaのM&A事例
2015年2月、株式会社ロイヤルホテル(以下、ロイヤルホテル)は、保有・運営するリーガロイヤルホテル京都の土地や建物などをFlorentia特定目的会社(以下、Florentia)に譲渡することを発表しました。ロイヤルホテル・Florentia・RRH京都オペレーションズ合同会社(以下、RRH京都オペレーションズ)の間で、譲渡・業務委託に関する三者間合意を締結しています。
Florentiaは、フォートレス・インベストメント・グループLLCの関係会社が運用するファンドが組成するホテル資産の所有会社です。フォートレスは、日本ですでに1,500以上の不動産物件に対する投資実績を有しています。
ロイヤルホテルでは、今後国内外からの観光客が増加する見込みの京都市でさまざまなニーズに対応すべく、かねてリニューアルによる魅力の向上や基幹設備の更新・耐震改修工事を検討していました。
今回、ロイヤルホテルの固定資産を譲渡することで、リニューアル工事を実現するとのことです。
リーガロイヤルホテル京都の土地・建物は、Florentiaが所有し、RRH 京都オペレーションズが賃借します。また、ロイヤルホテルは、RRH 京都オペレーションズからホテル運営を受託し、引き続き「リーガロイヤルホテル京都」の名前で運営を継続するとのことです。
なお、物件の譲渡価格については公表されていません。また、ロイヤルホテルは、事業譲渡益として約33億円の特別利益を計上する見込みとのことです。
参照元:
株式会社ロイヤルホテル「リーガロイヤルホテル京都に関する事業譲渡及び特別利益の計上に関するお知らせ」
株式会社ロイヤルホテル「2016 年秋、リーガロイヤルホテル京都、リニューアルオープン京都の風情と現代的なデザインを取り入れた大規模改修を実施」
ソラーレホテルズアンドリゾーツと浦和ロイヤルパインズのM&A事例
2016年4月、ソラーレホテルズアンドリゾーツ株式会社(以下、ソラーレホテルズアンドリゾーツ)は、「浦和ロイヤルパインズホテル」の運営会社である「株式会社浦和ロイヤルパインズ」の株式を取得する契約を締結しました。
浦和ロイヤルパインズホテルは、埼玉県の行政や周辺企業の宿泊・宴会ニーズが高い立地にあるホテルです。また、計2,800平方メートルの広さの宴会場があり、1,500名を収容できる大型バンケットホールもあります。
ソラーレホテルズアンドリゾーツは、浦和ロイヤルパインズホテルが自社のチェーンに入ることで、チェーンバリューのアップや、相乗効果の発生につながると考え、今回のM&Aに至りました。
同じタイミングで、ユナイテッド・アーバン投資法人が浦和ロイヤルパインズホテルの資産を取得しています。取得後、ホテル運営をソラーレホテルズアンドリゾーツに委託する形をとるとのことです。
なお、M&A後もホテル名は変更せず、「浦和ロイヤルパインズホテル」で運営を継続していましたが、2019年1月(開業20周年)に「ロイヤルパインズホテル浦和」へ変更しています。
参照元:
ソラーレホテルズアンドリゾーツ株式会社「「『浦和ロイヤルパインズホテル』の運営会社株式を 4 月 1 日取得」
ユナイテッドアーバン投資法人「資産の取得に関するお知らせ(浦和ロイヤルパインズホテル)」
鈴縫工業とブリーズベイホテルのM&A事例
2015年10月、鈴縫工業株式会社(以下、鈴縫工業)は、子会社の株式会社ナガクラが営むホテル事業と付随する固定資産をブリーズベイホテル株式会社(以下、ブリーズベイホテル)へ譲渡することを発表しました。
鈴縫工業は、主に土木・建築・上下水道・管工事の請負などを営んでいます。グループにおけるホテル事業の収益性や将来性を検討した結果、子会社が営む事業の譲渡に至ったとのことです。
譲渡先のブリーズベイホテルは、横浜のブリーズベイホテルを旗艦店とするホテルグループで、さまざまなホテルを運営しています。
参照元:鈴縫工業株式会社「子会社のホテル事業の譲渡に関するお知らせ」
アパホテルインターナショナルINC.とONAのM&A事例
2016年7月、APA Hotel International Inc.(以下、AHI)は岡部株式会社(以下、岡部)との間で株式譲渡契約を締結し、同年9月にOkabe North America Inc.(以下、ONA)の発行済株式をすべて取得しました。株式譲渡に伴い、ONAの社名はAPA HOTEL CANADA Inc.に変更されます。
Coast Hotelsを運営するCoast Hotels Ltd.はONAの100%子会社です。Coast Hotelsは、カナダ発のホテルブランドで、主にカナダやアメリカ西海岸で知られています。
AHIは、アパホテル株式会社がカナダで100%出資する子会社です。アパグループは、Coast HotelブランドとAPA HOTELブランドの相乗効果を出すために、ポイントプログラムや予約システムの統合を早期に進めていくと発表しています。
今後、CoastとAPA双方のホテルをカナダやアメリカに展開していくとのことです。同年11月には、Coast Hotelsに日本発のアパホテル新都市型ホテルコンセプトを融合させた新ブランド「COAST hotels by APA」を立ち上げ、第一弾として「COAST coal harbour hotel by APA」をオープンさせました。
参照元:アパグループ「アパグループカナダ現地法人を通じてCoast Hotelsの取得を完了」
サンケイビルと地域経済活性化支援機構のM&A事例
2015年3月、株式会社サンケイビル(以下、サンケイビル)は、株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズ(以下、JWP)が管理運営するファンドと共同で、株式会社地域経済活性化支援機構(以下、機構)から株式会社グランビスタホテル&リゾート(以下、グランビスタ)の株式を取得することを発表しました。
グランビスタは、日本のシティホテルの草分けとされる札幌グランドホテルや札幌パークホテルに加え、鴨川シーワールドなどを運営する会社です。2011年12月以降、機構がグランビスタの事業再生を進めていました。
今回のM&Aに伴い、機構はグランビスタに対する支援決定にかかるすべての再生支援を完了します。
サンケイビルは、傘下に株式会社フジテレビジョンを始めとするメディア関連企業を擁する、株式会社フジ・メディア・ホールディングスを親会社に持つ会社です。グループ企業と総合リゾート事業のノウハウを有するグランビスタが連携することで、高いシナジー効果を発揮し、さらなる成長を期待しているとのことです。
なお、サンケイビルとJWPが管理運営するファンドが出資する合同会社ジェイ・エックス・エーで、普通株式37,333,800株(普通株式に占める割合約 99.6%)を、A種優先株式 2,000,000株(A種優先株式に占める割合 100%)を取得しています。
参照元:
地域経済活性化支援機構「株式会社グランビスタホテル&リゾートに対する再生支援の完了について」
株式会社サンケイビル「株式会社グランビスタホテル&リゾートの株式取得に関するお知らせ 」
ブラックストーンと近鉄グループのM&A事例
2021年3月、近鉄グループホールディングス株式会社(以下、近鉄G)は、米国・ブラックストーンが設立した法人(以下、合弁パートナー)との間で、完全子会社の近鉄不動産株式会社と株式会社近鉄・都ホテルズ(以下、近鉄・都ホテルズ)が保有するホテル資産の一部を特定目的会社等(SPC)へ譲渡する取引に関する基本合意書を締結しました。
SPCは、近鉄Gと合弁パートナーで出資して設立するものです。また、基本合意書には、譲渡後に近鉄Gのグループ会社がホテル運営業務を受託することも含まれています。
新型コロナウイルスの感染拡大による影響を受け、急速に変化する社会・経済構造に対応すべく、近鉄Gではさまざまな施策を進めていました。
本M&Aに伴い、運営に特化したノンアセット経営に移行することで、対象のホテルのさらなる成長を実現できると判断したとのことです。
その後2021年10月より、近鉄Gとブラックストーンが都ホテル京都八条を始めとする8ホテルの合弁事業を開始しました。
今後は、合弁事業対象外の16ホテルについても、アフターコロナを見据えて近鉄Gとブラックストーンの間で持続的かつグローバルな発展を目指していくとのことです。
参照元:
近鉄グループホールディングス株式会社「当社グループが保有するホテル資産の一部に係る合弁事業に関する基本合意書締結のお知らせ 」
近鉄グループホールディングス株式会社「近鉄グループとブラックストーンとのホテル事業に関する合弁事業開始について 」
リゾートトラストとRTCCのM&A事例
2023年5月、リゾートトラスト株式会社(以下、リゾートトラスト)が連結子会社であるRTCC株式会社(以下、RTCC)を吸収合併することを取締役会で決議し、合併契約を締結することを発表しました。
RTCCは、効力発生日をもって解散します。
吸収合併消滅会社のRTCCは、旅行業を営む会社です。
一方、吸収合併存続会社のリゾートトラストは、会員制ホテルやゴルフ場の建設・運営、ホテル会員権の販売などを営んでいます。
RTCCが提供するサービスをリゾートトラストに集約することで、同社グループにおける経営の合理化・効率化を図ることが吸収合併の目的とのことです。もともと、リゾートトラストがRTCCの全株式を保有していたため、本件による株式・その他金銭などの割り当てはありません。
参照元:リゾートトラスト株式会社「連結子会社の吸収合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ」
アゴーラ・ホスピタリティー・グループと難波ホテルオペレーションズのM&A事例
2019年7月、株式会社アゴーラ・ホスピタリティー・グループ(以下、アゴーラ・ホスピタリティー・グループ)が難波・ホテル・オペレーションズ株式会社(以下、難波・ホテル・オペレーションズ)の株式を取得し、子会社化することを発表しました。
難波・ホテル・オペレーションズは、大阪の中心部、難波地区の千日前にある約200室規模のホテルを賃貸借契約に基づき運営する会社です。
アゴーラ・ホスピタリティー・グループは、宿泊事業やその他投資事業を営んでいます。今回、宿泊事業の拡充のためにM&Aに至ったとのことです。
アゴーラ・ホスピタリティー・グループが取得する株式は60,100株(議決権割合100%)です。相手先や価格などは明らかにされていません。
M&A後、子会社化された難波・ホテル・オペレーションズがホテル不動産の新たな所有者から賃借し、ホテル事業を運営します。新たな所有者は、対象ホテル不動産を所有するための特別目的会社です。
参照元:株式会社アゴーラ・ホスピタリティー・グループ「難波・ホテル・オペレーションズ株式会社の株式の取得(子会社化)に関するお知らせ 」
ヒューリックと日本ビューホテルのM&A事例
2019年6月、ヒューリック株式会社(以下、ヒューリック)と日本ビューホテル株式会社(以下、日本ビューホテル)の間で株式交換契約が締結されました。
ヒューリックが株式交換完全親会社、日本ビューホテルが株式交換完全子会社です。
ヒューリックや連結子会社18社、非連結子会社2社およびその関連会社12社(2019年3月31日時点)で構成されるヒューリックグループは、不動産賃貸事業を主に営んでいます。
一方、日本ビューホテルや連結子会社2社、非連結子会社1社(2019年4月30日時点)で構成される日本ビューホテルグループは、ホテル事業や施設運営事業、遊園地事業を主な事業とする会社です。
新規参入者の増加による競争激化や全国的な人手不足、「働き方改革」に伴う人件費の上昇、少子高齢化に伴う婚礼需要の減少などで、ホテル業界における経営環境は厳しさを増しています。
ヒューリックと日本ビューホテルは2015年10月に資本・業務提携契約を締結して提携関係を強化していました。
しかし、多様な顧客ニーズに対応するためには、資本・業務提携契約だけでは十分ではないと判断し、両社で協議を重ねていました。また、ヒューリックの有する好立地かつ豊富な不動産や情報を活用しながら協業をさらに強化すれば、時代の変化や顧客のニーズをとらえた新規ホテルの展開を加速させ、ホテル運営収益を取り込めると判断したとのことです。
上記の点を総合的に勘案し、株式交換を通じて日本ビューホテルがヒューリックの完全子会社になることが最善と両社が決断しました。本株式交換で交付する株式数は10,839,231株(ヒューリックの普通株式)を予定しており、ヒューリック1:日本ビューホテル1.57の交換比率で割り当てます。
参照元:ヒューリック株式会社「ヒューリック株式会社による日本ビューホテル株式会社の完全子会社化に関する株式交換契約締結のお知らせ」
オンワードHDと星野リゾートのM&A事例
2022年3月、株式会社オンワードホールディングス(以下、オンワード HD)が、株式会社星野リゾート(以下、星野リゾート)の完全子会社である株式会社グアムホテルマネジメントに、連結子会社の株式や、同社が有する貸付債権を譲渡することを発表しました。
オンワードHDの連結子会社である株式会社オンワードリゾート&ゴルフが保有するオンワードビーチリゾートグアムINC.の全株式、オンワードビーチリゾートグアムINC.に対してオンワードHDが有する貸付債権が、譲渡の対象になります。
オンワードHDは、アパレル関連事業やライフスタイル関連事業を営む関係会社を傘下にもつ、純粋持株会社です。
2019年10月より、不採算事業からの撤退や規模の縮小を進めていました。
その中で、オンワードHDグループのグローバル事業構造改革の観点から、グアム等におけるホテル運営事業から撤退して第三者に譲渡することが最善の選択と判断し、M&Aに至ったとのことです。
譲渡先の星野リゾートグループは総合リゾート運営会社で、高い集客力と施設運営ノウハウを有するため、対象事業とのシナジー効果も期待できると、オンワードHDは判断しました。
なお、株式譲渡価額は61億円で、譲渡債権の譲渡価額は24億円とのことです。
参照元:株式会社オンワードホールディングス「連結子会社の異動(株式譲渡)及び債権譲渡に関するお知らせ 」
アドベンチャーとレ・コネクションのM&A事例
2022年6月、株式会社アドベンチャー(以下、アドベンチャー)は、連結子会社の株式会社Vacations(以下、Vacations)が株式会社レ・コネクション(以下、レ・コネクション)の宿泊事業を承継することを発表しました。
Vacationsが承継する旨の会社分割契約書をレ・コネクションと締結し、会社分割の手法で事業承継します。
アドベンチャーは、航空券予約販売サイト「skyticket」を運営する会社です。
新型コロナウイルス感染拡大やウクライナにおける人道危機の発生などで旅行事業を取り巻く環境が急激に変化しているため、同社は事業の選択と集中で旅行業関連事業に集中し、宿泊に特化した事業を担うVacationを設立していました。
Vacationsで宿泊事業の展開を模索するなかで、京都で59の宿泊施設を運営するレ・コネクションの宿泊事業に関心をもち、本M&Aに至ったとのことです。
吸収分割では、Vacationsを吸収分割継承会社、レ・コネクションを吸収分割会社としています。本件に伴い、継承会社が分割会社に対して2億円の金銭を交付する予定とのことです。
参照元:
株式会社アドベンチャー「当社子会社である株式会社 Vacations による宿泊事業承継に関する会社分割基本合意書締結のお知らせ」,「(開示事項の経過)当社子会社である株式会社 Vacations による宿泊事業承継に関する会社分割契約書締結のお知らせ」
名古屋鉄道とヒーローのM&A事例
2021年3月、名古屋鉄道株式会社(以下、名古屋鉄道)は、連結子会社の発行済株式のすべてを株式会社ヒーロー(以下、ヒーロー)に譲渡することを発表しました。
対象となる連結子会社は、金沢名鉄丸越百貨店(以下、名鉄丸越百貨店)と、株式会社金沢スカイホテル(以下、金沢スカイホテル)です。
名鉄丸越百貨店は百貨店の運営、金沢スカイホテルはホテルの運営をしています。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大でインバウンドや国内旅行の需要が冷え込んだことで、いずれも厳しい事業環境に置かれていたとのことです。
そこで、名古屋鉄道は金沢名鉄丸越百貨店と金沢スカイホテルをヒーローに譲渡することを決断しました。ヒーローの事業運営ノウハウや過去のM&Aで蓄積された経験から、両者の事業再生・収益改善や従業員の雇用維持を期待できると判断したことが、M&Aの決め手になったとのことです。
金沢名鉄丸越百貨店の55,840,000株、金沢スカイホテルの30,000株(いずれも議決権割合100%)を、ヒーローに譲渡しています。いずれも、直近決算で債務超過であることを踏まえて、譲渡価額を決めたとのことです(金額非開示)。
参照元:名古屋鉄道株式会社「連結子会社の異動(株式譲渡)に関するお知らせ」
シャトレーゼホールディングスと談露館のM&A事例
2023年5月、山梨県の株式会社シャトレーゼホールディングス(以下、シャトレーゼHD)が、同じく山梨県の談露館株式会社(以下、談露館)の株式を取得し、子会社化したことを発表しました。
談露館は、1887年創業の老舗旅館「ホテル談露館」を運営する会社です。
シャトレーゼHDは、菓子事業・ワイナリー事業・リゾート事業・ゴルフ事業を企画・管理しています。甲府の老舗旅館がシャトレーゼグループに加わることで、地元で顧客に新たな付加価値を提供できると判断したことが、本M&Aのきっかけとのことです。
シャトレーゼHDでは、今後ホテル事業を新たな基幹事業として、さらに注力していくとのことです。
参照元:株式会社シャトレーゼホールディングス「談露館株式会社の株式取得に関するお知らせ」
ユニゾン・キャピタルとフォーブスのM&A事例
2017年12月、株式会社フォーブス(以下、フォーブス)は、プライベートエクイティファンドのユニゾン・キャピタル株式会社(以下、ユニゾン)が運営するファンドと資本提携を実施したことを発表しました。
ユニゾンは、これまでも31社(企業価値ベースで8,000億円)に対して出資実績があるプライベートエクイティファンドです。
フォーブスは、「ホテルウイングインターナショナル」のブランドで、食と泊のコラボレーションという発想をプラットフォームとして進化させています。
今回、長期的なホテル100店舗体制構築を目標に策定した経営計画「WING100」の施策を推進していく一環として、ユニゾンが運営するファンドからの出資を受け入れたとのことです。創業家は、引き続き一部の株式を保有します。
なお、フォーブスはその後2020年4月に株式会社ミナシアに社名変更しました。
参照元:株式会社フォーブス(株式会社ミナシア)「経営計画「WING 100」の策定- ホテル 100 店舗体制の構築に向けて -」
MGMとハードロックのM&A事例
海外企業同士のM&Aも紹介します。
2021年12月、米・カジノ大手のMGMリゾーツ・インターナショナルが、ラスベガスのカジノホテル「ミラージュ」の運営事業を米・ハードロック・インターナショナルに売却することを発表しました。売却額は10億7,500万ドル(当時約1200億円)です。
ミラージュは、1989年開業のラスベガスを代表するホテルのひとつでした。2000年にMGMが買収しています。MGMは近年、ラスベガスで資産の入れ替えを進めており、売却に至ったとのことです。
ハードロック・インターナショナルは、カジノの複合施設やライブ会場などを開発するほか、ハードロックカフェ(飲食店)も運営しています。日本でのIR事業展開を目指し、2017年1月には日本法人も設立しました。
参照元:日本経済新聞(電子版)「米カジノMGM、ハードロックにホテル売却 1200億円」
小田急とブリーズベイホテルのM&A事例
小田急電鉄株式会社(以下、小田急)は、2020年3月に保有する株式会社ホテル小田急静岡(以下、小田急静岡)の全株式(発行済株式の94.72%)をブリーズベイホテル株式会社(以下、ブリーズベイホテル)に譲渡することを発表しました。
ホテル小田急静岡は、飲食施設や婚礼施設を備えるシティホテル「ホテルセンチュリー静岡」を運営しています。小田急は、シティホテル業界を取り巻く事業環境が変化するなかで、将来的にも顧客に上質なサービスを提供できるよう、ホテル業やホテル買収再生業のリーディングカンパニーとして知られるブリーズベイホテルへ株式譲渡することを決断したとのことです。
なお、ホテルセンチュリー静岡は、M&A後に「ホテルグランヒルズ静岡」にホテル名を変更しています。
参照元:
小田急電鉄株式会社「子会社の異動を伴う株式の譲渡に関するお知らせ」
日本経済新聞(電子版)「静岡市のホテルセンチュリー、新名称は「グランヒルズ」に」
小野写真館と桐のかほり咲楽のM&A
2020年10月、株式会社小野写真館(以下、小野写真館)が、静岡県の河津町にある「桐のかほり 咲楽」をM&Aで取得して運営することを発表しました。「桐のかほり 咲楽」は、客室4室の小規模でゆったりとくつろげる空間づくりを心がけている温泉旅館です。
一方、小野写真館は、人生の節目の写真撮影・衣装レンタルなどを提供しています。今回、写真から派生した感動体験を生み出す方法として、異業種である旅館運営に挑戦することになったとのことです。
M&Aに伴い、今後「桐のかほり 咲楽」では宿泊だけでなく、還暦祝いや銀婚式・金婚式など、写真館としてさまざまなプランも提供していくと発表しています。
参照元:株式会社小野写真館「企業情報プレスリリース2020年10月1日」
NAPによるファーストキャビンのM&A
2020年7月、株式会社新日本建物(以下、新日本建物)の非連結子会社である株式会社NAP(以下、NAP)が、株式会社ファーストキャビン(以下、ファーストキャビン)の事業を譲受しました。
事業譲受するのは、ファーストキャビンが保有するホテルのフランチャイズ事業や運営受託事業です。
ファーストキャビンは、元々直営や運営受託、フランチャイズチェーンなどで約25軒のホテルを展開していました。しかし、競合の新規参入による競争激化で赤字が続くなか、新型コロナウイルスの感染拡大によりさらなる打撃を受け、2020年4月に破産申請していました。
新日本建物は収益物件の開発・販売や、既存収益ビルのバリューアップなどの事業を展開する会社です。今回のM&Aでフランチャイズ事業・運営受託事業を新規事業として営むことになります。
新日本建物の有する物件仕入力と、ファーストキャビンの有する知的財産権・フランチャイザーとしての運営ノウハウを融合することで、企業価値につながると判断し、本M&Aに至ったとのことです。
なお、本件譲受価額については、非公開とされています。
参照元:
日本経済新聞(電子版)「ファーストキャビン、破産申請 新型コロナで客急減」
株式会社新日本建物「当社非連結子会社による事業譲受に関するお知らせ」
大東建託とマレーシアのホテル事業者のM&A事例
2017年11月、大東建託株式会社(以下、大東建託)がマレーシアの会社を連結孫会社とすることを発表しました。
大東建託と同社の連結子会社である Daito Asia Development Pte. Ltd.が、Daisho Asia Development (M)Sdn. Bhd.の発行済み全株式を取得します。
大東建託は、すでに孫会社のDaito Asia Development(Malaysia)Sdn. Bhd.が同国・クアラルンプール市にて、ルメリディアンが運営するホテル事業(以下、ルメリディアンホテル)を経営していました。
一方、今回M&A対象のDaisho Asia Development(M)Sdn. Bhd.は、ルメリディアンホテルに隣接するヒルトンインターナショナルが運営するホテル事業(以下、ヒルトンホテル)を経営しています。
大東建託は、隣接するルメリディアンホテルとヒルトンホテルを同社グループが所有することが集客力強化やコストダウンにつながり、シナジー効果を期待できると判断し、M&Aに至りました。
本M&Aは、大東建託のコア事業である建設事業・不動産事業に加え、新コア事業と位置付ける事業のひとつ、「海外事業」に該当するとのことです。
なお、今回大東建託およびその子会社は、79,034,660株(所有割合:100%)を取得します。取得価額は、約137億円とのことです。
参照元:大東建託株式会社「子会社における孫会社の異動を伴う株式取得に関するお知らせ」
ATPとオムロンのM&A事例
2019年5月、株式会社レンブラントホールディングス(以下、レンブラントHD)は、子会社である株式会社ATP(以下、ATP)が、ヘルスケア事業などを営むオムロン株式会社が運営する「LaLa 御殿場ホテル&リゾート」の土地・建物を取得することを発表しました。
今回の運営権の取得により、レンブラントHDは国内10ホテル、国外1ホテル、国内ゴルフ場1施設を運営することになります。
取得した不動産は、重厚感ある趣と高品質なおもてなしを提供する新ブランド「レンブラント プレミアム」として展開するとのことです。
レンブラントHDの子会社、株式会社レンブラントホテル厚木が事業運営会社になり、同年6月より「レンブラント プレミアム 富士御殿場」の名で事業運営しています。
なお、レンブラントグループが成長戦略の柱として掲げているのが、「事業再生・事業承継事業」「ホテル・レジャー事業」「不動産事業」「ウェルネス事業」の4事業です。
今回の運営権取得は、その内の「ホテル・レジャー事業」の拡大につながるものとしてさらなる成長が期待されています。
参照元:
株式会社レンブラントホールディングス「『LaLa 御殿場ホテル&リゾート』の運営権取得について 6 月 1 日 新ブランド『レンブラントプレミアム』にて運営開始(予定)」
ファンドクリエーションとAJ社のM&A事例
2017年3月、株式会社ファンドクリエーショングループ(以下、ファンドクリエーションG)の連結子会社である株式会社ファンドクリエーション(以下、ファンドクリエーション)が、株式会社エイジェーインターブリッジ(以下、AJ社)と業務提携することを発表しました。
また、同日付で、AJ社の第三者割当による新株の引受をします。
AJ社は、町屋旅館オペレーターとして事業を展開する会社です。日本の伝統的な家屋「町屋」を再生し、外国人観光客をメインターゲットとした宿泊施設として運営してきました。
AJ社では、減少傾向にある町屋の保存・再生の進展のため、事業活動を通じて取り組みを世界に知らしめることにも努めています。
ファンドクリエーションGは、不動産・証券などの各種アセットを対象としたファンド開発を主軸とする会社です。ファンドクリエーションとAJ社が競業してそれぞれの経営資源やノウハウを活用していくことで、町屋再生ビジネスや外国人向け宿泊施設の運営ビジネスを拡大することを目的として、今回のM&Aが実施されることになりました。
提携に伴い、ファンドクリエーショングループは、町屋再生インバウンド投資ファンド設立を協働し、インバウンドビジネスへの参入を図るとのことです。
本件で、ファンドクリエーションは議決権所有割合9.1%に相当する株式数を引き受けます。引受金額は2,200万円です。
参照元:株式会社ファンドクリエーショングループ「当社連結子会社の資本業務提携に関するお知らせ」
ストライダーズとロテルド倉敷のM&A事例
2014年6月、株式会社ストライダーズが、ロテルド倉敷株式会社(以下、ロテルド倉敷)の株式を取得し、子会社化しました。
ロテルド倉敷は、「ホテル日航倉敷」の保有と経営を目的として設立された会社です。
ストライダーズは、不動産事業やホテル事業、投資事業などを営んでいます。新たなホテル取得によるホテル関連事業の拡大を目指していたところ、仲介会社から紹介を受けたことが、M&Aのきっかけになったとのことです。
また、取得後の稼働率低下リスクや、投下資金に対する収益率などを総合的に判断し、高い収益性が見込まれると判断して物件取得を決断しました。
ストライダーズは、所有割合100%の500株を取得します。取得価額(概算額)は、約4億6,300万円です(アドバイザリー費用込み)。
なお、子会社化に伴い、ロテルド倉敷は「株式会社倉敷ロイヤルアートホテル」に商号を変更しました。また、同年10月にホテル日航倉敷を「倉敷ロイヤルアートホテル」にリブランドしています。
参照元:
株式会社ストライダーズ「ロテルド倉敷株式会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ」
株式会社ストライダーズ「ロテルド倉敷株式会社の株式取得(子会社化)の取引完了及び商号変更等に関するお知らせ」
ホテル・旅館業界の現状
新型コロナウイルス拡大に伴う規制が解除されたことにより、国内外の需要が高まりつつあるのがホテル・旅館業界の現状です(2023年11月現在)。
ここから、ホテル・旅館業界に関する以下のデータを紹介します。
- ホテル・旅館施設数の推移
- 宿泊者数の推移
- 訪日外国人数の推移
それぞれ確認していきましょう。
ホテル・旅館施設数の推移
厚生労働省の「令和3年度衛生行政報告例の概況(p.5)」によると、2021年度末現在の「旅館・ホテル営業」の施設数は50,523施設でした。
2020年度(50,703施設)と比較すると、180施設(0.4%)の減少です。
2019年度は51,004施設であったため、旅館・ホテルの施設数は2019〜2021年で減少傾向にあります。
株式会社帝国データバンクの「特別企画 : 旅館・ホテル経営業者の動向調査 (2021)」によると、2020年は旅館・ホテルの倒産件数が前年66件から118件まで大幅に増加しています。新型コロナウイルスの流行がホテル・旅館業界に大きな影響を与えていたといえるでしょう。
参照元:
国土交通省「令和3年度衛生行政報告例の概況」
厚生労働省「令和3年度衛生行政報告例 第4章(表番号8)旅館・ホテル営業の施設数・客室数及び簡易宿所・下宿営業の施設数・許可・廃止・処分件数,都道府県-指定都市-中核市(再掲)別」
厚生労働省「令和2年度衛生行政報告例 第4章(表番号8)旅館・ホテル営業の施設数・客室数及び簡易宿所・下宿営業の施設数・許可・廃止・処分件数,都道府県-指定都市-中核市(再掲)別」
株式会社帝国データバンク『特別企画 : 旅館・ホテル経営業者の動向調査 (2021)』(2022年1月31日)
宿泊者数の推移
観光庁の「宿泊旅行統計調査(令和4年・年間値(速報値))(p.1)」によると、2022年度の延べ宿泊者数は4億5,397万人泊で、前年比+ 42.9%でした。新型コロナウイルス流行に伴う規制が解除されるにつれて観光需要が高まりつつあることが、2020年の約3億3,170万人泊と、2021年の約3億1,780万人泊と比べて大幅に増加している要因といえるでしょう。
外国人延べ宿泊者数が増加していることも、2021年で特筆すべき点です。延べ宿泊者数4億5,397万人泊のうち、日本人は4億3,721万人泊で前年比+39.5%、外国人は1,676万人泊で前年比+288.2%でした。
一方で、コロナ禍以前の水準を取り戻せていない問題があります。2022年の延べ宿泊者数(全体)は、2019年比で-23.8%でした。
とくに、外国人は2019年比で−85.5%です。コロナ禍が落ち着いた今後、まだ増加の余地はあるといえるでしょう。
参照元:
国土交通省観光庁「宿泊旅行統計調査(令和4年・年間値(速報値))」
国土交通省観光庁「宿泊旅行統計調査(令和5年7月・第2次速報、令和5年8月・第1次速報)」
訪日外国人数の推移
日本政府観光局(JNTO)の「訪日外客数および出国日本人数の推移」によると、2018年度の訪日外客数は約3,119万人、2019年度は約3,188万人で、いずれも3,000万人を突破しました。
しかし、コロナ禍の影響を受けて2020年度には約411万人、2021年度には約25万人と急速に減少しました。
緊急事態宣言の全面解除、GO TOトラベル事業の実施などをきっかけに、2022年度は回復の兆しが見られています。2022年度の訪日外客数は約383万人で、2021年度を約358万人も上回りました。
2023年に入ると、さらに回復の勢いが加速しています。JNTOの「訪日外客数(2023年10月推計値)」によると、2023年10月の訪日外客数は約251万人で、新型コロナウイルス感染症拡大以降、初めて2019年同月を超えました。
東南アジアや欧米豪地域の訪日外客数が増加したことが、主な要因です。国際線定期便も、2023年冬ダイヤ時点でコロナ禍以前の8割まで運行便数が回復しています。
なお、政府が発表した「『新時代のインバウンド拡大アクションプラン』の決定について」によると、観光立国推進基本計画(第4次の目標)として、2025年までに年間の訪日外国人旅行者数が2019年水準(3,200万人)を超えることを目指しているとのことです。
参照元:
日本政府観光局(JNTO)「訪日外客数および出国日本人数の推移」
日本政府観光局(JNTO)「訪日外客数(2023年10月推計値)」
国土交通省観光庁「『新時代のインバウンド拡大アクションプラン』の決定について」
ホテル・旅館業界のM&A動向
ホテル・旅館業界のM&A動向の特徴は、以下のとおりです。
- 休廃業を選択するホテル・旅館の数は減少している
- 市場変化に対応するためのM&Aが増えてきている
- 業界再編の動きや異業種の参入が活発になっている
- 中国企業がM&Aを通じて参入してきている
それぞれ詳しく解説します。
市場変化に対応するためのM&Aが増えてきている
近年、市場変化に対応するためのM&Aが増加傾向にあります。
コロナ明けを見越して今後増加するであろう訪日外国人の需要を取り込むため、観光地のホテルを買収することが具体例のひとつです。
また、今後の成長を期待できる海外市場を目指して国外の企業をM&Aするケースも、市場変化に対応した例といえるでしょう。
そのほか、デジタル化導入のため、Web業界の企業とM&Aに至るケースもあります。
全体の休廃業が減少する一方で「資産超過型」の休廃業は増加
株式会社帝国データバンクの『全国企業「休廃業・解散」動向調査(2021 年)』と『全国企業「休廃業・解散」動向調査(2022年)(p.6)』によると、2022年のホテル・旅館業の休廃業・解散件数は124件で、2021年比で28.7%減少しました。
金融機関などの支援策により、資金調達の環境が整ったことがホテル・旅館業を営む企業に休廃業をとどまらせた要因として考えられるでしょう。
一方で、財務内容にも問題がないにもかかわらず、休廃業を選択する企業が増えています。
2022年、「資産超過型」企業の休廃業率は63.4%で、前年から1.4%増加しています。
現在の財務内容やキャッシュに余力があり今は問題がなくても、物価高や人件費増加などの影響で将来的に事業を継続することが困難と判断したことが、資産超過型企業の休廃業の理由のひとつとして推測できます。
参照元:
株式会社帝国データバンク『全国企業「休廃業・解散」動向調査(2021 年)』(2022年1月18日)
株式会社帝国データバンク『全国企業「休廃業・解散」動向調査(2022 年)』(2023年1月16日)
業界再編の動きや異業種の参入が活発になっている
ホテル・旅館業で業界再編の動きや、異業種の参入が活発になっている点も特徴です。
事例でも紹介したように、海外企業や、他業種の企業がホテル・旅館業をM&Aによって獲得するケースがいくつもあります。
業界再編に伴い、今後ホテル・旅館のサービス見直しや施設の形態の変更が進むでしょう。資本力のある企業や、異業種の企業が参入することで、ホテル・旅館業において従来にはない新たなサービスが開発される可能性もあります。
中国企業がM&Aを通じて参入してきている
新型コロナウイルスの流行以降、中国企業がM&Aを通じて日本のホテル・旅行業界に進出しているといわれています。
ホテル旅館経営研究によると、2021年2月に中国人による買収案件の相談が240件で、前年同月の2.4倍であったとのことです。
中国人観光客のインバウンド獲得や、今後の価値上昇を見込んだ投資が、M&Aを進める主な目的と考えられます。
参照元:日本経済新聞「中国人投資家、苦境の旅館に食指 2月の相談2倍も」(2021年4月12日 5:00)
【買い手側】ホテル・旅館業界でM&Aを行う4つのメリット
買い手側にとって、ホテル・旅館業界とM&Aを行う主なメリットは、以下の4つです。
- 異業種の会社が買収することで、新たにホテルや旅館の運営を始められる
- すでにホテル・旅館を運営している場合は、事業規模を拡大して売上や顧客を増やせる
- 単独で進める場合よりも、迅速に経営戦略を実現できる
- 語学力・接客力、観光地や施設に関するノウハウなどを備えた人材を獲得できる
新規事業としてホテル・旅館業界への進出を検討している企業、事業拡大を目指すホテル・旅館業界の企業は、M&Aを検討するとよいでしょう。
【売り手側】ホテル・旅館業界でM&Aを行う4つのメリット
ホテル・旅館業界でM&Aを行う売り手側の主なメリットは、以下の4つです。
- 廃業せずに済むため、従業員の雇用を守れる
- 外部の経営者や会社に引き継ぐことで、後継者不在の問題を解消できる
- 資本力やブランド力を持つ企業とのM&Aにより、経営基盤を強化して事業を拡大できる
- M&Aの手法によっては売却益を得られる
ホテル・旅館業界で、「後継者が不在」「物価高に対応できない」などの理由で今後も事業を続けていくことが困難な企業はM&Aを検討しましょう。
また、M&Aの手法によっては創業者利益を獲得できます。
まとめ
2020年以降、コロナ禍の影響で宿泊客数や訪日外国人が落ち込み、ホテル・旅館業界は打撃を受けました。
しかし、新型コロナウイルスに関する規制が解除されるにつれて、ホテル・旅館業界にも復調の兆しが見えつつあります。
2022年度の延べ述べ宿泊者数は4億5,397万人泊で、前年比+ 42.9%でした。また、2023年10月の訪日外客数は約251万人で、新型コロナウイルス感染症拡大以降、初めて2019年同月を超えました。
今後、コロナ明けの観光客の需要増加を見越して、ホテル・旅館業でさまざまなM&Aが進められるでしょう。すでに、海外企業からのM&A、異業種からのM&Aなどの事例がいくつもあります。
ホテル・旅館業界でM&Aを実施することで、買い手は異業種からでもホテル・旅館運営を始められる点や、人材を獲得できる点などがメリットです。また、売り手は、後継者不在の課題を解消できる点、相手の知名度などを活かして経営基盤を強化できる点などがM&Aのメリットとして挙げられます。
そこで、後継者不在で事業継続が困難でも、従業員の雇用を守りたいと考えているホテル・旅館業界の企業や、新規事業としてホテル・旅館業界への進出を検討している異業種の企業などは、M&Aが有効です。M&Aを決断し、候補先を選定する際は、M&A仲介会社などの専門家に相談すると良いでしょう。
M&AならレバレジーズM&Aアドバイザリーにご相談を
レバレジーズM&Aアドバイザリー株式会社は、M&A全般をサポートする仲介会社です。40事業以上を展開する実績を活かし、幅広く候補先企業を提案しています。
料金体系はM&Aご成約時に料金が発生する完全成功報酬型で(譲受会社のみ中間金あり)、ご相談は無料です。ホテル・旅館業界でM&Aをご検討の際には、ぜひお問い合わせください。