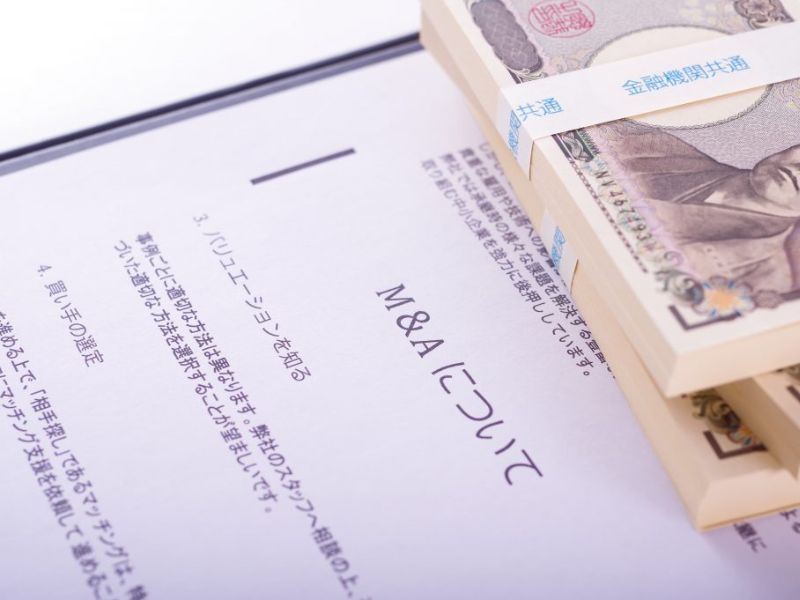このページのまとめ
- 後継者不足や経営状態の悪化などで廃業する会社が増えている
- 廃業する会社を買う主な方法は「株式譲渡」「事業譲渡」「会社分割」「合併」の4つ
- 廃業する会社を買うメリットは、安価に購入しやすい・事業拡大を狙えるなど
- 廃業する会社を買う際は、簿外債務の有無の調査や廃業する理由の確認が必要
- 廃業する会社を買うときは、公的機関やM&A仲介会社を利用することがおすすめ
「廃業する会社を買うにはどうしたらよい?」と考えている経営者の方もいるのではないでしょうか。
廃業する会社を買えば、人材や取引先を獲得できたり、ノウハウを承継できたりする点がメリットです。
本記事では、廃業する会社を買うメリットや選び方、注意点などについて解説します。この記事を読んで廃業する会社を買うポイントを押さえ、M&Aを成功させましょう。
目次
廃業する会社を買うとは?
後継者不在や経営難の結果、廃業する予定にある会社を買うことが、経営戦略の一つとして選ばれることがあります。
廃業する会社を買う場面は、経営戦略の一環として企業が購入するほか、起業やライフプランの実現などを目的に個人が廃業する会社を買うケースも少なくありません。特に、退職後に会社経営者になる選択肢として、廃業する会社を購入することに注目が集まっています。
そもそも廃業とは?
廃業は法律上で定義されている用語ではありません。廃業とは、一般的に経営者が自主的に経営をやめることを指します。後継者不在や経営の悪化など、廃業する理由はさまざまです。
廃業と似た言葉に「倒産」がありますが、両者の意味は異なります。
廃業と倒産の違い
廃業は、倒産とは異なります。
会社の倒産とは、経営が破綻して債務の支払いが困難となった状態です。
廃業は自ら会社経営をやめるのに対し、倒産は事業を続けたくてもできなくなった状態を指します。廃業は経営者が持つ選択肢のひとつですが、倒産自体はやむを得ず選ぶことになります。倒産となった状態で手続きの方法を選択できるにすぎません。
ただし、廃業する場合にも債務が残っているケースがあり、そのような場合は清算手続きが必要です。
関連記事:廃業とは?倒産や閉店などとの違いやメリット・デメリットなどを解説
会社が廃業する理由
会社が廃業する理由はさまざまです。2023年のアンケート調査では、高齢や健康上の理由、家庭の事情など経営者の事情が75.6%、売上の低迷など事業の継続困難による廃業が21.8%という結果になっています。
また、経営者が高齢化する中で、後継者がいないために事業承継ができない企業は増え続けています。その主な理由には、少子高齢化や人口の都市部集中などがあげられます。
多くの中小企業が、「後継者がいない」「子どもが都市部の企業に勤めて家業を継がない」といった後継者不在問題を抱えています。
これらの企業は廃業するといっても赤字経営とは限りません。赤字経営ではない廃業する会社の購入は、経営戦略や起業を目指す場合に有効な手段のひとつといえるでしょう。
参照元:日本政策金融公庫「「経営者の引退と廃業に関するアンケート(2023年調査)」
廃業する会社を買う4つの方法
廃業する会社を買う方法は、主に以下の4つがあります。
- 株式譲渡
- 事業譲渡
- 会社分割
- 合併
ここでは、それぞれの特徴やメリット・デメリットを解説します。
株式譲渡
株式譲渡とは、廃業する会社の株式を買い取ることで、経営権を取得する買収方法です。
基本的には株主が変わるだけであるため、会社名をそのまま使用でき、資産、事業なども全て引き継ぎます。
株式譲渡のメリットは、比較的簡単な手続きだけで買収ができ、買収における時間や手間が抑えられる点です。
デメリットは、前述の通り会社の債務も引き継ぐため、後から簿外債務が発覚し、借金を抱えてしまう恐れがあります。
また、採算が合わない不要な事業まで抱えてしまい、後から大幅な費用がかかる可能性もあります。
こうした事態を防ぐために、財務状況の事前確認やリスク調査を念入りに実施することが重要です。
事業譲渡
事業譲渡とは、廃業する会社から事業の一部もしくは全部を買い取る方法です。
事業譲渡のメリットは、買収対象は事業に限られるため、買い取りたい事業だけを選択できる点です。
株式譲渡と違い、不測の簿外債務や望まない事業を引き継ぐリスクも抱えずに済みます。
デメリットは、各種契約関係の承継について、廃業する会社から個別に承認を得る必要があるため、買収手続きが完了するまでに大幅な時間と手間がかかる点です。
また、廃業する会社の従業員にも個別の同意を得る必要があるため、移籍を拒否されてしまった場合は従業員を承継することができません。会社の取引先の契約関係も同様に個別同意が必要です。
そのため、事業譲渡を行う際には取引先や従業員に丁寧に説明をし、承諾を得ておくことが大切です。
会社分割
会社分割とは、事業を包括的に承継する方法です。
会社分割の場合、廃業する会社の法人格は、買い手の法人格に吸収されるため、消滅します。
新たに設立する会社が権利義務を承継する場合は「新設分割」、既に存在する会社が承継する場合は「吸収分割」といいます。
会社分割のメリットは、新会社の株式発行だけで承継が可能なため、手元に十分な資金がなくても、廃業する会社を買収できる点です。
また事業譲渡と違い、各種契約関係の承継について、廃業する会社や取引先、従業員から個別に承認を得る必要がありません。
ただし会社分割で買収するには、株主総会の特別決議による事前承認が必要です。
また労働承継法に基づく継承手続きが必要であるなど、厳しい手続きを要します。
合併
合併とは、複数の会社をひとつの会社に統合する方法です。
合併には「吸収合併」と「新設合併」の2種類があり、吸収合併では、購入される会社が保有していたすべての権利義務を合併後の存続会社が引き継ぎます。新設合併は、新しく会社を設立したうえで、購入される会社が持っていたすべての権利や義務を新設会社が引き継ぐ方法です。
合併の主なメリットは、事業の強みがうまく融合してシナジー効果(相乗効果)を発揮したり、人件費や設備費などのコストを削減したりできる点です。
一方、社内ルールの統合が難しく、従業員の不満や不安が起こりやすいといったデメリットがあります。
廃業する会社を買うことで得られる5つのメリット
廃業する会社を買うことで、買い手側は次のようなメリットを得られます。
- 安価で買える可能性がある
- 交渉がスムーズに進みやすい
- 事業拡大を狙える
- 人材や取引先を獲得できる
- ノウハウを承継できる
それぞれのメリットを紹介します。
安価に買える可能性がある
一般的な会社の売却では、売り手側はより高い価格にするために交渉をします。しかし、廃業する会社は何らかの事情を抱えていることも多く、売却価格にこだわらないケースも少なくありません。そのため、通常よりも安価に買える可能性があります。
購入価格を抑えることで余剰資金を購入後の新たな事業にあてることができるでしょう。
また、金額によっては個人がローンを組んで購入するのも不可能ではありません。コストを抑えて起業することが可能です。
交渉がスムーズに進みやすい
廃業を検討している会社は事業の継続や従業員の雇用継続などを主な目的とすることも多く、一般的な会社の売買に比べて交渉がスムーズに進みやすいのもメリットです。
たとえば、会社の売却益獲得が主な売却理由の場合、条件面で折り合いがつきにくく、交渉が長引く可能性があります。
しかし、廃業予定の会社は売却価格にこだわらないことも多く、早く合意に進む可能性があるでしょう。
事業拡大を狙える
買い手側のメリットは、事業拡大が期待できることです。
一般的に事業をスタートするには、設備投資や人材の確保・マーケット調査・販路の構築などするべきことが多岐にわたり、膨大な時間と費用を要します。
廃業する会社を買うことで、これらの設備や資本、業務のノウハウなども取得できるため、事業設立時にかかる時間と費用を削減できます。
さらに、買い手側のこれまで培ってきたノウハウや資本、設備の共同化などが上手くできれば、相乗効果で事業拡大も見込めるでしょう。
人材や取引先を獲得できる
廃業する会社を買う場合、在籍していた従業員を引き継げるため、人材を確保する手間がありません。事業に関する技術・ノウハウを持つ人材を獲得できることで、購入後の事業もスムーズに進められるでしょう。
また、取引先に関しても同様です。経営者が変わっても会社の方針や制度などが変わらない限り、基本的に取引先との信頼関係も崩れることはないと予想できます。
ノウハウを承継できる
廃業する会社を買う場合、ノウハウを継承できるケースがあることもメリットです。独自の技術や企業秘密となっているノウハウを持つ会社であれば、買収により獲得できます。
企業のノウハウは他社と差別化できるポイントで、市場で生き残るために重要な要素です。引き続き活用したり、新たな活用方法を考えたりすることで、利益を生み出すことができるでしょう。
廃業する会社を買う際の3つの注意点
廃業する会社を買う際は、次のようなトラブルに注意が必要です。
- 簿外債務を引き継ぐことがある
- 従業員を引き継げない可能性がある
- 取引先を承継できない可能性がある
詳しくみていきましょう。
簿外債務を引き継ぐことがある
本来、企業の負債は全て貸借対照表に記載されるべきですが、何らかの事情で記載されないケースもあります。これを「簿外債務」といいます。
簿外債務は決して珍しくなく、たとえば、経営者が個人の保証人であることを会社に報告しないまま計上が漏れているなどによって発生します。また、未払い残業代も簿外債務にあたります。
簿外債務を引き継がないためにも、買収前の調査を徹底して行うことが重要です。
従業員を引き継げない可能性がある
廃業する会社を買ったあと、経営者が変わったことで従業員が辞めてしまうリスクがあります。経営者に対する従業員の人望が厚い場合、経営者の交代は従業員の去就に影響を与えるでしょう。
また、企業文化が変わる場合、なじめない従業員は辞めてしまう可能性もあります。優秀な人材を失うことになれば、買い取った事業に失敗してしまう恐れもあるでしょう。
従業員の離脱を防ぐため、購入の前後にわたって従業員との丁寧なコミュニケーションが必要です。
取引先を承継できない可能性がある
既存の取引先も、購入後の事業運営に大きな影響を与えます。取引をしている理由が、前の経営者の人柄やコネクションによる部分が大きい場合、経営者が変わることで取引を停止されるリスクもあるでしょう。
取引を継続するためには、取引先とのコミュニケーションをとり、経営者の交代が取引先にとってメリットがあることを伝えたり、信頼関係を築いたりすることが必要です。
M&Aにおける弊社契約事例
ここでは、実際にあった弊社でのM&A契約事例をご紹介します。
【弊社事例1】HRテック×マーケティング支援
株式譲渡によるM&Aの事例です。売り手側の会社は国内屈指の導入企業数を誇るASPサービスの展開をしており、株式上場も目指していました。しかしながら自社だけでの事業拡大に限界を感じてM&Aの検討をすることに。一方で買い手側の会社は東証上場、売り手側の会社同様ASPサービスを展開しており業界2位のシェアを誇る企業でしたが、これ以上のシェア拡大に苦戦しているところでした。
事業の親和性が高い両社のM&Aを実行することで、売り手側の会社は上場企業の傘下に入り、さらなる事業拡大を目指せるでしょう。
買い手側の企業は業界トップのシェアを獲得できました。
【弊社事例2】Web制作×自社プロダクト開発
次の事例も株式譲渡によるM&Aです。
売り手側の会社は、Web制作やアプリケーション開発を扱う会社です。
従業員のエンジニアとしての高い技術力を活かし、自社でプロダクト開発に取り組みたいと思いながらも、会社の規模が小さく、資金面やリソース面から実行に移せずにいました。
そこで弊社でM&Aのサポートをさせていただき、大手企業の傘下に入ることで、これまで実行できずにいた自社でのプロダクト開発を1年経たずして成功させました。
また、大手企業の既存のクライアントから、これまで自社だけでは獲得できなかった案件も依頼を受けるようになり、従業員のスキルアップやリテンションにもつながっています。
実際に会社はどこで購入できるのか?
実際に廃業する会社を買うには、公的機関や地元の金融機関に紹介してもらうか、M&A仲介会社、マッチングサイトを利用するという方法があります。
ここでは、それぞれの方法のメリットや注意点について解説します。
事業承継・引継ぎ支援センターを利用する
都道府県ごとに設置されている事業承継・引継ぎ支援センターを経由して、会社を買うことができます。
事業承継・引継ぎ支援センターは後継者不足に悩む中小企業を支援するために国が開設した公的機関です。
M&Aについてよく知らない方でも窓口で相談ができ、手続きの流れや疑問点に答えてもらえます。
また、希望の予算や業種を伝えて、売り手の中小企業を紹介してもらうことも可能です。
地元の金融機関に相談して決める
地元の金融機関に相談し、廃業する予定がある会社を紹介してもらう方法もあります。取引先の地方銀行であれば、自社や地域の会社の事情を把握していることから、相談しやすいでしょう。
銀行は融資も行っているため、会社を買収する際の資金不足が気になる場合にも良い相談先といえます。
地方銀行は地域に根差し、専門家と連携したM&Aのサポートを行っています。懇意にしている銀行があれば、一度相談してみるとよいでしょう。
M&A仲介会社に相談して決める
M&Aに関する業務を専門的に扱っている支援機関が、M&A仲介会社です。
M&Aのあらゆるプロセスに対応してくれるので、安心してサポートを任せられるでしょう。
数多くの案件を持っているM&A仲介会社を選べば、幅広い相手からM&Aの候補先を探してもらえます。
M&Aの仲介会社はさまざまな種類があるので、サービス内容や成約事例を確認して自社に合った仲介会社を選びましょう。相談は無料で受け付けている仲介会社も多いので、複数社に相談してから見極めることがおすすめです。
マッチングサイトを使う
M&Aマッチングサイトを利用すれば、会社の売却情報を簡単に確認できます。
マッチングサイトのメリットは、会社を買う予算や希望の業種を絞り込んで検索できる点です。
どのような会社が売られているのかを、気軽に検索するにはおすすめの方法でしょう。
サイト非公開の情報やさらに詳しい情報を知るためには、会員登録や問い合わせが必要になることがほとんどです。
マッチングサイトに掲載されている会社の規模は多種多様で、300万円程度で購入できる会社もあれば、1,000万円を超える会社も掲載されています。
M&Aを成功させるための会社選びの3つのポイント
廃業する会社の買収に成功するためには、会社選びが重要です。失敗しない会社選びには、次の3点を押さえましょう。
- 廃業する理由を確認する
- デューデリジェンスを行う
- 理解できる業種を選ぶ
それぞれの内容を解説します。
廃業する理由を確認する
M&Aを成功させるためには、会社を買う前の段階で廃業する理由をしっかりと確認することが必要です。
経営者が廃業を選択する理由はさまざまです。
たとえば、廃業する会社が黒字経営だった場合にも注意しなければなりません。表面には出ない理由が事業に大きく影響する可能性もあります。理由がわかれば、事前に対策を立てることもできるでしょう。
また、赤字で廃業する会社の場合は、負債を引き継いでも採算が合うのかを確認することが必要です。
デューデリジェンスを行う
廃業する予定の会社に隠れた問題がないかを確認するためにも、保有資産や債務、財務状況などへのデューデリジェンス(企業価値やリスクの徹底調査)が欠かせません。
まず、簿外債務などのリスクがないかを調べます。簿外債務とは、貸借対照表に記載されていない債務のことです。税務会計で決算書を作成する中小企業では、退職給付引当金や賞与引当金などが簿外債務となっているケースがあります。貸借対照表を見ても把握できないため、デューデリジェンスによる確認が必要です。
また、業績悪化が廃業の理由である場合、事業を立て直せる可能性がどのくらいあるのかもチェックしなければなりません。
買収の失敗を回避するためには、デューデリジェンスの結果をみて購入を決めることが大切です。
理解できる業種を選ぶ
実際に廃業する会社を買ってみたものの、参入した市場に対しての知識やノウハウ不足が原因で想定していた利益を見込めなかったという事例は少なくありません。
現在営んでいる事業と同じ業界・業種であれば、市場の特徴や事業拡大のために必要な情報を把握しやすいでしょう。少なくとも理解の及ぶ業種を選べば、買収後により的確な戦略を実行でき、事業の成功確率が高まります。
もし詳しくない業種を購入しようとする場合、その業種に対する理解を深めたり、その業種に通じた人材を採用したりするなど、対策を講じましょう。
まとめ
廃業する会社は安価で購入しやすいというメリットがあり、、人材や取引先を獲得できる可能性もあります。ノウハウを承継し、事業拡大につなげられることもあるでしょう。
廃業する会社を買う方法は「株式譲渡」「事業譲渡」「会社分割」「合併」の4つがあります。それぞれの特徴やメリット・デメリットを把握して、自社に合う方法を選ぶとよいでしょう。
ただし、廃業する会社を買うためには複雑な手続きやプロセスがあり、必要とする知識も多々あります。財務状況や簿外債務の有無を調査するためのデューデリジェンスには、専門家のサポートも必要です。
レバレジーズM&Aアドバイザリー株式会社は、M&A支援サービスを提供する仲介会社です。各領域で実績を積み重ねたコンサルタントが、相談から成約まで一貫してサポートを行います。廃業する会社を買うときの相談も無料で行いますので、お気軽にお問い合わせください。