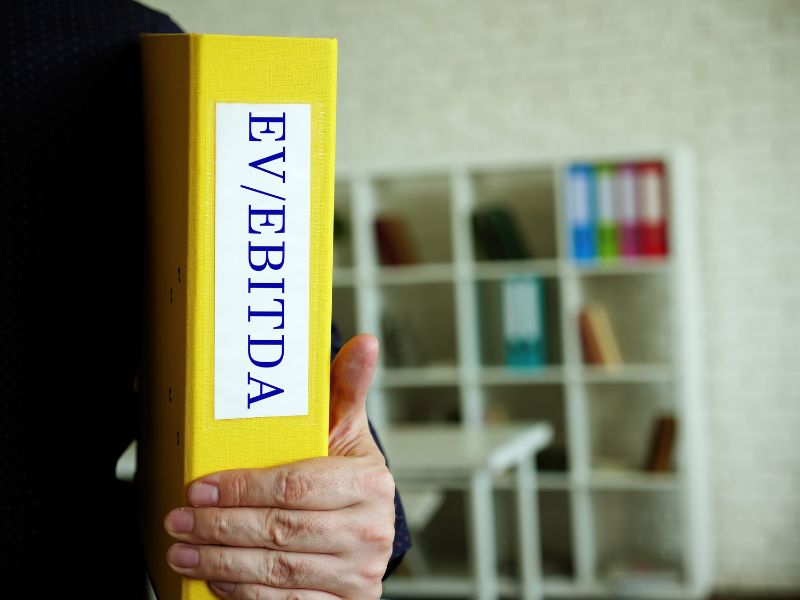このページのまとめ
- M&Aの相談では、必要な準備や期間、売却金額などさまざまなことを相談できる
- M&Aの相談先には商工団体や金融機関、士業、M&A仲介会社などがあげられる
- M&Aの初回の相談料は無料が多く、M&Aの成立では成功報酬がかかる
- M&Aの相談先を選ぶときは、サポート範囲や成約実績、報酬などの確認が必要
「M&Aの相談をしたいけれど、どこにすればいいのかわからない」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか?M&Aの相談先は、M&A仲介会社や士業、金融機関などがあげられます。それぞれにメリット・デメリットがあるため、自社に合う相談先を選びましょう。
本記事では、M&Aの相談先やその特徴、選ぶ際のポイントなどを解説します。M&Aの実施でかかる費用も紹介しますので、ぜひチェックしてください。
目次
売り手・買い手に共通するM&Aの相談内容
M&Aを進めるには専門知識や経験が必要であり、専門家・専門機関への相談が欠かせません。
相談先に相談する内容は、売り手・買い手に共通するものと、それぞれに特有の内容があります。
売り手・買い手に共通する相談内容には、次のものがあげられます。
- M&Aに必要な準備
- M&Aにかかる期間
- 機密情報の取り扱い
- デューデリジェンスについて
ここでは、売り手・買い手に共通する相談内容を紹介します。
M&Aに必要な準備
M&Aでは売り手・買い手それぞれに必要な準備があり、しっかり準備してから取り組まなければなりません。そのため、売り手・買い手ともに、どのような準備が必要なのかを相談することが多いでしょう。
必要な準備として相談するのは、次のような項目です。
- 揃える必要資料
- 企業概要書の作成方法(売り手側)
- 自社の分析に必要なこと
- 把握しておくべきリスクはなにか
- M&Aの実施が自社の状況に本当に適しているのか
- 自社の目的に合う相手先企業の探し方
- 対象企業のリスクを把握する方法
M&Aを成功させるためには、シナジー効果を発揮できる相手先企業を探すことが大切です。そのためには、自社分析が必要であり、その方法を相談するとよいでしょう。M&Aの目的を定め、それを実現するためにM&Aが適しているのかの確認も必要です。
M&Aにかかる期間
M&Aにはどのくらいの期間はかかるのかは、売り手・買い手のどちらも気になるところでしょう。期間の目安を知ることで、具体的なスケジュールを組むことができます。
M&Aにかかる期間は一般的に半年から1年程度とされていますが、案件ごとに異なります。数ヵ月程度で完了するケースもあれば、数年など長期にわたる場合もあるでしょう。
期間について目安をつけるため、相談では次の点を確認してください。
- 案件ごとの期間の目安
- どのような点を工夫すれば期間が短縮できるか
- どういった場合に期間が延びてしまうのか
- 期間が長引かないようにできる対策はあるか
相談先では過去の実績から判断し、目安となるおおよその期間を示してくれます。それをもとに、具体的な計画を立てるとよいでしょう。
機密情報の取り扱い
M&Aで売り手企業は、自社の機密情報を買い手側の候補に開示する必要があります。自社の企業秘密についてどう扱われるかは、重要な問題といえるでしょう。
機密情報としては、次の内容があげられます。
- 取引先に関する情報
- 顧客・従業員などの個人情報
- 財務・経理に関する情報
- 未公開の新商品・プロジェクトに関する情報
これらの情報がどのように扱われるのか、しっかり確認しておきましょう。
話し合いを通して企業秘密についてやり取りすることも多く、秘密保持の方法についは早い段階で確認が必要です。
また、万が一、情報漏洩が起こってしまった場合の対処法や、相談先の情報管理体制についても相談で確認しておく必要があるでしょう。
デューデリジェンスについて
デューデリジェンスも確認しておきたい事項です。デューデリジェンスとは買い手企業が行う調査であり、財務、法務、人事など幅広い面で売り手企業が抱えるリスクを確認します。
買い手側が相談する項目は、次のとおりです。
- 専門家の選定
- 必要な調査内容
- 質問する事項
- 揃える資料
- 実施にかかる期間
- かかる費用
相手先企業のリスクをしっかり把握するために、どのような調査を行えば良いかを確認しておきましょう。
売り手側が相談する項目は、次のとおりです。
- どのような調査が行われるか
- 揃えておく資料
- 質問への回答
- デューデリジェンスまでに行うべきこと
売り手側は、デューデリジェンスで問題を指摘されないために、何をしておくべきか相談すると良いでしょう。
売り手企業におけるM&Aの相談内容
売り手企業として相談することの多い内容は、次の2つです。
- 買い手企業が見つかるか
- 売却金額について
それぞれの内容をみていきましょう。
買い手企業が見つかるか
売り手企業にとっては、自社の買い手企業が見つかるのかが気になるところでしょう。最初の相談では、まずその点を確認したい経営者が多いかと思います。
買い手企業が見つかるかを相談する際は、M&Aで実現したいことを明確にして、次のような相談をしてみるのもおすすめです。
- 目的の実現のためにどのような企業を選べば良いか
- 自社と似た案件では、相手先企業にどのような企業が選ばれているか
- 自社のような企業とM&Aを希望している会社はあるか
M&Aでは信頼して事業を任せられる相手先が見つかるとは限らず、不安に感じることもあるでしょう。買い手企業が見つかるのかという相談とともに、そもそもM&Aという選択が正しいのかも合わせて確認しておく必要があります。
売却金額について
売却金額がどのくらいになるかも、売り手企業にとって重要な事項です。相談先には、売却金額の大体の目安を出してもらうことができます。
売却金額を上げるためにはどうすれば良いかも確認しておきましょう。具体的には、次のような相談をします。
- 自社の評価を高めるためには何をすれば良いか
- 企業価値を上げるために今からできることはあるか
- マイナスポイントを減らすことはできるか
売却金額を高める方法がわかれば、M&A実施までに対策ができます。
最終価額は交渉によって決まりますが、交渉の過程で算出する企業価値については、ある程度の算定方法が決まっています。そのため、相談の段階でも算出することは可能です。どのくらいの金額で売却できるのか目安を知っておけば、条件交渉も進めやすいでしょう。
買い手企業におけるM&Aの相談内容
買い手企業が相談することの多い内容は、次の2つです。
- 資金調達について
- M&Aの実行後について
それぞれの内容を紹介します。
資金調達について
買い手側は相手先企業を買収するため、多額の資金が必要になります。金額の目安はM&Aの手法や譲り受ける範囲によっても変わるため、自社が行うM&A手法でどのくらいの資金が必要かを相談しておくことが大切です。
また、資金の準備のために融資が必要になる場合、資金繰りをどのようにすればよいか相談をすることも可能です。
資金調達についての相談項目は、主に次のような内容です。
- 資金調達にはどのような方法があるか
- どのくらいの調達が可能か
- これまで、自社のような規模の会社でどのくらいの資金が必要になっているか
- 補助金や助成金は利用できるか
資金調達については、自社と同じようなM&Aでの事例も確認しておくとよいでしょう。
M&Aの実行後について
M&Aは成立して完了ではなく、事業運営が円滑に進むようPMI(経営統合)が重要です。PMIは業務体制やシステムの統合だけではなく、企業文化など意識の側面も含まれます。PMIがうまく進まなければ思うような事業運営ができず、シナジー効果も発揮できません。
M&A仲介会社ではPMIのサポートも行っているところもあり、相談先ではどのようなサポートを行うのかを確認しておくとよいでしょう。
PMIについての相談項目は、主に次のような内容があげられます。
- PMIの実施期間
- 実施の流れ
- 準備すること
- どのような体制を作るか
- どのような人材が必要か
相談機関でPMIもサポートするのであれば、詳細を確認しておきましょう。
M&A相談先の特徴とメリット・デメリット
M&Aの相談先は、主に次の5つです。
| 相談先 | 特徴 | メリット | デメリット |
| 商工会・商工会議所 | ・中小企業の相談窓口 ・会員になると、さまざまなサポートを受けられる | ・助成金などの支援制度に詳しい ・地元企業の情報を持ち、紹介してくれる場合がある | ・会員にならなければ相談できない ・入会金・会費が必要 |
| 事業承継・引継ぎ支援センター | ・全国に設置されている公共の相談窓口 ・事業承継・M&Aの情報提供やアドバイス、マッチングを行う | ・相談窓口が全国にあり、無料で利用できる ・専門家に相談できる | ・サポート範囲が限定される場合もある ・支援実績がまだ十分ではない |
| 金融機関 | ・融資が必要なケースで有用な助言を受けられる ・M&Aの専門部署を持つ金融機関もある | ・付き合いのある金融機関であれば自社のデータがあり相談しやすい ・資金調達の相談ができる | ・中小企業のサポートは行っていないこともある ・報酬が高額になるケースもある |
| 士業など専門家 | ・税理士や公認会計士、弁護士などの専門家にはM&Aの相談もできる | ・顧問契約のある士業であれば相談しやすい ・税務や財務など専門的な助言が受けられる | ・M&Aの支援経験がない場合もある ・相談できる範囲が限定されやすい |
| M&A仲介会社 | ・中立的な立場で売り手と買い手を仲介する ・相手先の紹介や交渉を支援する | ・候補先が豊富で、複数の候補から相手先を見つけやすい ・相談からM&A成立までの一貫した支援が受けられる ・交渉が円滑に進みやすい | ・着手金や中間金が発生する会社がある ・希望よりも低い金額で売却になることもある |
M&Aの相談先について、特徴やメリット・デメリットを詳しくみていきましょう。
商工会・商工会議所
商工会や商工会議所は、地域の中小企業をサポートしている団体組織です。事業承継やM&Aに関する相談にも対応しています。地元企業の情報を多く保有しているため、自社に合う相手先を探してもらうことも可能です。
助成金や補助金、税制優遇措置など公的な支援制度についての相談もでき、具体的な手続きなどを聞くこともできるでしょう。
中小企業と多く関わっていることから、経営者に寄り添ったサポートが期待できます。
相談は無料ですが、会員でなければ相談できず、入会費や会費がかかる点がデメリットです。また、M&Aの専門機関ではないため、相談内容によっては詳しく確認できないこともあるでしょう。
事業承継・引継ぎ支援センター
事業承継・引継ぎ支援センターとは、全国の都道府県に設置されている公共の相談窓口です。2021年、親族内支援を行う「事業承継ネットワーク」と、M&A支援を行う「事業引継ぎ支援センター」が統合し、法令に基づく認定機関として全国に設置されました。
後継者問題に悩む中小企業・小規模事業者を対象として、事業承継やM&Aの情報提供、アドバイス、マッチングなどを行っています。
各センターでは中小企業診断士や税理士といった専門家が相談に対応しており、無料で利用できます。
参照元:事業承継・引継ぎ支援センター
金融機関
融資を受けているなど、普段から懇意にしている金融機関がある場合は、M&Aの相談先になります。すでに自社の業務内容や財務状況などを把握しているため、スムーズに話を進められるでしょう。とくに、買い手企業は資金調達の相談ができます。
近年は、事業承継やM&Aに関する専門部署を設置している金融機関もあり、専門知識を持った担当者が相談に対応してくれます。
ただし、M&Aに関する支援を行っていない金融機関もあり、支援はしていても中小企業には対応していないケースがあるでしょう。専門部署を置く金融機関は、主に大企業が対象です。
また、金融機関にサポートを依頼する場合の手数料や成功報酬は、高額になる傾向にあります。
士業など専門家
財務や税務、法務などの専門知識を持つ士業も、M&Aの相談先となります。顧問契約をしていて普段から交流のある士業であれば、具体的なアドバイスを受けたり、複雑な手続きを依頼したりすることもできるでしょう。
顧問会計士や税理士であれば、自社の会計や税務の状況をよく理解しているため、相談しやすいのがメリットです。
とくに公認会計士は、企業価値の算出や買い手企業によるデューデリジェンスを行う場合の相談に適しています。複雑な企業価値の算出について、専門家のアドバイスを得られることもメリットです。
税理士は、M&Aによって発生する税金に関してアドバイスを受けられます。税務関連のデューデリジェンスについて相談もできるでしょう。
M&Aでは秘密保持契約書や基本合意書、譲渡契約書など契約を締結する場面も多く、法律の専門知識も必要です。そのため、弁護士も良い相談先になり、具体的なアドバイスを受けられます。雇用に関する契約関係についても、専門的な相談ができるでしょう。
ただし、公認会計士や税理士は、財務・税務に関する内容や資金面では専門的なアドバイスを期待できますが、M&Aについての知識や経験が十分でないケースもあります。
また、弁護士はそれぞれ得意分野があり、M&A支援について経験が不足するケースもあるでしょう。
士業への相談はあくまで限定的な範囲で、ほかの相談先と合わせて利用するのが一般的です。
M&A仲介会社
M&A仲介会社とは、売り手と買い手を中立的な立場で仲介する会社です。M&Aを専門として運営しており、税務や法務などの専門家も在籍しています。M&Aについて、専門的な知識・経験に基づいたアドバイスやサポートが期待できるでしょう。
多くの仲介会社では、初期相談から相手先企業の選定、企業価値評価、相手先との交渉など、M&Aの全工程をサポートしています。
M&A仲介会社は、多数の候補企業から相手先を探せることが大きなメリットです。売り手側・買い手側の双方が納得できるような企業を探してマッチングするため、自社の希望する相手先を探しやすいでしょう。
また、M&A成立まで一貫して支援する会社も多く、M&Aをスムーズに進行できるのもメリットです。
料金体系は、完全成功報酬型でM&Aが成立するまで報酬が発生しない会社もありますが、着手金や中間金が発生する場合もあります。初期段階ではできるだけ支出を抑えたい場合は、完全成功報酬制を採用する会社を選ぶとよいでしょう。
M&Aにかかる費用
M&Aの実施では、さまざまな費用がかかります。どのような費用があり、金額はどのくらいなのかをあらかじめ確認しておけば、事前に資金を用意しておくことができます。
M&Aにかかるのは、主に次のような費用です。
- 相談料
- 着手金
- 中間金
- 成功報酬
このほか、買い手側はデューデリジェンス費用がかかり、M&A仲介会社と契約する場合は月額報酬(定額顧問料)としてリテイナーフィーの支払いが必要です。
ここでは、M&Aにかかる費用を解説します。
相談料は無料のケースが多い
相談料とは、M&Aの正式な依頼を行う前に相談するときの費用です。M&A仲介会社に相談する場合、相談料は無料の場合がほとんどですが、会社によっては1万円程度の相談料を設定しているケースもあります。相談する前に、相談料の有無を確認しておくと安心です。
士業など専門家に相談する場合は相談料がかかる場合が多いため、確認してから予約するとよいでしょう。
また、商工会議所など、会員でなければ利用できない場合は入会金や会費が必要です。
着手金を支払う場合もある
相談をしてM&Aの依頼を決定した場合、着手金が必要な会社・専門家もあります。着手金は100万円〜200万円程度が相場で、M&Aが成立しなかった場合も返還されません。
着手金を支払う仲介会社の場合、「M&Aをまだ具体的に考えてはいないものの登録だけしている」という買い手や売り手がいないということがわかります。M&Aの成功を真剣に目指している企業が集まっていることがメリットといえるでしょう。
ただし、一度支払えば返金されないため、資金に余裕がない場合は着手金のかからない仲介会社を選ぶ必要があります。
中間金がかかる場合もある
M&Aを依頼して交渉がある程度進行した際、中間金を支払う場合もあります。支払いのタイミングは、基本合意書を締結した段階に設定されていることが多いでしょう。
金額は、100万円程度の固定報酬か、M&A成約時にかかる成功報酬の10%~20%程度に設定されているか、いずれかのパターンに分かれます。
基本合意書は一般的に法的拘束力がなく、基本合意書の締結後に中間金を支払った場合でも、M&Aが成立しないことはあります。デューデリジェンスの結果や条件交渉の内容によっては、成立しないケースも多いといえるでしょう。
M&Aが成立しない場合でも、着手金と同じく中間金は返金されません。中間金かがかからない仲介会社もあるため、検討材料のひとつとしてチェックしておきましょう。
成功報酬はM&A最終価格による
M&Aの最終契約を締結したら、成功報酬が発生します。取引金額が少額の場合は設定されている最低報酬金額が成功報酬となりますが、ほとんどの場合は「レーマン方式」で手数料額が算出されます。
レーマン方式とは、M&Aの取引金額に一定の手数料率を乗じる計算方式です。手数料率は支援機関ごとに設定されていますが、次のような数値に設定されているケースが多いでしょう。
| 取引額 | 手数料率 |
| 5億円以下 | 5% |
| 5億円超~10億円以下 | 4% |
| 10億円超~50億円以下 | 3% |
| 50億円超~100億円以下 | 2% |
| 100億円超 | 1% |
レーマン方式では、報酬基準額を複数の区分にして、区分ごとに成功報酬を計算します。
たとえば、取引額が6億円の場合、4%の手数料率を乗じるのではなく、5億円までの金額には5%の報酬率を乗じ、さらに5億円超の1億円分については4%の手数料率を乗じるという方式です。
一例として、M&Aの取引額が12億円だった場合、成功報酬の計算式は次のとおりです。
(5億円×5%)+(5億円×4%)+(2億円×3%)= 5,100万円
最低報酬額が設定されている場合、レーマン方式により算出された成功報酬額が最低報酬額より低ければ、最低報酬額を支払うことになります。
たとえば、最低報酬額が300万円で設定されている場合、レーマン方式で算出した額が200万円であっても、300万円を支払わなければなりません。
デューデリジェンス費用やリテイナーフィー
デューデリジェンス費用は、買い手が行うデューデリジェンス(買収監査)に支払う費用です。買い手自身が調査を依頼する公認会計士や税理士、弁護士などの専門家に支払います。
費用相場は、依頼する内容や案件の規模によって変動するでしょう。中小企業の調査で会計・税務、法務の調査を依頼した場合、数十万円〜数百万円程度かかります。
リテイナーフィーとは、M&A仲介会社へ毎月支払う定額手数料です。リテイナーフィーの金額はM&Aの難易度や担当するコンサルタントのレベルにより異なり、発生しない仲介会社もあります。
リテイナーフィーがある場合、契約期間中は発生し続けるため、M&Aの成立が長引けば、それだけ費用の負担も大きくなるでしょう。
近年はM&A件数の増加に伴ってM&A仲介会社も増え、価格競争でリテイナーフィーがかからない仲介会社も増えています。
M&Aの相談先を選ぶポイント
M&Aの相談先を選ぶときは、いくつか押さえるべきポイントがあります。
自社に合う相談先を選んでM&Aを成功させるためにも、選び方のポイントをチェックしておきましょう。
サポート範囲・サービス内容が自社に合っているか
すでにご紹介したように、M&Aの相談先は複数あり、依頼できる内容はそれぞれ異なります。サポート範囲やサービス内容について、自社が求めているものと合致するかを確認しましょう。
近年は、初期相談から交渉、クロージングまで一貫してサポートするM&A仲介会社も増えており、M&A後のPMIをサポートする会社もあります。
M&Aの工程は複雑であり、自社が受けたいと考えるサービスが整っていないと、思うようなM&Aを実現できません。提供しているサポート・サービスの内容を確認し、自社に合う相談先を選びましょう。
また、相談先は、大企業を専門に扱ったり中小企業に特化したりなど、得意とするジャンルがあります。特定の業界に強みを持つ相談先もあるでしょう。自社と同じ業界・規模の案件を多く扱っている相談先であれば、M&Aがより円滑に進められます。
親身になって相談にのってくれるか
M&Aの相談先は、親身になって相談にのってくれるかも重要なポイントです。実際に依頼したあとは頻繁にやり取りをするため、信頼できる担当者であるかどうかはM&Aの進行に大きく影響します。信頼できるかどうかを見極めるためにも、最初の相談で対応する担当者の印象はよくチェックしておきましょう。
どれだけ有名な会社で実績が豊富でも、担当者がこちらの話をよく聞かず、自社のアピールばかりしていたり、一方的に自分の意見を伝えたりする場合は円滑なM&Aが期待できません。
M&Aに関する疑問や悩みに対してしっかり耳を傾け、自社に寄り添って考えながらアドバイスをしてくれる相談先を選びましょう。
M&Aの実績が豊富か
M&Aは専門的知識が必要ですが、それだけではM&Aをスムーズに進められるとはいえません。豊富な成約実績があればあるほど、それだけ経験に基づいた質の高いアドバイスが期待できます。
成約実績数が豊富にあるということは、優秀なM&Aアドバイザーが多数在籍していることを証明しています。
最初の相談時に、これまでの成約実績について質問してみてください。できれば、具体的な成功事例も確認しておくとよいでしょう。自社が予定しているM&Aと似ている案件を扱っていれば、より有益なアドバイスが期待できます。
必要な情報を提供してくれるか
M&Aの相談では、必要な情報を提供してくれるかもチェックしましょう。
M&Aアドバイザーは、M&A全体の工程に関わって調整を行い、円滑に進める役割があります。そのためには、必要な情報をどのタイミングで提供するかを、適切に判断できなければなりません。
M&A依頼前の相談でも、必要な情報を漏れなく提供してくれる相談先であれば信頼できます。
M&Aの相談が無料であるからといって、必要な情報を出し惜しむ相談先ではあまり信用できないでしょう。
最終的なM&Aの成功を願うのであれば、相談の段階から必要な情報を提供してくれると考えられます。
成果に対して報酬額が妥当か
M&Aにかかる費用は相談先によってさまざまで、成果に対する報酬が妥当かどうかの判断も必要です。報酬額が、M&Aを成功させることで達成できる目的や得られる利益、シナジー効果からみて十分に見合うものか確認しましょう。
成功報酬の算出方法や、着手金・中間金、リテイナーフィーの有無については初期段階でしっかり確認しておいてください。よく確認しておかないと、想定外の費用が発生してトラブルの原因になることもあります。
相談先のサイトや資料で報酬額の仕組みがよくわからない場合、そのままにせず、相談時に質問して説明を受けることをおすすめします。
迅速に対応してくれるか
M&Aを依頼したあと、迅速に対応してくれるかどうかも確認が必要です。M&Aには数多くのプロセスがあり、実際に進めていく上で、速やかな進行が求められる場面も多々あります。
M&Aアドバイザーは全体を調整し、円滑に進行する役割があり、スジューリングや時間管理の能力が必要です。
段取りがうまくできずに遅延が発生すると、M&Aが不成立に終わる可能性もあります。M&Aをスムーズに成功させるためには、何事も迅速に進められる相談先を選びましょう。
たとえば、連絡や問い合わせをした際に、速やかに返答があるかどうかも判断材料になります。
まとめ
M&Aのプロセスは複雑であり、専門的な知識を持つ期間や人材のサポートが不可欠です。M&Aのサポートを依頼する前には専門家や専門機関に相談するのが一般的で、相談では、必要な準備やM&Aにかかる期間、売却金額など、M&Aに関するさまざまな内容を確認できます。
M&Aの相談先は複数あり、最初はほとんどの相談先が無料で相談に対応しています。商工団体や金融機関などでも相談はできますが、相手先の選定や交渉のサポートなどを依頼したい場合は、成約まで一貫してサポートを行うM&A仲介会社を選ぶとよいでしょう。
依頼先を選ぶときは、サポート範囲やサービス内容が自社に合っているか、自社に寄り添って対応してくれるか、実績は豊富かなど、チェックすべきポイントがあります。
「M&Aについて相談したいが、どこを選べばよいかわからない」「親身になって相談にのってくれる相談先を選びたい」と考えている方は、レバレジーズM&Aアドバイザリー株式会社のご利用をご検討ください。各領域で実績を積み重ねたコンサルタントが在籍し、相談から成約まで一貫してサポートを行います。
料金体系は、M&Aご成約時に料金が発生する完全成功報酬型です。譲受会社のみ中間金の設定があるものの、M&Aのご成約まで、ご相談も含めて無料でご利用いただけます。「信頼できる相談先を見つけたい」という方は、お気軽にお問い合わせください。