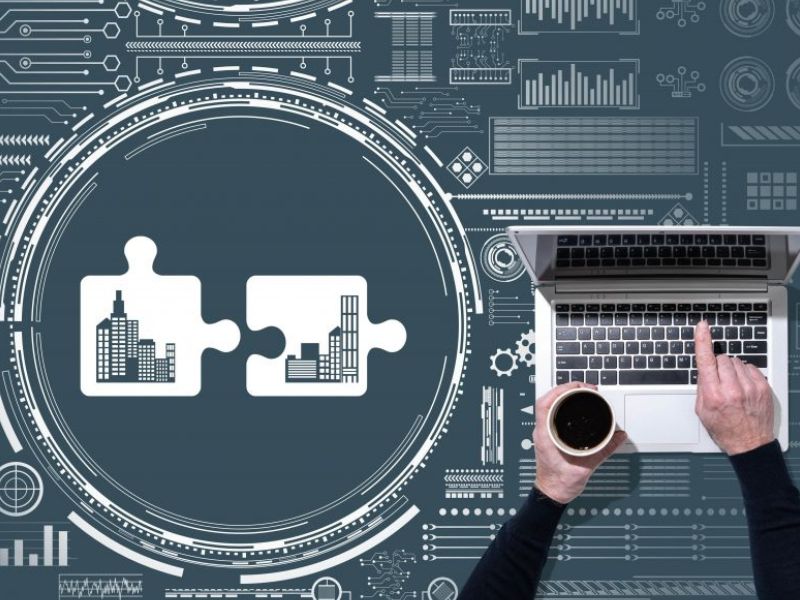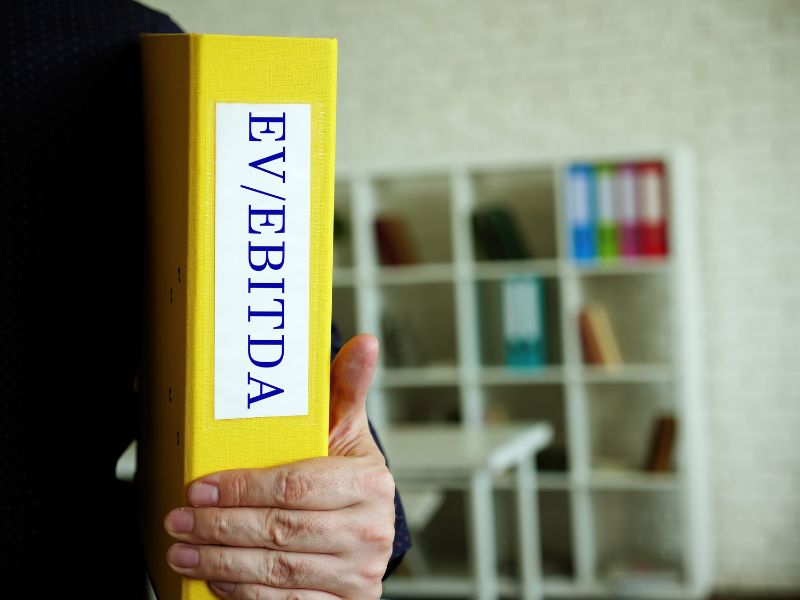このページのまとめ
- 中小企業のM&Aが増えている背景には、後継者不在や縮小する国内市場への対策がある
- 売り手側が中小企業M&Aを行う目的は、後継者不在の解消や事業拡大など
- 買い手側が中小企業M&Aを行う目的は、人材獲得や新規事業への参入など
- 中小企業がM&Aを実施する際は、株券の取り扱いやコンプライアンス違反に注意する
- M&Aの実施には専門的なノウハウが必要であり、支援機関の利用がおすすめ
「中小企業でもM&Aはできるのだろうか」と不安に思っている方も多いのではないでしょうか。
後継者不在の解消などを目的に、M&Aを検討する中小企業は年々増加しています。M&Aの実施には専門知識が必要であり、円滑に手続きを進めるためには支援機関のサポートが必要です。
本記事では、中小企業のM&Aを進めるプロセスや成功のポイントを解説します。支援機関やM&Aの成功事例も紹介しますので、チェックしてください。
目次
中小企業M&Aとは
中小企業M&Aとは、中小企業が行うM&Aを指します。近年、中小企業が行うM&Aは拡大の傾向にあります。
ここでは、中小企業のM&Aを考える前提として中小企業の定義を確認するとともに、中小企業M&Aの現状をみていきましょう。
中小企業の定義
中小企業基本法では、中小企業者を業種ごとに分類し、資本金の額または出資の総額と常時使用する従業員数によって、次のように定義しています。
- 製造業その他:資本金・出資金が3億円以下、または従業員数が300人以下の会社・個人
- 卸売業:資本金・出資金が1億円以下、または従業員100人以下の会社・個人
- 小売業:資本金・出資金5千万円以下、または従業員50人以下の会社・個人
- サービス業:資本金・出資金5千万円以下、または従業員100人以下の会社・個人
これらの定義は原則であり、法律や制度によって「中小企業」の範囲は異なることもあります。
参照元:中小企業庁「中小企業・小規模企業者の定義」
中小企業M&Aの現状
近年、M&Aは増加傾向にあります。中小企業庁が公表した「2022年版 中小企業白書・小規模企業白書 概要」によると、2013年度には215件だった年間件数が、2020年度の調査では2,139件に増加しました。
(成約件数)
| 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 215 | 343 | 521 | 844 | 1,221 | 1,535 | 1,886 | 2,139 |
また、全都道府県に設置されているM&Aの支援機関である事業承継・引継ぎ支援センターの相談社数も増加傾向にあります。
2012年度には994件だった相談件数は、2019年度には11,514件にまで増加しました。
(相談件数)
| 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
| 1,634 | 2,894 | 4,924 | 6,292 | 8,526 | 11,477 | 11,514 |
参照元:中小企業庁「2022年版 中小企業白書・小規模企業白書 概要」
参照元:中小企業庁「第2節 M&Aを通じた経営資源の有効活用」
中小企業M&Aが増える背景
中小企業でM&Aが増えている背景には、後継者不在が深刻化している状況と、縮小する国内市場に合わせて経営の合理化や統廃合が行われているという事情があげられます。
ここでは、中小企業M&Aが増える背景をみていきましょう。
後継者の不在
中小企業M&Aが増加傾向にあるのは、経営者の高齢化により、後継者不在が深刻化していることが背景にあります。
帝国データバンクの「全国「社長年齢」分析調査(2023年)」によると、全国の社長の平均年齢は60.5歳と、33年連続の上昇です。
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| 59.9歳 | 60.3歳 | 60.4歳 | 60.5歳 |
社長の8割が50歳以上であり、都道府県別のトップは秋田県の62.5歳で、最も低いのは三重県の59.4歳となっています。
円滑な事業承継には中長期的な準備期間が必要ですが、後継者が決まらないまま経営者が高齢になれば、引継ぎや育成に時間をかける時間がなくなるでしょう。
全国の後継者不在率は低下する傾向にあり、2023年は過去最低の53.9%となっているものの、経営者の高齢化は加速しています。そのため、引き継ぎが間に合わず事業の継続に影響を及ぼすケースが増えることが懸念されている状況です。
(後継者不在率)
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| 65.1% | 61.5% | 57.2% | 53.9% |
経営者の高齢化とともに、親族内承継の減少も後継者不在の問題を深刻化させています。近年は親族に事業を引き継ぐ意思がなく、家業とは異なる道を選ぶ傾向があるのが実情です。そのため、親族内での事業承継が減少する一方で、M&Aの割合が増えるという状況があります。
参照元:株式会社帝国データバンク「全国「社長年齢」分析調査(2023年)」
縮小する国内市場
少子高齢化による人口減少により、国内市場が縮小していることも中小企業M&Aの増加につながっています。
2023年6月に内閣府が発表した推計によれば、2023年1〜3月期の日本経済の需要と供給の差を表す「需給ギャップ」はマイナス0.9%になりました。金額にすると年換算で5兆円の需要不足となっています。
市場の縮小に合わせて大企業では集約化やグローバル化の戦略が採用され、大規模なM&Aが進められています。国内市場の縮小は中小企業にも影響し、新規事業への参入や海外進出、シェアの拡大、経営の合理化などを模索する企業も増えてきました。市場開拓の手段として、M&Aも積極的に選択されるようになっています。
参照元:内閣府「今週の指標」
【売り手側】中小企業がM&Aを行う目的
中小企業がM&Aを行う目的やメリットは、売り手側と買い手側で異なります。ここでは、売り手企業の視点からの目的・メリットをみていきましょう。
後継者不在の解消
中小企業M&Aが増えた背景ともいえますが、売り手側企業がM&Aを行う大きな目的は、後継者不足の解消です。
日本では中小企業の経営者の高齢化が進み、事業承継への関心が高まっています。後継者不在の中小企業は黒字経営であったとしても廃業等を選択せざるをない状況にあり、廃業事業者のうち黒字廃業の比率は6割を占めるという状況です。
従業員を抱える中小企業にとって、事業の継続は経営者個人の問題ではありません。後継者不在で廃業や解散の選択をする場合、従業員は仕事を失います。長年培ってきた技術やノウハウも失われることになるでしょう。そのような事態を避けるため、事業承継を目的としてM&Aを実施する中小企業が増えています。
事業承継のタイミングとしては、株式譲渡と同時に引き継ぐほか、株式譲渡後、数年間の引継ぎ期間を経て経営者が交代するという2つのパターンがあります。
参照元:経済産業省「中小M&Aの意義」
廃業・清算の回避
後継者不在以外でも、会社の業績が上がらないなどの理由で廃業の危機にある会社は多いでしょう。M&Aを選択し、業績が悪化している部門を切り離す、売却先の傘下に入るといった方法で廃業・清算を回避することが可能です。
廃業・清算を回避することで、従業員の雇用を確保できる可能性があり、取引先も新たな取引相手を探す手間を避けられるでしょう。
個人保証からの解放
中小企業では、会社の借入に対して経営者が個人保証や担保の提供をしていることが多く、廃業や清算を選択する場合、経営者は個人保証・担保の負債を負うことになるでしょう。M&Aを選択することで、これらの負担を解消することが可能です。
M&Aでは、会社の負債は譲受企業が引き継ぎます。売り手企業の経営者は、事前に譲受企業や金融機関に交渉しておくことで個人保証や担保から解放されるともに、株式売却等で資金も得られ、新しいことに挑戦したり、経営から引退して生活資金に回したりすることもできるでしょう。
事業の拡大
事業を拡大し、市場の縮小や競争の激化の中で生き残るためにM&Aを選択する場合もあります。自社だけでは、事業の将来性に不安がある経営者も多いでしょう。M&Aで大手の傘下に入れば、安定した経営を行うことが可能です。
M&Aによって経営資源の集約化を行った中小企業は、そうでない企業に比べて生産性や売上高などを向上させたという統計もあります。
M&Aでは買い手側の規模が大きいケースが多く、大企業のブランド力やノウハウ、新規取引先情報などを得ることで、事業の拡大や経営の安定につながるでしょう。
参照元:経済産業省「中小M&Aの意義」
従業員の雇用確保
M&Aは、従業員の雇用を確保する目的もあります。業績不振による事業停滞が続いている場合、廃業を選択すると従業員は職を失います。長年、一緒に働いてきた従業員は家族のような存在という会社も多いでしょう。
M&Aを選択することで、従業員の雇用を維持することが可能です。
2015年以降にM&Aを実施したことがあるという中小企業への調査では、82.1%が従業員を雇用継続しているという調査結果もあります。
中小企業M&Aの多くは株式譲渡で行われ、雇用契約も買い手企業へと引き継がれます。M&Aによって安定した経営を続ける企業に売却できれば、雇用を維持するだけでなく、これまでより処遇を良くすることも可能です。
参照元:経済産業省「中小M&Aの意義」
資金調達
M&Aは売り手企業にとって、売却益を得る目的もあります。
未上場株式を換金することは難しく、相続時には相続税が発生するため、多くの未上場企業では相続税の資金準備を考えなければなりません。株式譲渡でM&Aを行うことにより、株式を保有する経営者が譲渡対価として現金を取得できます。
自社にとっては赤字の事業でも、他社の事業を補い、シナジー効果を期待できる事業もあるでしょう。買い手が見つかれば、売却対価は引退後の生活資金を確保できるほか、調達した資金をほかの事業の運転資金に充てることも可能です。
参照元:経済産業省「中小M&Aの意義」
【買い手側】中小企業がM&Aを行う目的
中小企業M&Aの目的やメリットについて、買い手企業側の視点からもみていきましょう。
人材の獲得
買い手企業がM&Aを行う目的のひとつに、人材の獲得があげられます。人手不足に悩む企業は多く、特に即戦力になる有資格者や経験者を獲得するのは難しい状況です。
M&Aであれば、売り手企業で活躍している従業員を引き継ぐことができます。採用や教育にかける時間を削減しながら、即戦力となる人材をまとめて獲得できることは大きなメリットといえるでしょう。
新規事業への参入
買い手企業にとって、M&Aは新規事業への参入という目的もあります。自社にはないリソースを持つ企業を買収することで、効率的な事業拡大が可能です。
新規事業を展開する場合、準備には時間やコストがかかるだけでなく、軌道に乗って収益化できるまでにも時間が必要であり、不成功に終わるリスクもあります。
M&Aですでに収益化されている事業もしくは企業を獲得することで、これらの時間やコスト・リスクを軽減できることがメリットです。
買収により、買い手企業は有形資産だけでなく、ノウハウや技術、人材、取引先、顧客などをまとめて獲得できます。ただリソースを引き継ぐだけでなく、既存事業とのシナジー効果を発揮してさらに事業拡大・成長を図ることもできるでしょう。
スケールメリットの獲得
M&Aにより、買い手企業はスケールメリットの獲得も期待できます。スケールメリットとは、事業や経済活動の規模(スケール)が拡大することで、一社で行うよりも大きな成果を生み出し、市場での優位性・知名度といったメリットを得られることです。M&Aによって企業や事業の規模が拡大すれば、コストを削減しながら市場におけるシェアの向上を図れます。
買収先がすでに実績をあげている場合、ブランド力や販路も獲得できるでしょう。
経営の効率化
買い手企業にとって、M&Aは経営の効率化も目的のひとつです。重複する部門や機能を統合し、経営を効率化して生産性の向上を図れます。設備や販路、技術などを相互に活用することで、新たな価値の創出など多くのシナジー効果も期待できるでしょう。
M&Aにより生産の規模が大きくなれば、製品あたりのコストが下がる効果も得られます。経営の効率化でリソースを最適に配分できるようになり、競争力強化にもつながるでしょう。
中小企業M&Aの手法
M&Aを成功させるためには、自社に合う手法を選択することが重要です。
| 手法 | 特徴 | メリット | デメリット |
| 株式譲渡 | 売り手が保有する株式を譲渡して、買い手が経営権を取得する | ・短期間でM&Aを完了できる ・売り手企業の独立性を維持しやすい | ・包括承継のため、買い手は簿外債務も引き継ぐ |
| 事業譲渡 | 事業の全部または一部を譲渡する | ・買い手は負債や不要な資産を除外できる ・売り手は経営を継続できる | ・契約上の移転手続きに手間や時間がかかる ・売り手は税負担が重くなる |
| 会社分割 | 売り手の事業を買い手が丸ごと引き継ぐ | ・買い手は新株発行すれば資金を用意する必要がない ・包括承継のため手続きがシンプル | ・買い手側の株主構成が変化する ・システム統合などで現場が混乱する場合がある |
| 合併 | 複数の会社を1つの会社に統合する | ・対価を株式の交付にすれば資金調達をする必要がない ・新規で事業を立ち上げるよりも時間や手間を節約できる | ・手続きのステップやすり合わせをする項目が多い ・新設合併新会社の設立に手間と時間が必要 |
| 株式交換・株式移転 | ・株式交換は、完全親子会社関係を成立させる ・株式移転は持株会社体制を作るために行う | ・売り手企業の株主総会特別決議による合意があれば少数株主を排除して100%子会社化ができる ・M&A実施後も売り手企業は別法人として存続し、経営統合を急ぐ必要がない | ・買い手企業が上場企業の場合、株価下落のリスクがある ・買い手企業の株主構成が変化する |
ここでは、M&Aの代表的な手法の特徴やメリット・デメリットを解説します。
株式譲渡
株式譲渡とは、売り手企業の保有する株式を買い手企業が買い取り、経営権を取得する手法です。株式の売買でM&Aを完了させる簡易な手続きのため、中小企業M&Aでは多く採用されています。
株式譲渡には、次の方法があります。
- 相対取引:大株主から直接株式を買い取る
- 市場買付:上場企業の株式を証券取引所などで買い入れる
- 公開買付け:株式買付けの募集を行い、市場外で株式を買い集める
このうち、上場していない会社からの買い取りは、相対取引のみとなります。
株式総会の承認や債権者保護手続きが不要で手続きを進めやすく、比較的短期間でM&Aを実施できるのがメリットです。
買い手企業は権利・義務などを包括的に承継でき、売り手企業は独立性を維持しやすいというメリットもあります。株式を100%取得すれば、M&A成立後に起こりがちな少数株主や反対株主との問題を回避できます。
一方、包括承継であるため、買い手側は簿外債務を引き継ぐ可能性がある点がデメリットです。また、株主が分散している場合は、株式を100%取得できないケースもあるでしょう。対価として現金を用意しなければならない点もデメリットといえます。
事業譲渡
事業の全部または一部を譲渡する手法です。資産・負債などを個別に承継するため、不採算部門を切り離して赤字を解消するといった場合などに利用されます。
買い手企業は契約範囲を決めて負債や不要な資産を除外することができる点がメリットです。
また、会社を売却するわけではないため、売り手企業の経営者は事業譲渡後も引き続き会社を保有し、経営を継続できます。不採算事業だけを売却し、主力事業に集中することもできるでしょう。
一方、契約上の移転手続きに手間や時間がかかる点がデメリットです。買い手企業は雇用契約や資産の権利を個別に契約し直す必要があり、許認可なども再取得しなければなりません。対象となる事業の規模によっては、手続きが煩雑になるでしょう。
売り手企業は税務上の優遇措置がなく、税負担が重くなるデメリットがあります。また、譲渡した事業には競業避止義務を負う可能性があるでしょう。
会社分割
会社分割とは、売り手企業の事業部門を買い手企業が引き継ぐ手法です。事業譲渡のように譲渡対象の選別ができず、丸ごと引き継ぐ点が特徴です。既存の会社に事業を承継する「吸収分割」と、新設した会社に事業を承継する「新設分割」の2種類があります。
さらに、対価の受け取り方によって分類があり、対価を分割会社が受け取る場合は「分社型分割」、分割会社の株主が受け取る場合は「分割型分割」に分かれます。そのため、会社分割は「吸収分割」と「新設分割」のそれぞれに「分社型分割」と「分割型分割」がある4つの組み合わせということです。
買い手企業は、対価として新株を発行すれば、買収資金を用意する必要がありません。また、包括承継のため、事業譲渡に比べて手続きがシンプルな点がメリットです。
一方で、売り手企業の株主が新しく買い手企業の株主となるため、買い手側の株主構成が変化するというデメリットがあります。人事制度やシステムを統合する際、現場が混乱することもあるでしょう。
合併
合併とは、複数の会社を1つの会社に統合する手法です。消滅する会社が持つ権利や義務を存続会社が引き継ぐ「吸収合併」と、新規に会社を設立し、消滅するすべての会社の権利・義務を新会社に承継させる「新設合併」の2種類があります。
消滅する会社が持つ資産・権利はそのまま存続会社に引き継がれ、消滅する会社の株主は株式・社債・現金のうち、いずれかを対価として受け取れます。
新設合併は、消滅する会社が持つ資産や権利を新会社に引き継ぐために承継の手続きが必要であり、上場企業の場合はあらためて上場申請を行わなければなりません。
合併は株式を対価として交付できるため、必ずしも資金調達をする必要がない点がメリットです。消滅する会社から人材や設備、取引先といった資産をそのまま承継できるため、新規で事業を立ち上げるよりも時間を節約できます。
一方で、ほかのM&A手法に比べて、手続きのステップが多く、会社間ですり合わせが必要な項目が多いことがデメリットです。経営統合にも十分な時間が必要になるでしょう。特に、新設合併は新会社を立ち上げるため、さらに手間と時間がかかります。
株式交換・株式移転
株式交換は、完全親子会社関係を成立させる手法です。子会社化したい売り手企業の全株式を取得し、その対価として親会社の株式を交付します。売り手企業を完全子会社化する目的で行われます。
株式移転は、持株会社体制を作るために用いる手法です。新設会社が親会社(持株会社)となり、既存企業が子会社となります。株式交換と同様に、子会社化したい売り手企業の株式取得と親会社の株式交付を行います。
株式交換も株式移転も、株主の同意を得ずに会社間の合意で行える点がメリットです。株主総会でも株主全員の合意を得る必要がなく、特別決議(出席した過半数の株主の議決権の3分の2以上による賛成)で済みます。
株式交換では買い手企業の株式を対価とする場合、株式移転では対価をすべて新設会社の株式とする場合には買収資金が不要です。
また、M&A実施後も売り手企業は別法人として存続するため、経営統合を急ぐ必要がありません。
ただし、どちらの手法も買い手企業が上場企業の場合、株価下落のリスクがあり、買い手企業の株主構成が変化するというデメリットがあります。
中小企業がM&Aを行う流れ
中小企業がM&Aを行う際、大まかな流れは次のとおりです。
|
売り手企業(譲渡側) |
買い手企業(譲受側) |
|
アドバイザーへの相談(検討・準備フェーズ) |
|
|
1.ニーズの発生・M&Aの検討 |
|
|
2.M&A業者の選定・契約 |
|
|
3.機密保持契約書の締結 |
|
|
4.アドバイザーとの面談 |
|
|
5.企業価値評価 |
|
|
マッチング(マッチング・交渉フェーズ) |
|
|
6.ロングリストの作成 |
|
|
7.ショートリストの作成 |
|
|
8.ノンネームリストの作成 |
|
|
9.ネームクリアの検討 |
|
|
トップ面談・条件交渉(マッチング・交渉フェーズ) |
|
|
10.機密保持契約書の締結 |
|
|
11.企業概要書の提示 |
|
|
12.企業価値評価・スキームの絞り込み |
|
|
13.トップ面談 |
|
|
14.条件の交渉 |
|
|
15.意向表明書の提出 |
|
|
16.基本合意書の締結 |
|
|
最終契約の締結(最終契約フェーズ) |
|
|
17.デューデリジェンスの実施 |
|
|
18.最終条件の交渉 |
|
|
19.最終契約書の締結 |
|
|
20.クロージング |
|
ここでは、売り手側の視点に立った手続きの流れをみていきましょう。
1.アドバイザーに相談する
自社の現状を把握し、アドバイザーに相談するフェーズです。まずは自社の課題や今後の事業展開などを考え、M&Aを行う必要があるのかについて検討します。
M&Aの実施を決めたら関連情報を収集し、M&Aを行う目的や実現したいことを明確にしましょう。どのような手法が適切かを検討する際、自社にM&Aに関する専門知識やノウハウがない場合は、M&A仲介会社といったM&Aの専門家に相談するのが一般的です。
また、M&Aの実施にあたっては、財務や法務、税務といった専門知識が必要であり、適切な買い手企業を見つけるのも自社だけでは難しいのが実情です。そのため、相談先を早めに決定し、サポートを受けながら効率的にM&Aを進めるとよいでしょう。
外部の専門家にアドバイスを求める場合は、アドバイザリー契約と機密保持契約を締結することになります。
売り手企業は買い手企業を探す際、自社の強みをアピールする資料の作成が必要です。そのため、決算資料や事業に関する資料などをアドバイザーに提出します。
また、非上場企業の場合、上場企業の株式と異なり、時価総額が簡単には把握できないため、株式の価値評価を行わなければなりません。算出した数値はあくまでも参考値ですが、今後の交渉で希望価額を設定する際の判断材料となるものです。企業価値の算出方法については、あとの項目で解説します。
2.マッチングを行う
アドバイザーに相談後、M&Aの実施を決めたら売却先の企業を選定します。候補先企業を探す際には、アドバイザーのサポートを受けながら、ロングリスト・ショートリストを作成しましょう。ロングリストとは20~30社程度の候補企業を掲げたリストであり、そこから数社に絞ったものがショートリストです。
また、アドバイザーからは候補先企業の概要が掲載されているノンネーム資料が提供されるため、それをもとに候補企業を検討します。ノンネーム資料に記載されているのは企業の業種や事業規模、エリアなどで、具体的な企業名はわかりません。
買い手候補を絞ったら、M&Aの実施に向けて打診します。相手企業から詳細な情報を求められた場合には、秘密保持契約を締結して企業概要書により詳細な情報を開示しましょう。
買い手企業は売り手企業の登記簿謄本や定款などを取得し、企業情報を確認するのが一般的であるため、これらの資料は事前に用意をしておいてください。
3.トップ面談・条件交渉を行う
買い手企業を決定したら、トップ面談・条件交渉のフェーズに入ります。トップ面談は、売り手企業・買い手企業の経営者同士が顔を合わせ、資料だけではわからない会社の価値観や、M&A後の方針などを確認する貴重な場です。
主に、次のような内容を話します。
- M&Aを決意するまでの経緯
- 経営理念
- 社風や企業文化
- 今後の経営方針
トップ面談は経営理念や事業内容、お互いの人間性などへの理解を深め、信頼関係を構築する場です。そのため、具体的な条件交渉は行いません。
トップ面談は複数回行われることもあり、初回のトップ面談はお互いを知るということを念頭において実施されます。アドバイザーがいる場合は適切に司会進行をしてくれるため、階段をスムーズに進めるためには任せるのもよいでしょう。
面談後、お互いに交渉を進めたいという意思の確認が取れたら、具体的な条件交渉に入ります。譲渡価額などの条件を調整したのち、ある程度条件が固まった段階で基本合意契約を結びます。
基本合意契約は、独占交渉権の付与や秘密保持義務などの条項を除き、法的拘束力は持たないのが一般的です。
4.最終契約を締結する
基本合意契約の締結後、最終契約のフェーズに入ります。このフェーズでは、デューデリジェンスの実施と最終条件の交渉を行います。
デューデリジェンスとは、買い手企業が売り手企業の実態を事前に把握し、価格や取引について適切な判断をするための調査です。「買収監査」とも呼ばれます。
売り手側から得た情報だけでは客観性や信頼性が十分とはいえず、財務や法務・労務などに関するリスクが隠れている可能性があります。売り手側も把握していないリスクが潜んでいる場合もあるでしょう。
M&A後にリスクが発覚して事業継続に支障をきたすことのないよう、買い手側は弁護士や会計士などの専門家に依頼し、デューデリジェンスを実施します。
デューデリジェンスは、一般的に1〜2ヶ月程度の期間をかけ、財務や法務、税務など幅広い範囲にわたって行われる調査です。
デューデリジェンスが無事終了したら、最終合意に向けて交渉を行います。交渉で話し合うのは、売買条件のほか、経営者・役員・従業員の処遇や今後のスケジュールといった内容です。
最終的な売却価格を決定し、そのほかの条件にもお互いに問題がなければ最終契約を締結します。買い手から譲渡代金を受け取り、その後に最終的な諸手続きを行って最終契約は完了です。
最終的な手続きはクロージングと呼ばれ、売り手企業の経営者の私的資産の買い取りや株券・会社代表印の引き渡しなどを行います。
中小企業M&Aで売却価格を決める方法
中小企業M&Aでは適正な売却価格を決定することが大切であり、企業評価の方法として、次のような3つのアプローチがあります。
| アプローチの種類 | 特徴 | 算定方法 |
| マーケットアプローチ | 株式市場での市場価格をベースに企業価値を評価する | ・類似会社比較法 ・類似取引比較法 ・市場株価法 |
| コストアプローチ | 純資産から売却価格を算出する | ・簿価純資産法 ・時価純資産法 |
| インカムアプローチ | 企業の収益力をベースに評価する | ・DCF法 ・配当還元法 ・収益還元法 |
企業評価の算定結果はM&Aを成立させるための大きな判断基準になります。それぞれの手法にはメリット・デメリットがあるため、1つの方法だけではなく、複数の方法を組み合わせて算定するのが一般的です。
ここでは、それぞれの特徴や注意点を解説します。
マーケットアプローチ
マーケットアプローチとは、株式市場での比較対象となる企業・業界を基準に企業価値を評価する方法です。
上場企業の場合は市場株価をベースに価値を算出できますが、非上場の中小企業ではそれができないため、類似の企業・業界の市場株価を参考にします。
計算方法には、次の3種類があります。
- 類似会社比較法:類似する上場企業の各種指標を参考にして算出する
- 類似取引比較法:過去の類似したM&Aの取引価格をもとに算出する
- 市場株価法:評価対象とする上場企業の一定期間における株価の平均値を基準に算出する
このうち、中小企業では、類似会社から簡便に計算できる類似会社比較法を使って計算するのが一般的です。
マーケットアプローチは市場における公開データをもとに計算するため、誰が行ってもほぼ同じ結果になり、客観的な評価ができる点がメリットです。
ただし、条件に合う企業が見つからないと適用が難しい場合もあります。
コストアプローチ
コストアプローチとは、対象企業の純資産や負債を基準に評価する方法です。貸借対照表に記載されている資産や、負債の時価などから企業価値を算出します。
計算方法は、次の2種類です。
- 簿価純資産法:貸借対照表に記載されている純資産から算出する
- 時価純資産法:保有する資産の時価から、負債の時価を差し引いて算出する
コストアプローチは純資産をもとに計算するため、客観性の高い評価を行える点がメリットです。純資産にフォーカスしていることで中小企業でも比較的馴染みやすく、どちらも一般的に用いられています。
ただし、貸借対照表に計上されない無形資産の価値等を含まないため、評価対象企業の収益性や将来性が反映されないというデメリットがあります。
インカムアプローチ
インカムアプローチとは、将来見込まれる収益に着目して評価する方法です。
主に、次の計算方法を使います。
- DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法):評価対象となる企業が将来獲得すると予想されるキャッシュフローを現在価値に割り引いて株価を算定する
- 配当還元法:株主への配当金を基準に評価する
- 収益還元法:将来的な収益価値を現在価値に換算する
インカムアプローチはキャッシュフローに基づいて企業価値を評価する方法であり、将来性を評価に反映させやすいことがメリットです。
ただし、客観性に欠けるというデメリットがあります。
事業計画等の将来予測が難しいなどの理由で、中小企業ではあまり採用されない手法です。
中小企業M&Aを成功させるポイント
中小企業がM&Aを成功させるためには、次のポイントを押さえて進めることが大切です。
- M&Aの目的を明確にする
- 売り手企業の関係者に及ぼす影響を考える
- 自社の企業価値を把握する
- 譲歩可能な価格を定める
- M&Aの支援機関を活用する
詳しくみていきましょう。
M&Aの目的を明確にする
M&Aを実施するにあたって、目的を明確にすることが大切です。自社の課題を見極め、どのようなゴールを達成したいかを明確にすることが、M&Aの成功につながります。
M&Aはあくまで目的を達成するための手段であり、目的が曖昧のまま進めるとM&Aを行うこと自体が目的化してしまいます。目的が不明確な場合、買い手企業を選ぶ基準も明確にできません。
例えば、M&Aの目的が後継者不在を解消したいのであれば、自社の経営理念や社風と親和性があり、従業員の雇用を維持できることなどが買い手企業を選ぶ基準となるでしょう。
買い手企業の場合は、ノウハウや技術、人材など、買収によって得たいものを明確にしておくと、対象企業を絞り込みやすいでしょう。
売り手企業の関係者に及ぼす影響を考える
売り手企業・買い手企業ともに、M&Aによって売り手企業の関係者に及ぼす影響を把握しておくことが必要です。
影響を受ける主な関係者は、次のとおりです。
- 株主
- 従業員
- 取引先
- 金融機関
M&Aの実施により、売り手企業の株主はこれまで受けてきた自益権(経済的利益を受ける権利)や共益権(経営に関与できる権利)を失う可能性があります。
従業員は、経営者や会社の環境が変わることに不安を感じるでしょう。
中小企業では、経営者との個人的なつながりで取引をしている会社も多く、M&Aで経営者が変わると、取引が終了になるケースが出るかもしれません。
融資の取引がある金融機関も、経営者の交代によって取引の条件を見直す可能性があります。
これらの関係者へ配慮し、説明責任を果たすことが大切です。買い手企業の経営者や関係者も同席する説明の場を設けるなど、M&Aの実施と今後について丁寧に説明することを検討しましょう。
自社の企業価値を把握する
売り手企業は、あらかじめ自社の企業価値を把握しておくことも大切です。前に紹介した企業価値の算定方法はあくまで参考値で、実際の譲渡価格は交渉によって決まります。
しかし、客観的な企業価値を把握していなければ、譲渡価格を交渉する上で適切な希望価額の設定ができません。
自社の企業価値を正確に把握していない場合、条件交渉で高すぎる希望価額を出すなど交渉が難航する可能性があるでしょう。それではM&Aの実現が難しくなります。事前に自社の客観的価値を算出しておくことで、適切な判断のもとに交渉を行えます。
譲歩可能な価格を定める
交渉がスムーズに進むよう、あらかじめ譲歩可能な価格を定めておくことも大切です。最初に譲歩可能な取引価格を決めておけば、不本意な金額で取引をしてしまうことを防げるでしょう。
譲歩できる金額として、売り手側は下限額を、買い手側は上限額を決めておいてください。買い手企業は、売り手企業に対して最初に提示する金額として下限額も設定しておくとよいでしょう。
下限額の目安は、売り手企業の現時点での清算価値です。上限額の目安は、売り手企業の時価に、経営統合を経て獲得できると予測される収益額を足して算出します。
M&Aの支援機関を活用する
M&Aの成否を左右する要素となるのが、候補先企業を見つけるマッチングのフェーズです。M&Aの目的を明確にしても、目的に合った企業が見つからなければ、M&Aを成功させることはできません。
目的を達成できる候補先企業を見つけるためには、豊富な候補企業の情報を持ち、適切なマッチングができるM&Aの支援機関を活用するとよいでしょう。
M&Aの支援機関には、商工団体や事業承継・引継ぎ支援センターなど無料で相談できる機関や専門家、M&A仲介会社などがあります。
中小企業のM&Aをサポートする機関
M&Aを成功させるためには、M&Aの専門知識を持つ支援機関のサポートが欠かせません。
ここでは、M&Aの相談ができる支援機関の特徴やサポート内容を紹介します。支援機関を選ぶ際の参考にしてください。
| 機関名 | 特徴 |
| 商工団体 | 事業承継をメインに中小企業のM&Aを支援する |
| 事業承継・引継ぎ支援センター | 承継コーディネーターが 中小企業の事業承継に関するあらゆる相談に対応する |
| 金融機関 | 主にM&Aアドバイザリー業務と融資で支援する |
| マッチングサイト | インターネットを介してM&Aの売り手と買い手のマッチングを行う |
| 専門家 | 税理士・公認会計士がM&Aの財務・税務の側面でアドバイスを行う |
| M&A仲介会社 | 売り手企業・買い手企業の双方と契約し、中立的な立場から交渉を仲介する |
商工団体
各地域にある商工会議所や商工会などの商工団体では、事業承継をメインに中小企業のM&Aを支援しています。商工会は主に町村部にあり、地域の事業者が事業と地域の発展のために活動する非営利の公的団体です。
商工会議所は市や特別区にあり、地域の事業者を会員とした会員制の非営利団体です。商工会に比べて規模が大きく、中小企業の活力強化と地域経済の活性化の実現を目的としています。
これら商工団体では、M&Aの無料相談や専門家の紹介などを行い、中小企業のM&A・事業承継を支援しています。
中小企業の支援に実績があり、経営者の悩みに寄り添って支援をしてくれるのがメリットです。
M&Aの相談は無料ですが、会員になる必要があり、その際は会費・入会費が必要になります。
事業承継・引継ぎ支援センター
「事業承継・引継ぎ支援センター」 は、 国が設置する公的相談窓口です。 全国に設置され、各センターでは承継コーディネーターが親族内承継や第三者への引継ぎなど、 中小企業の事業承継に関するあらゆる相談に無料で対応しています。
相談件数は累計10万件以上、事業承継の成立は8千件以上の実績があり、成約譲渡企業の約7割が小規模事業者です。相談に対応するのは、中小企業診断士や金融機関OBなどのプロフェッショナルで、事業引継ぎや経営に対する経験をもとに、事業引継ぎに向けたアドバイスを行います。
相談を受けたら「事業承継診断」を実施して課題を整理し、事業承継の早期・計画的な準備の働きかけや今後の取り組みをアドバイスするというのが一般的な流れです。また、税理士や中小企業診断士等の外部専門家と連携し、「事業承継計画」策定の支援も無料で行っています。
マッチングから成約までをコーディネートしており、多くの案件情報が登録された全国規模のデータベースから候補先企業をマッチングしています。
センターに登録された民間M&A仲介会社や金融機関など、民間のM&A支援機関も紹介しており、紹介によりマッチングから契約成約までのサポートを受けることも可能です。
参照元:事業承継・引継ぎ支援センター
金融機関
近年は、M&A支援を行う金融機関も増えており、M&A支援を専門に行う部署を置く金融機関もあります。金融機関がM&Aで果たす役割は、主にM&Aアドバイザリー業務と融資です。
M&A仲介会社が売り手・買い手の間に立って中立的な立場で交渉の仲介を行うのに対し、M&Aアドバイザリーは買い手・売り手どちらか一方と契約を結び、利益を最大化するために尽力するという点が異なります。
買い手企業が金融機関のアドバイザリーを利用する場合、予算内で買収できる企業や、買収後の企業経営を考慮して、利益を出しやすい企業を紹介してもらうことが可能です。一方、売り手側は、売却価格の最大化や、希望に基づいた条件交渉を行ってもらえるでしょう。
また、M&Aで金融機関が果たす大きな役割は融資です。M&Aについて相談するとともに融資も得たい場合は、金融機関は適した相談先といえるでしょう。
金融機関にはほかのM&A支援機関や士業と連携しているところもあり、必要に応じて紹介してもらうことも可能です。
ただし、大手の金融機関の場合は基本的に大規模なM&A案件を取り扱っており、中小企業のM&Aには対応していない場合もあります。
また、アドバイザリー業務を依頼する場合は費用が高くなる傾向にある点は把握しておきましょう。
マッチングサイト
マッチングサイトとは、インターネットを介してM&Aの売り手と買い手のマッチングを行うサービスです。
売り手・買い手は会員としてサイトに登録し、売り手は売りたい案件情報を入力してサイトに公開します。
買い手は案件情報を閲覧し、気になった売り手に交渉をリクエストするという流れです。交渉の結果、条件が合えば成約へと進みます。
売り手側がサイトに公開されている買い手の希望をみて、交渉のリクエストをするパターンもあります。
マッチングサイトには多くの事業者が登録しているため、豊富な案件から相手先企業を比較検討できる点がメリットです。成約までの期間が短いというメリットもあります。気になる案件を見つけたら直接相手にアプローチできるため、余計な工程を省いてスムーズに契約まで進めることが可能です。
また、仲介業者にマッチングを依頼するよりも、低コストで利用できる点もメリットです。
ただし、マッチングサイトはサービスによってサポート内容に違いがあります。サポートがほとんどなく、成約まで自社で行わなければならないサービスもあるため、選ぶ際はよく確認しましょう。
また、サイトには企業名を伏せることができても、登録されている情報から企業が特定されるリスクがあります。自社がM&Aを行う意思があることを知られたくない場合、特定されるような情報は出さないよう注意が必要です。
専門家
税理士、公認会計士といった専門家にM&Aの相談をすることもできます。多くの中小企業では会計士もしくは税理士と顧問契約を結んでおり、信頼関係が構築できているケースが多いでしょう。
顧問会計士あるいは税理士は自社の会計や税務の状況をよく把握しているため、M&Aについても相談しやすい点がメリットです。
また、税理士、公認会計士は、主にM&Aにおいて税務・財務のデューデリジェンスを担当します。
買い手企業は、売り手企業を買収することにリスクがないか、買収価額はいくらが妥当かを判断する必要があり、税務・財務のデューデリジェンスの結果が重要な判断材料になります。
ただし、税理士や公認会計士は、M&Aについては専門知識や経験が十分ではないケースも多い点がデメリットです。あくまでも相談先のひとつとして位置づけ、マッチングや条件交渉などのサポートは、ほかの専門機関を探すとよいでしょう。
M&A仲介会社
M&A仲介会社は、M&A支援を専門に行う会社です。売り手企業・買い手企業の双方と契約し、中立的な立場から交渉を仲介します。
売り手と買い手どちらか一方の利益を高めるのではなく、両者の間に立ち、客観的・中立的な立場で交渉の仲介を行うのが特徴です。
マッチングを行うことが一般的で、初期の相談からM&Aの成立まで、売り手・買い手双方の要望を汲み取り、それぞれの利益のバランスを考えながら交渉を進めます。
M&A仲介会社は多くの候補先企業の情報やネットワークを持ち、希望条件に合う相手企業を見つけやすいというメリットがあります。
また、初期段階の相談からM&A成立まで、専門的なアドバイスを受けられる点もメリットです。M&A成立後のトラブルをなくすためには、豊富な経験と専門知識に基づいたサポートが欠かせません。
M&Aの交渉は利害が対立しやすく、双方のどちらかが自社の利益を強く主張すれば、交渉が決裂する可能性も高いでしょう。交渉をM&A仲介会社が仲介し、双方と直接コミュニケーションを行うことで、友好的なM&Aの成立が可能になります。
仲介により情報がスピーディに整理され、成約までの期間を短縮できるでしょう。その結果、成功率も高まります。
中小企業M&Aの注意点
中小企業M&Aでは、大企業のようにはシステムや資料が揃っていないケースも多く、トラブルが起こりやすい状況があります。
どのようなトラブルに注意すればいいのか、株式、コンプライアンス、資料収集の3点で確認していきましょう。
株式のトラブル
株式では、株券の喪失と未発行のトラブルに注意が必要です。
中小企業は株式の売買を予定しておらず、家族や親族での保有も多いために株式を保有している意識が薄くなりがちです、そのため、いざ株式が必要になったときに見つからなかったり、「株式そのものが発行されていない」というトラブルが起こる場合があります。
会社が株券発行会社である場合、株券の発行と株券の相手への交付がなければ株式譲渡はできません。そのため、株券を喪失した場合は再発行が必要です。
手続きは、株券喪失登録簿へ株券紛失を登録したあと、株券喪失の登録日から1年経過後に株券が再発行されるという流れです。
株券発行会社がまだ株式を発行していない場合は、株式の数を公表し、株式不保持の申し出を行うこともできます。
あるいは、定款変更と公告・通知、登記を経て株券不発行会社へ移行するという方法もあります。
コンプライアンスのトラブル
コンプライアンスが遵守されていないため、M&Aの工程でトラブルが起こる場合があることにも注意が必要です。
中小企業では、大企業ほどにはコンプライアンスの遵守を意識していないケースもあります。重大なコンプライアンス違反がM&A成立後に発覚した場合、経営に悪影響を及ぼす可能性があるでしょう。
コンプライアンスの一例として、定時株主総会終結後の決算公告を行っていないというケースがあげられます。
M&Aを行う上で大きな問題になりうるコンプライアンス違反がないか、違反がある場合、許容の範囲内かどうかを事前に調査しておきましょう。
資料収集のトラブル
買い手企業が行うデューデリジェンスでは、売り手企業に資料提出が求められます。その際、資料を揃えられないというトラブルが想定されます。
デューデリジェンスで求められるのは、主に次の資料です。
- 定款
- 商業登記簿謄本、決算書等の基礎資料
- 株主名簿
- 取引の契約書
- 議事録
- 賃貸契約書
必要な書類はできるだけ揃える必要があります。契約書が揃わない場合は「再作成は可能か」、見つからない資料がある場合は、「記載された内容を他の資料で補足できるか」などを検討しましょう。
どうしても用意できない資料があるときは、正直にその旨を伝えてください。
中小企業のM&A(事業承継)で利用できる補助金・制度
中小企業が事業承継やM&Aを実施する場合、利用できる補助金やサポート制度があります。
詳しくみていきましょう。
事業承継・引継ぎ補助金
事業承継・引継ぎ補助金は、事業承継やM&Aに取り組む中小企業等を支援する国の制度です。
補助金制度を設けた背景には、経営者の高齢化が進んでいることや、後継者不在率が依然として高い水準にあることがあげられます。近年は中小企業の休廃業が増加傾向にあり、そのうち黒字の廃業が約6割を占める状態が続いています。後継者がいない中小企業では、黒字経営でも廃業を選択しなくてはならない状況にあるのが現状です。
このような現状に対応するため、国は補助金制度で中小企業等の事業承継・引継ぎを支援しています。
補助金は、支援の対象によって次の3つの事業に分かれています。
| 申請類型 | 補助対象 |
| 経営革新事業 | 経営資源引継ぎ型創業・事業承継、M&Aを過去数年以内に行った者、または補助事業期間中に行う予定の者 |
| 専門家活用事業 | 補助事業期間に経営資源を譲り渡す、または譲り受ける者 |
| 廃業・再チャレンジ事業 | 事業承継やM&Aの検討・実施等に伴い、廃業等を行う者 |
それぞれ、補助率(1/2〜2/3)・補助上限(最大800万円)が設けられています。
経営革新事業は、事業承継後の取り組みに必要な費用の補助金です。次の3つのタイプがあります。
- 創業支援型:ほかの企業を引き継いで創業した場合
- 経営者交代型:親族や従業員が引き継ぐ場合
- M&A型:M&Aにより引き継ぐ場合
補助対象は、店舗等の借入費・設備費など、幅広い経費が対象になっています。
専門家活用事業は、M&Aの際に必要な費用の補助金です。事業承継前の引継ぎにかかる費用で、仲介会社の手数料やFA(ファイナンシャルアドバイザー)に支払う料金、企業価値を算定する費用、デューデリジェンスの費用などがあげられます。
仲介会社やFAの費用は、「M&A支援機関登録制度」に登録された仲介会社・FAによる支援費用だけが対象になります。
廃業・再チャレンジ事業は、承継に伴う廃業にかかる費用の補助金です。
「M&Aが成約せずに廃業になった」「承継時に事業の一部を廃業した」という場合に、廃業登記費や在庫処分費、原状回復費等を補助します。
参照元:事業承継・引継ぎ補助金
参照元:中小企業庁「中小企業庁担当者に聞く「事業承継・引継ぎ補助金」
事業承継税制
事業承継税制とは、会社や個人事業の後継者が取得した一定の資産について、贈与税や相続税の納税を猶予する制度です。円滑な事業承継を妨げる要因のひとつに、自社株式の引き継ぎで発生する高額な贈与税・相続税があります。事業承継税制は、このような問題を解決し、事業承継を推進するために設けられた制度です。
事業承継税制の活用により、事業承継で後継者が取得した自社株式にかかる贈与税・相続税について、納税猶予を受けられます。その後、一定期間に要件を満たすと、猶予された税額は免除されるという仕組みです。
2018年度税制改正により、事業承継税制の利用促進するため、従来の措置の内容を大幅に拡充した特例措置が設けられました。特例承継計画を提出すると、納税猶予割合や対象者が拡充されるという特例です。
拡充された内容は、次のとおりです。
- 対象株式数の上限を撤廃
- 対象者の拡充
- 雇用要件の見直し
- 経営環境の変化に応じた減免
猶予割合を100%に拡大し、事業承継時の贈与税・相続税の現金負担がゼロとなっています。また、一般措置では1人の経営者から1人の後継者へ贈与・相続される場合のみが対象でしたが、特例措置では親族外を含む複数の株主から、代表者である最大3人までの後継者への承継も対象になりました。
また、特例措置においては、事業承継後5年間の雇用平均が8割を満たすという雇用条件を満たさなくても猶予が継続されます。ただし、この場合は理由報告が必要です。
さらに、売却額や廃業時の評価額をもとに納税額を再計算し、事業承継時の株価をもとに計算した納税額との差額を減免されるなど、経営環境の変化に応じた措置も講じられています。
特例承継計画の提出期限は2度にわたり延長されており、2026年3月31日までとなっています。
参照元:国税庁「事業承継税制特集」
中小企業M&Aの成功事例
中小企業M&Aを実施する企業は増え続けており、多くの成功例があります。
ここでは、3つの成功事例をみていきましょう。
ソフトウェア開発の事例
DX支援サービスを行う株式会社コアコンセプト・テクノロジーは、2023年、株式会社ピージーシステムの発行済株式 400株のうち自己株式50株を除く350株を取得し、ピージーシステムを子会社化しました。
ピージーシステムは山口県と広島県を拠点に、地場企業や官公庁・自治体向けの各種システム開発及び運用・保守などを手がける会社です。
コアコンセプト・テクノロジーは、ピージーシステムを完全子会社化することにより、地方拠点の拡大とリソースの確保による事業拡大を図る目的でM&Aを実施しました。
コアコンセプト・テクノロジーでは、受注案件への参画や採用・人材育成のノウハウ提供などを行ってピージーシステムの成長に貢献することで、両社の発展を実現できると判断し、今回の子会社化を決定したということです。
参照元:株式会社コアコンセプト・テクノロジー「株式会社ピージーシステムの株式取得(子会社化)に関するお知らせ」
商社の事例
部品メーカーの株式会社ヤマシナは、2023年、ヤマヤエレクトロニクス株式会社の株式を取得し、子会社化しました。
ヤマヤエレクトロニクスは独立系の半導体商社であり、世界各国の主要都市にある協力会社と連携し、半導体・電子部品など各種製品を国内企業へ供給している会社です。
同社は大手企業との取引を強化して飛躍的に業績を拡大しており、経営者の業界経験も長く、培った人脈や情報網による調達力、営業力を武器としています。同社がヤマシナのグループに入ることにより、成長性の高い半導体事業がセグメントに加わりました。同社の取り組む多角化戦略にもマッチすることが、今回のM&Aを実施した理由です。
ヤマヤエレクトロニクスが得意とする販売力により、販路拡張等のシナジー効果も期待できます。さまざまな面でグループの企業価値向上に貢献するという判断のもとに、M&Aが行われました。
参照元:株式会社ヤマシナ「ヤマヤエレクトロニクス株式会社の株式の取得(子会社化)に関するお知らせ」
運輸会社の事例
一般貨物自動車運送事業を営む日伸運輸株式会社は、2016年、物流業を営む東亜物流株式会社に会社を譲渡し、事業承継を実現しました。
日伸運輸では後継者不在に悩み、事業承継・引継ぎ支援センターに相談をしたのが今回のM&Aの始まりです。日伸運輸は事業承継を視野に入れて借入金を完済しており、買い手である東亜物流が高く評価したのが無借金経営でした。
東亜物流には日伸運輸の前にもM&Aの実績が2社あり、買収を検討する際は、スケールメリットを実現できるかを意識しているということです。日伸運輸には東亜物流が基盤としていない地域に密着しており、引越しなどニッチな分野の事業にも魅力を感じて買収を決定しました。
参照元:事業承継・引継ぎ支援センター「事業承継前の事業磨き上げが、M&A成功のカギ」
まとめ
近年は、M&Aの増加に比例して、中小企業でもM&Aを検討するケースが増えています。売り手側は後継者不在の解消や廃業の回避、事業拡大などを目的に、買い手側は主に人材の獲得や新規事業参入などを目的にM&Aが行われています。
M&Aを実施する際は、まずアドバイザーに相談し、マッチングで相手先企業を見つけたのちに条件交渉へと進むのが一連の流れです。M&Aには財務や税務、法務など幅広い専門知識とM&Aの豊富な実績が必要であり、M&A支援機関によるサポートが不可欠です。
「後継者不在でM&Aを検討しているが、どのような手続きを行うのかわからない」「買い手企業は見つかるのか」など、中小企業のM&Aが不安な方は、レバレジーズM&Aアドバイザリー株式会社の利用をご検討ください。各領域で実績を積み重ねたコンサルタントが在籍し、相談から成約まで一貫してサポートを行います。
料金体系は、M&Aご成約時に料金が発生する完全成功報酬型です。譲受会社のみ中間金の設定があるものの、M&Aのご成約まで、ご相談も含めて無料でご利用いただけます。「中小企業のM&Aを成功させたい」という方は、お気軽にお問い合わせください。