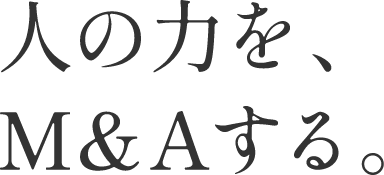このページのまとめ
- 事業譲渡とは、特定の事業の全てかその一部を他社に売却するM&A手法を指す
- 事業譲渡は、譲渡する資産の引き継ぎを個別に行う点が会社分割と異なる
- 事業譲渡は、譲渡の対象範囲を交渉次第で柔軟に設定できる点が大きなメリットである
- 譲渡する事業や資産によって、許認可の取得や納税義務が生じる点に注意が必要である
自社の経営戦略の一環として事業譲渡を検討している経営者の方もいるのではないでしょうか。
事業譲渡は譲り渡す対象範囲を柔軟に設定できるM&Aの手法です。
本記事では、事業譲渡のメリットとデメリットについて、売り手と買い手の両視点から詳しく解説します。また、事業譲渡に必要な手続きや税務、スムーズに事業譲渡を成功させるための注意点についても解説するので、ぜひ参考にしてください。
目次
事業譲渡とは
事業譲渡とは、ある企業が持つ事業の一部またはすべてを他の企業に売却するM&A手法です。
既存事業を売却・買収する事業譲渡は、売り手側と買い手側の双方にとってさまざまなメリットが期待できることから、経営戦略上の選択肢の1つとなっています。
事業譲渡とその他のM&A手法との違い
M&Aの手法は、事業譲渡以外にも数多く存在します。
ここでは、特に混同されがちな手法である株式譲渡と会社分割の2つの手法にフォーカスして、事業譲渡との違いについて解説します。
株式譲渡との違い
株式譲渡と事業譲渡との最大の違いは、経営権の移転があるかどうかという点にあります。
株式譲渡とは、売り手である譲渡会社の株式を譲受会社(買い手)が取得するというM&A手法の1つです。
株式の保有割合によって発行会社の経営に及ぼす影響力が変動します。
一方、事業譲渡はあくまで事業の移転があるのみで、株式の移転は発生せず経営権の移転も生じません。
会社分割との違い
会社分割とは、自社が保有する特定の事業を切り離し、既存または新設の会社へと移転するというM&A手法の1つです。
特定事業を切り出して他社へ移転するという点においては、会社分割と事業譲渡で共通しています。
会社分割と事業譲渡との違いは、譲渡会社から譲受会社へ引き継がれる方式が異なるという点にあります。
会社分割では、移転する事業に関連する資産や負債が包括的に譲受会社へと引き継がれます。そのため、手続きは簡易になりますが、簿外債務なども承継してしまうリスクがあります。
対して事業譲渡では、引き継ぐ資産を個別に選択できるため、必要な資産だけを承継し、負債などの譲受会社にとって不要なものは承継対象から外すことができます。
事業譲渡のメリット
ここからは、事業譲渡によって期待できるメリットを、売り手と買い手のそれぞれの視点から解説します。
売り手側の6つのメリット
事業譲渡によって、売り手側には下記6つのメリットが期待できます。
- 譲渡益を獲得できる
- 売りたい事業だけを譲渡できる
- 事業の選択と集中ができる
- 譲渡先が見つけやすくなる
- 法人格を継続できる
- 後継者問題を解決できる
それぞれ解説します。
1.譲渡益を獲得できる
事業譲渡では、譲受会社が引き受けた事業の対価として現金が譲渡会社に支払われるため、譲渡会社は譲渡益を獲得できます。
獲得した譲渡益は、新規事業の立ち上げ資金や債務返済などに充てることが可能です。
事業譲渡の対価は、対象事業の将来性も加味したうえで価額が決定するため、実際に譲渡する資産額よりも高額な対価を得られる可能性もあります。
2.売りたい事業だけを譲渡できる
事業譲渡のメリットは、譲渡対象をあらかじめ選択できることです。
先述の会社分割の手法では包括承継となるため、移転する事業とともに優秀な人材や特許権などの権利も譲受会社へと移ってしまいます。
人材や権利関係は自社に残したまま事業のみを移転させたい場合、事業譲渡がおすすめです。
3.事業の選択と集中ができる
事業譲渡により、事業の多角化によって生じた不採算事業を切り離すことで、経営資源を中核事業に集中させて、さらなる成長につなげることとが可能です。
加えて、譲渡対価で得た資金を今後成長が見込まれる新規事業に投入することもできます。
事業ポートフォリオの改善・強化が見込まれ、収益拡大を図れます。
4.譲渡先が見つけやすくなる
事業譲渡では、譲渡対象とする事業や資産の選択が可能です。
譲受会社にとっても負債などのマイナス資産を引き継ぐリスクを軽減できることから、マッチングが成立しやすくなります。
加えて、引き継ぐ事業や資産が明確であることにより、譲受会社となる企業がリスク評価や事業価値の算定が行いやすくなる点も、マッチングが成立しやすくなる要因となります。
5.法人格を継続できる
事業譲渡においては、他社へ移転するのは特定の事業と資産だけであるため、譲渡会社の法人格をそのまま残すことができます。
新設会社となって新たに事業をスタートさせるには、膨大な手続きと準備が必要となります。しかし、存続している会社であれば、新規事業の立ち上げから成長軌道に乗せるまでをスムーズかつ迅速に進めることができます。
また、法人格が継続することにより、譲渡会社がそれまで培ってきたブランド価値を今後の事業展開に有効活用することも可能です。
6.後継者問題を解決できる
事業譲渡の実施により自社の事業の運営を他社へ委ねることで、事業を存続させることができます。
後継者不在で事業の継続が難しい場合、事業譲渡を活用すれば、それまで培ってきたノウハウや技術を含めて事業そのものは存続させていくことができるでしょう。また、法人格が現世代で途絶えたとしても、事業に携わる従業員の雇用も守ることが可能です。
株式会社帝国データバンクによる『全国企業「後継者不在率」動向調査(2022)』では、全国約27万社の調査対象企業において、後継者不在率は57.2%と2021年の調査から4.3pt減少しています。非同族によるM&A実施率も増加しており、事業譲渡を含むM&Aによって後継者問題の解決が進んでいることが示唆されています。
出典:株式会社帝国データバンク『全国企業「後継者不在率」動向調査(2022)』(2022年11月16日)
買い手側の3つのメリット
事業譲渡によって買い手側に期待できるメリットは以下の3つです。
- 買収範囲を選択することができる
- 負債や債務を引き継ぐリスクを回避できる
- 節税効果が望める
それぞれ解説します。
1.買収範囲を選択することができる
買い手側となる譲受会社は、自社の経営戦略に基づき、必要な事業や資産のみを選択して買収することができます。
不要な資産を引き継ぐ必要がないことから、財務面でのリスクを抑えながら自社に必要な経営資源などを獲得できます。承継する資産を個別で選択できる事業譲渡の大きなメリットです。
また、必要な事業や資産だけを獲得することで効率的に事業成長を加速化できる効果が期待できます。
個別承継により、本来、人材育成や研究・開発にかかるはずの時間と手間を大幅に省くことができるでしょう。また、すでに高い技術や経験を持った人材や効果が実証されているノウハウを、自社の事業に投入することもできます。
自社の事業展開において弱みとなっている部分を補完できたり、強みに変えるパーツを柔軟に選択できたりする自由度の高さが、買い手側にとっての大きなメリットとなります。
2.負債や債務を引き継ぐリスクを回避できる
事業譲渡では、買い手側が不要とする資産を受け継ぐ必要がないため、譲渡事業にかかる負債や簿外債務を負うリスクを回避することができます。
ただし、承継する資産の範囲や内容については、双方間の交渉で決定するため、ケースバイケースで債務を含めて引き継ぐ場合もあります。
3.節税効果が望める
事業譲渡では、買収価格に含まれるのれんの損金算入による節税効果を望むことができます。
のれんとは、M&Aにおける買収価格を決定する際に、譲渡会社の時価純資産額に上乗せしたプレミアムのことです。主に、賃借対照表上に反映されていないブランドの知名度や高い技術を持った人材などの無形固定資産を意味します。
株式譲渡の場合は税務上のれんが生じることはありませんが、事業譲渡の場合は税務上の「のれん」として計上することが可能となります。
事業譲渡のデメリット
事業譲渡にはデメリットとなる側面も存在します。
事業譲渡のメリットを最大限に活かすためにも、デメリットについてもしっかりと理解したうえで適切な対応をしていくことが大切です。
ここからは売り手と買い手の両視点から、事業譲渡のデメリットについて解説します。
売り手側の6つのデメリット
事業譲渡において売り手側には、以下の6つのデメリットが生じることが考えられます。
- 譲渡後の事業展開に制限が生じる場合がある
- 譲渡益に法人税が発生する
- 負債が残る可能性が高い
- 株主総会の特別決議が必要となる
- 従業員の承諾を個別に得る必要がある
- 取引先からの承認が必要となる
それぞれについて解説します。
1.譲渡後の事業展開に制限が生じる場合がある
会社法第21条で定められた競業避止義務により、譲渡会社は同一および隣接する区市町村において原則20年間、譲渡した事業と同一の事業を行うことができません。
なお、特約を結ぶことで禁止期間を30年まで延長することが可能です。
これは、譲渡会社には事業に関する技術やノウハウ、人材が残っている可能性が高いことから、譲受会社と競合することを防ぐために設けられた規定です。
競業避止義務に違反した場合は、債務不履行により譲受会社から損害賠償を請求される可能性が生じます。
出典:e-Gov法令検索「会社法第21条」
2.譲渡益に法人税が発生する
事業譲渡によって譲渡会社が得た譲渡益は法人税の課税対象です。
実効税率は2023年時点で約31%となっており、譲渡する事業規模が大きくなれば、それに乗じて負担も増大します。
ただし法人税は譲渡益単独ではなく、同年度の譲渡会社の全損益に対して課されるため、計上される損金次第で税金負担が軽くなる可能性があります。
3.負債が残る可能性が高い
譲渡する事業にかかる負債があったとしても、譲受会社は引き継ぐ必要がないため、譲渡会社側に負債が残る可能性が高くなります。
実際に承継する資産の範囲や内容は交渉によって決めることができますが、個別に債務を引き受け契約を結ぶ場合は、債務の譲渡手続きが必要となってきます。
4.株主総会の特別決議が必要となる
事業譲渡を実施するためには、一部特例を除いて株式総会における特別決議によって承認されなければなりません。
株主が多ければ多いほど手間と時間を要するため、規模の大きな会社ほど負担が大きくなります。
5.従業員の承諾を個別に得る必要がある
株式譲渡や会社分割が包括承継であることに対し、事業譲渡は個別承継です。
そのため事業譲渡では、対象事業に関わる従業員の雇用に関して、譲受会社で継続するか否かを個別に確認・対応する必要があります。
事業と一緒に従業員も譲受会社へ譲渡する場合は、従業員一人ひとりと転籍交渉を行わなければなりません。従業員数が多いほど、説明や交渉に多くの時間・手間が割かれることになります。
6.取引先からの承認が必要となる
従業員の転籍と同様に、契約している取引先に対しても、事業譲渡を行うことについて個別に説明して同意を得る必要があります。取引先の数が多ければ、その分手間と時間がかかります。
また、仕掛かり中の契約がある場合はさらに注意が必要です。売掛負担先などを明確に定めたうえで、譲受会社へ取引契約を引き継ぐ手続きを進めましょう。
買い手側の3つのデメリット
事業譲渡により買い手側には、以下の3つのデメリットが考えられます。
- 買収資金の準備が必要となる
- 契約移転手続きが発生する
- 従業員と個別に雇用契約承継手続きをする必要が生じる
1.買収資金の準備が必要となる
事業譲渡では譲渡対価が現金であるため、譲受会社は買収資金を準備しておかなければなりません。
社内のキャッシュが足りない場合、銀行などから資金調達する必要性が発生します。
2.契約移転手続きが発生する
事業譲渡では、承継したい権利義務に対して、個別に引き受けの契約を締結しなければなりません。取引先との契約や許認可はそのまま引き継がれないため、注意が必要です。
特に許認可に関しては取得までに時間がかかるものもあり、取得まで事業をスタートできないといった空白期間が生じるリスクも考えられます。
3.従業員と個別に雇用契約承継手続きをする必要が生じる
譲渡会社から従業員も承継する場合、対象の従業員一人ひとりと雇用契約を締結しなければなりません。
従業員が多い場合はその分手間や時間がかかってしまうでしょう。また、交渉が難航する可能性もあり、その結果、人材の流出が起こってしまう可能性も考えられます。
事業譲渡における4つの注意点
ここからは、事業譲渡を成功させるためにおさえておくべき注意点4つについて解説します。
- 従業員の処遇に配慮する
- 譲渡する資産を明確に定める
- 免責登記の必要性を確認する
- 再取得・再認可が必要な許認可を確認する
それぞれ解説します。
従業員の処遇に配慮する
事業譲渡に際しては、譲渡する事業に従事していた従業員も承継するケースがほとんどです。従業員の移籍プロセスを慎重に進めなければ、人材の流出につながるおそれがあるため、従業員の処遇に十分に配慮しましょう。
従業員の移籍に際しては、譲受会社側で個別に労働契約を再度締結する必要があります。提示する雇用条件や従事する業務、職場環境、社内風土などの諸条件に大きな変化があると、従業員にとって不満の種となり、従業員が離職する可能性も考えられます。
譲受した事業に必要な高い専門性やノウハウ・経験を持った優秀な人材が離れてしまうと、当初期待したようなシナジー効果は半減してしまいます。
従業員の離職を防ぐために、従業員の処遇については、譲渡会社・従業員・譲受会社の3者の合意のうえで決定することが大切です。また、譲渡後も従業員が移転先で活躍できる処遇に配慮することが、事業譲渡を成功させるポイントです。
譲渡する資産を明確に定める
事業譲渡では、譲渡対象とする資産を明確に定めることが大切です。対象範囲が曖昧なまま譲渡を行うと、後にさまざまなトラブルに発展する可能性があります。
特に譲渡事業に債務がある場合、事業譲渡後にどちらの会社がその債務を負うのかという点は重要な交渉事項となります。一般的には債務は譲渡対象から外され、譲渡会社に残るケースが多いと考えた方がよいでしょう。
また、知的財産権やノウハウなどの無形資産に関しても、明確に譲渡対象を定めておかなければ、譲渡・譲受双方の企業にとって今後の事業展開に支障をきたすおそれがあるため、注意が必要です。
免責登記の必要性を確認する
譲渡会社の商号・屋号を引き継ぐ場合、譲受会社が債務も一緒に引き継ぐことが商法によって定められています。免責登記を行うことで債務責任を負う必要がなくなるため、免責登記を行う必要性があるかは両社間でしっかりと確認を行いましょう。
出典:e-Gov法令検索「商法第17条1項・2項」
再取得・再認可が必要な許認可を確認する
事業譲渡において許認可が必要な事業を譲渡する場合、譲受会社は許認可の再取得・再認可が必要となります。
許認可の再取得・再認可が必要な事業の一例は下記のとおりです。
- 宅地建物取引業
- ホテル・旅館営業
- 介護事業
- パチンコ店営業
- 一般貨物自動車運送事業
- 一般旅客自動車運送事業
事業譲渡に伴う許認可の再取得や再認可には届出の手間がかかります。また、認可されるまでに時間がかかるものもあります。
認可されなければ事業を開始することができず、譲渡後の事業展開に支障をきたす可能性があるでしょう。許認可の取得にかかる期間を考慮に入れて、計画的に譲受手続きを進めていくことが大切です。
事業譲渡に必要な手続き
ここからは、売り手側と買い手側のそれぞれの視点から、事業譲渡で必要となる手続きについて解説します。
売り手側で必要となる6つの手続き
事業を譲渡する売り手側の会社において必要となる手続きは、主に6つが挙げられます。
- 取締役会で事業譲渡を決議する
- 事業譲渡の基本合意契約を締結する
- 事業譲渡契約書を締結する
- 臨時報告書を提出する
- 株主への通知・公告を行う
- 株主総会における特別決議にて株主からの承認を得る
それぞれ解説します。
1.取締役会で事業譲渡を決議する
事業譲渡のスケジュールや譲渡価格をはじめとする希望条件が固まったら、譲渡会社は事業譲渡を行うことを、取締役会で決議する必要があります。
取締役設置会社でない場合は、取締役のうち過半数の賛成が得ることが必要です。
2.事業譲渡の基本合意契約を締結する
譲受会社の選定を行い、譲渡条件に関して双方が合意に達したら基本合意契約を締結します。
基本合意契約とは、事業の譲渡会社と譲受会社の双方が譲渡に際し、譲渡する対象資産や譲渡価格、譲渡日などに合意した旨を書面化した契約書類です。
基本合意契約は、譲受会社と条件交渉や今後のスケジュール調整などを進めていき、実現性が高まった段階で行います。
3.事業譲渡契約書を締結する
デューデリジェンスへの対応後、条件交渉を終えて、最終的な合意に至ったら、事業譲渡契約書を締結します。
事業譲渡契約書は基本合意書よりもさらに具体的な内容が記載される書類です
最終契約書にあたる事業譲渡契約書には法的拘束力があります。
内容をしっかり精査したうえで締結しましょう。
4.臨時報告書を提出する
譲渡会社が有価証券報告書の提出義務がある会社である場合、事業譲渡の契約内容によっては内閣総理大臣に対し臨時報告書を提出する義務が生じます。
臨時報告書の提出に該当するケースとしては、「企業内容等の開示に関する内閣府令」にて以下のように定められています。
- 事業譲渡実施後の資産額が、純資産額の30%以上増減することが見込まれる場合
- 事業譲渡実施後の資産額が、売上高の10%以上増減することが見込まれる場合
臨時報告書を提出していない場合や内容に虚偽が発覚した場合は罰則が課されるため、報告書の提出義務に該当するかどうかをしっかりと確認しておく必要があります。
出典:e-Gov法令検索「金融商品取引法第24条の5-4項」「企業内容等の開示に関する内閣府令第19条8項 」
5.株主への通知・公告を行う
事業譲渡においては、実施する旨を株主に対し、官報公告や電子公告、個別通知にて事業譲渡を実施する旨を通知し、併せて株主総会の招集手続きを行います。
公告掲載にかかる期間や株主総会開催のタイミングは、会社法にて下記のように期限が設けられているため、余裕をもったスケジュールで手続きを進めることが大切です。
| 手続き内容 | 期限 |
| 株主総会での承認 | 事業譲渡の効力発生日前日まで(会社法第467条) |
| 株主への周知および株主総会への招集通知 | 株主への周知および株主総会への招集通知:事業譲渡の効力発生日の20日前まで(会社法第469条3項・4項) |
| 公告掲載 | 掲載期間は最短で、事業譲渡の効力発生日の前日までの20日間。申し込みから掲載までに1週間から10日程度のリードタイムが生じるため、効力発生日の1ヶ月程度前までの申し込みが必要 |
このとき、事業譲渡に反対する株主には、自分の保有する株主の譲渡会社による買取を請求できる「株式の買取請求権」があることを、効力発生日の20日前までに公告または個別通知で周知します(会社法第469条)。
出典: e-Gov法令検索「会社法第467条・第469条」
6.株主総会における特別決議にて株主からの承認を得る
事業譲渡の実施に対しては、一部の例外を除いて、株主総会における特別決議で承認を得なければなりません。
株主総会では、議決権の過半数を持つ株主が出席し、その出席者の3分の2以上の賛成が得られた場合に承認されます。
反対株主の株式買取請求権は、株主総会での承認後に行使することができるようになります。
出典: e-Gov法令検索「会社法第467条」
買い手側で必要となる7つの手続き
事業を譲受する買い手側の会社において必要となる手続きは、主に下記の7つです。
- デューデリジェンスを行う
- 事業譲渡契約書を締結する
- 公正取引委員会へ届け出る
- 臨時報告書を提出する
- 株主への通知・公告を行う
- 株主総会における特別決議にて株主からの承認を得る
- 承継財産の名義変更や許認可の再取得手続きを行う
1.デューデリジェンスを行う
譲渡会社との基本合意契約締結後に実施されるデューデリジェンスは、買い手側の企業にとって非常に重要なプロセスです。
「買収監査」を意味するデューデリジェンスでは、買収する企業の財務状況をはじめ、買収後にリスクとなり得る要因や企業価値の調査・検証を行い、その結果をもとにこのままM&Aを実施して良いかどうかを判断します。
デューデリジェンスの結果を踏まえて最終交渉を進め、双方が合意に至った段階で基本合意契約書を締結します。
2.事業譲渡契約書を締結する
条件交渉を終えて、最終的な合意に至ったら、事業譲渡契約書を締結します。
デューデリジェンスで発覚したリスクが重大な場合は、本契約前に破談にする決断をする必要があるかもしれません。デューデリジェンスの内容を踏まえ、慎重に判断しましょう。
3.公正取引委員会へ届け出る
国内売上高の合計額が200億円を超える規模の会社が譲受会社である場合、以下のいずれかの状況下で事業を譲受する際には公正取引委員会への届出が必要となります。
- 国内売上高が30億円を超える会社の全事業を譲受しようとする場合
- 譲り受ける事業の国内売上高が30億円を超える場合
- 譲り受ける事業にかかる全ての固定資産の国内売上高が30億円を超える場合
このとき提出する書類は「事業等の譲受けに関する計画届出書」という書類で、原則として届出が受理されてから30日間は事業を譲り受けてはいけません。
出典:公正取引委員会「事業等の譲受けの届出制度 事業等の譲受けの届出制度(独占禁止法第16条第2項)、届出後の手続(独占禁止法第16条第3項)」
4.臨時報告書を提出する
譲受会社が有価証券報告書の提出義務がある場合は、譲渡会社と同様に財務局を通じて内閣総理大臣へ臨時報告書を提出しなければなりません。
臨時報告書の提出が必要となるケースは、譲渡会社にて挙げた条件と同じです。
5.株主への通知・公告を行う
譲受会社も譲渡会社と同様に、事業を譲受する旨を株主に対して官報公告や電子公告、個別通知などの方法で周知します。
6.株主総会における特別決議にて株主からの承認を得る
譲渡会社では原則として株主総会での特別決議が必要となるのに対し、譲受会社ではある2つのケースに該当する事業譲渡の場合、株主総会による決議が不要となります。
1つ目は、譲受会社が譲渡会社の株式の9割以上をすでに保有している「特別支配会社」である場合です。
譲受会社が譲渡会社の特別支配会社である場合、譲受会社の意向を優先した事業譲渡となるため、わざわざ株主総会で承認を得る必要性がなくなってしまいます。
2つ目のケースは、譲受会社が譲渡会社に対価として交付する財産の帳簿価額の合計額が、法務省令で定められた方法で算定される譲受会社の純資産額の5分の1未満である場合です。
このケースでは、事業を譲受するにあたって支払う対価が、譲受会社の財務状況や株価に対してさほど大きな影響を及ぼさない規模であることから、株主の承認は不要であると考えられるためです。
ただし、一定数の株式を保有する株主から反対するとの通知があった場合は、事業譲渡の効力発生日の前日までに株主総会の特別決議によって承認を得る必要があります。
出典元: e-Gov法令検索「会社法第468条第1項〜第3項」
7.承継財産の名義変更や許認可の再取得手続きを行う
事業譲渡では、事業にかかる許認可や契約などを包括的に引き継ぐことができないため、個別で名義変更や再申請などの手続きをしなければなりません。
先に述べたとおり、許認可が必要な事業を譲受する場合、事業内容によっては改めて認可を取得したり、届出を再度提出したりする手続きが生じます。
事業譲渡にかかる税金
事業譲渡では、売り手と買い手の間で取引される財産に対して税金が発生します。
ここからは、譲渡会社と譲受会社それぞれの立場において生じる税金について解説します。
売り手側に生じる税金
事業の売り手側となる譲渡会社に課される税金は、法人税と消費税の2つです。
法人税
法人税は実際に対価として支払われた譲渡額そのものに対してではなく、譲渡した資産と比較した際に実際に得た利益(譲渡益)に対して課されます。
具体例を挙げてみましょう。下記は譲渡額が5億円で、譲渡した資産の価値が3億円、負債が1億円だった場合の譲渡益の計算方法です。
(5億円) – (3億円 – 1億円) =3億円
この場合、譲渡益の3億円に対して約31%の実効税率が課されることになります。
3億円×約31% = 9,300万円
このように、法人税・法人住民税・事業税などの税金を合わせて約9,300万円が納税額となります。
消費税
事業の譲渡会社においては、譲渡する資産のうち課税資産に対して10%の消費税が課され(2023年11月現在)、納税義務が発生します。
具体的には、譲渡金額から課税対象外となる土地・有価証券・債券などの資産額を差し引いた額が消費税の課税対象となります。
譲渡金額が5億円、課税対象外資産が2億円の場合、下記の計算で3,000万円を支払うことになります。
(5億円 – 2億円) × 10% = 3,000万円
消費税は、法人税のように「譲渡益」に対してではないため、たとえ事業譲渡によって赤字が発生した場合でも、消費税が生じる点には注意が必要です。
また、消費税は形式的には譲渡側が支払いますが、実際に負担しているのは譲受側となります。
買い手側に生じる税金
事業の買い手側となる譲受会社に課される税金は、消費税・登録免許税・不動産取得税の3つです。
消費税
消費税は譲渡会社に課される税金です。しかし、事業の譲渡額には消費税分があらかじめ上乗せされているため、実質的には譲受会社が消費税を負担するという構図になります。
登録免許税
事業譲渡により不動産や先述の許認可を要する事業を譲受した場合、不動産登記や許認可の再取得に際して、登録免許税を納税する必要があります。
不動産取得税
譲受した資産に不動産が含まれる場合、不動産取得税の支払いも発生します。
不動産取得税は登記の有無や有償・無償に関係なく、不動産の所有権を持った時点で生じる税金であるため、納税漏れに注意が必要です。
不動産取得税は不動産評価額に対して課され、税率は4%です。ただし、2024年3月までに取得した場合、3%の軽減税率が適用されます。
まとめ
事業譲渡は、譲渡する範囲を柔軟に設定できるという点が特徴的なメリットであるM&A手法です。
譲渡会社と譲受会社の双方にとって対象範囲を柔軟に設定できることにより、より希望条件に合った取引が可能となる一方で、包括的な引き継ぎができないことから、さまざまな資産の引き継ぎを個別で対応しなければならないという手間が発生します。
また、譲渡する資産の対象範囲の設定や個別の引き継ぎ手続きに際しては、法務・税務・労務・経理など幅広い知識が必要です。
そのため、事業譲渡においてはM&Aの専門家にサポートを依頼する方が、譲渡会社・譲受会社の双方にとってストレスなく事業譲渡を進められるでしょう。
レバレジーズM&Aアドバイザリー株式会社は、M&Aのすべてのプロセスをサポートする仲介会社です。M&Aにおいて多岐にわたる知識を有したコンサルタントが、円滑な事業譲渡をサポートいたします。
料金体系は完全成功報酬型ですので、M&Aのご成約まで無料でご利用いただけます(譲受会社のみ中間金あり)。無料相談も承っておりますので、M&Aをご検討の際にはぜひお気軽にお問い合わせください。