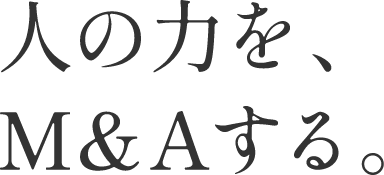このページのまとめ
- 株式交換は企業買収の1つの方法で、実施後は完全親会社・完全子会社の関係が成立する
- 株式交換では現金のやり取りは発生しない
- 株式交換の実施後、完全親会社は仕訳が必要になるが株主は仕訳不要
- 株式交換の実施後、完全子会社とその株主は状況によって仕訳の必要性や方法が異なる
「株式交換を実施した後、どのような仕訳が必要になるのだろうか」と疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。株式交換では現金のやり取りが発生しないため、通常の購入・売却のような仕訳方法は使えません。とはいえ、資産は動くため仕訳が必要です。
本コラムでは、株式交換における仕訳について説明します。完全親会社とその株主、完全子会社とその株主の4つの立場に分けて仕訳方法を具体的に紹介します。
株式交換をスムーズに進めるためにも、ぜひお役立てください。
目次
株式交換とは?
株式交換とは、株式を交換することで、完全親会社・完全子会社の関係をつくるM&Aの手法の1つです。完全子会社となる企業の発行済み株式を、完全親会社がすべて取得することで成立します。
株式交換は、合併のように企業が1つにまとまる手法ではありません。完全親会社・完全子会社という立場の違いは生じますが、それぞれが独立した企業として存続するため、社員や取引先などにはほとんど影響を及ぼさないことも特徴です。また、社内ルールも従来のものを踏襲できるため、ルール改正の必要がなく、新しい体制に移行しやすい手法といえます。
株式移転との違い
株式移転とは、新たに設立した企業を親会社(特定親会社)として、すでに存在する企業の発行済み株式をすべて取得させるM&Aの手法です。株式移転を実施する企業はすべて新設会社の完全子会社となるため、株式交換のように既存の会社間で親会社・子会社の関係は生まれません。
たとえばA社とB社が株式移転によりM&Aを実施する場合は、完全親会社となるC社を新たに設立し、A社・B社の発行済み株式をすべてC社に移転します。つまり、株式移転の実施後、A社・B社の株主は自動的にC社の株主となります。
一方、株式交換では新たに企業を設立する必要はありません。完全親会社となる側、完全子会社となる側に分け、完全親会社となる側が完全子会社の発行済み株式をすべて取得します。完全親会社がD社、完全子会社がE社とすると、株式交換後はE社の株主は自動的にD社の株主になります。
関連記事:株式交換とは?実施のメリット・デメリットや事例をわかりやすく解説
株式交換のメリット
株式交換には次のメリットがあります。
- 現金のやり取りが発生しない
- すべての株主が同意しなくても実施できる
それぞれのメリットについて見ていきましょう。
現金のやり取りが発生しない
株式交換は、株式を交換することで成立するM&Aの手法です。現金のやり取りが発生しないため、資金がないときでも企業買収を実施できます。
なお、基本的には株式を交換することによりM&Aを実施しますが、完全子会社の株主は完全親会社の株式以外で対価を受け取ることも可能です。たとえば社債や新株予約権、完全親会社の親会社の株式、あるいは現金などでも対価を受け取ることがあります。
ただし、完全親会社の株式以外で対価を受け取ると、手続きが複雑になることもあるため注意が必要です。また、後述しますが適格株式交換に該当せず、税金が増える可能性もあります。
すべての株主が同意しなくても実施できる
通常、他社の株式をすべて取得するときは、すべての株主から同意を得なくてはいけません。しかし、株式交換においては、子会社となる企業で株主総会を開催し、過半数の議決権を持つ株主が参加して2/3以上の賛成を得れば実施できます。
ただし、同意を得られなさそうな株主が大株主であるときは、株式交換の成立は難しいと考えられます。株式交換の実施が総意になりにくそうなときは、株式移転などの別のM&A手法も検討しましょう。
株式交換の区分
株式交換には、会計上・税務上いくつかの区分があります。区分を正確に把握することで、仕訳や税務処理も正確に遂行できるようになります。各区分について見ていきましょう。
会計上の区分
株式交換では、どの企業が主に事業規模や議決権を支配しているのかによって、会計上の区分をします。主な区分は次の4つです。
- 取得
- 持分の結合
- 共同支配企業の形成
- 共通支配下の取引
それぞれの区分について説明します。
取得
「取得」とは、株式交換によってどちらの企業が相手企業を取得したのか明らかな状態を指します。事業規模や議決権の割合などから取得関係が明白なときは、取得扱いとなります。
株式交換が取得だと判断されるときは、パーチェス法によって会計処理をすることが一般的です。パーチェス法では完全子会社となる企業の資産や負債は、すべて公正価値で評価します。取得価額と公正価値に差が生じているときは、差額をのれんとして計上することが必要です。
持分の結合
「持分の結合」とは、株式交換によってどちらの企業が取得した、あるいは取得されたのかが明らかではない状態を指します。事業規模や議決権の割合を見ても、取得関係が明白ではないときは、持分の結合扱いとなります。
たとえば現金で企業買収を実施したときは、現金を支払った側が取得企業です。しかし、株式交換のように対価を株式とするときは、自己株式を交付した側が取得企業とは限りません。取得企業・非取得企業が明白でないときは、持分プーリング法によって会計処理をすることが一般的です。持分プーリング法では完全子会社となる側の資産や負債は、帳簿価額で計上します。
ただし、持分プーリング法による会計処理は、国際的には廃止の流れにあります。今後は日本においても廃止が進み、パーチェス法だけで会計処理をおこなう可能性がある点に注意しましょう。
共同支配企業の形成
「共同支配企業の形成」とは、株式交換によって複数の企業がある企業を共同して支配する状態が生まれることです。対価が議決権のある株式で、なおかつ当該企業がすべて独立企業であり、企業間に共同支配の契約が締結されているときに「共同支配企業の形成」と判断されます。
持分プーリング法に準じた方法で会計処理をおこなうことが一般的ですが、将来的にはパーチェス法で計算する可能性もあります。
共通支配下の取引
「共通支配下の取引」とは、グループ内企業が株式交換するケースを指します。
共通支配下の取引も、持分プーリング法に準じた方法で会計処理をおこなうことが一般的です。しかし、持分の結合や共同支配企業の形成と同じく、将来的にはパーチェス法で計算する可能性があります。
税務上の区分
株式交換は税務上の処理が必要かどうかによって、次の2つに分類できます。
- 適格株式交換
- 非適格株式交換
それぞれの違いや条件について説明します。
適格株式交換
適格株式交換とは、適格要件を満たした株式交換のことです。資産は帳簿価額で移転されるため、譲渡損益がなく、完全子会社とその株主に対しては課税がおこなわれません。
適格株式交換の要件には、次の7つがあります。
- 完全支配関係あるいは支配関係が継続していること
- 株式以外を交付していないこと
- 従業員を引き継ぐこと
- 事業を継続すること
- 事業の関連性があること
- 株式を継続保有すること
- 親会社と子会社の規模の差が5倍を超えない、もしくは株式交換後に1人以上の子会社の役員が退任せずに残ること
完全支配関係とは、子会社のすべての株式を親会社が保有していることです。また、支配関係とは親会社が子会社の株式の過半数を保有していることを指します。適格株式交換では、完全支配関係か支配関係が株式交換後も継続することが必要です。
共同事業目的で株式交換を実施する場合は、上記のすべての要件を満たすことが求められます。しかし、株式交換により完全支配関係を構築する場合なら、上記の「完全支配関係あるいは支配関係が継続していること」と「株式以外を交付していないこと」の2つの条件を満たせば、適格株式交換と認められます。
また、株式交換により支配関係を構築する場合は、「完全支配関係あるいは支配関係が継続していること」「株式以外を交付していないこと」「従業員を引き継ぐこと」「事業を継続すること」の4つを満たすことが必要です。
非適格株式交換
適格株式交換の要件を満たしていないときは、非適格株式交換と判断されます。非適格株式交換においては、次の2点に注意が必要です。
- 繰越欠損金の扱い
- 会計処理・税務処理の有無
適格株式交換では完全子会社の繰越欠損金は、完全親会社がそのまま引き継ぎます。一方、非適格株式交換では繰越欠損金を引き継げないため、完全子会社に繰越欠損金がある場合でも課税対象額を減らすことができません。
また、適格株式交換では完全子会社に会計処理や税務処理が発生しません。しかし、非適格株式交換では完全子会社は完全親会社に時価で株式を譲渡したことになるため、会計処理が必要です。それに加え、完全子会社には、株式交換を実施した事業年度において時価評価による課税がおこなわれます。
【株式交換の仕訳】完全親会社の場合
完全親会社と完全子会社の取得関係によって、「取得」「持分の結合」「共同支配企業の形成」「共通支配下の取引」の4つの種類に分かれます。取得の場合はパーチェス法、それ以外の場合は持分プーリング法で会計処理をおこなうことが一般的です。
「取得」のときは、完全親会社は完全子会社の資産と負債を引き継ぎ、個別財務諸表に計上します。完全子会社の株式を取得した原価については、株式交換を実施した日の時価により評価し、取得の対価に直接かかった費用を上乗せして「取得原価」にします。
新たに株式を発行したことで増加した資本金等についても、財務諸表への計上が必要です。交換対価として交付した自社株式の時価のうち、株式交換契約で定めた金額を「資本金」「資本準備金」として計上し、差額があるときは「その他資本剰余金」として計上します。
「持分の結合」のときは、現金が動かない場合であれば、どちらが取得企業になるのか判別できないこともあるため注意が必要です。たとえば自己株式を交付したとしても、事業規模や議決権などによっては非取得企業になることがあります。
完全親会社の資本が増加した場合は、完全子会社の帳簿価額の資産・負債の差額を基準とし、株式交換契約で定めた金額を「資本金」「資本準備金」として計上しましょう。差額は「その他資本剰余金」として計上します。
「共同支配企業の形成」のときは、取得企業がどの企業かを判別できないため、すべての結合企業の資産・負債を帳簿価額で引き継ぎます。
「共通支配下の取引」では企業間の取引はなく、発生した取引はいずれも内部取引です。企業ごとの個別の財務諸表では簿価として処理しますが、連結時に相殺により消去されます。
完全親会社が上場企業の場合の例
仕訳の書き方は、完全親会社が上場企業か非上場企業かによって異なります。完全親会社となるA社が上場企業で、同じく上場企業であるB社と株式交換をおこなう場合について考えてみましょう。
たとえば交換比率は2:1、株式交換する日の株価がA社は2,000円、B社は800円とします。B社の発行済み株式の総数が1,500万株、A社が発行した新株のうち、半分は資本金、残りは資本剰余金に計上する場合は、以下のように会計処理ができます。
A社が発行する株式総数:1,500万株×1/2=750万株
A社がB社に支払う取引対価:750万株×2,000円=15,000百万円
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
| 子会社株式 | 15,000百万円 | 資本金 | 7,500百万円 | B社との株式交換 |
| 資本剰余金 | 7,500百万円 | |||
完全親会社が非上場企業の場合の例
完全親会社となるC社が非上場企業で、同じく非上場企業のD社を完全子会社として株式交換を実施する場合について考えてみましょう。この場合は株価がないため、企業価値の算定が必要です。自社での計算では公正性に欠けると思われるときは、M&A仲介会社や公認会計士などの専門家に依頼して企業価値を計算してもらい、発行済み株式数から株価を割り出すことになります。
精査の結果、C社の株価は100円、D社の株価は300円、交換比率は3:1との評価を受けたとしましょう。また、D社の発行済み株式数は1,500万株、C社が発行する新株のうち、半分は資本金、残りは資本剰余金に計上する場合は、以下のように会計処理ができます。
C社が発行する株式総数:1,500万株×1/3=500万株
C社がD社に支払う取引対価:500万株×100円=500百万円
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
| 子会社株式 | 500百万円 | 資本金 | 250百万円 | D社との株式交換 |
| 資本剰余金 | 250百万円 | |||
【株式交換の仕訳】完全親会社の株主の場合
株式交換では、完全親会社が新株を発行し、完全子会社の株式と交換する形で買い取ります。完全親会社は取引の当事者ですが、完全親会社の株主は当事者ではないため、資金の移動はなく、仕訳の必要もありません。
ただし、株式交換により持分が大きく変化することがある点に注意しましょう。たとえば株式交換によって取得した完全子会社の株式の時価総額が大きく、完全子会社の株主に多くの株式数が割り当てられると、完全親会社の株主の持分が大幅に減る可能性があります。
【株式交換の仕訳】完全子会社の場合
完全子会社は株式交換の当事者で、なおかつ株式を交換する際に完全親会社の株式などの対価を受け取ります。とはいえ、株式として受け取るときは資金のやり取りが発生していないため、会計処理の必要がなく、仕訳も必要がありません。
しかし、株式以外の方法でやり取りをしたときなど、いくつかの状況下では会計処理が必要です。新株予約権が消滅した場合と交換対価が生じた場合、非適格株式交換となった場合に分けて説明します。
新株予約権が消滅した場合
株式交換を実施すると、企業間で完全親会社・完全子会社の関係が生まれます。完全子会社の株式はすべて完全親会社が保有することになるため、完全子会社が発行している新株予約権がある場合は、株式交換後はその新株予約権は消滅すると考えることが自然です。
新株予約権が消滅すると、新株予約権を発行していた完全子会社は、帳簿から新株予約権の価格を減額処理します。また、減額した分は「免除益」となり課税対象となるため、税効果会計によって控除した金額を利益として処理します。
自己株式に対して交換対価が生じた場合
完全子会社の株式に対して、完全親会社の株式ではなく現金などの対価が割り当てられることがあります。この場合は、会社が取得した自己株式を処分する「自己株式処分」が発生したと考え、交換の対価と完全子会社の自己株式の簿価の差を「その他資本剰余金」として計上します。
非適格株式交換を実施した場合
適格要件を満たさず、非適格株式交換が成立した場合は、完全子会社の資産も課税対象となるため、会計処理をしておくことが必要です。株式交換前に所持していた時価評価資産の評価損益については、完全子会社の益金もしくは損金に算入します。
【株式交換の仕訳】完全子会社の株主の場合
株式交換において、完全子会社の株主は取引の当事者となります。完全子会社とその株主が保有するすべての株式(完全子会社の株式に限る)が株式交換の対象となるため、完全親会社の株式や現金などの形で対価を受け取ります。
しかし、会計処理が常に必要とは限りません。投資の継続性が見られた場合と投資が清算された場合に分けて、会計処理や仕訳について説明します。
投資の継続性が見られた場合
株式交換後も完全子会社の株式が、完全子会社の自己株式として存続する場合は、「投資の継続性」が見られたと判断します。株式交換においては、投資の継続性が見られるときは、交換によって損益が発生したとは判断しません。
株式交換によって交換された株式は、帳簿価額を引き継ぎます。また、会計処理の必要がないため、仕訳も必要ありません。
投資が清算された場合
株式交換の実施により、完全子会社の自己株式が消滅することがあります。なお、株式交換は完全支配関係か支配関係、共同事業目的のいずれかの形を実現するためにおこなわれますが、完全支配関係か支配関係を実現する場合は子会社の自己株式は消滅することが一般的です。消滅した場合は、「投資の継続性」がなく、すべての投資は清算されたと判断します。
株式交換では、投資における継続性が見られないときは、交換を遂行したことで損益が発生したと判断することが通常です。交換により消滅した株式を確認し、完全親会社により交付された株式を時価で帳簿に計上します。
株式交換の税務処理
株式交換により資産の移動や利益が発生すると、税金が課せられることがあります。なお、株式交換によって生じる税務は、適格要件を満たしているかによっても異なるため注意が必要です。
適格要件を満たしているかに注目し、想定される税金の種類や税務処理を、完全親会社とその株主、完全子会社とその株主の4者に分けて説明します。
完全親会社の税務処理
株式交換の際、完全親会社は新たに自社株式を発行します。発行した自社株式により完全子会社となる企業の株式を受け取るため、現金による利益はないものの、資産が増えることになります。
ただし、適格要件を満たすかによって、税務処理が異なる点に注意が必要です。適格要件を満たしているかによってケースを分け、完全親会社の税務処理を説明します。
適格株式交換の場合
適格要件を満たしている場合、完全子会社の株主数が50人以上か未満かによって、完全子会社の株式
を取得した価額の決め方が変わります。
完全子会社に50人以上の株主が存在するときは、完全子会社の簿価純資産価額相当額に株式取得にかかった費用を加えた金額が、株式の取得価額となります。
一方、完全子会社の株主の人数が50人に満たないときは、完全子会社の株主が保有していた完全子会社の自社株式の帳簿価額相当額(株式交換直前の価額)が、株式の取得価額です。株主の人数が50人以上のときと同じく、株式価額に株式取得にかかった費用も加えて算出します。
資本金については、帳簿上の資産と負債の差額をそのまま計上します。ただし、計上する金額については、株式交換契約で定めることが可能です。
非適格株式交換の場合
適格要件を満たしていない場合、株式交換時の時価で完全子会社の株式の取得価額を算出します。また、資本金については、完全子会社の株式の取得価額から、株式交換によって生じた資本金額を減額した金額を記します。
ただし、株式交換により資本金が増えた場合は、適格要件を満たしているときと同じ方法で資本金を計算する点に注意が必要です。原則としては帳簿上の資産と負債の差額をそのまま資本金として計上しますが、株式交換契約で定めた金額に従って調整します。
完全親会社の株主の税務処理
完全親会社に関しては、資産の移動や資本金の増減が発生します。しかし、完全親会社の株主は取引の当事者ではないため、基本的に税務処理は発生しません。
適格株式交換の場合
適格要件を満たしている場合も、完全親会社の株主に関しては取引の当事者ではないため、税務処理は発生しません。
ただし、株式ではなく現金などを対価として受け取っている場合は、適格要件から外れるだけでなく、利益が生じたと考えられるため、課税対象になることがあります。利益に対しては正しく税計算を実施し、適切な時期に納税しましょう。
非適格株式交換の場合
適格要件を満たしていない場合も、完全親会社の株主に関しては取引の当事者ではありません。そのため、税務処理は発生せず、株式交換関連での納税義務もありません。
ただし、株式交換の際に保有する株式を売却し、現金などで対価を受け取っている場合は課税対象となることがあります。正しく税計算を実施し、適切なタイミングで納税しましょう。
完全子会社の税務処理
完全子会社は、株式交換の当事者です。利益が生じたときや、適格株式交換の要件を満たさないときは、適切に税計算を実施して税務処理をおこなう必要があります。適格要件を満たしているかによってケースを分け、税務処理の必要性を説明します。
適格株式交換の場合
適格要件を満たす場合は、税務処理の必要はありません。ただし、適格要件の項目は多いため、見落としがあると意図的ではなくても脱税になる恐れがあります。以下の表を参考に、株式交換の目的によって定められているすべての要件を満たしているか確認しておきましょう。
| 完全子会社から見た適格株式交換の要件 | 完全支配関係 | 支配関係 | 共同事業目的 |
| 完全支配関係あるいは支配関係が継続している | 必要 | 必要 | 必要 |
| 株式以外の交付を受けていない | 必要 | 必要 | 必要 |
| 従業員が引き継がれている | 不問 | 必要 | 必要 |
| 株式交換後も事業を継続している | 不問 | 必要 | 必要 |
| 完全親会社と事業の関連性がある | 不問 | 不問 | 必要 |
| 親会社により株式が継続的に保有されている | 不問 | 不問 | 必要 |
| 親会社との規模の差が5倍以下、あるいは自社の役員が1人以上、株式交換後も残留する | 不問 | 不問 | 必要 |
非適格株式交換の場合
適格要件を満たさなかったときは、完全子会社の時価評価損益に対する課税がおこなわれます。株式交換の直前の時価評価資産について損益を計算し、株式交換がおこなわれた事業年度に算入します。
完全子会社の株主の税務処理
完全子会社の株主は、株式を完全親会社に譲渡した当事者です。譲渡した価額や譲渡に要した費用などから所得を計算し、適切に税務処理をすることが必要です。適格要件を満たしているかによってケースを分け、完全子会社の株主がおこなう税務処理を説明します。
適格株式交換の場合
適格要件を満たして株式交換をおこなった場合、完全子会社の株主は、保有する株式(完全子会社の株式に限る)を完全親会社にすべて譲渡したことになります。事業年度ごとの所得の金額から算出した帳簿価額をもとに、譲渡損益を計算して繰り延べます。
非適格株式交換の場合
適格要件を満たしていない場合は、完全子会社の株主が保有する株式(完全子会社の株式に限る)の対価の種類によって税務処理が変わる点に注意しましょう。
株式交換の対価を完全親会社の株式として受け取ったときは、株式交換の直前の完全子会社株式の帳簿価額が、完全親会社の株式に付け変わることになります。この場合は、みなし配当は発生しません。
一方、完全親会社の株式以外のもの、たとえば新株予約権や現金として対価を得たときは、対価を時価で計上し、完全子会社株式との差額を損益とします。この場合も、完全親会社の株式で対価を得たときと同様、みなし配当は発生しません。
なお、みなし配当とは、ある企業の株主が、企業から配当金を受け取っていないのに受け取ったとみなされることです。実際には配当金は発生していませんが、税制上の都合上により、利益分配が生じたことにされるため、課税対象となります。
みなし配当が発生するのは、会社から株主に何らかの払い戻しがされたときか、組織再編により別会社の株式や対価を株主が受け取るときが多いです。株式交換では、完全子会社の株主は別会社である完全親会社の株式や対価を受け取りますが、みなし配当は発生しないものとして税務処理をするため、注意しましょう。
まとめ
株式交換における仕訳は、立場や取得関係、上場しているかどうかなど、状況によって必要性や方法が異なります。仕訳のパターンは多岐にわたり、複雑です。
自社の株式交換がどのパターンに当てはまるかをしっかり確認したうえで、仕訳をおこないましょう。
非上場企業が株式交換をするときは、まずは自社の企業価値と相手企業の企業価値を正確にバリュエーションすることが必要です。企業価値を正しく計算しないと、株式価額が実情を反映したものとならず、不平等な株式交換となる可能性があります。
正確なバリュエーションには高度なスキルと知識、経験が必要です。株式交換を検討している場合は、ぜひM&Aの専門家であるM&A仲介会社に相談してみましょう。
M&AならレバレジーズM&Aアドバイザリーにご相談を
レバレジーズM&Aアドバイザリー株式会社には、各領域の専門性に長けたコンサルタントが在籍しています。さまざまな手法のバリュエーションにも対応しており、相手企業の紹介・選定からM&Aの成立まで、一貫したサポートを提供することが可能です。
ぜひレバレジーズM&Aアドバイザリー株式会社のご利用をご検討ください。