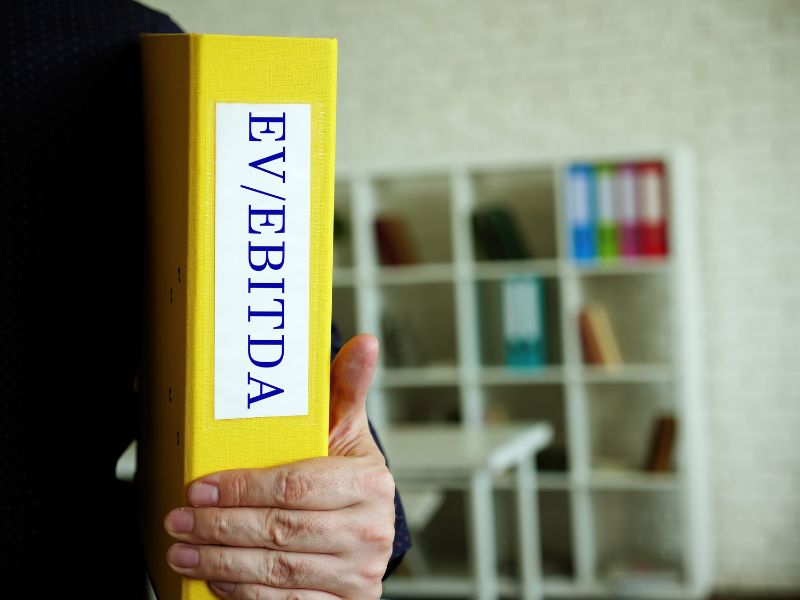このページのまとめ
- 有利発行とは、市場価格よりも安い価格や有利な条件で株式を発行する手続きのこと
- 有利発行は、非上場企業の資金調達や福利厚生施策として利用される
- 非上場企業の株価算定では、財務諸表やキャッシュフローをもとに企業価値を測る
- 有利発行で必要となる税務は、発行株式を取得した相手が法人か個人かによって異なる
資金調達を行うにあたって、有利発行を検討している経営者の方もいるのではないでしょうか。有利発行を利用して資金調達を行う際は、法制度に遵守した形で必要な手続きを踏むことが大切です。
本記事では、有利発行の特徴や税務について詳しく解説します。有利発行に際して必要となる手続きや非上場企業の株価算定方法についても解説するので、ぜひ参考にしてください。
目次
有利発行とは
第三者割当増資や新株発行の際に、株主以外の第三者に対して有利となる価格や条件にする手続きのことを「有利発行」といいます。有利発行は、投資家と企業の双方において複数のメリットが期待できる一方で、株式の希薄化が発生し、既存の株主の権利を害する恐れがあるというデメリットが存在します。
そのため、有利発行は株主総会による特別決議にて承諾を得てからでないと行うことができません。
また、有利な価格や条件で株式を発行する有利発行に対し、公正な金額で株式を発行することを公正発行といいます。公正発行を行う際は、公開会社が行う場合は取締役会、非公開会社の場合は株式総会の特別決議にて募集事項を決定するように定められています。
有利発行の判断基準
会社法199条3項では、”払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合”が有利発行とされると定義づけられていますが、明確な金額の基準などは定められていません。
そのため、一般的には発行条件を決定する直前の株価を基準として「公正な発行価額」を算定し、その金額とあまりにも乖離した低い金額である場合は、有利発行と判断されます。
有利発行を判断する目安としては、公正な発行価額に対して10%以上値引きされた金額である場合が有利発行と判断されることが通例となっています。
引用元:会社法 | e-Gov法令検索(199条3項)
有利発行が利用される場面
有利発行は、資金調達目的で行われる場面が大半ですが、そのほかの目的のために有利発行を行う場面も存在します。
ここからは、有利発行が利用されることが多い2つのケースについて、解説していきます。
第三者割当増資
第三者割当増資とは、特定の第三者に対して株式を発行し資金を調達する手法です。特に債務超過など財務状況が悪化している非上場企業においては、財務基盤強化を目的に第三者割当増資を行うケースがみられます。
債務超過状態にある場合、なかなか増資を実現させることは難しい中で、有利発行により通常より安い価格に株式を設定することで、引き受け相手を見つけやすくなることが期待できます。
新株予約権発行
新株予約権とは、一定期間内であれば、あらかじめ決められた金額や条件で新株を取得することができる権利のことを指します。
新株予約権は、第三者割当増資を含む資金調達目的として社外向けに発行されることが多い一方で、企業が社内向けに発行するケースもみられます。社内向けに発行される新株予約権は「ストックオプション」と呼ばれ、有利発行が行われることが一般的です。
市場価格よりも安く自社株式を取得できる権利を与えることで、従業員のモチベーション向上につながるため、近年はスタートアップを中心に福利厚生制度の一環として取り入れる企業が増えています。
非上場企業による有利発行に必要な企業価値評価
株式の市場価格を基準として行われる有利発行ですが、市場に対して株式公開を行っていない非上場企業の場合、適切な株価を算定することが困難であるという問題があります。
そのため、非上場企業の第三者割当増資に際して有利発行を行う場合は、まず適正な株価を算定することが必要となってくるのです。
ここからは、企業価値という観点から非上場企業の株価算定を行う3つの方法について解説していきます。
マーケットアプローチ
マーケットアプローチは、類似する企業の取引や株価を参考に、企業価値を評価する手法です。
自社に近い経営状況や業種の企業を参考に、実際に行った株式の取引実績や一定期間内の株価をもとにするなど、データを基準としたアプローチであるため、客観性の高い企業価値評価が可能となります。
しかし、非上場企業と類似する企業となると、相手も非上場企業であることが多いため、参考とする企業情報を見つけることが難しいというデメリットがあります。
コストアプローチ
コストアプローチは、企業の純資産から企業価値を評価する手法で、簿価と時価のいずれかによる資産評価によって株価算定を行います。
評価プロセスが明確でシンプルであることから、算定に際して専門家のサポートが不要となることが多いため、コストや手間を最小化できるというメリットがあります。
ただし、コストアプローチは現在の純資産にのみ着目されていることから、当該企業の将来的な価値が考慮されない株価となる点には注意が必要です。
インカムアプローチ
インカムアプローチは、当該企業の将来的な収益性やキャッシュフローに着目して企業価値を評価する手法で、株価算定においてよく用いられる手法です。
投資金額に対して、当該企業や事業が将来生み出すであろう利益予測をベースに評価を行うDCF法が、インカムアプローチにおける主な手法です。
DCF法のメリットは、現時点での企業価値のみならず、将来の業績を考慮して企業価値を算定できる点と、事業計画などをもとにさまざまなシナリオ予測を企業価値に反映できる点にあります。
ただし、不確実性の高い未来を予想しながらの評価となるため、主観的な株価に陥りやすいというデメリットがあります。
有利発行に伴う税務
資金調達目的に行われることが多い有利発行ですが、第三者割当増資において有利発行を行った場合、発行企業には株式の売却額に応じた法人税が課せられます。
有利発行された株式の引受人は、属性や発行企業との関係性によって、異なる税務が発生します。
ここからは、有利発行された株式の引受人が法人と個人のいずれかであった場合を想定し、それぞれで発生する税金について解説していきます。
有利発行を受けたのが法人の場合
有利発行によって株式を取得したのが法人である場合、新株を引き受けたことによる受贈益が法人税の課税対象となります。
受贈益とは、企業が無償または低額で資産を受け取った際に得た利益を指します。有利発行された株式の引受に際しては、新株を引き受けた際の払込金額と新株の引受時の時価の差額部分が受贈益とみなされます。
また有利発行は、既存株式を譲渡するのではなく新株を発行するという行為になるため、受贈益は消費財不課税取引となり課税されません。
受贈益は損益計算書において「特別利益」として資産計上する必要があります。
有利発行を受けたのが個人の場合
有利発行によって株式を取得したのが個人である場合、引受人の区分によって課せられる税金の種類が異なるため注意が必要です。
同族企業の株主である親族が有利発行にて新株を引き受けた場合は贈与税が課税され、新株の発行企業の従業員や役員が新株を引き受けた場合は、給与所得や退職所得とみなされて、所得税が課せられます。
引受人が上記のいずれにも該当しない個人である場合は、一時所得として所得税が課税されます。
まとめ
有利発行は、通常の市場価格よりも安い価格で株式を発行することで、新たな株主を募り資金調達を行う手法です。有利発行は、安易に行うことで既存株主が損失を被る恐れがあることから、法律で定められた手続きやルールを遵守して行う必要があります。また有利発行に際して必要となる税務もケースバイケースで異なるため、事前に関連する法制度をしっかりと理解したうえで行うことが大切です。資金調達を行いたい場合は、M&Aのスキームを利用することでもまとまった資金を得られるため、1つの選択肢としてM&Aを検討してみてはいかがでしょうか。
M&AならレバレジーズM&Aアドバイザリーにご相談を
レバレジーズM&Aアドバイザリー株式会社では、企業経営や会計において高い専門性を誇るコンサルタントが、希望条件でのM&Aをスムーズに実現するために、お客様と二人三脚で各プロセスを進めていきます。
料金体系は完全成功報酬型ですので、M&Aのご成約まで無料でご利用いただけます(譲受会社のみ中間金あり)。無料相談も承っておりますので、M&Aをご検討の際にはぜひお気軽にお問い合わせください。