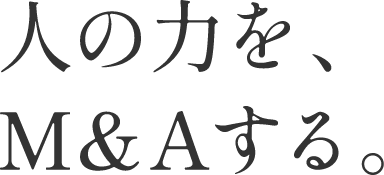このページのまとめ
- 業務提携とは、複数企業の協力により事業や施策の達成を目指すこと
- M&AやJVなどと業務提携の違いは資本関係がないことであり、企業同士は基本的に対等
- 資本関係がないため、速やかかつ少ないリスクで実施できる点が業務提携のメリット
- 一方で対等な関係であるが故に、進め方や提携方法については留意が必要
- 業務提携は技術提携・生産提携・販売提携に大別でき、それぞれでポイントは異なる
ビジネスに関わったことのある人であれば、業務提携という言葉をしばしば耳にすることがあるでしょう。一方で、その言葉の使われ方や意味は曖昧な要素が多く、また単に業務提携といっても、その選択肢はさまざまです。
本稿では、このような悩みをお持ちの方に向けて、業務提携の定義や特徴、また実施する際のポイントなどを、実際の事例も用いながら解説します。
目次
業務提携とは
初めに、業務提携の定義や、類似するさまざまな企業間の連携方法との違いを中心に解説します。
業務提携の概要
業務提携とは、企業が1社単独では実施できないような事業や施策を試みる場合に、他社のリソースやナレッジを借りて企業間の協力により達成を目指すための方法、と定義することができます。
近年のビジネス環境や顧客のニーズはますます複雑・多様化しており、これに1社のみで対応することは困難な場合があります。他社との協業を行うことは戦略上、必要不可欠なアクションであり、業務提携はその選択肢の1つとして存在します。
M&AやJV(ジョイントベンチャー)、資本提携との違い
業務提携が他社との協業における選択肢の1つであるということは、言い換えれば、他社との協業には他の選択肢もあるということです。その最たる例として、M&Aが挙げられるでしょう。
まず、M&A、JV、資本提携それぞれの定義を解説したうえで、業務提携との違いを解説します。
M&Aとは
M&Aとは、企業の合併および買収を指す言葉であり、複数の企業が1つになることや、ある企業が特定の企業を買収する行為を意味します。M&Aでは、買収側の企業が、被買収企業の経営権の過半数を得ることとも言い換えることができます。
JV(ジョイントベンチャー)とは
複数の企業が共同で新たな会社を設立し、その会社に相互に出資を行うことをJV(ジョイントベンチャー)と呼びます。
資本提携とは
資本提携とは、過半数ではなく少額の出資により経営権の一部を得ようとする方法のことです。
M&AやJV、資本提携と業務提携の違い
このようなM&Aや資本業務提携、JVも、企業間の連携、すなわち協業を狙いとして実施されることから、協業関係の選択肢となるわけです。
では、これらと業務提携の違いは何かというと、経営権の取得などのために、企業間に明確な資本関係が存在するかどうかということです。特にM&Aや資本業務提携は、企業間の支配関係が明確となる点が違いとして挙げられます。
これに対して業務提携は、経営権の取得などの資本的なやり取りは発生しません。特定の事業や目的のため、相互に経営資源を出し合って協業することが前提となります。JVはこれに近しい関係ではありますが、業務提携では新会社の設立を行わないのでより簡易的な関係性であると言えます。
また、M&Aや資本業務提携のように支配関係があるわけではなく、業務提携においては基本的に企業同士は対等な関係であるという点も大きな違いです。
業務委託との違い
もう1つの近しい協業の選択肢として、業務委託が挙げられるでしょう。業務委託とは、ある企業から別の企業に対して特定の業務を行うことを依頼し、それを請け負う関係のことを指します。
この業務委託についても企業同士が連携していることには変わりなく、一種の協業関係であると言えます。
業務提携と業務委託の決定的な違いとして、企業間での対価の支払いが発生するかどうかという点が挙げられるでしょう。
業務委託では、ある企業から別の企業へと発注を行い、業務を請け負ってもらう対価を支払う必要があります。
一方、業務提携では多くの場合、企業間で対価の支払いは発生しない、または発生してもそれが主目的でなく、両社の協力により生み出された価値から得られた対価を企業間で分割する形式が基本となります。
このように、企業間の協業の方法としてはさまざまな選択肢が存在します。その中でも業務提携は、企業間での資本関係や支配関係は存在せず、また対価の支払いが主目的として存在しないスキームであると理解しておきましょう。
業務提携のメリットとデメリット
続いて、このような業務提携の特徴を踏まえた上で、他の選択肢と比較した際のメリットやデメリットについて解説します。
業務提携のメリット
業務提携には下記のようなメリットがあります。
他手法より速やかに実現できる
業務提携の特徴として、企業間での資本関係や支配関係のない対等な協業手法であり、かつ相互に金銭など対価のやり取りは主目的として発生しないと解説しました。
このことから、業務提携はM&Aや資本提携などの手法と比較して、速やかに実施可能という点が1つの重要なメリットとなります。また、開始時だけでなく関係を終了する際も、資本関係があるスキームと比べて容易な点が挙げられます。
リスクを最小限に抑えることができる
業務提携は協業が上手くいかなかった場合の関係解消が容易なため、リスクを最小限に抑えることができるという点にもメリットがあります。
業務提携は特定の事業や目的の達成を目指すという焦点を絞った形で実施されることから、前記のメリットが生まれるわけですが、この速やかでスムーズに提携を実施できるという特徴がリスクを最小限に抑えることに寄与します。
具体例
例えばM&Aでは、上手くいかなかった場合に、その経営権の売却先を探したり、従業員や取引先に説明や契約の巻き直しを依頼したりとさまざまなやり取りが発生します。一方で業務提携では、基本的には関係企業との契約を破棄するのみで解消されるため、企業が被るリスクは比較的少なくて済みます。
業務提携のデメリット
業務提携も万能な選択肢というわけではなく、デメリットも存在します。
過度な効果は期待できない
業務提携はライトな協業関係であるが故に、必要以上の効果は期待できないという点が挙げられるでしょう。
業務提携は企業同士が特定の業務やプロジェクトで協力する形を取り、企業の統合や買収までは行なわないのが一般的です。そのため相手企業の経営や意思決定に直接影響を及ぼすことが難しく、両社のコミットメントが不足しがちです。
また、契約内容に基づいて一定の情報は共有されるものの、限定的であり、全ての情報が共有されるわけではありません。これにより、業務の進行において誤解や摩擦が生じる可能性があります。
これが、提携の成功を阻む要因になることがあります。
具体例
例えば、M&Aにおいて想像以上に互いの業務プロセスが類似しているとコスト削減効果が大きく得られたり、期待以上に従業員の文化が近しいと、統合後にモチベーションや生産性が向上したりといった、想定以上のプラスの効果が起こり得ます。
当然、その反対にマイナスの効果が発現する可能性も含んではいますが、このような期待を超える効果は、さまざまな範囲でのリソースの共有などの協業がなされて発現します。
したがって、特定のテーマを定めてそれに必要な範囲での協業を企図する業務提携ではまず起こり得ません。
会社間の調整が難しい
もう1つのデメリットは、両社間での協業がスムーズに進まないケースが多々起こり得るということでしょう。この主たる要因は、業務提携を行う企業同士の関係性が対等であることが挙げられます。
M&Aや資本業務提携のように明確な支配関係がある場合や、業務委託のように購買関係がある場合では、依頼をする側とそれを請け負う側の立場は明瞭です。しかしながら、業務提携では基本的に対等な関係性であるが故に、かえって上手くいかない事象が発生してしまう可能性があります。
例えば、意思決定の方法が挙げられます。ビジネスでは日々意思決定を行いながら施策や各業務を遂行していきますが、対等関係での連携となる場合、スムーズに合意に至らなかったり、予想以上の時間を要したりという問題を招きます。
他にも対価やコスト、リソースの分割をどのように定めるかや、問題発生時の責任の所在をどう明確にするのかといった点も業務提携においてトラブルとなりやすい内容です。
具体例
企業Aが技術力を提供し、もう一方の企業Bが販売力を提供した連携において、製品の故障によるクレームが生じたとしましょう。
この場合、企業Aが責任の大半を負うべきかが論点となり得ます。企業Aとしては、責任を負うのであればその分の対価を大きく得たいと考えるはずですし、一方で企業B側は、対価は公平にすべきだと主張するかもしれません。
ただ、製造と販売でどちらの方がその影響が大きいか、果たしてその関係は対等かと問われると、企業間で主張が異なることは想像に難くないでしょう。
業務提携を実施する上で検討しておくべきポイント
次に、上記のメリット・デメリットも踏まえながら、業務提携を実際に進めるにあたってのポイントを解説していきます。
関係性の中長期的な視点
業務提携の特徴は、スムーズに実行でき、その関係解消も容易である点だと前章で紹介しました。ただし、ビジネス環境において、他社との関係性が一過性で終了することを期待するケースは、そう多くないでしょう。
つまり、比較的速やかに実施できる業務提携であっても、提携企業との将来的な関係性をどのように捉えていくかは、事前に検討すべき重要なポイントとなります。例えば業務提携を、M&AやJVなどを見据えた試験的な関係構築と見なすこともできるでしょう。その場合、特定の業務だけでなく、包括的な企業連携を深めていくことを視野に入れた第一ステップとして扱うことができます。
したがって、足元の業務提携だけでなく、中長期的な視点も踏まえた業務提携と見なすことがポイントと言えるでしょう。この視点の有無によって、業務提携時のコミットメントの強さや、そもそもの業務提携の成否の判断基準など、検討事項の観点が大きく変わります。
具体例
例えばM&Aを見据えた業務提携とするのであれば、業務提携を通して、買収することへのリスクがなさそうか、シナジーは見込めそうかといった視点が重要となってきます。
このケースでは、業務提携の事業や施策そのものの成功は、買収を考えている企業にとってさほど重要でないかもしれません。それよりも、M&A後の懸念点がないかを整理できたか否かの方が、より重要だと位置付けられるでしょう。
このように、業務提携の先をどのように捉えておくかは、提携企業にとって欠かせない重要なポイントとなり得ます。
競争と共創の棲み分け
もう1つの重要なポイントは、提携先が現在または将来の競争相手となり得るかという観点です。
昨今のビジネス環境では、従来の業界の垣根がなくなってきているケースも少なくありません。自動車会社がヘルスケアや金融業界に参入したり、IT企業が小売や保険業界に参入したりするなど、今や業界の定義は非常に曖昧となっています。
それに伴い、競合企業の捉え方も会社によって大きく異なってきたと言えるかもしれません。例えばTV業界の企業が同じTV関連の企業のみを競合と見なす時代ではなくなってきました。視聴者の可処分時間を奪い合うという広い市場の中で、SNSの運営企業や映画などの映像コンテンツ企業、エンタメ産業の企業などを競合と見なすケースも存在しています。
近年では、他業界も含む多くの企業が競合になり得ると言っても過言ではありません。そのため、業務提携においては該当企業が現在もしくは将来の競合になるかという視点が重要です。
もし競合になり得るというのであれば、情報の扱いにはより慎重になるべきですし、お互いに市場のパイを奪い合わないかという点も考慮しなければなりません。
一方で、競合と認識したからといって、必ずしも業務提携を控えるなど、ネガティブな影響ばかりがあるというわけでもないことに留意してください。
競合であることを認識し、互いの競合優位性を損なわない範囲であれば、事業領域が似通っている分、提携による効果は大きくなる可能性を秘めています。むしろ競合と連携することで、自社では実施不可能な規模での施策を実施したり、業界を変えるイノベーションをもたらしたりする可能性も期待できます。
具体例
例えば、飲料メーカーが、ペットボトルの素材を統一することで業界全体でのリサイクルを促進しやすくなるというのは典型的な例の1つでしょう。他にも、自動車業界全体で自動運転の実験を促進することで、高精度な自動運転技術の開発の加速や、製薬メーカーが特定の疫病のワクチン開発に協力するということも例として挙げられます。
すなわち、競合でありながら共創をしていく姿勢が現在のビジネスでは重要な1つの観点になっているということです。そのため業務提携を行う際には、その相手企業が競合となり得るかどうかという視点で検討することは、重要なポイントとなるのです。
業務提携の流れ
続いて、業務提携を行うにあたっての具体的な流れを紹介します。
結論から言えば、業務提携の流れはM&Aなどのプロセスと大きく差異はありません。準備、交渉、クロージング、提携開始という基本的な以下のステップで実行されます。
| 準備 | 業務提携の目的の設定と戦略の策定 |
| 提携先企業の選定 | |
| 交渉 | 秘密保持契約(NDA)の締結 |
| 基本条件の交渉と締結 | |
| 提携企業や事業に関する調査および分析(デューデリジェンスなどを含む) | |
| 最終条件の交渉と締結 | |
| クロージング | 契約・法的関係・株主説明などのクロージング準備 |
| クロージング手続き | |
| 提携開始 | 体制の組成および運用方法の規定 |
| 短期・中長期施策の実行とモニタリング |
各プロセスにおける詳細なポイントや進め方などは、下記関連記事にて詳しく解説しています。M&Aを主眼としてはいますが、気になる方はぜひ合わせてご一読ください。
※関連記事:M&Aのプロセスとは?一連の流れや成功のポイントについても解説
業務提携の種類
続いて、さまざまある業務提携のパターンの中から、典型的な3つの種類を取り上げて解説します。企業の事業を営む基本的なプロセスは、業界を問わず「原料などから何かを生み出し」「それらを製品として加工し」「商品として販売する」という流れを経ます。
業務提携の種類についても大きくこのプロセスに従い、3つに大別することができます。何かを生み出すために必要とされる技術提携、それらを加工する際に必要となる生産提携、加工された商品を売るために必要とされる販売提携です。
多くの業務提携は上記の3つの種類に包含されますが、その他に、モノのやり取りに関わる調達提携や流通提携、特定の範囲を定めずに複数の事業領域で提携する包括提携などが存在します。
以降では、主流となる技術提携、生産提携、販売提携の3つに焦点を当てて、詳細に取り上げます。
技術提携
技術提携とは、他社や自社が保有する技術を用いて、製品の製造や研究開発などをより高度化することを企図した提携の種類です。代表的な技術提携として、次の2つが挙げられます。
- ライセンス契約
- 共同研究開発契約
ライセンス契約
ライセンス契約とは、著作権を有する人物または企業をライセンサーと見なし、その権利を利用者に一定の契約条件でのみ使用を許可するという提携方法です。
映画やアニメ、音楽などのコンテンツ産業がその典型的な例と言えるでしょう。作者やアーティストが持つコンテンツの著作権を、ストリーミングサービス事業者などが使用する際に、ライセンス契約が締結されます。
多くのケースでは、利用者からライセンサーに対してロイヤリティという形で使用料を渡す方法にて契約が履行されます。
共同研究開発契約
共同研究開発契約とは、その名の通り、複数の企業あるいは当該機関がそれぞれの有するノウハウや特許を用いて、特定の技術や製品の研究開発に協力する際に用いられる提携方法です。
例えば、大学の研究機関と政府、一部の企業などが提携し、各分野の先行技術の研究を推進するケースが挙げられます。アメリカのシリコンバレーはその最たる例となるでしょう。シリコンバレーでは、大企業や大学、研究機関の連携が盛んであり、一種のエコシステムを形成することで、各業界のグローバルな市場をリードする働きを見せています。日本でも産官学連携という言葉で類似の取り組みが推進されています。
このような技術提携においては、協力範囲とその目的および成果の定義が非常に重要となります。これは、技術というテーマそのものが非常に曖昧な性質を持っているためと言えるでしょう。何をもって成果と見なすか、どのような力関係で進めるか、リソースの配分はどのようにするかなどの点は、各関係機関の主観的な解釈に依存する部分も多くなるため、慎重な合意形成が必要です。
また、技術に関する部分は各社の競争優位の源泉に直結することから、当然、秘密保持にも慎重に対処すべきです。さらに、当初対象とした技術だけでなく、この提携によって得られた技術やノウハウの財産権などの取り扱いについても整理が必要でしょう。
例えば、共同研究開発によって得られた技術を用いて1つの企業が10年後に爆発的なヒットとなる新製品を出した場合、この利益はどの程度関係者に還元されるべきか、といった論点が生じます。
したがって、得られた成果物の将来的な取り扱いについても、事前の取り決めが不可欠と言えます。
生産提携
生産提携は、製品の生産および加工といったプロセスにおいて企業間で連携を行うスキームであり、こちらも2つの代表的な提携方法が存在します。
- OEM契約(Original Equipment Manufacturing):製造過程における一部をOEMメーカーが扱う
- ODM契約(Original Design Manufacturing):製品の企画や設計などまで担う
生産提携は多くの業界で用いられています。例えば、化粧品や医薬品の製造を専門的な成分の開発を担うOEM/ODMメーカーに委託して、完成品を目指すケースが挙げられます。他にも、自動車やIT機器などの複雑な部品を扱う業界でも生産提携が頻繁に行われています。
これは、冒頭で紹介した業務委託の一種であるという解釈もできるかもしれません。業務提携と業務委託の主たる違いは、対価の支払い有無が主な違いであると解説しました。その定義に則れば、OEM/ODM契約ともに業務委託であるとも言うことが可能です。
業務委託と生産提携の違い
より深く両者の違いを定義づけるとするならば、生産提携においては対価の支払いのみという淡白な関係だけでなく、より包括的な範囲で連携がなされている点がポイントでしょう。
生産提携をする場合、企画段階からの議論やすり合わせ、対応方針の策定、返品対応なども共同で行うことになります。業務委託では、製品を生産し納品することに対して対価が支払われる関係に留まりますが、より深い関係性を構築する点で生産提携は異なります。
そのため、生産提携は業務提携の一種であるとしつつも、単なる顧客と供給者という支払取引関係だけでない連携を目指していると理解しておきましょう。
生産提携のポイント
責任の所在の明確化
生産提携において特に重要なポイントは、責任の所在と言えるかもしれません。例えば製品に重大な欠陥が生じた際に、その原因は必ずしも生産側にあるとは限りません。企画時の設計に問題があった可能性もありますし、検収を怠った可能性もあり得ます。
一概にOEM/ODMメーカーと依頼企業側のどちらが悪いということはいえないことから、責任をどのように分担して負うかを事前に取り決めておくことが、トラブルを回避する重要な策となるでしょう。
生産提携の範囲の明確化
製品の仕様変更などが生じた際にどのように対処するかについても、事前の取り決めが肝要です。
通常、生産提携では特定の製品の生産・加工を対象とするわけですが、仕様変更やリニューアルなどをその対象内とするか対象外と扱うかは、解釈が分かれがちです。どこまでを生産提携の範囲として扱うかについても、事前に合意しておくように留意しましょう。
販売提携
業務提携の代表的な種類として最後に紹介するのは販売提携です。販売提携とはその名の通り、商品の販売において、地域のネットワークや取引チャネル、販売人材などの点で企業間で連携することを指します。
販売提携の3つの形態
販売提携には主に下記の3つの方法があり、それぞれの違いは、商品の権利を有する企業に対してその販売を請け負う企業が有する自由度にあると言えるでしょう。
- 代理店契約
- 販売店契約
- フランチャイズ契約
代理店契約
代理店契約では、販売側企業はあくまで販売チャネル、すなわち仲介会社と位置付けられます。言い換えれば販売側企業の自由度は高くなく、顧客が実際に取引を行うのは商品の権利を有する企業になります。家電量販店や自動車ディーラーなどは代理店契約の代表的な例です。
販売店契約
販売店契約は代理店契約よりも販売側企業の自由度が高く、商品を仕入れて実際に顧客との売買取引までを担います。スーパーやドラッグストアなどを想像していただくと理解が進むかもしれません。
フランチャイズ契約
フランチャイズ契約ではさらに自由度は高くなり、販売側企業が商品を販売する権利そのものを請け負う形式となります。コンビニエンスストアや飲食店でこの形態が広く採用されています。ブランドの名前を借りつつも、各店舗オーナーの意向で店舗のレイアウトや商品ラインナップなどを変更できる裁量を有している点が特徴です。
販売提携におけるポイント
契約形態の戦略的選択
販売提携においてまず重要なのは、前記3つの形態のうちどれを選択すべきかという点に他なりません。
自由度を制限するほど柔軟性や変化に弱くなる一方、自由度が高いと企業の販売戦略を各店舗で一気通貫して実施することが困難になるなど、それぞれメリットとデメリットが存在します。したがって、どのような方法が自社に最適かを戦略的に判断することが重要となります。
適切な販売目標とインセンティブの設定
また、商品の権利を有する企業にとっては、提携する販売側企業に課す目標値の設定、およびインセンティブとペナルティの設定も非常に重要なポイントとして挙げられるでしょう。
目標が達成困難すぎてはモチベーションを下げる要因になりますし、一方で容易な設定であっても、本来ならもっと販売できたはずの商品の売上が限定的となる可能性があります。自社の商品を最大限販売できるような設定が重要です。
業務提携の事例 – Apple
最後に、上記で解説した3種類の業務提携について、Appleを例にそれぞれの違いを解説します。
GEとの技術提携
Appleといえば、iPhoneやMacなどのITデバイスの企画・生産・販売を中心としたグローバルの巨大企業ですが、それでも自社でビジネスの全てを完結することはできず、多くの企業と提携を行っています。
まず技術提携について見ていきましょう。Appleは2017年に同じアメリカの総合電機メーカーであるゼネラル・エレクトリック(GE)と技術提携を行っています。GEは産業機器向けのIoT(Internet of Things)プラットフォームであるPredixという製品を有しており、さまざまな業界の企業とのコネクションを強みとしていました。
そこで両社は互いの強みを生かして、iPhoneやiPadで使用可能なPredixに関するアプリケーションを共同開発しました。Predixソフトウェア開発キットと呼ばれるこのアプリケーションにより、顧客である企業は、iPhoneやiPadからPredixによるデータや分析結果などの閲覧および操作が可能となります。
この結果、AppleはiPhoneなどのデバイスの更なる販売加速だけでなく、各業界の企業のデータを獲得することが可能となりました。AppleとGEは共同のアプリケーション開発を行っているため、技術提携における共同研究開発と理解することができます。
TSMCとの生産提携
続く事例は、2021年に発表された台湾積体電路製造(TSMC)との生産提携です。TSMCは半導体の受託製造において世界でも有数の企業と認識されています。
AppleはAR(拡張現実)デバイスを開発するにあたって、このデバイスの一部である次世代有機EL技術の共同開発と、生産における提携を発表しました。これ以前からも、Appleは半導体部品の生産をTSMCとの提携により実現しており、中長期的な関係性を構築していることが伺えます。
両社の提携においては、各デバイスの企画部分は主にAppleが担っていると推察されることから、ODMではなくOEM契約であると言えるでしょう。
世界的な半導体不足が叫ばれている昨今、業界最大手であるTSMCと中長期的に関係を築けている点は、Appleにとって安定供給を実現するための重要な戦略的アクションであると言えるかもしれません。
大日本スクリーンとの販売提携
最後に販売提携に関する事例として、2000年に発表された大日本スクリーン製造との提携を取り上げます。大日本スクリーンは当時、印刷や広告、デザインなどの分野で業界を牽引しており、日本国内での幅広い販売網を有していました。
一方で2000年当時のAppleはまだグローバルで確立した地位を有しておらず(初代iPhone発売が2007年)、日本国内でのビジネス展開には販売ネットワークが不足していたと言えるでしょう。
したがって、当時のMac製品の展開において、日本国内で有数の企業である大日本スクリーンとの提携は非常に大きな意味を持っていたことが伺えます。
提携方法は代理店方式を採用しており、これは製品の修理やサポートなどはApple自身が担うことが背景にあるのではないかと推察されます。
まとめ
本稿では、昨今のビジネスで頻繁に行われている業務提携について、M&Aなどの類似する協業形態との違いや、メリットとデメリット、提携の種類などをAppleの事例も用いて解説しました。
Appleの事例からも分かる通り、企業間の協業にはさまざまな種類があります。業界や事業特性に合わせた唯一の形態というものは存在せず、企業の戦略に応じて適切な形態を選択することが肝要です。今回ご紹介したポイントなどを参考に、企業価値の最大化に資する最適な業務提携の在り方を検討してみてください。
M&AならレバレジーズM&Aアドバイザリーにご相談を
レバレジーズM&Aアドバイザリー株式会社には、各領域の専門性に長けたコンサルタントが在籍しています。
M&Aだけでなく、業務提携などにも幅広く対応しており、提携のご成約まで一貫したサポートを提供することが可能です。
ぜひレバレジーズM&Aアドバイザリー株式会社のご利用をご検討ください。