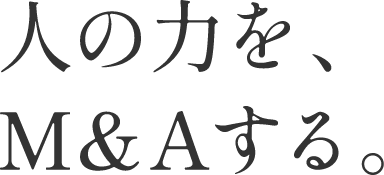このページのまとめ
- DCF法は、企業が将来生み出す利益をもとに企業価値を算出する方法
- DCF法では、将来の利益を現在価値に割り引いて企業価値を求める
- DCF法は、ベンチャー企業や大企業の評価に適している
- DCF法は企業の実態を評価しやすく、将来性を加味できるのがメリット
- DCF法の計算は複雑であるため、用語や計算方法を正しく理解することが必要
DCF法は、事業計画書から企業が将来生み出す利益を予測し、それを現在価値に割り引いて企業価値を算出する方法です。M&Aにおける企業価値評価でよく用いられます。しかし、DCF法の計算方法は複雑であり、どのように計算すればよいかわからない方も多いでしょう。
本記事では、DCF法を用いた計算方法やDCF法のメリット・デメリット、利用時の注意点などを解説します。
目次
DCF法(ディスカウント・キャッシュ・フロー方式)とは
DCF(ディスカウント・キャッシュ・フロー)法とは、その会社が将来どのくらいの利益を生み出すかをもとに企業価値を算出する方法です。事業計画書から将来の利益を見積もり、現在価値に割り引いたうえで企業価値を求めます。
DCF法は、将来的な利益の発生とそれに伴うリスクを加味したうえで企業価値を算出できるのが特徴です。
DCF法のように、将来期待される利益をもとに企業価値を計算する手法を「インカムアプローチ」といいます。
企業価値とは
そもそも企業価値とは、事業以外の非事業資産の価値も含めた企業全体の価値のことであり、その企業にどのくらいの価値があるのかを表すものです。
企業価値を算定することをバリュエーションといい、M&Aでは買収価格を決めるためにバリュエーションを実施する必要があります。算定された企業価値をもとに交渉が進められ、最終的な買収価格が決まるため、バリュエーションはM&Aにおいて非常に重要なプロセスです。
企業価値を算出するほかの手法
企業価値の算出方法には、DCF法以外にも多くの種類があります。
何をもとに企業価値を算出するかによって、大きくインカムアプローチ、コストアプローチ、マーケットアプローチの3つに分けられます。それぞれの内容は以下のとおりです。
| 手法 | 内容 | 具体的な方法 |
| インカムアプローチ | 将来期待される利益を予測して企業価値を算出する方法 | DCF法、配当還元法 |
| コストアプローチ | 企業が有する純資産を根拠に企業価値を算出する方法 | 簿価純資産法、時価純資産法 |
| マーケットアプローチ | 市場価格をもとに企業価値を算出する方法 | 市場株価法、類似会社比較法(マルチプル法) |
さらに、以下のように複数の算出方法があります。
| 手法 | 具体的な方法 | 内容 |
| インカムアプローチ | DCF法 | 将来的な利益とそれに伴うリスクを加味したうえで企業価値を算出する方法 |
| 配当還元法 | 将来どのくらい収益をあげるかを計算し、資本還元率を利用して現在の収益に還元し、企業価値を割り出す方法 | |
| コストアプローチ | 簿価純資産法 | 企業の貸借対照表をもとに純資産額を評価する方法 |
| 時価純資産法 | 全ての資産や負債を時価に換算して純資産を算出し、評価する方法 | |
| マーケットアプローチ | 市場株価法 | 上場会社の平均株価を基準に企業価値を算定する方法 |
| 類似会社比較法(マルチプル法) | 対象企業に類似する上場会社の時価総額や事業価値を参考に企業価値を算定する方法 |
それぞれにメリット・デメリットがあるため、状況に応じて適切な算出方法を選ぶことが大切です。
DCF法を利用できる場面
DCF法は、M&Aで売却価格を算出する際によく利用されます。将来の利益をもとに企業価値を算出するため、「将来性を加味した価額で企業を売却したい」という場合に適した方法です。
DCF法は、M&A以外でも、知人の会社に出資する際や新規事業に投資するか否かを判断する際、不動産価格が適正であるかを判断する際などに用いられます。
関連記事:企業価値とは?計算方法や高めるための4つの方法をわかりやすく解説
DCF法で企業価値を算出する3つのメリット
DCF法で企業価値を算出するメリットは、以下の3つです。
- 企業の実態を把握しやすい
- 将来性を加味した計算ができる
- 債権の評価や投資先の事業性評価の計算にも使える
ここでは、それぞれのメリットをほかの算出方法と比較しながら解説します。
企業の実態を把握しやすい
DCF法のメリットとしてまず挙げられるのが、「企業の実態を把握しやすい」という点です。
DCF法のベースとなる、事業計画に基づくフリーキャッシュフロー(純現金収支)には経営者の意向や思惑が介入する余地がほとんどありません。
事業計画の内容が適切なものであれば、DCF法によって算出される企業価値は透明性が高く、公正性を保った数字であるといえます。
DCF法と同様に企業価値を客観的に評価できるのが、コストアプローチである簿価純資産法です。簿価純資産法は、貸借対照表の数値を用いて計算します。しかし、簿価で評価するため、資産に含み益や含み損が発生している場合は実態に即した評価が難しいのが難点です。
将来性を加味した計算ができる
DCF法では、事業計画が立っている期間と、その後の収益や成長性を考慮したうえで企業価値を算出します。
そのため、企業が現時点で有する純資産に基づく計算方法(コストアプローチ)とは異なり、「今後発生する利益」を加味したうえで、企業価値を算出できます。
債権の評価や投資先の事業性評価の計算にも使える
DCF法は、債権や株式の評価や投資先の事業性評価、不動産価値の算出など、M&A以外の場面においても活用できる手法です。
これは、DCF法が将来的な成長とそれに伴うリスクを加味して対象の価値を算出する、より現実的な方法であるためです。
DCF法で企業価値を算出する3つのデメリット
企業価値を算出するために最も合理的な方法とも呼ばれるDCF法ですが、デメリットがないわけではありません。デメリットには下記の3つが挙げられます。
- 計算が複雑で手間がかかる
- 事業計画書やビジネスプランの影響を大きく受ける
- DCF法を利用するのに適さない場面もある
ここでは、DCF法を用いて企業価値を算出する際の懸念について解説します。
計算が複雑で手間がかかる
DCF法の計算方法は、非常に多くのデータが要求される複雑なものです。特に将来的な利益の発生に伴うリスクを指す「割引率」の計算には手間がかかります。
一方、簿価純資産法は貸借対照表の資産から負債を引いた簿価純資産額をもとにするため、単純な計算で企業価値を求められます。時価純資産法では資産と負債を時価評価する必要がありますが、同様に時価評価した資産から負債を引けばよいため、DCF法に比べると簡便な方法です。
事業計画書やビジネスプランの影響を大きく受ける
DCF法では、事業計画書などをもとに将来性を加味した企業価値の算出を行います。
そのため、「DCF法を用いて企業価値を算出したが、事業計画書通りに事業が進まなかった」といった場合、算定した金額と実際の企業価値に大きな差が生じてしまうこともあるでしょう。
また、事業計画書に示されている数値に関して、将来的な利益の程度が明確でなかったり、恣意性のある数値だったりした場合、的確な企業価値を算出することは困難です。
恣意性を排除したい場合は、簿価純資産法や時価純資産法を利用しましょう。また、上場企業の中に対象企業と類似している企業が存在する場合は、マーケットアプローチである類似企業比較法や類似取引比準法も利用できます。
DCF法を利用するのに適さない場面もある
DCF法は、将来のフリーキャッシュフロー(純現金収支)をもとに計算を行うため、利益を上げられていない場合や、企業を畳むことが決定している場合には適用できません。
利益を上げられていない企業や、清算が決定している企業の価値を算定する場合は、簿価純資産法や時価純資産法のように、貸借対照表のみに注目した計算方法を適用する必要があります。
DCF法の利用が向いているケース
DCF法は、会社の将来性を考慮して企業価値を評価できるため、成長途中のスタートアップやベンチャー企業の企業価値を算出する際に適した方法です。
また、コストアプローチと異なり、無形資産であるのれんも加味して算出します。そのため、ブランド力やノウハウなどの無形資産を有する大企業の評価にも利用されるケースが多いです。
DCF法を理解するために知っておきたい用語
ここでは、DCF法を理解するために知っておきたい3つの用語について解説します。
割引現在価値
割引現在価値とは、将来の価値を現在価値に引き直したものです。将来のある時点での価値(将来価値)から、時間の経過によって変動した分を割り引き、現在のお金の価値(現在価値)を求める必要があります。
価値は時間の経過によって変動します。現在の100万円と将来の100万円の価値は同じではありません。1年間の金利を10%とした場合、1年後の100万円を現在価値に直すと、約90万9,090円となります。
このように、現在価値と将来価値はイコールではないため、将来価値を現在価値に置き換えることが必要です。
残存価値
残存価値とは、将来キャッシュフローを見積もった期間後の企業価値のことです。
DCF法では、会社が永続的に存続し(ゴーイングコンサーン)、キャッシュを生み続けると仮定します。しかし、予測期間より後のフリーキャッシュフローを求めることは難しいです。そこで、予測期間より後のフリーキャッシュフローを単純化して残存価値として求め、企業価値に組み込む必要があります。
残存価値は、事業計画をもとに計算した予測期間最終年度のフリーキャッシュフローを、「割引率-永久成長率」で割ることで求められます。
永久成長率
永久成長率とは、予測期間終了後に企業のフリーキャッシュフローがどのくらい成長するかを表すものです。遠い未来の利益が一定の割合で増え続けると仮定するもので、残存価値をより現実的なものに修正するための考え方といえます。
永久成長率を正確に見積もることは難しく、1%以内で設定されることや、永久成長率0と設定されることもあります。
DCF法の計算方法
DCF法は、以下の5ステップで計算しましょう。
- 予測期間を設定する
- FCF(フリーキャッシュフロー)を算出する
- 割引率を計算する
- TV(ターミナルバリュー)を算出する
- 現在価値のFCFとTVを合算する
ここでは、DCF法の計算方法をステップごとに解説します。
1.予測期間を設定する
まずは、予測期間を設定しましょう。予測期間とは、事業計画書からフリーキャッシュフローを予測できる期間のことです。
予測期間は算定者が自由に設定できます。長期間にしてしまうと正確性に欠ける恐れがあるため、事業計画書でフリーキャッシュフローを予測できる3〜5年程度に設定するケースが多いです。
なお、予測期間以降の将来は予測が難しいため、TV(ターミナルバリュー)として見積もります。TVについては後述します。
2.FCF(フリーキャッシュフロー)を算出する
DCFを用いて企業価値を算出するうえで、ベースとなるのがフリーキャッシュフロー(FCF)です。
この場面におけるフリーキャッシュフローは、「純現金収支」を意味します。
フリーキャッシュフローは、「営業活動によるキャッシュフロー」から投資活動によるキャッシュフローで発生した損失を差し引くことで計算できます。
FCF(フリーキャッシュフロー)=営業活動によるキャッシュフローー投資活動によるキャッシュフロー
DCF法を適用する場合には、事業計画書に記載されている範囲内の、複数の年度のフリーキャッシュフローを計算する必要があります。
3.割引率を計算する
DCF法では、将来的なキャッシュフロー(純現金収支)を「割引率」をもって割り引きます。
この割引率とは、収益の発生に伴うリスクのことと考えてよいでしょう。そのため、リスクが高いと思われる将来的な収益ほど、割引率は高く設定されます。
WACC(加重平均資本コスト)とは
DCF法の割引率として使用されるのは、「WACC(加重平均資本コスト)」です。
WACC(加重平均資本コスト)とは、借入にかかるコストと株式調達にかかるコストを加重平均したものを指します。
■WACC(加重平均資本コスト)の計算方法
WACC = 負債総額/(負債総額+株式の時価総額)×(1-実効税率)×負債コスト + 時価総額/(時価総額+有利子負債)× 株主資本コスト
■株主資本コストの計算方法
株主資本コスト投資の期待収益率)= リスクフリーレート(一般に10年国債の利率) +ベータ値(一般に1)× (マーケットリスクプレミアム -リスクフリーレート)
4.TV(ターミナルバリュー)を算出する
TV(ターミナルバリュー)とは、事業計画の立っていない未来の収益を、企業価値に組み入れるために必要となる要素です。TVは「継続価値」や「残存価値」とも呼ばれます。
TVは、「予測された最終のフリーキャッシュフロー」を割引率(加重平均資本コスト)から割り引く形で算出できます。
■TVの計算方法
TV = 予測された最終のフリーキャッシュフロー ×(1+成長率)/(割引率-成長率)
また、企業の成長見込みによっては1%程度までの「永久成長率」を設定することも可能です。
5.現在価値のFCFとTVを合算する
事業計画が立っている期間のFCF(フリーキャッシュフロー)に割引率を適用することで、企業の現在価値を理解できます。
これにTV(ターミナルバリュー)を加えることで、DCF法による企業価値の算出が完了します。
DCF法を利用する際の注意点
DCF法を利用する際は、以下の点に注意が必要です。
- 結果が必ずしも正しいとは限らない
- 税効果会計を適用する際に注意が必要
ここでは、DCF法の注意点について解説します。
結果が必ずしも正しいとは限らない
DCF法による算定結果が必ずしも正しいとは限りません。DCF法は、数ある企業価値算定方法の中でも比較的結果の信頼性が高い手法です。しかし、計算のために単純化している部分や恣意的な要素もあります。
そのため、DCF法で算出した結果を鵜呑みにしないようにしましょう。あくまでも参考にしながら、売り手と買い手で協議して両者が納得できる価格を目指すことが大切です。
税効果会計を適用する際に注意が必要
DCF法において、含み益のある事業外資産がある状態で税効果会計を適用する際は注意が必要です。
例えば、含み益のある土地を保有する会社を買収するとしましょう。買収後にこの土地を売却する予定の場合、買い手は売却益を得られるため、その分企業価値を上乗せして算定できます。しかし、売却益は課税対象であるため、土地の時価をそのまま企業価値に上乗せすると損失が発生してしまいます。
そのため、事業外資産の時価を企業価値に反映する場合は、含み益に対して発生する税金を同時に減額しなければなりません。
まとめ
DCF法は、企業が将来生み出す利益をもとに企業価値を算出する方法です。事業計画をもとにフリーキャッシュフローを求め、現在価値に割り引いて企業価値を求めます。将来性やのれんも加味して評価できるため、ベンチャー企業や大企業の企業価値評価に適しています。一方、計算方法が複雑である点や、事業計画の内容によっては正確な評価ができない点には注意が必要です。
企業価値の算出方法には、DCF法以外にも複数の種類があります。どの方法を選ぶべきかアドバイスを受けたい場合や、自社の企業価値を評価してもらいたい場合は、M&Aの専門家であるM&A仲介会社に相談するのがおすすめです。
M&AならレバレジーズM&Aアドバイザリーにご相談を
レバレジーズM&Aアドバイザリー株式会社には、信頼できるコンサルタントが多数在籍しています。M&Aの相手探しから企業価値評価、成約まで一貫してサポートするため、はじめてM&Aを行う方でも安心です。料金は成約時に発生する完全成功報酬型であり、M&A成約まで無料で利用できます。(譲受側のみ中間金あり)M&Aをスムーズに進めたい方は、ぜひレバレジーズM&Aアドバイザリー株式会社のご利用をご検討ください。