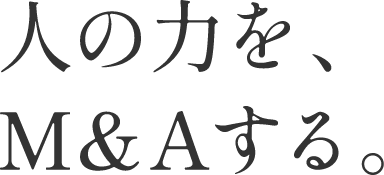このページのまとめ
- 関連会社とは親会社が20%以上50%未満の議決権を保有している会社のこと
- 親会社の議決権保有率が50%以上となると子会社に分類される
- 関係会社は親会社・子会社・関連会社を含む関係のある会社の総称
- 関連会社にはリスク分散や意思決定の自由度が高いなどのメリットがある
- 関連会社は連結決算が必要で持分法が適用される
関連会社とは、親会社が20%以上の議決権を保有している会社を指します。
子会社と混同されるケースが多いですが、両者は議決権の保有率によって区分されます。会社の定義に深くかかわる、議決権についての知識もつけておくことが重要です。
本記事では、関連会社の定義や知っておきたいその他の会社の呼称、関連会社のメリットなどを解説します。
目次
関連会社とは
| 用語 | 定義 |
| 関連会社 | 親会社が20%以上の議決権を保有している会社 |
| 関係会社 | 親会社や子会社、関連会社を含めた関係性のある会社全体 |
| 子会社 | 親会社が50%以上の議決権を保有している会社 |
関連会社とは、親会社における財務や事業運営が影響を与える会社のことを指します。「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第八条において、定義されています。
親会社が経営を支配している状態ではありませんが、一定の議決権を持ち、実質的な経営権を握っていることが特徴です。つまり、完全に独立した意思決定が可能な会社とは異なります。
関連会社と混同されやすいものとして、関係会社と子会社が挙げられます。それぞれの違いを正しく把握しておけば、M&Aの手続きをする際にも役立つでしょう。
関連会社と関係会社の違い
関連会社と名前が似ているため、とくに間違われやすいのが、関係会社です。関係会社は、親会社・子会社・関連会社を含めた総称を意味します。
関連会社と子会社が議決権の保有比率で区分されるのに対して、関係会社は関係性のある会社全体のまとまりを指す点を認識しておきましょう。
関連会社と子会社の違い
関連会社と子会社の違いは以下の表にまとめています。
| 議決権 | |
| 関連会社 | 親会社が議決権の20%以上を保有している |
| 子会社 | 親会社が議決権の50%超を保有している |
子会社だと判断される基本的な基準は、親会社が議決権の50%超を保有していることです。議決権の保有率が50%以下の場合は、その他の要件を満たす必要があります。
- 40%以上50%以下の場合:特定の者の議決権とあわせて50%超または一定の要件
- 40%未満の場合:特定の者の議決権とあわせて50%超かつ一定の要件
「特定の者」とは、親会社と同じ意思で議決権を行使する人たちを意味します。子会社認定には、親会社と特定の者を合算した議決権が条件となっています。
また、状況によっては、次の「一定の要件」を満たすことが子会社と判定される条件です。
- 親会社の意思決定に従う人員が取締役会等の構成員の50%を超えている
- 該当会社の事業の方針の決定などを支配する契約関係を結んでいる
- 他の会社などの資金調達額の総額の過半について融資を実施している
関連会社は、親会社が議決権の20%以上を保有している場合を指すため、子会社ほどではないものの、親会社の影響を強く受ける会社を意味します。
その他さまざまな会社の呼称や定義
関係会社や子会社だけではなく、次の6つの会社の呼称や定義を知っておくことも重要です。
| 用語 | 定義 |
| 完全子会社 | 親会社が100%の議決権を保有している会社 |
| 特定子会社 | 業績面でとくに影響力が強い子会社 |
| 特例子会社 | 障がい者雇用促進の目的で設立される子会社 |
| 連結子会社 | 連結決算の対象となる子会社 |
| 持株会社 | 傘下の子会社株式を保有し支配する会社 |
| グループ会社 | 親会社・子会社・関連会社をまとめた総称 |
それぞれを解説します。
完全子会社
完全子会社とは、子会社のなかでも親会社が保有する議決権が100%であるものを指します。経営面でも、親会社と一体であると捉えられるのが一般的です。
特定子会社
特定子会社とは、親会社の売上高または仕入高の総額が10%以上の子会社を意味します。また、子会社が親会社の純資産額の30%以上を保有している場合や、親会社の資本金の10%に相当するだけの資本金あるいは出資を保有する子会社も含まれます。
特定会社は、主に会計に用いられる用語である点も認識しておきましょう。
特例子会社
障がい者雇用率制度に関連して用いられる用語で、障がい者の雇用を促す目的で設立された子会社を意味します。障がい者の雇用実績が5人以上で、会社全体に占める割合が20%以上など、いくつかの条件を満たす必要があります。
特例子会社として認められると、障がい者が親会社に雇用されたものとして雇用率を算定することができるのがメリットです。
連結子会社
連結子会社とは、親会社の連結財務諸表に連結される子会社のことです。実際には、基本的に子会社は連結決算をおこないます。
子会社のなかでも、親会社の支配が一時的な場合や、影響力などが低い場合は、連結決算の対象外です。それらの子会社は、非連結子会社と呼ばれます。
持株会社
持株会社とは、他の会社を傘下にすることを目的として株式を保有し、支配する会社を意味します。持株会社という呼称のほかに、ホールディングスと呼ばれるものです。
株式保有による子会社の支配のみを行う会社は純粋持株会社、その他の事業も実施している会社は事業持株会社と定義されます。持株会社は、経営効率化を図る手段として、1997年の独占禁止法改正により解禁されました。
グループ会社
グループ会社とは、親会社や子会社、関連会社を含む全体を指す言葉です。先にご紹介した、関係会社と近い概念だといえるでしょう。
そのため、法的にグループ会社と定義されているものはありません。しかし、ビジネスシーンでは頻繁に用いられる用語であるため、意味を知っておくと安心です。
議決権とは
関連会社と子会社は、親会社が議決権を所有する割合によって区別されています。
議決権とは「株主総会での決議に参加して票を投じられる権利」のことを指します。今後の経営方針を決めるにあたって、非常に重要な役割を持っています。
保有株数と議決権の関係
議決権は、株主1人に対して1票ではなく、「保有する株の数」に比例します。つまり、多くの株式を保有しているほど、多くの議決権を得られるということです。会社法上では、50%以上の議決権を持つ会社は、経営を支配することができるため、親会社と定義されています。
一定数以上の株保有量に応じて付与される権利
株は、1単元株につき1つの議決権が発生します。1単元株のうち、1株でも足りなければ、議決権が認められないなどの制限があります。
また、株主は所有する株数に応じて以下の権利を有します。
- 3分の1超:重要事項における特別決議の拒否権
- 2分の1超:取締役の任命権
- 3分の2超:定款の変更権
議決権が20%未満でも関連会社とされる場合もある
前述したように、原則として親会社が「議決権の20%以上50%未満を保有している」会社は、その親会社の「関連会社」とされます。
ただし、一定の条件を満たしている場合には、親会社が保有する議決権が20%未満であっても、関連会社とされる場合があります。その条件について、詳しく解説しましょう。
議決権の保有率が15%以上20%未満
親会社が所有する議決権が「15%以上20%未満」の場合でも、以下のいずれかの条件に当てはまる場合には、関連会社とみなされます。
- 親会社の役員等が、代表取締役または役員に就任している
- 親会社が重要な融資を行っている
- 親会社が重要な技術を提供している
- 財務や事業の方針の決定に関して重要な影響を与えると推測される事実がある
議決権の保有率15%未満
親会社が所有する議決権が15%未満になる場合であっても、上記4つのいずれかの条件に該当しており、なおかつ自己所有等の議決権数が20%以上になる場合には、関連会社とされます。
自己所有等議決権数とは、以下の合計数のことです。
▼自己所有等議決権
- 自己が所有する議決権
- 人事・資金・技術・取引などに密接な関係があり、自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有する議決権
- 自己の意思と同等の内容の議決権を行使することを同意する者が所有する議決権
株の保有者に権利が与えられる2つの理由
株の保有者(株主)は、なぜ株数に応じて権利が付与されるのでしょうか?
その理由として、以下の2つが挙げられます。
1.株は資金調達の手段
会社は、資金調達のために株式を発行して、株主からの出資を募ります。出資を募るためには、株主に対して何らかの利益を付与する必要があります。
株主の議決権は、この出資の見返りとして付与されます。会社の株式を保有すると、業績が向上した場合には株価が上がり、売却によって利益を得ることが可能です。一方で、経営が失敗した場合には、当初出資した株価から下がってしまい、損失が出てしまうリスクがあります。
株主は、このような損失リスクを防ぐために、出資した資金を用いて健全かつ成長に向けた経営を行ってもらう必要があります。議決権を所有することで、経営に関する決議に参加して、投票を行ったり、意見を述べたりできるようになります。
2.株主を増やすための配当金や優待
出資者である株主には、経営に参加するための議決権だけでなく、配当や株主優待などの権利が与えられます。このように株主に対して権利を付与することで、「出資者にはメリットがある」ことを示せるため、より多くの出資者を集められます。
多くの出資者を獲得できれば、その出資金を活用して、事業を拡大させたり、大規模な設備投資を行ったりできるようになります。なお、配当や株主優待についてはすべての会社にあるわけではなく、持ち株数に応じて設定されているケースもあります。
関連会社の5つのメリット
関連会社は、親会社の経営上の決定に対して重大な影響がおよびます。
ここでは、企業が関連会社をつくる、または他社の関連会社になることによるメリットを5つ紹介します。
1.会社をスリム化して身軽にする
株主や取締役が多く存在している企業では、経営の重要な意思決定に時間がかかる場合があります。関連会社を設立することで、組織がスリム化されて、株主総会や取締役会での承認が得やすくなることが期待できます。意思決定が早くなると、ビジネスチャンスに素早く対応できるようになります。
2.新しい事業に挑戦する際のリスクを減らせる
親会社が関連会社を設立することで、財務上のリスクを分散させることが可能です。新しい事業や業界に参入する際に、経営がうまくいかなかった場合にも、親会社を守れるようになります。例えば、多額な投資が必要になる研究開発のような分野にも向いています。
また、大手企業の関連会社となることで、技術やノウハウの面でサポートを受けられたり、信頼性のあるネームバリューを使用できたりするため、安定した経営を行いやすいといったメリットもあります。
3.事業継承がしやすい
親会社で行っていた事業を分割して、特定の事業だけを譲渡した関連会社を設立することで、柔軟に事業継承を行えるようになります。親会社の後継者が多く育った場合には、関連会社に継がせるといった選択肢もあります。
4.親会社から仕事を回せる
親会社で捌ききれない仕事を、関連会社に依頼するといった方法も可能です。関連会社は、親会社から安定した仕事の受注が得られるため、仕事が無くなるリスクを避けられます。また、親会社と関連会社が互いにサポートする体制を築くことで、一社では難しい大きな仕事を、より多く受注できる可能性もあります。このような安定した経営によって、社員にとっても働きやすい環境をつくれます。
5.事業の売却がしやすくなる
親会社の一部の事業を売却する場合、会社分割や事業譲渡などの複雑なM&Aが必要になります。親会社と事業が分離している関連会社をつくることで、株式譲渡といったシンプルな手続きで売却がしやすくなり、売却に伴う手続きの負荷を軽減できます。
関連会社で想定される2つのデメリット
関連会社にはメリットが多く存在することがわかりました。一方で、関連会社にはいくつかのデメリットがあります。
1.関連会社で問題が起きると親会社にも影響がある
もしも関連会社で不祥事が発生した場合に、親会社の信頼やイメージが低下してしまうおそれがあります。親会社で起きた問題と比べると、損害は少なくなる可能性もありますが、まったく影響が無いとは言い切れません。
問題に親会社の指示が関係していた場合や、深刻な問題が起きた場合には、親会社にも相応の責任が追及される可能性もあります。反対に、親会社で不祥事をはじめとする問題が起きた場合には、関連会社全体に悪影響が出る可能性があるため注意が必要です。
2.親会社に依存してしまう
親会社から関連会社に仕事を振るばかりになってしまった場合、「新しい営業先を探す」「効率よく仕事を回す」などの可能性を模索することが少なくなる可能性があります。
このようなことは、関連会社の成長が鈍化することにつながり、その影響は親会社にも及ぶリスクがあります。親会社の経営者が関連会社を設立する際は、「親会社からの仕事に頼りきってしまい、関連会社の顧客が増えない」といったことにならないために経営戦略を立てることが欠かせません。
関連会社の決算の取り扱い
将来的に関連会社をつくることを検討している場合は、決算の取り扱いにまつわる知識が欠かせません。関連会社ならではの決算について解説します。
連結決算で連結財務諸表を作成する
関連会社は、子会社と同様に基本は連結決算として連結財務諸表を作成する必要があります。連結財務諸表とは、関係する企業を含めたグループでの財務状況を明確にするための決算書類です。
特定の子会社の赤字を補填するために子会社間で資金を移動した場合でも、連結決算であれば事実を正しく把握することができます。反対に、連結決算が行われない場合、透明性が損なわれ投資家や債権者に不利益が生じてしまう可能性があるでしょう。
関連会社に適用される持分法とは
とくに関連会社の決算で押さえておきたいポイントとして、持分法が挙げられます。持分法とは、関連会社の資本と損益のうち、親会社に帰属する部分のみを連結決算に計上する仕組みです。
持分法は、全部連結決算と比べて、会計処理がしやすいというメリットをもちます。具体的には、持分法による投資損益と投資有価証券という勘定科目が用いられます。
持分法が適用されるのは、関連会社のほかに非連結子会社が該当します。
関連会社の適切な運営にはM&Aの知識が必要
関連会社は、親会社が経営に影響を与える会社となるため、リスクを踏まえたうえでM&Aを検討する必要があります。ここからは、関連会社におけるM&Aについて解説します。
M&Aとは
M&Aとは、「Mergers(合併)and Acquisitions(買収)」のことを指します。会社分割や事業譲渡、株式移転、吸収合併・分割などもM&Aに含まれます。
売り手企業は、主に事業継承や不採算事業の切り離しなどを目的にM&Aを実施します。買い手企業は、事業の拡大や多角化、新事業への参入、シナジー効果の創出などを目的として実施することが一般的です。
M&Aのメリット
M&Aでは、売り手企業・買い手企業の立場によって、期待できるメリットが異なります。ここからは、それぞれの立場から見たメリットについて解説します。
売り手企業の2つのメリット
売り手企業がM&Aを実施するメリットには、以下が挙げられます。
1.事業を継続することができる
M&Aによって事業の継続が可能となります。廃業を防ぐことができれば、今まで会社を支えてくれた社員を解雇しなくて済みます。また、大きな資本を持つ親会社のサポートを受けて経営を続けることができれば、業績を改善できる可能性もあります。
2.後継者問題を解決できる
後継者問題を解決できることも、M&Aのメリットの一つです。後継者問題が解決しない場合、廃業を余儀なくされてしまう可能性があります。M&Aによって事業を継承することで、廃業を避けられるほか、創業者利益を得られるようになります。
買い手企業の2つのメリット
買い手企業が得られるメリットは主に以下の2つです。
1.新しい事業と顧客による利益向上
事業の一部を譲り受けることで、新しい事業への参入や多角化が可能となります。
新しい事業に参入するにあたって、一から事業を立ち上げる場合、技術やノウハウ、人材などを確保しなければなりません。M&Aを実施すれば、売り手企業が持つ技術やノウハウ、人材などを受け継ぐことができ、コストを削減できるほか、事業開始までのスピードを早められます。
2.優秀な人材や技術の獲得
近年では、優秀な人材や技術を確保することを目的にM&Aを行う会社も多く見られます。自社にはない人材や技術を取得することで、シナジー効果が生まれて、既存事業での業績向上につなげられることが期待できます。
M&Aの2つの注意点
M&Aにはメリットがありますが、これまでと組織体制が変化するほか、経営への関与がなされるケースもあるため、いくつか注意しておきたい点があります。
ここでは、M&Aの注意点について解説します。
1.労働環境の変化
「親会社」と「関連会社や子会社」は、単なる取引先よりも根深い関係になっていきます。
その関係性が、人事や業務などに影響して、従業員の労働環境が変化してしまう可能性があります。それが原因で、従業員から不平不満が発生すると、離職につながるおそれもあります。
また、関連会社や子会社では、親会社での経営上の意思決定の影響を受けるため、内容によっては親会社との対立が起きてしまうケースも考えられます。そのほかにも、関連会社や子会社同士が円滑な協力体制を築けずに、トラブルが起きてしまうこともあります。
2.隠されていた問題による悪影響
M&Aの契約を交わした後に、売り手企業と買い手企業との間で、想定しない問題が発生する可能性があります。例えば、役員や社員による不祥事や、財務上のコンプライアンス違反などが挙げられます。このような問題によって、大きな損失が発生する可能性があるため、契約を交わす前には十分な情報収集はもちろん、リスクを想定した契約書を作成しておくことが重要です。
まとめ
関連会社とは、親会社が20%以上50%未満の議決権を有している会社を意味します。親会社の議決権保有率が50%以上の子会社と比べると、意思決定を自由におこなえるのが特徴です。
ご紹介したように、関連会社と子会社の他にも、さまざまな会社の呼称があります。それぞれの定義を確認しておくことで、混同することなくスムーズに理解ができるでしょう。
関連会社をつくることを検討している場合は、議決権についての知識が欠かせません。親会社の議決権保有率によって、会社の名称や決算上での取り扱いが異なるからです。
関連会社には、新しい分野へ挑戦するハードルを下げられたり、事業継承がしやすかったりというメリットがあります。関連会社買収後の運用面の注意も把握したうえで、自社の将来を検討するようにしましょう。
M&AならレバレジーズM&Aアドバイザリーにご相談を
レバレジーズM&Aアドバイザリー株式会社では、M&Aの取引を一貫してサポートいたします。他社を買収し、関連会社や子会社を設立したいとお考えの場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。