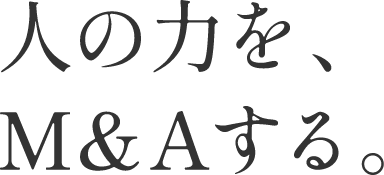このページのまとめ
- 事業譲渡は譲渡会社が行う事業とそれに関連する資産や権利義務などを選別して売買する
- 事業譲渡の手続きを進める過程では、会社法の規定に沿わなければならない
- 会社法とは、会社の設立や経営、組織、解散などの手続きを定めたもの
- 会社法では、競業避止義務や反対株主の株式買取請求、特別決議などが定められている
- 会社法では、特別決議が不要なケースとして簡易事業譲渡、略式事業譲渡が定められている
譲渡を行う場合に会社法はどのような関係があるのだろうか?」とお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。会社法は事業譲渡のプロセスに関わっており、定められたルールを遵守して手続きを進める必要があります。具体的には、株主への通知・公告や特別決議による承認、反対株主の株式買取請求などの手続きが関わってきます。本記事では、事業譲渡と会社法について詳しく解説します。
目次
事業譲渡と会社法
会社法は、その名のとおり、会社に関する全ての規定が集約されている法律のことです。その中には、事業譲渡などのM&Aを行うにあたって実施するべき手続き内容なども細かく定められています。
ここでは、事業譲渡の概要と類似する言葉や類似するM&Aスキームとの違い、会社法の概要などを解説します。
事業譲渡とは
事業譲渡とは、譲渡会社側が行う事業の運営権と、それに関連する資産や権利義務などを売買するM&Aスキームです。
事業譲渡の主な特徴は以下のとおりです。
- 事業譲渡は個別承継
- 売りたいもの・買いたいものを選別できる
- 他のM&Aスキームに比べて手続きが煩雑
M&Aスキームの中で個別承継のスキームは事業譲渡だけです。個別承継の特徴は、譲渡対象を選別できることにあり、これにより譲受会社は不要な資産・負債を引き継がずに済みます。
その反面、取引先との契約、従業員との雇用契約、債務の移転などは個別交渉を行って、新たに契約締結をしたり同意を得たりする必要があります。
事業譲渡については、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:レバレジーズ「M&Aにおける事業譲渡とは?メリット・デメリット、手続き・ポイントなどを解説」
会社法とは
会社法とは、会社の設立・経営・組織・運営・意思決定・管理・解散・清算などを行うにあたって、遵守しなければならない手続き面などを細かく取り決めた法律です。
施行後も幾度となく見直しが図られ、その都度、改正がなされてきています。会社法には、株主総会の決議事項や議決権といった株式会社の基本的な項目に加え、事業譲渡や合併などのM&A手法に関する手続きも規定されています。
会社法については、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:レバレジーズ「商法と会社法の違いを解説!改正後の内容やM&Aに関する法律も紹介します」
事業譲渡のメリットとデメリット
この章では、各種法律の規定から見える事業譲渡のメリットとデメリットを売り手・買い手それぞれの視点から解説します。
事業譲渡のメリット
まずは事業譲渡メリットについて解説します。
売り手のメリット
売り手側のメリットは以下の点です。
- 不採算事業を売却できる
- 事業の選択と集中を実現できる
- 債権者保護手続きが不要
譲渡する範囲を自由に選択できるため、不採算事業を売却して主力事業に集中することで選択と集中を果たせます。また、会社法に定めがないため、会社分割などの手法と異なり、債権者保護手続きを行う必要もありません。
買い手のメリット
買い手側のメリットは以下の点です。
- 事業を短期間で展開できる
- 買収する事業を選択できる
- 不要な資産や債務を引き継がずに済む
事業をゼロから展開するには多くの時間とコストがかかります。ある程度の規模に育っている事業を選択して買収することで人材や技術、設備、販路などをまとめて獲得できるため、事業を短期間で軌道に乗せることが可能です。
また、大きな損失をもたらす可能性のある簿外債務や偶発債務を引き継がずにM&Aを行えることも、リスクを軽減できる点でメリットです。
事業譲渡のデメリット
次に事業譲渡のデメリットについて解説します。
売り手のデメリット
売り手側のデメリットは以下の点です。
- 特別決議や株式買取請求などの手続きが複雑である
- 競業避止義務によって事業運営に制限が生じ得る
- 債務や資産の移転に個別の同意が必要
特に注意すべきは、手続きの複雑さと競業避止義務です。
会社法には、事業譲渡の際に原則として特別決議や株式買取請求といった手続きを行うことが規定されています。そのため、簡便な手続きで行える株式譲渡と比較すると手続きが複雑になります。また、競業避止義務によって事業運営に制限が生じ、会社としての売上や利益が減少する、成長性が低下するなどのリスクがあります。
買い手のデメリット
買い手側のデメリットは以下の点です。
- 取引先や従業員との契約は交渉の上で引き継ぐ必要がある
- 許認可は原則引き継げない
特筆すべきデメリットは1つ目です。会社分割と異なり、事業譲渡は前述のとおり個別承継となります。取引先や従業員を自動的に引き継ぐことはできないため、個別に条件等を交渉した上で再契約が必要です。
場合によっては、取引先から取引を打ち切られたりキーパーソンが移籍を拒否したりすることで、買収後の事業運営に支障が生じるおそれがあります。
事業譲渡で会社法に基づく特別決議が必要となるケース
事業譲渡では、条件に合致した場合、株主総会における特別決議が欠かせません。特別決議を簡潔に解説した上で、どのような事業譲渡(類似する取引を含む)で特別決議の承認が必要となるか、具体的なケースを解説します。
特別決議とは(会社法第309条第2項)
特別決議とは、原則として議決権を有する株主の過半数が出席し、出席者における議決権のうち3分の2以上の賛成が必要となる決議です。
売り手側で特別決議が必要となるケース
売り手側では、以下のケースで特別決議による承認が必要です。
- 事業の全部譲渡(会社法第467条第1項第1号)
- 事業の重要な一部の譲渡(会社法第467条第1項第2号)
- 子会社株式または持分の全部もしくは一部の譲渡(会社法第467条第1項第2号の2)
- 事業の全部賃貸、事業全部の経営委任(会社法第467条第1項第4号)
以下でそれぞれ解説します。
事業の全部譲渡
売り手側が展開する全ての事業を売却するケースでは、特別決議が必要となします。
事業の重要な一部の譲渡
一般的には、以下に挙げた量的基準および質的基準の両方を満たす場合に、重要な一部の譲渡であると判断されます。
- 量的基準:譲渡資産の簿価が譲渡会社の総資産額の20%(5分の1)超である
- 質的基準:その企業にとって重要性の高い事業の一部である
たとえば量的基準を満たしていても単純な資産の譲渡に過ぎない場合には、事業の重要な一部の譲渡に該当せず、特別決議による承認は不要と考えられます。ただし、質的基準は明確なものではないため、判断の正確性を高めたい場合には専門家である弁護士に相談することがおすすめです。
なお量的基準の20%は、定款によってより低い数値に設定することも可能です。
子会社株式または持分の全部もしくは一部の譲渡
下記いずれにも該当する場合には、特別決議による承認が必要です。
- 譲渡する子会社株式・持分の帳簿価額が、譲渡企業の総資産の20%(5分の1)超である
- 効力発生日において子会社における議決権総数のうち過半数を有さなくなる
つまり、一定割合以上の子会社株式を売却した結果、親会社(譲渡会社)の影響力がなくなった場合には、当該株式譲渡は実質的に「親会社による事業譲渡のようなもの」とみなされ、特別決議が求められます。
事業の全部賃貸、事業全部の経営委任(会社法第467条第1項第4号)
事業の全てを貸し出したり、他社に運営を委任したりする場合、当該事業の所有権は売り手企業に残ります。しかし、会社法上は実質的に事業譲渡のような行為であるとみなされ、特別決議による承認が必要です。
買い手側で特別決議が必要となるケース
買い手側では、以下のケースで特別決議による承認が必要です。
- 事業の全部譲受け(会社法第467条第1項第3号、第2項)
- 事後設立による譲受け(会社法第467条第1項第5号)
以下でそれぞれ解説します。
事業の全部譲受け
売り手側が有する全ての事業を買収するケースです。譲り受ける資産に株式が含まれている場合、取締役は株主総会で対象株式に関する事項を説明する義務を負います。
事後設立による譲受け
事後設立による譲受けとは、あらかじめ事業譲渡の約束をした上で会社を設立し、設立後2年以内に実行する事業譲渡のことです。
対価が買い手企業における純資産額の20%超を超える場合に、特別決議による承認が必要となります。この場合、定款で20%よりも低い数値に設定しておくこともできます。
特別決議が不要な事業譲渡
会社法第468条「事業譲渡等の承認を要しない場合」では、株主総会の特別決議を省略できる事業譲渡の条件も定めています。具体的には、以下の名称で呼ばれる2種類の事業譲渡です。
- 簡易事業譲渡
- 略式事業譲渡
特別決議を省略できる場合は、取締役会の決議で事業譲渡を進められます。それぞれの事業譲渡の具体的な内容をみてみましょう。
簡易事業譲渡
簡易事業譲渡とは、譲受会社が譲渡会社に支払う対価が、譲受会社の総資産額の20%(5分の1)を超えない事業譲渡です。譲渡会社の全事業または重要な事業を譲受した場合であっても、対価の比率がこの条件に当てはまれば株主総会の特別決議を省略できます。また、対価の比率は、定款で20%よりも低く設定することが可能です。
略式事業譲渡
略式事業譲渡とは、譲受会社が譲渡会社の特別支配会社である場合に行われる事業譲渡です。特別支配会社とは、単独あるいは企業グループの合計で譲渡会社の株式90%以上を保有している状態をいいます。定款で定めれば、株式保有比率について90%を上回る数値に変更することも可能です。
会社法が関わるその他の事業譲渡の手続き
ここでは、会社法で規定している事業譲渡の義務や手続きを説明します。具体的には以下の2点です。
- 競業避止義務(会社法第21条)
- 反対株主による株式買取請求(会社法第469条)
それぞれの内容を確認しましょう。
競業避止義務
会社法第21条「譲渡会社の競業の禁止」では、事業譲渡の譲渡会社に対し規定をしています。これは通称、競業避止義務と呼ばれているものです。競業避止義務とは、事業譲渡の譲渡会社は、譲渡した事業と同一の事業を、譲受会社所在地と同一の市区町村および隣接する市区町村で、20年間行えないという規定です。
事業譲渡の譲受会社が不利を被らないための条文といえます。条文では、譲渡会社側が特約すれば期間を30年間まで延長可能としていますが、事業譲渡の交渉の際に譲受会社が承諾すれば、期間の短縮や義務の免除も可能です。その場合は、事業譲渡契約書に条項として記載する必要があります。
ただし、現在はインターネットを介してビジネスが行われる状況となっており、同一および隣接した市区町村に限定した規定の有効性について、疑問視する声も出ているのが現実です。
反対株主による株式買取請求
会社法第469条「反対株主の株式買取請求」では、事業譲渡に反対する株主の立場を守るため、株主が所有する株式を公正な価格で買取請求できることを定めています。ただし、株式買取請求できる事業譲渡には制限があり、対象となるのは株主総会の特別決議を必要とする事業譲渡です。特別決議が必要となる事業譲渡の詳細は次項で説明します。
事業譲渡をする会社側は、事業譲渡の効力発生日の20日前以前に、各株主に対し事業譲渡の実施と、事業譲渡に反対する場合に株式買取請求ができることを通知しなければなりません。
事業譲渡に反対する株主側は、株主総会に先立って事業譲渡への反対を会社に表明します。その後、事業譲渡の効力発生日20日前から前日までが株式買取請求可能期間です。
株主と会社は協議して株式の買取価格を決めます。会社は事業譲渡の効力発生後60日以内に代金を支払うことになっていますが、協議が不成立だった場合は、裁判所に価格決定の申し立てを行うことができます。なお、株主総会での議決権を持たない株主でも株式買取請求が可能です。
会社法に則った事業譲渡の手順
ここでは、会社法の規定に則って実施する必要がある主な事業譲渡の手続きを紹介します。
- 取締役会での決議
- 事業譲渡契約の締結
- 株主への通知・公告
- 株主総会の開催・特別決議
- 株式買取請求手続き
- 事業譲渡の効力発生
取締役会から株主総会開催までの手順にしぼって説明します。
1.取締役会での決議
事業譲渡の手続きを進めるにあたっては、まず、取締役会設置会社であれば取締役会を開き、事業譲渡の実施を決議します。取締役会非設置会社であれば、過半数の取締役が事業譲渡に賛成することが必要です。事業譲渡実施の決議をする際は、同時に臨時株主総会招集の決定も行います。
取締役会決議または取締役の賛成決定の際には、取締役会議事録または賛成決定を示す書面の保存が必要です。これらのことは、会社法第348条「業務の執行」、第298条「株主総会の招集の決定」、第362条「取締役会の権限等」、第369条「取締役会の決議」、第371条「議事録等」などで定められています。
2.事業譲渡契約の締結
取締役会決議を経て、事業譲渡契約の締結が可能となります。つまり、取締役会決議の段階では、大方の事業譲渡交渉は合意が形成され、デューデリジェンス(譲受会社による譲渡会社への精微な監査)が終わっているようなタイミングとなるでしょう。
事業譲渡の交渉の内容やデューデリジェンスの実施などについて、会社法では特に何も規定していません。事業譲渡契約書も、その内容に関して会社法での定めはありません。しかし、基本的に記載すべき条項のひな形は整っています。事業譲渡契約書の重要な条項については、次章で説明します。
3.株主への通知・公告
株主への通知・公告は以下の2つがあります。
- 臨時株主総会の招集通知
- 反対株主の株式買取請求通知
株主総会の招集は会社法第296条「株主総会の招集」で定められています。また、会社法第298条「株主総会の招集の決定」と第299条「株主総会の招集の通知」によって定められている通知の期限は以下のとおりです。
- 上場会社:株主総会開催日の2週間前までに書面で送付
- 非上場会社:株主総会開催日の1週間前までに書面で送付
非上場会社でも、書面または電磁的方法で議決権が行使できる場合は株主総会開催日の2週間前までの送付が期限です。
反対株主の株式買取請求通知は、会社法第469条「反対株主の株式買取請求」に定められています。事業譲渡の効力発生日の20日前までに、株主に対し事業譲渡の実施と、事業譲渡に反対する場合に株式買取請求ができることを通知しなければなりません(会社法第469条第3項)。
なお、会社法第469条第3項に定められた通知は、以下いずれかの条件を満たす場合において公告として行うことが認められています(会社法第469条第4項)。
- 事業譲渡を行う株式会社が公開会社である
- 株主総会の特別決議によって事業譲渡契約の承認を受けている
上記より、大半のケースにおいて公告を選択できると言えます。
4.株主総会の開催・特別決議
事業譲渡に関する株主総会の特別決議については、会社法第309条「株主総会の決議」と会社法第467条「事業譲渡等の承認等」で規定されています。特別決議は、以下の2つの要件を満たさないと議決できません。
- 定足数:議決権を行使できる株主が過半数、出席している
- 議決要件:出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成
事業譲渡で株主総会の特別決議が必要となるケースなど詳しい内容については、上述の「会社法が関わる事業譲渡の手続き」をご参照ください。
5.株式買取請求手続き
前述のとおり、事業譲渡に反対する株主に対しては、株式買取請求に応じる必要があります。
株式買取請求の権利を行使するには、以下いずれかの要件を満たす必要があります(会社法第469条第2項第1号)。
- あらかじめ事業譲渡に反対する旨を表明し、かつ株主総会で実際に反対した株主である
- 株主総会で議決権を行使できない株主である
権利を行使する反対株主は、効力発生日の20日前から効力発生日の前日までに、買取してほしい株式数(種類株式発行会社の場合は株式の種類および種類ごとの数)を明らかにする必要があります(会社法第469条第5項)。
なお、株式買取請求をした株主が株式会社の承諾を得た場合には、株式買取請求は撤回できます(会社法第469条第7項)。また、事業譲渡が中止された場合には、株式買取請求の効力が失われます(会社法第469条第8項)。
株式の買取価格をめぐって協議が調った場合には、前述のとおり会社側が事業譲渡の効力発生後60日以内に代金を支払う流れとなります。
6.事業譲渡の効力発生
会社法による明確な効力発生日の規定はありません。事業譲渡の効力は、事業譲渡契約書の記載内容(効力発生日)に従います。
一般的には、各種資産や契約、許認可等の移転手続きを終えるタイミングを逆算し、事業譲渡の効力発生日を設定します。
以上の手続きを全て終えることで、会社法に規定された事業譲渡のプロセスは完了となります。
事業譲渡契約書作成のポイント
事業譲渡契約書について会社法では規定がありません。しかし、契約内容がきちんと履行され、また後日のトラブルを防ぐためにも、法的に問題がない事業譲渡契約書を作成・チェックする必要があります。
ここでは、事業譲渡契約書でポイントとなる以下の条項を解説します。
- 事業譲渡の合意表明
- 事業譲渡の効力発生日
- 譲渡資産
- 譲渡対価
- 従業員について
- 表明保証
- 遵守事項
それぞれの内容について解説します。
1.事業譲渡の合意表明
事業譲渡契約書では、冒頭で「事業譲渡の合意表明」を記載するケースがほとんどです。契約書によっては単に「目的」などの条項名の場合もあります。条文例としては以下のようなものです。
甲と乙は、甲の行う〇〇〇〇〇事業を、乙に譲渡することで合意した。
ここでのポイントは、具体的な事業名まで特定することです。なお、上記の条文例には日にちなどが加わるケースもあります。
2.事業譲渡の効力発生日
事業譲渡の効力発生日は、株主総会の開催や反対株主の株式買取請求通知および対応などのスケジューリングの基になるものです。日程をよく勘案しながら逆算して、適切な日にちを定める必要があります。
また、状況によっては、譲渡会社・譲受会社の協議によって、事業譲渡の効力発生日を変更できることも書き加えておくといいでしょう。
3.譲渡資産
事業譲渡は会社分割のような包括承継ではないため、譲渡対象の資産・負債を契約書で特定することが必要です。理論上は、「〇〇〇〇〇事業に関する全ての資産・負債」などと表現すれば、簡単に済んで手間がかかりません。
しかし、その場合、本来は避けられるはずの偶発債務などの簿外債務が含まれてしまう可能性があります。そこで、事業譲渡契約書では、譲渡対象の資産・負債は契約書の別紙として目録化させて添付するのが一般的です。目録には、具体的な資産・負債の名称を1つずつ記載します。
細かく記載することになるので、抜けがないようにチェックすることも肝要です。
4.譲渡対価
事業譲渡の対価の記載も重要な条項です。ここでは、金額とともに支払い方法も記載します。支払い方法が金融機関への振り込みの場合には、譲渡会社が指定する金融機関と口座番号なども記載してください。
対価を支払う側の譲受会社の注意点としては、譲渡対象に消費税課税資産が含まれていると消費税が発生することです。以下の資産が消費税課税資産になります。土地と有価証券には消費税は課税されません。
- 土地以外の有形固定資産(船舶、自動車、機械、建物、設備、備品など)
- 無形固定資産(のれん、特許権、商標権、意匠権、ソフトウェア、その他の知的財産権など)
- 棚卸資産(在庫、部品、仕掛品など)
譲受会社は事業譲渡の対価支払いと同時に消費税分も譲渡会社に渡します。小売店の店頭で商品を買うのと同じです。
5.従業員について
事業譲渡では、雇用契約は譲受会社に承継されません。そのため、譲渡対象事業に従事している従業員を特定するため、転籍予定者として事業譲渡契約書にリストをつけることが多いです。付随して事業譲渡契約書に記載する内容としては、以下のような例があります。
- 譲渡会社は期日までに従業員から転籍の同意を得る
- 事業譲渡の効力発生日に譲渡会社側では該当従業員を解雇し、譲受会社側では雇用契約を締結する旨
その他、譲渡会社と譲受会社が転籍者に関して協議して決めるべきことは以下の点です。
- 勤続年数を譲受会社が引き継ぐかどうか
- 未消化の有給休暇を譲受会社が引き継ぐかどうか
- 退職金規程を引き継ぐかどうか
- 未払い残業代がないかどうか
また、譲渡される事業のキーマンとなるような幹部社員がいる場合、その従業員の転籍が事業譲渡の前提条件として事業譲渡契約書に記載される場合もあります。
6.表明保証
表明保証とは、事業譲渡契約書に記載されていることや、事業譲渡契約締結に至る交渉で提示された会社の情報などが真実かつ間違っておらず、また、不都合なことなどを隠していないことを表明し保証するものです。表明保証する内容の一例としては、以下のようなものがあります。
- 反社会的勢力ではない、また、関わりもない
- 司法や行政に対する違反行為をしていない
- 譲渡会社は資産や債務の状況などに虚偽はない
- 譲受会社は債務超過や未払いなど倒産のリスクはない
表明保証に違反があった場合は、損害賠償請求の対象になることを併せて記載したり、表明保証に違反しないことが事業譲渡実施前の前提条件として設定されたりすることが多いでしょう。
7.遵守事項
遵守事項は、事業譲渡契約の実現に向けて、および実現後も主に譲渡会社側に守ってもらう行動を記載するものです。事業譲渡実施前の遵守事項で必ず記載されるものとして以下のようなものがあります。
- 譲渡される事業の価値が下がってしまうような事業活動は行わない
- 譲渡される予定の資産などの売却をしない
- 転籍予定者の雇用維持
また、事業譲渡実施後の記載事項として記載されることが多いのは、競業避止義務です。会社法第21条で定められているので、あえて記載する必要はないともいえるのですが、遵守させるためにあえて記載されます。
事業譲渡で競業避止義務が問題となった事例
会社法に規定された競業避止義務をめぐって、裁判に発展した事業譲渡の事例を2件紹介します。
洗剤販売事業の譲渡
洗剤販売事業の譲渡で裁判となった事例を紹介します。
| 問題となった事業の概要 | 洗剤等の販売事業 |
| 裁判の争点 | ・事業譲渡後に、売り手側が同種事業の運営を開始したこと・譲渡した事業で扱っていた商品と同じ名称を付けたこと |
| 裁判の結果 | 競業避止義務違反が認定され、事業の差し止めと損害賠償の支払いが命じられた |
被告となった売り手企業は、事業譲渡によって洗剤等の販売事業を売却しました。その6年後、同社は新しく開発した洗剤等商品を販売する事業において、譲渡した事業で扱っていた商品と同じ名称を付けました。裁判では、この行為が競業避止義務違反かどうかが争点となりました。
地方裁判所で行われた裁判の結果、不正競争を目的とした競業であることが認められました。裁判所は、被告に対して同種商品名の使用・販売の停止および損害賠償の支払いを命じました。
裁判の資料では、判決の根拠として下記が示されています。
- 新たに事業を始める際に、譲渡した事業の商品名と同じ商品名を用いたこと
- 買い手企業から顧客を奪った事実がある
商品名を同じものとした上に、買い手企業に移転した顧客との取引を再開したことなどが、悪質性の高い競業であると認められる根拠となりました。
参照元:裁判所「平成27年(ワ)第7051号 不正競争行為差止等請求事件」
ECサイトの譲渡
ECサイトの譲渡で裁判となった事例を紹介します。
| 問題となった事業の概要 | 婦人用中古衣類のECサイトに関する事業 |
| 裁判の争点 | ・事業譲渡後に、売り手側が同種事業の運営を開始したこと・譲渡したサイトと同じジャンルのECサイトの運営を開始したこと |
| 裁判の結果 | 競業避止義務違反が認定され、事業の差し止めと損害賠償の支払いが命じられた |
被告となった売り手企業は、事業譲渡によって婦人用中古衣類のECサイトを売却しました。その後、新しく同ジャンルのECサイトを運営し始めました。
原告である買い手企業は、売り手企業が譲渡した事業と同じサイト運営を開始したことで自社に損害を与えたと訴え、競業避止義務違反およびそれに対する事業差し止めや損害賠償を請求しました。
裁判は高等裁判所まで進み、結果的には競業避止義務違反が認められました。それに伴い、裁判所は被告に対して事業の差し止めと損害賠償の支払いを命じました。
地方裁判所の資料では、判決の根拠として下記が示されています。
- 在庫やマニュアル等も譲渡対象に含まれていたため、財産譲渡ではなく「事業譲渡」とみなせる
- 売り手企業が新たに始めた事業の取引実態を見ると、同種事業を始めたと認定される
- 原告から顧客を奪おうとした事実があり、不正競争目的で同じ事業を始めたとみなせる
事業の実態から不正競争目的の競業が認められたことで、全面的に原告の訴えが認められたといえます。
参照元:裁判所「平成27年(ワ)第2617号 競業行為差止等請求事件」「平成28年(ネ)第10114号 競業行為差止等請求控訴事件」
まとめ
事業譲渡とは、会社が運営している事業の全部または一部を他社に譲渡することです。一方で会社法とは、法務省が定めた会社にまつわる法律です。会社の設立や組織、運営、管理、精算などのルールが定められています。
事業譲渡を実施するためには、会社法で定められたことを遵守して手続きを進める必要があります。具体的には、株主への通知・公告や反対株主の株式買取請求への対応を行います。条件に合致する場合には、株主総会で特別決議を行わなくてはいけません。
事業譲渡には会社法の専門知識が求められるため、事業譲渡をはじめとするM&Aに詳しい仲介会社や、会社法などの法律に詳しい弁護士などの専門家を頼ることも有効でしょう。
M&AならレバレジーズM&Aアドバイザリーにご相談を
レバレジーズM&Aアドバイザリー株式会社には、各領域の専門性に長けたコンサルタントが在籍しています。
フリーキャッシュフローの分析など、デューデリジェンスにも対応しており、事業譲渡を含むM&Aのご成約を、一貫したサポートで提供することが可能です。
安心かつ円滑なM&Aを実現します。ぜひレバレジーズM&Aアドバイザリー株式会社のご利用をご検討ください。