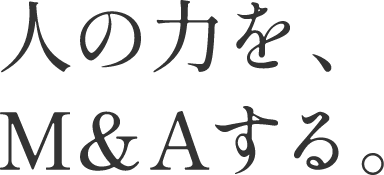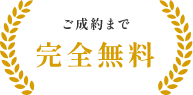このページのまとめ
- 敵対的買収とは、買収対象企業の経営者や株主の同意を得ずに株式を買い集めること
- 敵対的買収の対義語は、友好的買収である
- 敵対的買収では、一般的にTOB(株式公開買付)が行われる
- 敵対的買収を防ぐために、買収防衛策が実施されることも多い
- 買収防衛策を用意していない企業は敵対的買収のターゲットになりやすい
敵対的買収は、企業経営を揺るがす重大なイベントです。上場企業は、敵対的買収のリスクに備える必要があります。しかし、敵対的買収を仕掛けられた際にどのような防衛策をとるべきなのか、迷っている方もいるでしょう。
本コラムでは、敵対的買収と友好的買収の違いや、買収防衛策、敵対的買収のターゲットになりやすい企業の特徴などを解説します。
成功事例・失敗事例も紹介しているため、参考にして敵対的買収に備えてください。
目次
敵対的買収とは
敵対的買収とは、買収する企業や株主の合意を得ない状態で、対象企業の株式を買い集めることです。対象企業の経営権を取得し、実質的に支配する目的で実施されます。
株式を買い集める理由は、発行済み株式の総数のうち50%以上の獲得によって、対象企業の議決権の過半数を獲得できるからです。取締役選任を通じ、経営の支配が可能になります。
また、3分の2以上まで株式を取得すれば、特別決議も実施可能です。完全に経営を支配したい場合には、100%まで取得を目指します。
なお、経済産業省が2023年8月に策定した「企業買収における行動指針」において、敵対的買収という名前が「同意なき買収」に言い換えられました。今後は、同意なき買収という呼び方が一般的になると考えられます。
参照元:経済産業省「『企業買収における行動指針』を策定しました」
友好的買収との違い
友好的買収とは、買収する企業の経営者や株式から同意を得て行う買収のことです。合意を経て買収を行うため、手続きがスムーズに進みます。
また、合意済みであることから、TOBだけではなく、「株式移転・株式交換・合併」などの選択肢でも買収が可能です。
敵対的買収は、対象企業の同意を得ていません。買収を阻止するために、敵対的買収に対する防衛策(対抗措置)を発動するケースもあります。そのため、敵対的買収を行う企業は、友好的買収よりもコストや時間が必要になる可能性があります。
敵対的買収の方法
敵対的買収では、TOB(株式公開買付)が行われるケースが一般的です。
TOBとは、買収する企業の株式に関して「買付け期間・価格・株数」を公開し、市場外で買付けを行うことです。市場取引でも株式購入はできますが、株価が上昇するリスクを伴います。そのため、敵対的買収を行う際には、TOBを使用する企業が多い状況です。
敵対的買収の成功率は低い
敵対的買収を仕掛けても、買収に成功するとは限りません。事前の合意を得ておらず、株主や労働組合から買収の賛成を受けられないことが影響しているためです。
合意をしていないことで、買収目的に疑問を抱く株主も多くいます。そのため、TOBで買い付け価格を提示されても、買収に納得できず、売却に応じない株主が増加します。株式の購入ができなければ、買収は成功しません。
このように、敵対的買収が成功する確率は低いと理解しておきましょう。
敵対的買収を使う企業も少ない
敵対的買収を使う企業も少なく、友好的買収の活用が多い状況です。
敵対的買収を行うと、買収後の経営に影響を及ぼす可能性があるためです。
たとえば、経営陣を新しくしても、現場の従業員が敵対的買収に納得しない可能性もあります。従業員が買収に納得せず、指示に従わなければ、業務の遂行に支障が出るでしょう。
また、中小企業の場合は、株式に譲渡制限を設けているケースもあります。譲渡制限のある株式は、企業の承認を得なければ売却できません。買収したい企業の経営者が反対すれば、株式が集まらず、買収が難しくなります。
敵対的買収に対する事前の防衛策
敵対的買収を仕掛けられた側が行う防衛策(対応方針)には、事前に行うものと実施後に行われるものがあります。
敵対的買収に対する事前の防衛策には、以下のような主に6つの種類があります。
- ポイズンピル
- ゴールデンパラシュート
- プットオプション
- 黄金株
- チェンジオブコントロール条項
- マネジメント・バイアウト
それぞれの概要やメリット、デメリットなどについて見ていきましょう。
1.ポイズンピル
ポイズンピルとは、買収を行う企業の持ち株数が一定の基準を超えた場合に発動する防衛策です。既存の株主に条件付きの新株予約権を発行し、買収を行う企業の持ち株比率を下げる効果があります。
また、株式が発行されることで、買収を行う企業が持つ株式の価値が下がります。持ち株比率を上げるために株式を購入しようとすれば、必要なコストが増大するため、買収意欲を下げられるでしょう。
注意点は、既存の株主を巻き込んで、株式の保有割合を変えてしまうことです。ポイズンピルに反対する株主が現れた場合、新株発行の差し止めを請求される可能性もあります。
また、株主や買収を行う企業に不公平な場合、訴訟を起こされるリスクもあります。抑止力として活用されるケースが多く、実際には使用が難しい防衛策です。
2.ゴールデンパラシュート
ゴールデンパラシュートとは、買収価格を高騰させ、買収意欲を下げる防衛策です。
企業はあらかじめ、「敵対的買収で経営権が移動した場合、経営陣に払う退職金を通常よりも高くなるように設定する」と経営陣と契約を結びます。
これにより、買収する側は経営陣に支払う退職金が増加するため、買収コストが増加してしまいます。
買収コスト増加を嫌う企業が、買収をやめてしまうことを狙った防衛策が、ゴールデンパラシュートです。
3.プットオプション
プットオプションとは、ある商品をその時点の市場価格とは関係なく、あらかじめ決められた価格や数量で売却する権利のことです。
買収防衛策で活用する場合には、株式に対し、一定の価格で売る権利を与えます。また、金融機関などの債権者に対しては、債権回収の権利を付与します。
敵対的買収が行われると、プットオプションの権利が行使できるようになり、買収側には「株式の一斉買取り」や「債権の一括弁済」を行わなければなりません。買取や弁済には多額の費用が必要になるため、買収側に負担が生じます。
この負担が買収の抑止力につながるため、プットオプションが防衛策として活用されています。
4.黄金株
黄金株とは、買収や合併などの重要事項を、株主総会で否決できる特別な株式です。「拒否権付株式」と呼ばれることもあります。
普通株式は、一株一議決権の原則に基づき、出資した割合に応じて議決権を有します。しかし、黄金株の場合は、1株で拒否権を行使できる株式です。1株だけ発行されており、黄金株を持つ株主が同意しない限り、株主総会の決議が承認されません。そのため、買収が行われても、黄金株を用いて拒否できます。
注意点は、権限が濫用されるリスクがある点です。経営者が誤った判断で拒否権を行使してしまえば、株主や関係者に影響を及ぼします。
また、黄金株が不都合な相手にわたっても問題です。買収側に黄金株がわたってしまえば、経営権の掌握につながってしまうでしょう。
5.チェンジオブコントロール条項
チェンジオブコントロール(COC)条項とは、M&Aなどが原因で、一方の当事者に支配権や経営権の移動が発生した際に、もう一方の当事者が契約解除や契約の制限を可能にする条項です。
たとえば、A社が取引先であるB社とチェンジオブコントロール条項を結んでいたとします。その後、A社がC社に買収される際、B社がチェンジオブコントロール条項を発動したとしましょう。
この場合、取引先であるB社がチェンジオブコントロール条項に基づいて契約解除をしてしまえば、C社はA社の買収で得られるはずだったB社との取引を失うことになります。A社がB社に取引を依存していれば、A社に魅力がなくなり、C社は買収をためらうでしょう。
買収を機に、技術移転や機密情報の漏洩を防ぐためにも使用されています。
6.マネジメント・バイアウト
マネジメント・バイアウト(MBO)とは、経営者が自社の事業や株式の買収を行うことです。一般的には、事業承継で後継者問題を解決する場面や、会社を非上場化する目的で実施されます。
敵対的買収から防衛する場合には、マネジメント・バイアウトを行い、議決権の過半数を死守したり、上場廃止により株式取得をできないようにしたりします。また、市場にある株式を買い取り、買収を仕掛けた企業に株式を渡さないことも可能です。
敵対的買収実行後の防衛策
敵対的買収実行後に行う主な防衛策としては、以下の5つが挙げられます。
- ホワイトナイト
- 焦土作戦(クラウンジュエル)
- パックマンディフェンス
- 第三者割当増資
- 増配
それぞれ見ていきましょう。
1.ホワイトナイト
ホワイトナイトとは、敵対的買収を仕掛けられた際に、自社にとって友好的な企業を見つけ、代わりに買収や合併を行ってもらうことです。当然、買収や合併が行われるため、友好的な企業の傘下に加わることになります。
ホワイトナイトが発動するのは、友好的な企業にとって想定外のM&Aが行われる場合です。そのため、友好的な企業が有利になるような条件で、M&Aを行うケースが一般的です。
2.焦土作戦(クラウンジュエル)
焦土作戦(クラウンジュエル)とは、買収後の企業価値を低下させることによって相手の買収意欲を下げる買収防衛策です。
買収側の企業が目的にしている事業を売却や事業譲渡を行うことで事業を切り離し、買収する側のモチベーションを低下させます。
また、多額の負債を引き受けて企業価値を下げることも焦土作戦の策の一つです。
注意点は、買収される側の企業価値が下がってしまうため、経営者が責任追及をされるリスクを負うことです。
焦土作戦において、企業価値の低下を防ぐため、一時的に友好的な企業に事業を買い取ってもらうケースもあります。敵対的買収が不成立になったあとに、経営資源を買い直すことで買収前の状況に戻します。
3.パックマンディフェンス
パックマンディフェンスとは、買収を仕掛けてきた企業に対し、逆に買収を仕掛けて買収を阻止するために必要な25%以上の株式を取得し、防衛する方法です。
25%以上の株式を取得する理由は、買収を仕掛けられた企業が買収を仕掛けた企業の株式を25%以上取得すれば、株主総会での議決権行使が制限されるためです。
買収する側は取締役を送り込めないため、買収に失敗してしまいます。
注意点は、買収される側にも資金力が必要な点です。買収する側は資金力を持つ場合がほとんどであり、株価も低くありません。また、買収する側が上場企業でなければ、買収し返せない点もポイントです。
4.第三者割当増資
第三者割当増資とは、増資をする際に、特定の第三者に対して新株発行を行うことです。
買収を仕掛けられた場面では、新株や新株予約権を第三者に割り当てることで、買収側の持ち株比率を下げられます。
注意点は、会社法第210条で、「株式の発行が著しく不公正な方法で行われる場合は、発行中止を請求できる」と定められている点です。第三者割当増資を行った場合、裁判所に仮処分申請が行われる可能性があります。
日本でも、第三者割当増資が、東京地裁の仮処分で差し止められた事例があるため、注意しましょう。
5.増配
増配とは、株主に対する配当を通常よりも増やすことです。
買収側が預貯金などの資産を目的に買収を仕掛けた場合、増配を行うことで目的を達成できないように対策します。
注意点は、増配で自社の価値が壊れてしまう点です。買収を防げた場合でも、その後の経営が難しくなるリスクを背負うことになります。
敵対的買収実行後の株価
敵対的買収実行後、買収企業の株価は上昇するケースが多いです。買収によって事業が拡大し、業績がアップすることが期待されるためです。
しかし、買収の内容や買収後の結果次第では、株価が下がることもあります。
買収対象企業については、大量の株式が買付けられることにより、敵対的買収の過程で株価が急上昇するケースが多いです。
しかし、買収防衛策の影響を受けて、実行後に株価が落ち着く場合があります。たとえば、買収防衛策で新株予約権を発行した場合は、買収企業の株式保有率が低下し、株価の上昇がストップする可能性が高いです。
敵対的買収を行う7つのメリット
敵対的買収を行うことで、買い手側には次の7つのメリットが期待できます。
- 企業規模を拡大できる
- 経営資源の獲得につながる
- シナジー効果が発生する
- 合意なしで買収できる
- 買収計画を立てやすい
- 企業改革を素早く実施できる
- コスト増加のリスクが減る
それぞれのメリットに関して、解説します。
1.企業規模を拡大できる
敵対的買収のメリットは、企業規模を拡大できる点です。
自社を成長させるためには、企業規模の拡大が必要になります。
しかし、自社だけで企業規模を大きくするには、コストと時間が掛かり、実現が困難でしょう。
買収を活用すれば、自社だけで進めるよりも簡単に事業拡大ができます。新しい事業への進出や、新規顧客の獲得なども実現できるでしょう。
2.経営資源の獲得につながる
経営資源を獲得できることも、敵対的買収のメリットです。
買収する企業の従業員や資産、設備などを獲得できます。
経営資源を活用し、事業拡大にもつなげられるでしょう。
ただし、買収による人材の流出には注意が必要です。
敵対的買収では従業員が不満を持つケースもあるため、人員を獲得したい場合には慎重に進めましょう。
3.シナジー効果が発生する
買収企業との間で、シナジー効果が発生するのもメリットです。
自社だけで事業を行うよりも、相乗効果で良い効果が発揮されます。
たとえば、新しい商品やサービスが展開できることで、売上にシナジー効果が発生する場合があります。また、仕入れや販売をまとめて行うことで、コスト削減のシナジー効果が発生する場合もあるでしょう。
4.合意なしで買収できる
合意なしでスムーズに買収できる点もメリットになります。
買収する企業の合意を得ないため、交渉に必要な時間や手間が掛かりません。
資金をもとに、一気に買収できます。
友好的買収の場合は、買収する企業との話し合いが必要です。交渉が長引いたり、売り手の意向を多く反映しなければならなかったりするケースもあるでしょう。
敵対的買収であれば、売り手の意向を考えなくても、買収できることがメリットです。
5.買収計画を立てやすい
TOBで買収を行うことで、買収計画を立てやすい点もメリットです。
「買付け期間・価格・株数」などを公告するため、自社も必要なコストが計算できます。
買収にあたって、どれくらいの期間や予算が必要か予測できる点は、事業運営を進める点でもメリットになります。
6.企業改革を素早く実施できる
企業改革が素早く実施できる点もメリットです。
買収に成功してしまえば、買収した企業の経営陣と相談せず、企業改革に乗り出せます。
自社の考えを軸に、思い切って、素早い改革ができるでしょう。
7.コスト増加のリスクが減る
TOBの活用によって、買収に必要なコスト増加のリスクを減らせます。
事前に、買取価格や買取株数を公告した状態で、買収を行うためです。
市場で株式を購入すると、株価が上昇を続けるため、買収コストが増加してしまいます。買収する企業の株式を50%取得するのが、大変になるでしょう。
TOBを活用すれば、市場外で株式を購入できます。買収コストの増加を抑えて、必要な分の株式を集められます。
敵対的買収で発生する3つのデメリット
敵対的買収では、買い手側は次の3つのデメリットに注意が必要です。
- 買収失敗のリスクがある
- シナジー効果が発生しない
- 企業イメージが低下する
それぞれのデメリットに関して、解説します。
1.買収失敗のリスクがある
敵対的買収では、買収失敗のリスクに注意が必要です。
対象企業が、防衛策を発動し、買収を阻止するために動き出すためです。
少なくとも、50%以上の株式を取得できなければ、買収は失敗になります。
また、買収に失敗しても、株式の購入費用や、アドバイザリーに支払った手数料などは変わりません。失敗した場合でもコストが掛かるため、リスクを抱える点には注意が必要です。
2.シナジー効果が発生しない
買収に成功しても、シナジー効果が発生しない場合があります。
買収した企業の従業員の協力を得られず、経営統合に失敗する可能性があるためです。
また、買収に納得できない従業員が離職してしまい、企業のパフォーマンスが低下してしまうリスクもあるでしょう。
期待していた技術やノウハウを活用できず、シナジー効果が発揮できないリスクに注意しましょう。
3.企業イメージが低下する
敵対的買収を行うことで、自社の企業イメージが低下する可能性がある点に注意が必要です。
取引先や顧客からのイメージが低下した結果、取引や売上が下がるリスクもあります。
たとえば、買収に反対する取引先が現れ、契約が継続できない場合があります。
また、消費者がサービスの利用や商品購入をやめるケースもあるでしょう。
企業イメージ低下に備えて、ブランディングを強化するなど、対策が必要です。
敵対的買収のターゲットになりやすい企業の特徴
敵対的買収のターゲットになりやすい企業の特徴には、次の4つが挙げられます。
- 特許や独自のサービスを所持している
- 買収防衛策を用意していない
- 総資産額に対して株価が割安かつ持株比率が低い
- 負債比率が低く健全な経営をしている
それぞれの特徴を解説します。
1.特許や独自のサービスを所持している
特許や独自のサービスを所持している企業は、ターゲットになりやすい企業です。
買収を行う側からすると、買収を行うだけで新しい分野に参入できます。
また、すでにサービスが開発されているため、自社で研究を行う必要もありません。
買収側には魅力ある企業になり、敵対的買収で狙われやすくなります。
2.買収防衛策を用意していない
買収防衛策を用意していない企業も、狙われやすくなります。
買収側が先手を打ち、優位に買収を進められるためです。
もし、買収防衛策を持つ企業であれば、買収する側も買収リスクが高まります。
防衛策がなければ、リスクを減らして買収を進められるため、ターゲットにされやすくなるでしょう。
3.総資産額に対して株価が割安かつ持株比率が低い
総資産額に対して株価が割安、かつ持ち株比率が低い企業は、敵対的買収のターゲットになりやすい企業です。買収資金が集めやすく、買収しやすい企業になるためです。
持株比率が高い企業の場合は、買収を行っても、経営権の取得が難しくなります。
また、株価が高い企業の場合、買収コストが増加するため、買収をためらう企業も増加するでしょう。
持株比率が低く、株価が安ければ、買収側は手を出しやすくなります。
複数の企業が候補に挙がった場合、買収しやすい企業が狙われてしまうでしょう。
4.負債比率が低く健全な経営をしている
負債比率が低く、健全な経営をしている企業も狙われやすい企業です。
負債比率が低いと、買収後に負債の利子や債務返済に使うコストが少なくて済むためです。
もし、負債比率が高い場合、負債の返済に追われて、メリットが少なくなる可能性もあります。また、財務の維持が厳しくなったり、配当が難しくなるリスクもあるでしょう。
負債比率が低く、健全な経営をしている企業は、リスクが少ないことから、ターゲットに選ばれやすい企業といえます。
敵対的買収の成功事例
ここでは、敵対的買収の成功事例を3つ紹介します。
- ソレキアに対する敵対的買収
- デサントに対する敵対的買収
- ソフトブレーンに対する敵対的買収
敵対的買収実行までの過程や、買収防衛策の内容についても紹介しているため、ぜひ参考にしてください。
ソレキアに対する敵対的買収
2017年、フリージア・マクロス株式会社(以下、フリージア)の会長兼個人投資家である佐々木ベジ氏(以下、佐々木氏)が、ソレキア株式会社(以下、ソレキア)に対してTOBを仕掛けた事例です。
ソレキアは、もともと富士通グループ(以下、富士通)のパートナー企業でした。佐々木氏によって突然TOBを仕掛けられたソレキアは、富士通にホワイトナイトになるよう依頼します。富士通は、佐々木氏が提示した額よりも高い株価でTOBを発表し、ソレキアをめぐる争いが始まりました。
株式の買い付け価格は上昇していき、最終的には富士通は買い取りを断念しました。
結果、佐々木氏によるTOBが成立し、佐々木氏がソレキアの筆頭株主となります。その後、フリージアが佐々木氏からソレキアの株式を取得し、フリージアが筆頭株主およびその他の関係会社になりました。
買収防衛策が失敗に終わり、敵対的買収が成功した珍しい事例です。
参照元:
ソレキア株式会社「富士通株式会社による当社株券に対する公開買付けの結果に関するお知らせ 」
ソレキア株式会社「佐々木ベジ氏による当社株券に対する公開買付けの結果 並びに主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」
ソレキア株式会社「主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」
デサントに対する敵対的買収
2019年、伊藤忠商事株式会社とその完全子会社であるBSインベストメント(以下、伊藤忠)が、株式会社デサント(以下、デサント)に対してTOBを仕掛けました。
伊藤忠とデサントはもともと業務提携関係にありました。しかし、伊藤忠がデサントの経営体制や経営方針を問題視し、今後の企業価値向上に疑問を抱いたといいます。
そして、企業価値向上のためには伊藤忠との資本関係をさらに強化すべきとして、TOBに至りました。
デサントは反発していましたが、両社の協議はまとまらず、最終的に敵対的買収が成功した事例です。
参照元:
伊藤忠商事株式会社「株式会社デサント株式(証券コード:8114)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」
伊藤忠商事株式会社「株式会社デサント株式(証券コード:8114)に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」
ソフトブレーンに対する敵対的買収
2017年、株式会社スカラ(以下、スカラ)が、ソフトブレーン株式会社(以下、ソフトブレーン)に対して敵対的買収を仕掛けました。
スカラは、企業価値向上のためにソフトブレーンとの提携を検討し、2016年からソフトブレーンの株式を取得して株式保有率を高めていました。
金融商品取引法では、証券取引所外での買付けの結果株式の保有割合が5%を超える場合、TOBの実施が義務づけられる、という5%ルールが定められています。
スカラは、このルールが適用されるギリギリまで株式保有率を高めた後、一気に株式を取得し、敵対的買収を成立させました。
参照元:
ソフトブレーン株式会社「株式会社スカラ(旧商号:株式会社フュージョンパートナー)からの株主提案権行使に対する当社取締役会反対意見決定に関するお知らせ」
株式会社スカラ「決算説明資料(平成29年6月期)」
敵対的買収の失敗事例
ここでは、国内における敵対的買収の失敗事例を2つ紹介します。
- 明星食品に対する敵対的買収
- ぺんてるに対する敵対的買収
敵対的買収は成功率が低いため、失敗事例も複数存在します。敵対的買収に備えたい方は、特に失敗事例を参考に、買収防衛策について検討しましょう。
明星食品に対する敵対的買収
2006年、アメリカの投資ファンドであるスティール・パートナーズが、明星食品株式会社(以下、明星食品)に対してTOBを仕掛けた事例です。
スティール・パートナーズは明星食品に対してMBOの実施を要求しましたが、明星食品はこれに応じず、敵対的買収に発展しました。
敵対的買収を仕掛けられた明星食品は、買収防衛策として、日清食品株式会社(以下、日清食品)にホワイトナイトになってもらうよう依頼します。日清食品は、明星食品に対してTOBを行い、両社の間で資本業務提携を締結することを決めました。
結果、明星食品が日清食品の連結子会社となり、スティール・パートナーズの敵対的買収は失敗に終わりました。
参照元:
日清食品ホールディングス「明星食品と日清食品との資本業務提携および日清食品による明星食品株式の公開買付け実施に関するお知らせ」
日清食品ホールディングス「公開買付けの結果及び子会社の異動に関するお知らせ」
日清食品ホールディングス「日清食品株式会社の株式交換による明星食品株式会社の完全子会社化に関するお知らせ」
ぺんてるに対する敵対的買収
2022年、コクヨ株式会社(以下、コクヨ)がぺんてる株式会社(以下、ぺんてる)に敵対的買収を仕掛けた事例です。
コクヨは、もともとぺんてるの株式を保有し、持分法適用関連会社としていました。そして、ぺんてるの企業価値向上を目指し、海外事業の強化を目的に業務提携を進めていました。
コクヨはぺんてるに敵対的買収を仕掛けましたが、ぺんてるは買収防衛策として、プラス株式会社(以下、プラス)にホワイトナイトになるように依頼します。
結果、コクヨが保有していたぺんてるの株式をプラスが譲り受け、コクヨの敵対的買収は失敗に終わりました。
参照元:
プラス株式会社「コクヨ株式会社保有のぺんてる株式会社株式の譲受に関するお知らせ」
ぺんてる株式会社「当社株主変更に関するお知らせ」
まとめ
敵対的買収とは、経営権獲得を目指し、買収対象企業や株主の合意を得ていない状態で株式を買い集めることです。
敵対的買収は成功確率が低いです。しかし、万が一の買収リスクに備えられるよう、上場企業には事前に買収防衛策を検討することが求められます。買収防衛策を用意していない企業は、敵対的買収のターゲットになりやすいため注意が必要です。
また、独自の技術を持っている企業や健全な経営をしている企業など、買い手にとって魅力的な企業も注意しましょう。
買収防衛策には複数の選択肢があるため、敵対的買収の成功事例や失敗事例を参考に、自社に適した防衛策を選ぶことが大切です。
M&AならレバレジーズM&Aアドバイザリーにご相談を
レバレジーズM&Aアドバイザリー株式会社には、実績を積み重ねたコンサルタントが在籍しており、M&Aの相談から成約まで、一貫してサポートします。料金は、成約時に発生する完全成功報酬型です。M&A成約まで、無料で利用できます(譲受側のみ中間金あり)。
相談も無料で実施しているため、M&Aを検討している方は、お気軽にお問い合わせください。