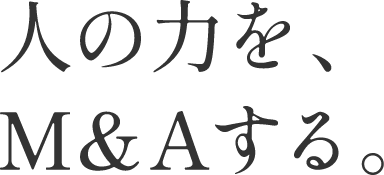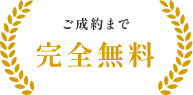このページのまとめ
- 休眠会社の買取には「相場より安い」「開業手続きを省略できる」などのメリットがある
- 休眠会社はM&A仲介会社や休眠会社売買サイトで見つけられる
- 休眠会社を買い取るときは、取引先や従業員を別途探す必要がある
- 休眠会社を買い取るときは、繰越欠損金や簿外債務などを確認することが必要
- M&Aアドバイザーや弁護士などの専門家に相談しつつ、慎重に買取を進めることが大切
「休眠会社の買取をしたいが、実際にはどうすればよいのだろうか」と気になっている方も多いのではないでしょうか。
休眠会社を探す方法には、M&A仲介会社に相談したり売買サイトを利用したりするなどの方法があります。
本記事では、休眠会社の買取の方法や実施手順を詳しくまとめました。休眠会社を買い取るメリット・デメリットやチェックポイント、相談先も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
目次
休眠会社とは
休眠会社とは、会社としては存続しているものの、事業を行っていない会社のことです。いずれ事業を再開する予定がある、廃業を準備しているなどの理由で、休眠状態になります。
法律上では、「最後の登記から12年を経過している株式会社」が休眠会社扱いを受けます。必要な登記申請を行わない場合、みなし解散扱いになり、解散登記がされる点に注意が必要です。
自ら休眠会社にするためには、税務署や市町村役所に、「異動届出書」の提出を行います。
休眠会社と混同しがちな言葉に「ペーパーカンパニー」が挙げられます。
休眠会社とペーパーカンパニーの違いは以下の表のとおりです。
| 休眠会社 | ペーパーカンパニー | |
| 法的定義 | 会社法第472条「株式会社であり、最後に登記した日から12年経過したもの」 | なし |
| 一般的な定義・イメージ | かつては企業活動をしていたが、現在はしていない会社 | 元々活動実績がない会社。税金対策や悪徳商法に利用されることがある |
参照元:法務省「休眠会社・休眠一般法人の整理作業について」
参照元:e-Gov法令検索「会社法第472条」
ペーパーカンパニーは法的に定義された用語ではありません。また、一般的にマイナスな意味で使用されています。
休眠会社が売られる2つの理由
休眠会社が売却される理由は、次の2つです。
- 休眠状態で放置できないから
- 高額で売却できる可能性があるため
それぞれの理由に関して、解説します。
1.休眠状態で放置できないから
休眠会社は、そのままの状態で放置できません。役員の任期ごとには、登記を行う必要があるからです。登記を行わない場合、過料が課せられてしまいます。
また、登記を行わずに放置していると、みなし解散に該当し、解散登記が行われてしまいます。株式会社は12年、一般社団法人や一般財団法人は5年間登記しなければ解散登記の対象です。
休眠状態で放置するにも限界があるため、売却しようと考える経営者が多くいます。
2.高額で売却できる可能性があるため
休眠会社であっても、高額で売却できる可能性があります。そのため、放置して収入にならないより、売却して利益を得たほうが良いと考える経営者も現れる状況です。
たとえば、長い社歴を持つ企業は、休眠会社でも売却しやすくなります。また、許認可を持つ企業や、資本金が高い企業も売却しやすいでしょう。
さらに、決算書や帳簿をきちんと残している企業も売却しやすくなります。記録が残っていれば、手続きを進めやすく、買収後に資金調達しやすいメリットもあるからです。
休眠会社の買取相場
休眠会社の買取相場は、10万円〜30万円前後です。相場よりも低く、3万円〜5万円程度で買取されるケースもあります。
有限会社の場合は。20万円〜50万円前後で買取が行われます。こちらも最低の買取相場は、3万〜5万円程度です。
相場に関しては、設立年数が古かったり、資本金が高額だったりするほど、高くなる傾向にあります。また、許認可も金額に影響し、建設業であれば50万円ほどの相場になります。
休眠会社買取の5つのメリット
休眠会社を買い取ることには、5つのメリットがあります。
- 安く買取ができる
- 許認可が引き継げる
- 社歴が獲得できる
- 会社設立に必要な手続きを省略できる
- 資本金が必要ない
それぞれのメリットに関して、解説します。
1.安く買取ができる
通常の相場よりも、安く買取できる場合があります。
事業を継続している会社と比べると、リスクが高くなり、価値が下がりやすくなるからです。
通常の企業や事業を買収する場合と比べると、安価で買取ができるでしょう。
2.許認可が引き継げる
許認可を持つ休眠会社を買収すれば、引継ぎができる点がポイントです。建設業や宅建業などの許認可が人気を集めています。
たとえば、宅建業免許を所有する休眠会社の場合、150万円〜200万円で取引されたケースもあります。
建設業許可の場合は、取得に必要な要件が難しく、新規で取得するのは大変です。自社で許認可を取る手間を省ける点もメリットになるでしょう。
3.社歴が獲得できる
社歴が獲得できる点も、休眠会社を買い取るメリットです。社歴が長い企業を買い取ることで、周囲から信頼を得やすくなります。
また、現在では有限会社を新規に設立できません。有限会社の買取ができれば、社歴が長い企業を所有していると認識してもらえます。
一から会社を設立する場合では難しい、社歴が獲得できる点がポイントです。
4.会社設立に必要な手続きを省略できる
会社の設立に必要な手続きを省略し、事業を始められます。
本来であれば、登記や設立の手続きなど、事業を始めるまでに準備が必要です。
休眠会社であれば、必要な手続きがすでに終えられています。
自分で手続きを行う手間を省き、スムーズな運営ができるでしょう。
5.資本金が必要ない
買収に資本金が必要ない点も、休眠会社を買い取るメリットです。
たとえば、資本金2,000万円の企業を買取できたら、その企業には2,000万円分の価値があります。たとえ、2,000万円が手元になくても、自分で設立したことと同じです。
資本金が自社の信用に影響し、金額が高いほど評価されます。
休眠会社であれば、資本金を持つ企業も買収しやすいでしょう。
休眠会社買取の4つのデメリット
休眠会社を買い取る場合、次の4つのデメリットに注意しましょう。
- 従業員や取引先が獲得できない
- 簿外債務も引き継ぐリスクがある
- 資金調達の実施が難しい
- 青色申告が取り消されている場合がある
それぞれのデメリットを解説します。
1.従業員や取引先が獲得できない
休眠会社の場合、従業員や取引先を引き継ぐことはできません。従業員はすでに退職しており、事業を行っていないことで取引先もありません。以前の取引先が、取引を再開してくれるとは限らないでしょう。
M&Aを行う目的に、人材の獲得や企業のネットワークを期待する経営者もいます。
しかし、休眠会社には人材や取引先などの基盤は、残っていないことが多いため注意しましょう。
2.簿外債務も引き継ぐリスクがある
簿外債務を引き継いでしまうリスクにも注意しましょう。入念に調査を行わないと、見落としてしまう可能性があります。
たとえば、不動産を所有している会社の場合、固定資産税を滞納している可能性もあります。また、簿外債務の実態を隠し、交渉に臨んでくる相手もいるでしょう。
さらに、ブラックリストに入っており、金融機関が対応してくれない可能性もあります。資金調達が実施できず、買取を行っても事業ができないリスクも想定が必要です。
3.資金調達の実施が難しい
休眠会社では、資金調達が難しい場合があるため注意しましょう。第二創業で融資を受ける場合、直近二期の決算書が求められるからです。
休眠会社は放置されている場合が多く、事業をやめてからの記録が残っていない場合もあります。納税や確定申告も放置されているかもしれません。
融資を受けたくても、融資に必要な書類を準備できない可能性があります。資金調達の実施を想定しているのであれば、決算書の有無を確認しておきましょう。
4.青色申告が取り消されている場合がある
青色申告が取り消されており、メリットが受けられない場合に注意が必要です。
青色申告は、2期連続で申告していない場合、取り消されてしまいます。
一度取り消されていると、再申請を行っても、却下される場合があります。繰越欠損金のようなメリットが受けられない場合もあるため、注意しましょう。
関連記事:事業買収とは?買い取る手法や目的、メリット・デメリットを解説
休眠会社を買取する際の流れ
休眠会社の買取は、以下の流れで進めていきます。
- 買取の目的とターゲットを定める
- 休眠会社を探す
- トップ面談をする
- デューデリジェンスを実施する
- 売買契約を締結する
- クロージングを実施する
- PMIを実施する
流れに沿って、説明します。
1.買取の目的とターゲットを定める
まずはなぜ休眠会社を買い取るのか、目的を明らかにしてください。
よくある目的としては、次のものが挙げられます。
- すぐに事業を開始したい
- 許認可を引き継ぎたい
- 安価に企業を買収したい
目的が明らかになると、ターゲットを絞りやすくなります。
たとえば許認可を引き継ぎたい場合なら、希望する許認可を有している休眠会社がターゲットです。ターゲットを絞り込むと無駄がなくなり、買取完了までの時間を短縮できます。
2.休眠会社を探す
目的とターゲットに合う休眠会社を探します。一般的な探し方は次の2つです。
- M&A仲介会社に相談する
- 休眠会社の売買サイトで探す
それぞれの探し方について説明します。
探し方1.M&A仲介会社に相談する
|
手数料相場 |
買取価格の5%程度(成功報酬費用) |
|
買取までの期間 |
半年~1年ほど |
|
案件数 |
M&A仲介会社による |
|
向いている人 |
|
M&A仲介会社は、企業買収・売却や事業買収・売却、合併などのさまざまなM&Aをサポートする会社です。
休眠会社の買取も相談でき、相手探しから契約締結までトータルで依頼できます。また、休眠会社の隠れたリスクについても調査してもらえるため、安心して契約しやすい点がメリットです。
料金体系は成功報酬制を採用している仲介会社も多く存在します。成功報酬制の場合、契約が成立するまでは料金が発生しません。
探し方2.休眠会社の売買サイトで探す
|
手数料相場 |
提示価格に含まれていることがある |
|
買取までの期間 |
3ヶ月~1年ほど |
|
案件数 |
休眠会社の売買サイトによる |
|
向いている人 |
|
休眠会社の売買サイトを利用する場合、買取までの工程を自力で行うことになります。自分で相手探しから交渉までを主導的に進めていくため、明確にターゲットや買取価格などが決まっているときにおすすめです。
休眠会社の売買サイトで探す場合、手厚いサポートがない分、M&A仲介会社よりも手数料が低くなる傾向にあります。
3.トップ面談をする
相手候補が見つかったら、トップ面談を行い、次に挙げる事柄を確認します。
- 売買の条件(価格、時期など)
- 取引完了後のビジョン
認識に相違がなければ、秘密保持契約や独占交渉権などに関する記載を含む基本合意書を締結し、デューデリジェンスに進みます。
4.デューデリジェンスを実施する
デューデリジェンスとは、買い手が売り手の法務・財務・税務状況などについて精査することです。買取後にトラブルが生じないためにも、丁寧にデューデリジェンスを実施し、リスクなどを洗い出しておきます。
あらゆる分野における専門的な知識が求められるので、M&A仲介会社や公認会計士、税理士などの専門家に依頼することが一般的です。
5.売買契約を締結する
デューデリジェンスの結果を踏まえて、最終的な売買条件を決定します。
たとえば、債務が予想以上に多かったときは、交渉をして価格を下げるなどの調整が必要です。最終的な売買条件を提示して、合意に至ったら、売買契約書を作成して締結します。
6.クロージングを実施する
売買契約締結後、クロージング(買取に向けての手続き)を実施します。
クロージングの内容は買取のスキームによって異なります。
たとえばスキームが株式譲渡だった場合は、買い手は売り手に対価を支払い、売り手は買い手に株式を譲渡し、株主名簿の書き換えを行います。
7.PMIを実施する
クロージング後にPMI(Post Merger Integration)を行います。
PMIとは異なる会社を統合させるための実務のことで、経営管理や業務効率化、意識統合など、PMIを行う範囲は多岐にわたります。
PMIを速やかに進めることで、期待したシナジー効果を発揮させることが可能です。
ただし、急いで統合しようとすると歪みが生じる恐れがあります。短期的に統合する分野と長期的に統合する分野に分け、計画的に進めていくことが大切です。
休眠会社の再開で行う手続き
買収後に事業を再開するためには、手続きが必要です。次の2つの手続きを行いましょう。
- 異動届出書などの提出
- 登記の実施
それぞれの手続きに関して、詳しく解説します。
異動届出書などの提出
事業再開にあたり、異動届出書などの提出が必要です。次のような書類を提出しましょう。
| 提出場所 | 必要書類 |
| 税務署 | 異動届出書・給与支払事務所等の開設届出 |
| 市町村区役所・都道府県税務署 | 異動届出書 |
| 年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届 |
企業によっては、青色申告が取り消しを受けている場合もあります。その場合は、税務署に対し、「青色申告承認申請書」を提出しましょう。
参照元:国税庁「[手続名]給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」
参照元:国税庁「[手続名]異動事項に関する届出」
参照元:日本年金機構「適用事業所が廃止等により適用事業所に該当しなくなったときの手続き」
参照元:国税庁「[手続名]所得税の青色申告承認申請手続」
登記の実施
事業を再開する場合、次の登記が必要になる場合もあります。
| 登記名 | 費用 |
| 役員変更登記 | 資本金が1億円以下の場合:1万円 資本金が1億円を超える場合:3万円 |
| 会社継続登記 | 3万円 |
| 本店移転登記 | 移転前後で管轄の法務局が同じ場合:3万円 移転前後で管轄の法務局が違う場合:6万円 |
本店移転登記に関しては、移転先によって金額が変わるため注意しましょう。移転前後で管轄の法務局が同じ場合は、3万円です。
ただし、移転前後で管轄の法務局が変わる場合、移転前と移転後それぞれで3万円掛かります。2箇所分で6万円掛かるため注意してください。
参照元:法務局「商業・法人登記の申請書様式」
参照元:法務局「株式会社継続登記申請書」
参照元:法務局「株式会社本店移転登記申請書」
休眠会社の買取に成功するためのチェックポイント
次のポイントに注目することで、休眠会社の買取を成功に導きやすくなります。
- 繰越欠損金
- 隠れた債務の有無
- オーナーの人間性
- 登記手続き
それぞれのポイントについて説明します。
1.繰越欠損金
休眠会社に繰越欠損金がある場合は、買収により節税効果を期待できることがあります。
通常であれば休眠会社の過半数の株式を購入することで繰越欠損金を活用できるようになりますが、以下のいずれかに当てはまるときは、繰越欠損金による節税効果は得られないことがあります。
- 休眠会社で実施されていた事業を止め、売上の5倍を超える資金を借りる、あるいは出資を受けて新事業を開始する場合
- 半額未満で債権を取得し、休眠会社の売上の5倍を超える資金を借りる、あるいは出資を受けて新事業を開始する場合
- 上記のいずれかの条件に該当したうえで、適格合併を行う、あるいは残余財産が確定した場合
- 全役員が退任し、なおかつ社員の20%以上を退職させたうえで、開始した新事業の規模が従来の規模の5倍以上になった場合
- 新事業を開始した場合
繰越欠損金による節税効果を期待して休眠会社の買取をしようと考えている場合は、上記の条件に当てはまっていないか必ず確認しましょう。
2.隠れた債務の有無
買収後に休眠会社の隠れた債務が見つかることがあります。場合によっては、買い手側が大きな負担を負うことにもなりかねません。
デューデリジェンスを丁寧に実施し、簿外債務がないかを調べておきましょう。
3.オーナーの人間性
休眠会社のオーナーの人間性に問題があると、買収後にトラブルが起こりかねません。
契約締結前に何度も会い、オーナーの性格や周辺の人間関係などを確認しておきましょう。
4.登記手続き
事業目的を変更する場合は、買収後2週間以内に登記手続きが必要です。また、事業目的を変更しないときでも、役員や代表者が変わるため、役員変更登記が必要です。
いずれの場合も登録免許税が発生するため、事前に準備しておきましょう。
休眠会社の買取を相談できる専門家
休眠会社の買取を行う場合、自分だけで進めるのは困難です。
次のような専門家に相談してみましょう。
- M&Aアドバイザー
- 弁護士
- 行政書士
- 税理士
ここでは、それぞれの専門家の特徴に関して、解説します。
1.M&Aアドバイザー
休眠会社の買取を行う場合、まずはM&Aアドバイザーに相談しましょう。休眠会社を買取する場合でも、通常のM&Aと同じように進むケースが多いからです。
買取では、専門的な知識が必要になったり、買収リスクが潜んでいたりします。買取を総合的にサポートしてくれる、M&Aアドバイザーが欠かせません。
買取でのメリットが最大限に受けられるよう、アドバイスを受けられます。
2.弁護士
買取を進めていくと、法律的な問題やリスクが明らかになる場合もあります。
たとえば、金融機関のブラックリストに入っている場合や、反社会的勢力との関わりが見つかるケースです。
弁護士に相談すると、不必要なトラブルを避けられるメリットがあります。自分で交渉を進めるより、弁護士に任せた方が安心できる場面も多いでしょう。
3.行政書士
買取を行う場合、手続きが複雑になり、対応が大変になる場合もあります。
その場合は、行政書士に依頼すると良いでしょう。
4.税理士
買収を行う際には、税金の問題を考慮しなければなりません。税理士に相談し、リスクを減らしておきましょう。
たとえば、休業中でも法人住民税の均等割りが発生する場合があります。また、青色申告が使用できるか、調べておく必要もあるでしょう。
地方自治体ごとにも変わるため、専門家への確認が大切です。
まとめ
休眠会社の買取には、価格が安価であることや許認可を引き継げるなどのメリットもありますが、隠れた債務が見つかるなどのリスクもあります。
トラブルなく買取を実現させるためには、慎重にデューデリジェンスを進めたり、話し合いの場でオーナーの人柄をよく確認したりすることなどが大切です。
また、自分の力だけでは不安が残る場合は、M&A仲介会社などの専門家に相談することがおすすめです。専門的な知識・経験を生かして、休眠会社の買取を手厚く支援してくれます。